基本知識 一問一答
相互作用、飲み合わせ その1
テキストのページは、「相互作用、飲み合わせ その1」です。
んでは、スタート。
『複数の医薬品を併用した場合や特定の食品と一緒に摂取した場合に、医薬品の作用が増強したり、減弱したりすることを相互作用という。』
正誤はこちら。
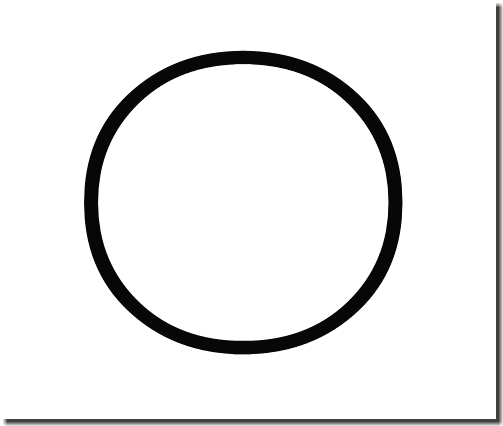
正しい記述です。
まさに、「相互作用」の説明です。
なお、大丈夫かと思いますが、相互作用は、効き目が強くなるのと弱くなるの両方の意味があります。
増強するだけ、減弱するだけではないので、注意してください。ときどき、出ます!
『相互作用には、医薬品が吸収、分布、代謝(体内で化学的に変化すること)又は排泄される過程で起こるものと、医薬品が薬理作用をもたらす部位において起こるものがある。』
正誤はこちら。
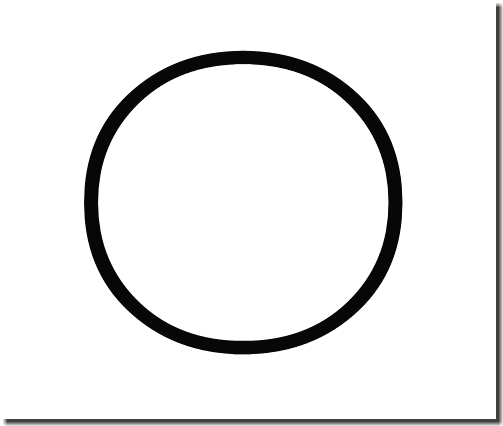
正しい記述です。
なぜだか、絶妙によく問われる記述です。
「吸収、分布、代謝、排泄される過程」と「薬理作用をもたらす部位」の2セットなので、押えておきましょう。
『かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、アレルギー用薬等では、成分や作用が重複することが多く、通常、これらの薬効群に属する医薬品の併用は避けることとされている。』
正誤はこちら。
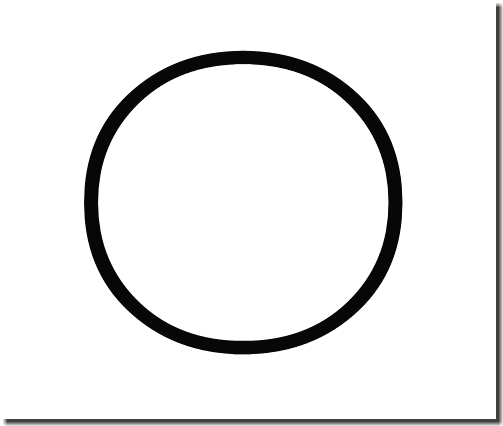
そのとおりの記述です。
難しく考えないで、解答してください。
たとえば、アレルギー用薬って併用を避けるようにテキストに書いてあったかな?とかです。
これまでの試験では、基本知識で細かい穿ったことは問われてないです。
一読して違和感なければ、「正しい」と判断しましょう。余計なところに、神経を使わないようにしましょう。
『複数の疾病を有する人では、疾病ごとにそれぞれ医薬品が使用される場合が多く、医薬品同士の相互作用に関して特に注意が必要となる。医療機関で治療を受けている場合には、通常、その治療が優先されることが望ましい。』
正誤はこちら。
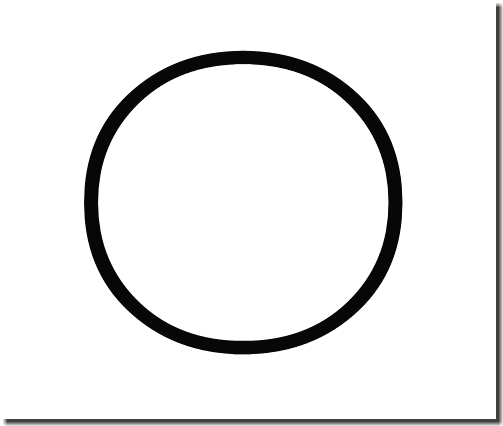
正しい記述です。
手引きそのまんまの記述です。
繰り返しますが、一読して、違和感を感じなければ、だいだい正しいです。
『一般用医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対し、医薬品の種類や使用する人の状態等に即して情報提供を行い、医療機関・薬局から交付された薬剤を使用している場合には、診療を行った医師若しくは歯科医師又は調剤した薬剤師に相談するよう説明がなされるべきである。』
正誤はこちら。
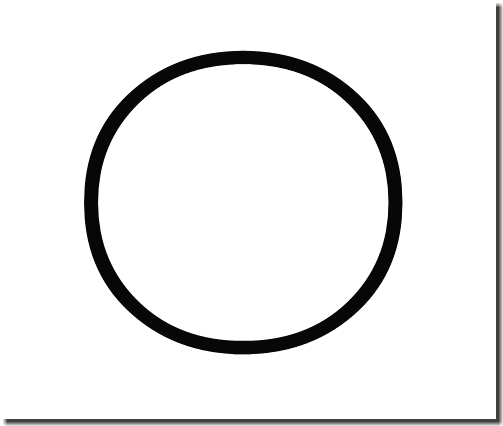
これも、正しい記述で、そのとおりです。そうしたほうがいいですよねー。
登録販売者ってこういう仕事をするんですよ、いいですね?と出題者が念押ししている感じです。
『医療機関を受診する際に、使用している一般用医薬品があれば、その添付文書等を持参して見せるよう説明がなされるべきである。』
正誤はこちら。
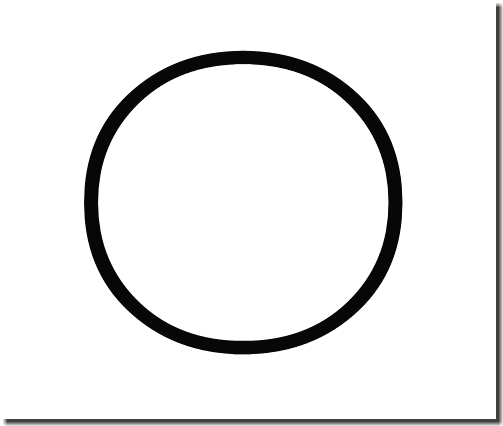
「注記」からの出題です。
「注記」からも当然出題されます。
常識的な内容が多いので、読み落とさないようにしてください。
本問は、まあ、そうしたほうがいいですよねーで解けるかと思います。
ページリンク
「一問一答:次のページ」へ。
補足リンク1
通読用・・・「相互作用、飲み合わせ 全記述」
補足リンク2
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
本章インデックス・・・「基本知識 インデックス」
本節インデックス・・・「医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因 インデックス」
こまごましたもの
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
★みんなとシェアする
Ⅰ 一問一答
├医薬品の本質 その2
├医薬品のリスク評価 その1
├医薬品のリスク評価 その2
├健康食品 その1
├健康食品 その2
├セルフメディケーション その1
├セルフメディケーション その2
├副作用 その1
├副作用 その2
├不適正な使用と副作用 その1
├不適正な使用と副作用 その2
├相互作用、飲み合わせ その1
├相互作用、飲み合わせ その2
├小児、高齢者等への配慮 その1
├小児、高齢者等への配慮 その2
├小児、高齢者等への配慮 その3
├小児、高齢者等への配慮 その4
├プラセボ効果
├医薬品の品質
├対処可能な範囲 その1
├対処可能な範囲 その2
├コミュニケーション その1
├コミュニケーション その2
├コミュニケーション その3
├基本的考え方
├サリドマイド訴訟
├スモン訴訟
├HIV訴訟
├CJD訴訟
├C型肝炎訴訟
└登録販売者の責務
登録販売者
概要
独学シリーズ
対策シリーズ
勉強方法
過去問+解説
├チェック問題 過去問リスト
├漢方 過去問リスト
├生薬 過去問リスト
├全ブロック 試験問題 科目別
├「医薬品的な問題」過去問リスト
├「添付文書」過去問リスト
└「資料問題」過去問リスト
