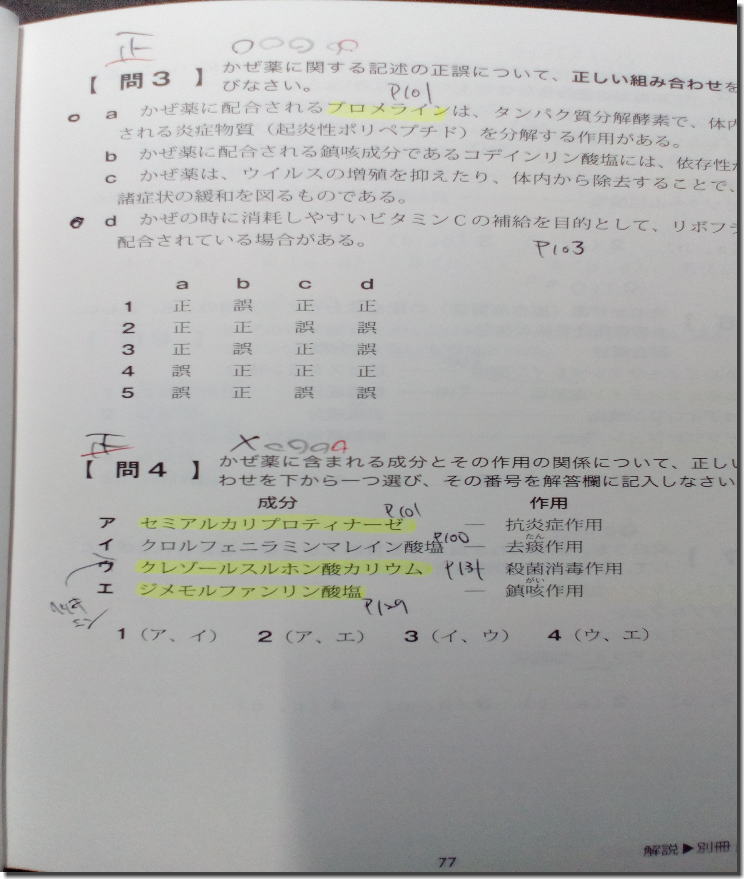登録販売者 不合格者対策
まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。
登録販売者が不合格だった人人を対象に、再受験のやり方を説述。「やってはいけない」こと失点科目対策、暗記方法を提供する。また、再受験時の教材の買い替えについて述べる。
インデックス
やってはいけない
まずは、効果のなかったことをやめましょう。
結論から言うと、「テキストを写すダメ。アヤフヤ知識ダメ。アルコールダメ」といった次第です。
テキストを写すダメ
年配の御姉様の方に多いのが、「テキストを1字1句写す勉強」です。時間と手間を食う割に実力の伸びは、いまいちです。
写経モドキの勉強は、ダメです。写経は写経であって、勉強ではありません。
テキストを写す時間があるなら、1問でも問題を解きましょう。はるかに実力アップします。
アヤフヤ知識ダメ
資格試験の鉄則なのですが、アヤフヤなうろ覚えの知識では点は取れません。。
アヤフヤ100より確かな10です。また、多くをざーと雑にやるより、1つ1つをシッカリやっていく方がラクです。
1つ1つをキッチリ正確に憶えていきましょう。結局、これが一番早いです。
アルコールダメ
アルコールは、忘却剤です。
酔った状態で勉強しても忘れる一方です。「飲んだら勉強しない」です。
逆を言えば、「勉強したら飲まない」です。飲んだら憶えたことが全部消えちゃいます。
失点科目を徹底集中
ひとまず、自分の受けた試験の自己採点をして、どの科目が極端に点が低かったか、把握してください。
再勉強のしばらくは、その失点科目だけを集中してやりましょう。点の取れた科目は、まあ点が取れるので、後回しです。
過去問演習しまくる
手っ取り早く実力を上げるには、過去問演習が一番です。
当サイトの「全ブロック 試験問題 科目別」には、全ブロックの科目別の過去問があります。
ここを利用して、失点科目の過去問を、徹底的に解いてください。
全ブロックの問題を解いて、キッチリ復習すれば、次の試験では、8~9割取れます。
理解云々より、問題を解いた「数」が物を言うのが登録販売者試験です。
ちなみに、わたしは、「医薬品」の問題は、5回くらい、繰り返し解きました。
見切る・捨て問
登録販売者試験は、ボリュームが大きいので、全部が全部の論点を完全に仕上げることは、到底無理です。
何度やっても苦手なところ(クソ面倒だなと思うところ)は、「捨て問」にしましょう。
特に、漢方処方製剤は、ざっくり捨てましょう。「適正使用」の「医薬品的な問題」も、「相談すること」は捨てましょう。
当サイトの勉強方法などを参考に、「やる・やらない・後でやる・余裕があればやる」を明白にしましょう。
暗記対策
登録販売者試験は、憶えるしかないです。
まず、キーワードとかは、朝に憶えましょう。起きたら即、憶えたいものを見るといいです。
1日2個くらいは、割に軽く憶えられます。朝は脳が元気なのか、リフレッシュしているのか、憶えやすいと実感しています。逆に、夜だと脳が疲れているのか、ドロドロしているのか憶えが悪いです。
さて、暗記のコツですが、「一気にやらない・長時間やらない」です。
細切れ時間の10~15分くらいを活用するのが一番負担ないです。また、憶える作業は1時間が限度な感じです。
憶える方法は、伝統的な手法ですが、「紙に何度も書く、声に出す」です。わたしは、紙に書いて憶える口です。白紙にドンドコ書き出して憶えました。
また、「短時間上書き憶え」のやり方があります。
憶えが悪いものに適していて、「ある語句を憶える→憶えたら5分後、15分後、30分後に思い出すようにする」ようにします。短時間で何度も上書きするような感じです。
ジオクチルソジウムスルホサクシネートとかアセチルコリンエステラーゼといった、(なんじゃいそら?)の記憶に有効ですよ。
学習計画を立てる
やることが明白だと、着手しやすいです。
難しく考えなくていいです。単に、この日までにここを終わらせるとか、この週は○○をするとか、たとえば、この日(この週)には、かぜ薬の復習をする、抗真菌成分のテキストを読み直す、○○県の〇年度の過去問を解くとか、です。
勉強を進めていくと、自分の弱点がぞくぞく見えてくるはずです。
それらの制覇のために、先々の時間を具体的な作業でどんどん埋めていきましょう。
補足1:足切り点知ってる?
大丈夫と思いますが、登録販売者試験には、科目ごとの足切り点(4割or3.5割正解)があります。
まだまだ、この合格基準を知ってない人がいて、たとえば、法規をほとんど勉強しないで本試験に臨んだりしています。
その挑戦心は大したものですが、ほぼ100%落ちるので無駄な受験とも言えます。
未勉強科目・捨て科目は、絶対にしないでください。
補足2:医薬品得意でも油断しない
「医薬品」ですが、傾向変化に注意してください。
本当に、全国的に難しくなってきていて、副作用、禁忌、使用上の注意ほぼすべて出てます。何でもない記述も出てます。
他の科目は何とでもなるのですが、「医薬品」は、ヤバいです。
まずもって、かつてのように、「出ることころだけ勉強する」が不適当となっています。
近年の「医薬品」では、過去問で問われたことの“ない”記述がドシドシ問われており、過去問演習後は、過去問で問われてないものをテキストでチェックして読み込んでおいてください。
(え!こんなものが出るの?!)といった感じで、「注記」を含むすべての記述が、ホント前文の何でもない記述まで、出ています。登録販売者も、難しくなりましたよ。
ちなみに、「医薬品」ですが、定番論点・頻出論点は、やっぱり出るので、これまた、注意してください。
補足3:教材の買い替えについて
基本的に、教材を買い替える必要はないです。
近年の手引き改正は、比較的小規模なので、古いテキストに加筆修正すれば、事が足ります。
例外的に、100ページ以上の巨大な改正が“あった”ときは、手間的に買い替えた方がいいですが、まあ、大丈夫でしょう。
本サイトの「登録販売者の独学」でも、手引き改正を告知するので、参考にしてください。「twitter」でも、告知してます。
補足4:傾向把握
近年まで受験生だったので、試験傾向はある程度、把握されているかと思います。
しかし、念のため、他県の動向ともつかんでおいて損はありません。
時間のある時に、「本試験 直前対策」を、一読願います。
各種勉強リンク
勉強に関するページですが、「サイトマップ」に、ブログのリンク集をまとめています。
くだらない語呂合わせがあるので、試験勉強の合間や細切れ時間などで、活用してください。
こまごましたもの
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
★みんなとシェアする
登録販売者
概要
独学シリーズ
対策シリーズ
勉強方法
過去問+解説
├チェック問題 過去問リスト
├漢方 過去問リスト
├生薬 過去問リスト
├全ブロック 試験問題 科目別
├「医薬品的な問題」過去問リスト
├「添付文書」過去問リスト
└「資料問題」過去問リスト