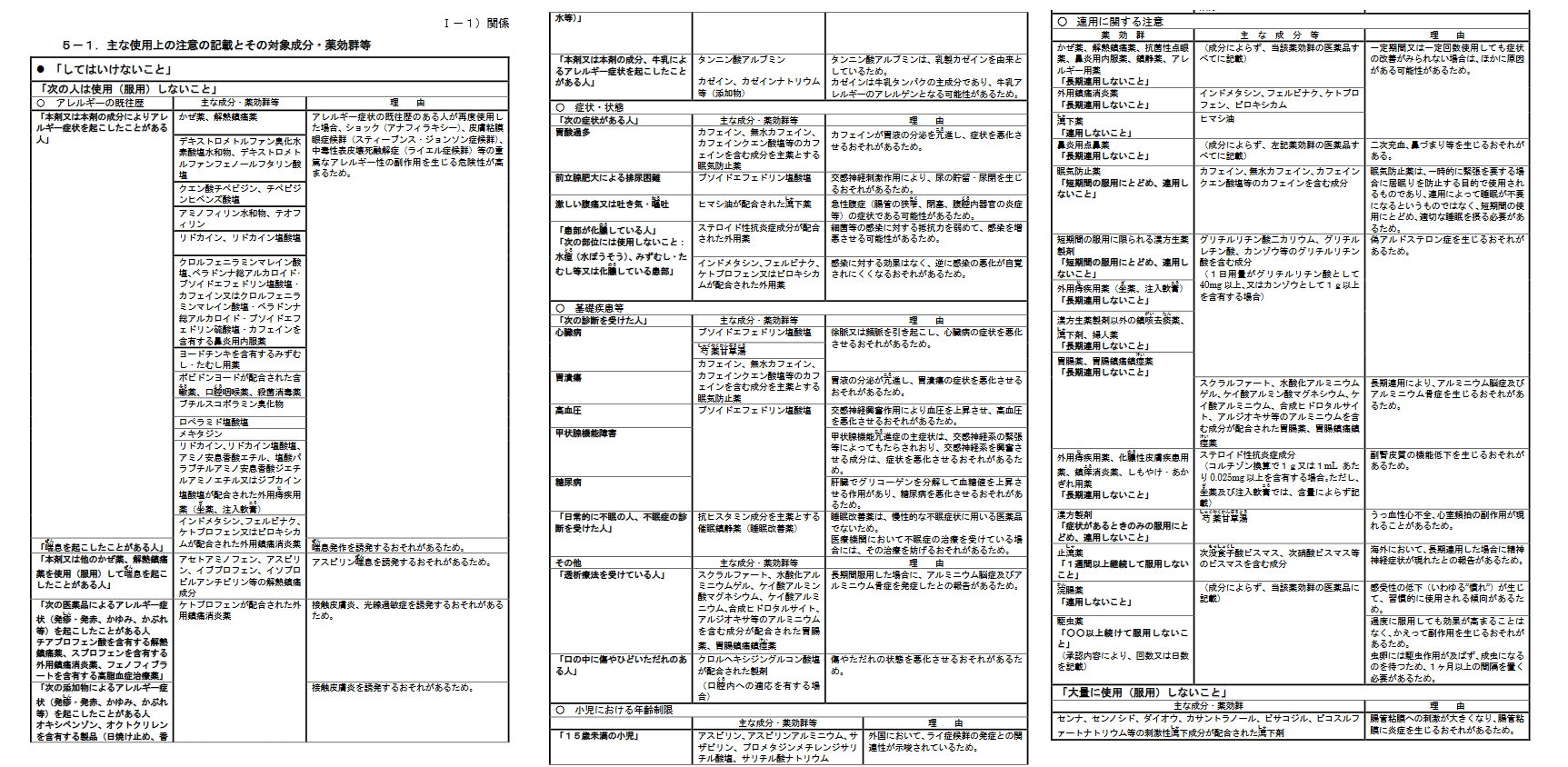登録販売者「適正使用」の「医薬品的な問題」対策‐令和7年度(2025年度)対応
まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。
登録販売者の試験科目「適正使用」の対策ページ。「医薬品的な問題」が増えてきたので、その対策を取りたい人向けのページ。このページでは、個々の解説ページのリンクのインデックスのほか、「医薬品」を優先や「使用(服用)しない」を優先や「相談すること」は一部だけ、勉強方法等を見ていきます。令和7年度(2025年度)対応。
インデックス
- 結論‐傾向変化に応じた対策
- 対策1‐「医薬品」を優先
- 対策2‐「使用(服用)しない」優先
- 対策3‐「相談すること」は、“ほぼ”捨てる
- 勉強方法1‐見る
- 勉強方法2‐調べる
- 勉強方法3‐問題を解く
- 「使用(服用)しない」リンク
- 「相談すること」リンク
- 個別論点リンク
結論‐傾向変化に応じた対策
「適正使用」の「医薬品的な問題」ですが、近年は、出題傾向が安定しています。
おおむね「5~8問」の出題です。
試験問題も、突飛なものは姿を消し、試験問題の定番化が進んでいます。
よって、現状では、徹底して過去問演習をするのが、効率の良い対策となっています。
「医薬品的な問題」の全ブロックの過去問を、「医薬品的な問題 過去問リスト」に挙げています。
上記ページに挙げている過去問を、“問いと答えを憶えて”、解けるようになっておきましょう。
“問いと答えを憶える”だけでも、1~3点くらいは取れます。
補足:0点じゃなければいい
昔から、「医薬品的な問題」は、0点じゃなければいいところです。
こういうとアレですが、「医薬品的な問題」をガチ対策すると、費用対効果が実に悪いです。暗記量が多すぎです。
繰り返しますが、現状では、多少の失点はあろうとも、過去問演習のみがベターかと思われます。
以下は、時間に余裕がある方で、かつ、やる気のある方へのコンテンツです。
東京都R1試験のように「11問」も、出題されたらと困る!という方は、参考にしてください。
対策1‐「医薬品」を優先
「適正使用」の「医薬品的な問題」ですが、「医薬品」の勉強が済んでいないなら、やらなくていいです。「後回し」にしてください。
「医薬品的な問題」は、ベースが「医薬品」のため、「医薬品」の知識がないと、まったく進みません。
試験戦術の点でも、「医薬品」の方が大事です。
まずは、「医薬品」の制覇に、尽力してください。
一通り、「医薬品」の勉強が済んでから、当該「医薬品的な問題」に着手するようにしましょう。
対策2‐「使用(服用)しない」優先
「医薬品的な問題」には、「2つ」の系統があります。
1つは、「使用(服用)しない」系統で…、
残るは、「相談すること」系統です。
優先すべきは、前者の「使用(服用)しない」です。
前者の方は、比較的ボリュームが小さく、また、出題を絞りやすく、勉強しやすいのです。
また、出題数も、こちらの方が“ちょっとだけ”多いことがあり、点数可能性が高いのです。
そして、「使用(服用)しない」は、割かし「医薬品」で問われることがあるので、費用対効果が“悪くない”のであります。
こうした塩梅なので、まずは、「使用(服用)しない」を、優先して勉強するってな次第です。
対策3‐「相談すること」は、ほぼ捨てる
対して、「相談すること」は、“ほぼ捨てる”ことにします。
理由は、「使用(服用)しない」の裏返しです。一口で言えば、「相談すること」は、費用対効果が悪いのです。
「相談すること」は、量がそこそこ多く、成分・項目が配偶者のカバンの中のように雑多過ぎて、対策を取り難いのであります。
よって、「“ほぼ”捨てる」のが賢明です。
過去問に出たものだけ、押さえるといいでしょう。
表を見る・憶えるなどの追及は、しなくていいです。
勉強方法1‐見る
「医薬品的な問題」の勉強方法を見ていきます。
まずもって、暗記対象の「第5章 別表」ですが、本当に文字の羅列です。
真剣に読もうとしてもシンドイだけです。
んなもんで、「読む」のではなくて、「見る」ようにします。
何十分も見る必要はないです。
5~10分程度の細切れ時間を活用して、何度も目を通しましょう。
たとえば、トイレで見る、通勤通学時に見るとかです。わたしは、夜寝る前に見てました。
ここで、重要なのは、「憶えようとしない」ことです。
こんな、配偶者のようなクソ「表」を憶えようとすると、嫌気が差すだけです。
何度も何回も見るうちに、そこそこ頭に残っていきますし、嫌悪感も和らぎます。
真剣な暗記と記憶は、「医薬品的な問題」の過去問演習を終えてからでいいです。
勉強方法2‐調べる
「見る」の次の段階は、「調べる」です。
当該「調べる」ですが、「表」に出てくる成分を、「医薬品」のところと照合する作業です。
「適正使用」の「表」に出てくる成分ですが、「医薬品」に出てくるものが多々あります。
たとえば、非ステロイド性抗炎症成分の「インドメタシン」です。
「適正使用」では「喘息を起こしたことがある人」とあり、そして、「医薬品」では、喘息を起こしたことがある人では、使用を避ける必要がある」との記述があります。
そして、当該インドメタシンは、上記の喘息のほかに…、
「アレルギー症状」や…、
「次の医薬品によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人:チアプロフェン酸を含有する解熱鎮痛薬、スプロフェンを含有する外用鎮痛消炎薬、フェノフィブラートを含有する高脂血症治療薬」、
「次の添加物によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人:オキシベンゾン、オクトクリレンを含有する製品(日焼け止め、香水等)」
…といった記述が、「医薬品」と「適正使用」とで共通して登場します。
こういう共通するものは、医薬品の勉強でカバーできるので、「適正使用」的には、ラクできるってな塩梅です。
対して、「適正使用」には出てくるが、「医薬品」には出てこない記述もあります。
たとえば、「本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人」に出てくる「非麻薬性鎮咳成分」の「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物」です。
当該成分は、「医薬品」では、当該アレルギーについての記述がないのです。
こういう「ない」ものは、医薬品の勉強でカバーできないので、「適正使用」の勉強時に、丁寧に押えていかねばならないってな次第です。
「表」の成分を、一通り調べれば、何と何を真剣に憶えないといけないか、明白に見えてきます。
チェックを入れる
さて、「表」の成分の「ある・なし」を調べる際は、チェックを入れていきましょう。
具体的には、医薬品にも「ある」ものには、「✓」を入れたり、赤ペンで線を引くとかです。
対して、医薬人に「ない」ものは、目立つマーカーで塗るとかするといいでしょう。
こうしておくと、一目見るだけで、どこを憶えないといけないか明白なので、「暗記と記憶」の効率が上がります。
注意点
当該「調べる」の注意点ですが、「ずーっと根を詰めて調べない」です。
時間的には、1回あたり15分くらいで十分です。ホント、他の科目の勉強に疲れてきたら、気分転換で「調べる」くらいでいいです。
細切れ時間とか、宅配業者待ちとか、リビングに配偶者しかいないときとかに、ささっと1~2成分を調べるといいでしょう。
そして、大事なことですが、「調べる」ときも、憶えようとしないでください。
無理に憶えようとすると、脳が疲れて、心気が萎えるだけです。
勉強方法3‐問題を解く
先の「見る」と「調べる」で、ある程度、「表」に「見覚え」ができてきたら、テキストや過去問題集、PDF過去問に着手しましょう。
優先すべきは、先述したように、「使用しない」の問題です。
さて、いくら見たり調べたりしても、最初のうちは、まず解けないはずです。
んなもんで、テキストを見ながら解いていってください。
本試験のその日までに、何もなしで解けるようになればいいので、ドンドコと“カンニング”して問題を解いていきましょう。
んで、問題に出たもの・間違えたもの・忘れていたものを、復習を通じて、憶えていってください。
問題集・過去問等の問題は、最低でも、「3回」は繰り返しておきましょう。
なお、「使用しない」の各論点を、「「使用(服用)しない」リンク」にまとめています。
くだらない語呂合わせがある論点もあります。使えるものがあれば、活用して脳に叩き込みましょう。
対策は、以上です。
このくらいの対策をしていれば、「医薬品的問題」の7~8割くらいを安定して得点できるかと思います。最終得点は、だいぶ余裕が生まれるはずです。
「使用(服用)しない」リンク
「使用(服用)しない」の各論点をまとめたページへのリンクです。
くだらない語呂合わせもあるので、憶えにくいものがあれば、活用してください。
- 【語呂あり】使用しない‐アレルギー症状
- 使用しない‐アレルギーの既往歴
- 【語呂あり】使用しない‐基礎疾患
- 使用しない‐次の症状がある人
- 【語呂あり】使用しない‐小児
- 【語呂あり】使用しない‐女性系
- 【語呂あり】使用しない‐飲酒しない
- 【語呂あり】運転操作しない
- 長期連用しない1
- 連用しない各種
- 特徴系+その他【語呂あり】
- 使用(服用)しない 一覧
「相談すること」リンク
「相談すること」の各論点をまとめたページへのリンクです。
時間に余裕があれば、活用してください。時間がないなら、読む必要はありません。
- 相談すること 妊婦等【語呂あり】
- 相談すること 高齢者
- 相談すること 小児
- 相談すること 次の症状がある人
- 相談すること 基礎疾患1
- 相談すること 基礎疾患2
- 相談すること 基礎疾患3
- 相談すること 一覧
個別論点リンク
「適正使用」の「医薬品的な問題」の勉強がある程度済む中盤から終盤にかけて、目を通してください。
こまごましたもの
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
★みんなとシェアする
適正使用対策
├医薬品的な問題 R7 過去問リスト
├医薬品的な問題 R6 過去問リスト
├医薬品的な問題 R5 過去問リスト
├医薬品的な問題 R4 過去問リスト
├医薬品的な問題 R3 過去問リスト
└医薬品的な問題 R2~H28
使用(服用)しない
├アレルギーの既往歴
├基礎疾患
├次の症状がある人
├小児
├女性系
├飲酒しない
├運転操作しない
├長期連用しない
├連用しない各種
├特徴系+その他
└使用(服用)しない 一覧
相談すること
個別論点
登録販売者
概要
独学シリーズ
対策シリーズ
勉強方法
過去問+解説
├チェック問題 過去問リスト
├漢方 過去問リスト
├生薬 過去問リスト
├全ブロック 試験問題 科目別
├「医薬品的な問題」過去問リスト
├「添付文書」過去問リスト
└「資料問題」過去問リスト