第2種電気工事士 学科試験(筆記方式)の要チェックの難問・奇問・珍問・ひっかけ問題リスト
第2種電気工事士の学科試験(筆記方式)のうち、「繰り返し」出題された難問・奇問・珍問と、ひっかけ問題とをリスト化しています。
再度、「難問枠」で出題される公算が「大」なので、見ておくべきです。
運が良ければ、このページで、「1点」取れます。
インデックス
・法令難問
・計測器系
・LED
見たことない写真鑑別
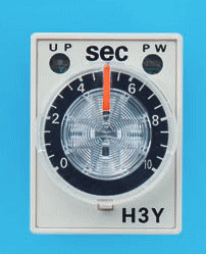

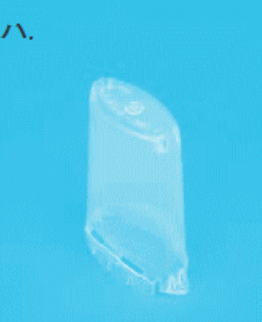
昨今の筆記では、写真鑑別の問題に、上記の画像のような、市販のテキストには載ってない「ブツ」が出題されています。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、再出題に備えて、チェックしておきましょう。
ちなみに、先の画像の「ブツ」は、左から、「ソリッドステートタイマ」、「レーザー墨出し器」、「ナイスハット」といった塩梅です。
では、以下に難儀な写真鑑別の問題を挙げていくと…、
・R4 上期 午後筆記‐第41問:図記号写真鑑別・・・選択肢ハ。
・R4 上期 午後筆記‐第50問:未使用のもの・・・選択肢ロ。
・R3 下期 午前筆記 48問:スイッチ写真鑑別…選択肢ハ
・R3 下期 午前筆記 49問:未使用器具…選択肢イ・ロ・ニ
・2021年度(令和3年度)上期午後 第17問:器具写真鑑別
・2021年度(令和3年度)上期午後 第41問:器具写真鑑別…ハとニ
…となっています。チェックしておきましょう。
なお、テキストには載っているのですが、全く出題されなかったので、受験生に忘れ去られていた器具が突然出題されました。
「2024年度(令和6年度)上期17問:器具写真鑑別」がそうです。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、チェックしておきましょう。
発想系問題
一目見ると無理っぽいのですが、よくよく勉強したことを思い出すと、解ける問題です。今後の流行となりそうなので、必ず解いておきましょう。
ひっかけ問題
ついに、2電工でも、「ひっかけ」問題が出るようになっています。再出題に備えましょう。
「2022年度(令和4年度)下期午前 第27問:クランプ形漏れ電流計」は、脳髄反射で解答してはいけない問題です。
次に、「2021年度(令和3年度)上期午前 第24問:測定器の用途」です。
ほぼ同じ問題が午後の「2021年度(令和3年度)上期午後 第24問:測定器の用途」にも、出題されています。
レア問題(ひさびさ問題)
この数年間、全く出なかった問題です。解けた受験生は、ほとんどいなかったでしょう。
挙げると…、
・R4(2022)上期午前 第20問:簡易接触防護措置の最小高さ
…です。
過去問に出たことは、“古い問題でも”甘く見てはいけないです。試験直前あたりで、押えておきましょう。
法令難問
以下は、ごく稀に出る「法令」の難問です。
まず解けない問題ですが、挙げると…、
…です。念のため、チェックだけは、しておきましょう。
次に、以下に挙げるのは、「法令」の新手の問題です。テキストにも載ってないことも多く、「お手上げ」となります。
ただ、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、解けるようにはなっておきましょう。
・2023年度(令和5年度)上期午前30問:電路の保護対策・・・知らんがな。
・2024年度(令和6年度)上期 第30問:電気設備に関する技術基準を定める省令・・・常識・推理を働かせろってか?
・2024年度(令和6年度)下期 第30問:電圧区分・・・そこの数字を出しますか・・・。
・2025年度(令和7年度)下期 第30問:電気設備に関する技術基準を定める省令・・・2024年度(令和6年度)上期の問題と、同じ。
技能試験的問題
技能で勉強する論点が、筆記にも登場しています。
まず、「リングスリーブ」ですが、ほぼ「定番化」しています。憶えることも少ないし、技能でも“絶対に”使う知識なので、解けるようになっておきましょう。
・R5(2023)上期午後 19問:リングスリーブの種類と刻印
さて、以下の「技能試験的な問題」は、筆記だけの勉強では、かなり厳しいハイレベルなものです。
できそうにないなら、「捨て問」推奨です。傾向把握の一環として、一目見ておいてください。
・2021年度(令和3年度)上期午後 第11問:ねじなしボックスコネクタ・・・ほぼほぼ同じ問題が「R7 上期 第11問」で出ています。
・2021年度(令和3年度)上期午後 第21問:スイッチボックス
アナログ計器とディジタル計器
アナログ計器とディジタル計器についての出題です。文系ド素人には、とても厳しいです。
対策は、「すべての選択肢問いと答えとを憶える」です。
「R3上期午後 筆記27問」に初登場かという問題です。
時間を置かず、「R3上期午後 筆記27問」に、再出題されています。
「R5下期午前 27問:アナログ計器とディジタル計器」に、再登場です。
計測器系の実務問題
文系や、工事ド素人には、厳しい問題が「計測器系」の実務的な問題です。実際の計器の使い方等が細かく問われています。
再出題(問題の使い回し)に備えて、過去問のすべての選択肢に当たっておきましょう。
ぶっちゃけ、選択肢を憶えましょう。
食器洗い機用コンセント
令和1年度(2019年度)の下期筆記にて、初登場。
ごくごく単純に考えれば、解けます。しかし、まあ、初見時は解けないでしょう。
直前期あたりに、問題と答えとを、憶えてしまってください。
小出力太陽光発電
検索でもかけないと解けない難問です。当然、テキストにも出てこないです。
まあ、問題と答えは同じなので、丸ごと憶えましょう。
発電設備の漏電遮断器
いきなりの登場。「使い回し」に備えて、チェックはしておく。
LED
電気一般の「常識」で、難しくはないです。
テキストにはあまり載ってない内容が問われることもあるんで、選択肢は、チェックしておくべきです。
なお、「蛍光灯」は、テキストに載っているので、テキストを精読しておきましょう。
・2021年度(令和3年度)上期午前 第15問:直管LEDランプ
過去問に出たことは、甘く見てはいけない
過去問の問題・選択肢は、可能な限り押さえておくべきです。それをわからせてくれるのが以下の問題です。
直前の上期試験に出てた「EM-CE」が、下期試験で正面から問われた事例。
過去問関連リンク
さて、難問・やや難問の問題をまとめた総リストは、「2電工筆記の難問・やや難問リスト」です。
これらが解ければ合格レベルです。実力試しに活用ください。
複線図の問題は、「2電工筆記「複線図」の過去問リスト」に、まとめています。
筆記の複線図だけ問題演習したい人は、利用してください。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記 | 2019年10月17日 11:25 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
令和元年度(2019年度)の第二種電気工事士:下期筆記試験の総評
「R1下期の筆記試験」ですが、きちんと勉強した受験生なら、穏当に合格できた試験となりました。
下期試験恒例の“難問”は影を潜めて、グーグル検索をしないとわからないタイプの問題は、1問もありませんでした。
こういう試験のときこそ、受からないとダメです。
落ちた人は、猛省してください。実に、もったいない試験でした。
第1部:一般問題
第1部の「一般問題」は、「奇問」が1問出たくらいで、ふつうの出題です。
その「奇問」とは、「11問:食器洗い機用コンセント」です。
正解を選べなくはないですが、これまでにない、新傾向の問題が出題されました。
難問・奇問枠として、今後も顔を出す予感が「大」です。押えておきましょう。
さて、試験問題の大半は、過去問からの問題でしたが、注意すべき問題があります。
「12問:最高許容温度」です。
かなり昔に出ていた論点なのですが、最近では、ずっと、姿を消していたのです。
しかし、復活傾向があります。
2018年(H30)の上期筆記にも、登場しているので、テキストで、押えておくべき論点です。
第2部:配線図
第2部の「配線図」ですが、これまた、特に難しい問題もありませんでした。
受験生泣かせの「複線図」ですが、難しい3路スイッチや4路スイッチ等がなく、オーソドックスな物ばかりとなっています。
「複線図」を少しでも勉強した人なら、1~2点は、上乗せできたはずです。
「図記号」や「写真鑑別」、その他の問題も、まったく問題なしかと思います。
以下、科目別のコメントです。
電気理論
今回の試験の電気理論ですが、一口で言えば、「やさしい」です。
オーソドックスで、かつ、定番の出題で、文系でも、点を確保できたはずです。
まあ、最低でも、「1問:合成抵抗」は、取れたはずです。
小難しいのは、「4問:正弦波交流回路」です。
これは、過去問でも、あまり出なかった問題なので、文系の人は、目を白黒させたことでしょう。
できなくても、仕方のない問題です。
正直、文系は、インピーダンスやらインダクタンスが出たら、脳が腐り始めるので、早々に「捨て問」にして、他の問題で、活路を見出しましょう。
配電理論
「配電理論」ですが、例年通りの出題であり、ちゃんと過去問を消化していれば、正解できる問題ばかりでした。
「7問:電圧降下」などは、公式さえ憶えていれば、文系でも取れます。
公式の暗記で取れる問題は、貪欲に、狙って行きましょう。
「捨て問」がビシバシできるようになります。
配線設計
「配線設計」ですが、最近の試験傾向からすると、ほぼ『固定化』しているといっていいです。
「8問:許容電流計算」や、「9問:分岐許容電流」、「10問:分岐回路設計」といった問題は、ほぼ、毎回出題されています。
どれも、「表」の数字を暗記すれば、点が取れます。
暗記で取れる問題こそ、文系の本領発揮。
通勤・通学時に憶えるのが一番です。
なお、再び、問われるようになったのが、「15問:遮断時間」です。
H30上期筆記にも、同様の問題が出題されています。
あまり出ないですが、「表」の暗記で1点なので、文系は、貪欲に取るようにしてください。
電気機器・工具材料
「13問:ノックアウトパンチャ」は、ストレートな出題です。
これまでになかった出題形式なので、この種の“一直線型”の問題が増えるかもしれません。
直接的に問われても、答えられるようになりましょう。
「14問:スターデルタ始動」は、「誘導電動機」のお馴染みの論点です。
とはいえ、当該誘導電動機の論点は、文系には敷居が高いので、何回テキストを読んでも、(???)なら、「捨て問」でもよいでしょう。
「工具材料」の写真鑑別は、基礎的なものですが、「16問:材料写真」には、注意してください。
最近は、「圧着端子‐圧着工具」と「圧縮端子‐圧縮工具」の出題が、目立つようになっています。
昔の試験ではそう出なかったのですが、昨今になって、チョコチョコと、親戚のおじさんのように、顔を出すようになっています。
個人的には、要注意工具なので、テキストでシッカリと、特徴を押さえておいてください。
電気工事・検査
電気工事と検査ですが、どれも、基礎的な出題で、特に、手こずることなく、解答できたと思います。
面倒なのは、「23問:電磁的不平衡」くらいです。
わからないなら、「捨て問」です。
法令
当該年度の法令も、特に、問題ないです。
本当に定番のものばかりで、ぜんぜん解ける問題です。
1問たりとも、落とさないようにしましょう。
配線図の図記号
特に、問題ありません。
「35問:ペンダント図記号」で、ドキッとするくらいです。
配線図の写真鑑別
ぜんぶ、テキスト・過去問で、お馴染みのものです。
十分に、点数は確保できたはずです。
ただ、「46問:図記号器具」の選択肢「イ」と「ロ」には、注意です。
今後、こういう出し方が増える感があるので、「出され方」を、押さえておくべきです。
テキストのコメントまで、キッチリ押えておきましょう。
配線図の複線図
先に述べたように、三路スイッチなど、難しいものがなかったので、取れる問題が多かったです。
余裕のある人は、取れないわけじゃないので、技能試験の予習を兼ねて、「複線図」を勉強してみてください。
まあ、無理なら無理なので、できそうにないなら、「捨て問」です。
わたしが受験生当時は、「複線図」は、捨ててました。失点は、「電気理論」などでカバーしました。
なお、「複線図」が書けないと、技能試験には“絶対に”受からないので、どのみち、技能で、しこたま勉強することになります。
まとめ
令和元年の下期筆記は、ざっと、こんな次第です。
正直、勉強が足りない人でも、そこそこ、通ったのではないか?と思います。
ただ、過去問演習においては、油断しないようにしてください。
当該年度の試験問題は、「やさしい」部類に入ります。
んなもんで、解けて当然・合格点が取れて当然です。
今後の試験では、もっと難しい問題が出ても、まったくおかしくないのです。
実際に、応用的・複合的な問題が、ドンドコ登場した試験もあるのです。
当該過去問で、合格点(6割正解)が取れたといっても、油断してはいけません。
どの問題も、基礎・基本的なものばかりなので、大半の問題を、解けるようになっておきましょう。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 2電工筆記 | 2019年10月12日 5:54 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
宅建無料ノート:宅建業者と宅建士の横断まとめ
このページは、「宅建業者」と「宅建士」を、横断的にまとめたページです。
復習や知識の整理に活用ください。また、ひっかけポイントも多々あるので、知らないものは、優先的に押えてください。
定義
“当たり前”と思いがちですが、だからこそ、狙われています。シッカリ押えておきましょう。
「宅建業者」とは、免許を受けて、宅建業を営むものをいいます。
なお、国・地方公共団体、それらに準じる集団(住宅供給公社など)は、宅建業の適用がないので、免許なくして、宅建業を営むことができます。
「宅建士」とは、「宅建士証の交付を受けた者」です。
単に、試験に合格した者とか、宅建士資格登録簿に登録された者は、宅建士でないので注意してください。
ちなみにわたしは、単なる合格者なので、宅建士ではありません。
業務内容
「宅建業者」の業務は、宅地建物の売買・交換・賃借の代理・媒介を行うものですが、『自ら賃借』を除きます。
当該自ら賃借が、超絶ド頻出事項です。
どんな風に問われても、判別できるようになっておきましょう。
たとえば、「宅建業者Aは、自社物件のビルを貸した際、35条書面を交付し、宅建士に説明させた」とあれば、「×」です。
この場合、「自ら賃借」なので、宅建業法の適用はなく、説明義務も交付義務もありません。
「宅建士」の業務は、3つあって、「重要事項の説明(35条)」「重要事項説明書への記名押印」「37条書面の記名押印(35条)」となっています。
「説明」と「記名押印」が、宅建士の業務です。
書類の交付は、“宅建業者”の義務なので、注意してください。
んで、よくある「ひっかけ」ですが、「37条書面」には、宅建士の説明義務が無いので、注意してください。
種類
「宅建業者」には、知事免許と大臣免許があります。
知事免許でも、全国で営業できます。
んで、大臣免許だと、「経由申請」があるので、注意してください。
参考:経由申請・直接申請・書換え・再交付・返納・廃業等の届出・死亡等の届出の横断まとめ
「宅建士」には、「専任の宅建士」と「一般の宅建士」とがあります。
専任の宅建士と一般の宅建士に、業務上の違い(できる・できない)はありません。両者とも同じです。
専任の宅建士は、主として、「事務所の設置要件」の規定です。
参考:専任宅建士のポイント
申請書のポイント
「宅建業者」の申請書に、代表者・役員、専任の宅建士の「住所」記入欄はありません。
よって、「宅建業者名簿」に、代表者・役員、専任の宅建士の「住所」は記載されず、従って、引越し等をしても、変更届を出す必要はありません。
「宅建士」の申請書には、宅建士個人の「住所」記入欄があります。
よって、「宅建士資格登録簿」には、宅建士の住所が登載され、引越し等すれば、変更の登録をする必要があります。
また、宅建士の申請書には、「本籍」もあります。
このあたりは、クソ細かいので、「宅建士の登録(宅建士資格登録簿・変更の登録・登録の移転)の横断まとめ」を、一読ください。
実務経験
「宅建業者」は、実務経験が無用です。
実務の有無で、免許が拒否される等は、ありません。
よって、宅建業者に、実務講習等も、ありません。
「宅建士」は、2年以上の実務経験が必要です。
実務経験がないと、宅建士資格登録簿に、登録されません。
ない人は、「登録実務講習」を受ける必要があります。
未成年者
「宅建業者」は、“ふつうの未成年者”でも、法定代理人が欠格要件に該当しないなら、免許を受けることができます。
ふつうの高校生でも、宅建業者になれる、ってな次第です。
「宅建士」は、“ふつうの未成年者”だと、なれません。
免許のように、法定代理人が欠格要件に該当しなくても、なれません。
このあたり、実にややこしいので、「未成年者の横断まとめ」を一読願います。
公開
「宅建業者」の「宅建業者名簿」は、一般公開されます。
また、「従業者名簿」も公開されます。請求があれば、閲覧させないといけないからです。
対して、「帳簿」は、非公開です。
「宅建士」の「宅建士資格登録簿」は、非公開です。
参考:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ
変更届系
「宅建業者」の変更届等は、「その日より30日以内」に行います。
「宅建士」の登録の変更は、「遅滞なく」となっています。
有効期限1
「宅建業者」の免許は、「5年」有効です。
「宅建士」の宅建士証は、「5年」有効です。
なお、「宅建士」の「宅建士資格登録簿」の登録は、一生有効です。
資格登録は一生で、宅建士証は5年と、整理して憶えましょう。
有効期限2
「宅建業者」が「免許換え」を行い、新しく免許を受けた場合、そのときから「5年」となります。
つまり、旧免許の有効期限を、引き継がない、といった次第です。
「宅建士」が「登録の移転」を行い、新たな宅建士証の交付を受けても、有効期限は、旧宅建士証の有効期限となります。
つまり、旧宅建士証の有効期限を、引き継ぐ、といった次第です。
なお、当該免許換えは、宅建業者の義務です。やらないと、免許取消となります。
んで、当該登録の移転は、「任意」です。宅建士の就職等の便宜を図る規定なので、義務ではありません。
更新手続き
「宅建業者」は、免許の有効期限の90日前から30日に申請します。
よって、提出期間は、「60日」となります。また、期限ギリギリに出すものではないことがわかります。
憶え方は、「ごくろーさん」で、「5、9、6、3」です。(5は、免許の期限5年です。)
なお、先に見たように、免許の更新に当たって、講習を受ける必要はありません。
車の免許や、宅建士との混同を狙ってくるので、注意してください。
「宅建士」は、申請前6月以内の「法定講習」を受けてから、行います。
免許のように、○日前にやるという規定ではないので、注意してください。
極端に言えば、新しい宅建証の交付を受けて、7~8ヶ月経過後、法定講習を受ければ、有効期限内であっても、新しい宅建士証を交付申請ができます。
破産
ひっかけポイントです。
「宅建業者」が破産すると、「破産管財人」が、廃業等の届出を行います。
「宅建士」が破産すると、「本人」が、死亡等の届出を行います。
届出権者が異なるので、注意してください。
なお、届出期間は、「その日から30日以内」と、同じです。
ちなみに、個人事業者の宅建業者と宅建士の死亡の場合は、「知ったときから」となっています。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐横断まとめ, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年10月5日 11:15 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |

