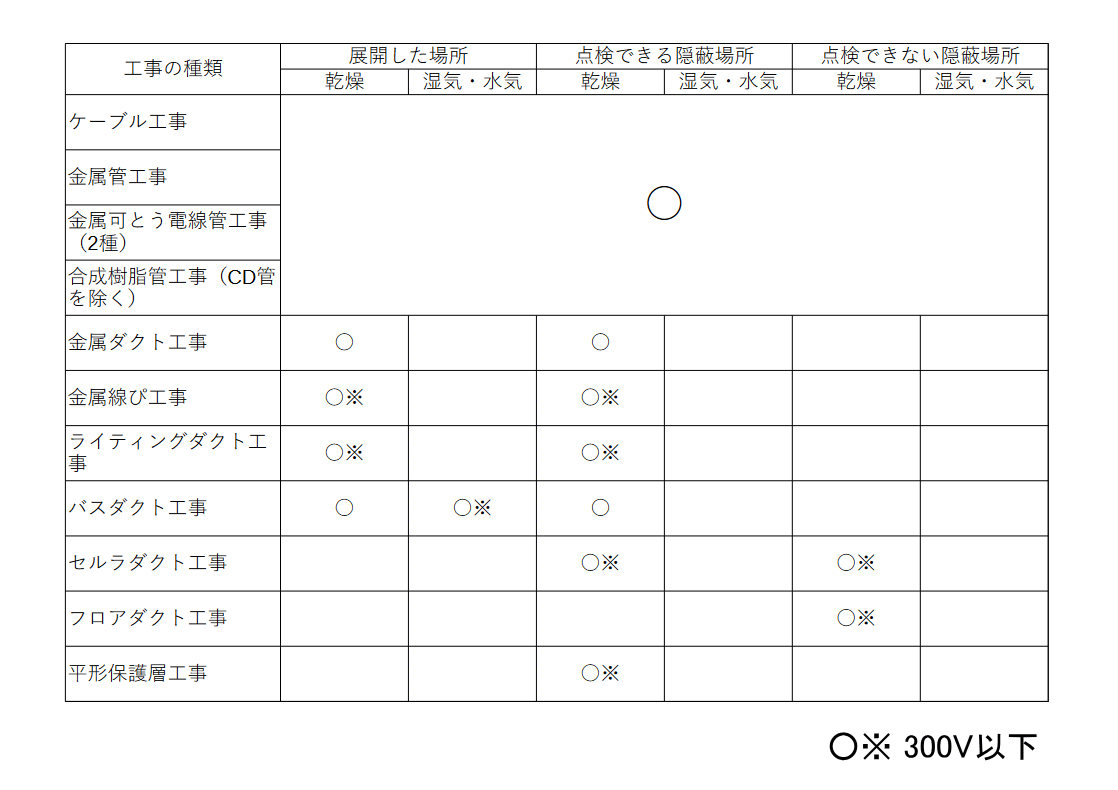変更届のまとめ+語呂合わせ‐二級ボイラー技士の法令
「法令」の論点「変更届」ですが、効率が良いのは、「変更届は無用」の方を憶えることです。
テキストには、長々と書かれていますが、まずは、届出をしなくてよいケースを、憶えましょう。少ない労力で点が取れます。
変更届が無用
変更届が無用なのは…、
・水管
・煙管
・水処理装置
・給水装置
・空気予熱器
…となっています。
最初の2つの「水管」と「煙管」には、注意してください。
「水管」と「煙管」は、ボイラーにおいて、主要な部分ですが、任意に長さを変えられるため、変更届が必要ありません。
間違えやすいので、注意してください。
語呂合わせ
変更届は、「水と空気と煙は、要らん」くらいの語呂で、憶えるとよいでしょう。
語呂ですが…、
水・・・“水”管、“水”処理装置、給“水”装置
空気・・・“空”気予熱器
煙・・・“煙”管
…といった寸法です。
変更届が必要
変更届が必要な箇所ですが、よくよく考えれば、すぐわかります。
ボリュームもそこそこあるので、余裕のある人だけ、押えればいいでしょう。チェック用に見ておいてください。
変更届が必要な箇所は…、
胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー
エコノマイザ(節炭器)、過熱器
燃焼装置
据付基礎
…となっています。
どれも、ボイラーの重要な部分なので、大丈夫かと思います。
付属装置に注意!
付属装置のエコノマイザ(節炭器)、過熱器は、注意してください。
この2つは、変更届が「必要」です。
対して、同じ付属装置である「空気予熱器」は、届出が「無用」です。
以下のように…、
エコノマイザ(節炭器)、過熱器・・・変更届必要
空気予熱器・・・変更届無用
…整理して憶えましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: ボイラー技士, ボイラー技士‐法令, ボイラー技士‐語呂合わせ | 2019年10月23日 9:22 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
伝熱面積(丸ボイラー,鋳鉄製ボイラー,水管ボイラー,貫流ボイラー,電気ボイラー)のまとめ+語呂合わせ‐二級ボイラー技士の法令
「法令」の論点「伝熱面積」ですが、単純に、暗記なだけです。
試験では、「伝熱面積に算入するもの」と「伝熱面積に算入しないもの」を問うのがほとんどです。
試験では、後者の「伝熱面積に算入しないもの」がよく出るので、こちらを優先してください。
伝熱面積に算入しないもの
伝熱面積に算入しないものは…、
・水管ボイラーのドラム(水ドラム・蒸気ドラム)
・空気予熱器
・エコノマイザ(節炭器)
・過熱器
…となっています。
語呂合わせですが、「泥水、食えるか!」で、憶えます。
「泥水、食えるか!」の詳細
当該語呂合わせの「泥水、食えるか!」ですが、詳細は…、
泥水→ドロミズ→ドロ水→“ド”ロ“水”→“水”管ボイラーの“ド”ラム
食→く→空気予熱器の「く」
え→エコノマイザの「え」
か!→過熱器の「か」
…となっています。
補足ですが、「水管ボイラー」には、注意してください。
水管ボイラーのドラムには、水ドラムと蒸気ドラムが該当します。
これら、水管ボイラーの水ドラムと蒸気ドラムは、伝熱面積に参入されません。
他のボイラーだと、ドラムが算入されるものもありますが、水管ボイラーに到っては、算入されません。
ひっかけ問題として出しやすいので、「水管ボイラー・・・ドラム・・・算入しない」と、正確に暗記しましょう。
次に、「食えるか!」の「空気予熱器・エコノマイザ・過熱器」は、それぞれの頭文字なので、大丈夫かと思います。
強いて注意するなら、「エコノマイザ」くらいです。
当該エコノマイザは、別名の「節炭器」で出題される可能性があるので、併せて、押えておきましょう。
伝熱面積に算入するもの
さて、次は、「算入するもの」について、見ていきましょう。
テキストには、細かい記述がありますが、試験に出るポイントは、以下です。
水管ボイラー(貫流ボイラーを除く)
水管ボイラーで、伝熱面積に参入されるのは、「水管」や「管寄せ」などです。
逆に、先述したように、水管ボイラーの水ドラムと蒸気ドラムは、伝熱面積に参入されません。
「水管」ですが、「ひれ付き水管」や「耐火煉瓦で覆われた水管」でも、伝熱面積に参入されます。
当該論点で最もよく問われるのが「水管ボイラー」なので、される・されないを、正確に暗記です。
ところで、「水管」ですが、「外径側」の面積で計算します。
水管の周りに燃焼ガスがあるからです。これも、出ます!
貫流ボイラー
貫流ボイラーは、水管のうち、燃焼ガスに触れる面の面積が、伝熱面積に参入されます。
貫流ボイラーですが、試験的には、ざっと読むだけでいいです。
問題を作り難いため、あまり出ないからです。
丸ボイラー・鋳鉄製ボイラー
丸ボイラー・鋳鉄製ボイラーですが、伝熱面積の対象は、「燃焼ガスに触れる面」です。
試験に出るのは、伝熱面積の対象です。
煙管の場合、管内に燃焼ガスが通るので、「内径側」の面積で計算します。
水管の場合、水管の外に燃焼ガスが通るので、「外径側」の面積で計算します。
電気ボイラー
電気ボイラーの伝熱面積は、「電力設備容量20kWを、1m2」と計算します。
これは、伝熱面積の論点ではなく、「ボイラー技士の選任」等で、出題されます。ガチ暗記しておきましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: ボイラー技士, ボイラー技士‐法令, ボイラー技士‐語呂合わせ | 2019年10月23日 9:13 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
施工場所と工事種類(合成樹脂管工事、金属管工事、2種金属可とう電線管工事、ケーブル工事)の語呂合わせ‐2電工学科
第2種電気工事士の学科試験の「電気工事」の「低圧屋内配線の施設場所による工事の種類」の憶え方等についてです。
要は、上記「表」を憶える論点です。
本ページでは、当該表の上から4つの「ケーブル工事、金属管工事、金属可とう電線管工事(2種)、合成樹脂管工事(CD管を除く)」について述べています。
当該ケーブル工事、金属管工事、金属可とう電線管工事(2種)、合成樹脂管工事(CD管を除く)の「4つ」は、「すべて工事可能」なので、まとめてドンで憶えるのがラクです。
本ページで述べる「語呂合わせ」は、選択肢を即答できるので、押さえておきましょう。
さて、対して、金属ダクト工事、金属線ぴ工事、ライティングダクト工事、バスダクト工事、セルラダクト工事、フロアダクト工事、平形保護層工事については、「施工場所と工事種類(金属ダクト工事、金属線ぴ工事、ライティングダクト工事、バスダクト工事、セルラダクト工事、フロアダクト工事、平形保護層工事)の語呂合わせとまとめ」の方を、参考にしてください。
ぜんぶ工事可能
先の「表」の“大きな○”を見てもらえばわかるように、ケーブル工事、金属管工事、金属可とう電線管工事(2種)、合成樹脂管工事(CD管を除く)の4つの工事は、どこでも工事が可能となっています。
以下、4つの電気工事の語呂合わせです。
合金2ヶ
結論から言うと、「合成樹脂管工事(CD管除く)、金属管工事、2種金属可とう電線管工事、ケーブル工事」の4つの語呂合わせは、『合金2ヶ』です。
語呂の詳細ですが…、
合・・・合成樹脂管工事(CD管除く)
金・・・金属管工事
2・・・2種金属可とう電線管工事
ヶ・・・ケ・・・ケーブル工事
…といった寸法です。
この語呂合わせがあれば、選択肢の1~2つを、即断できます。
過去問参考
「施工場所と工事種類」ですが、ほぼ毎年の如く出ていて…、
…といった出題で出ることが多いです。
先の4つの工事は、ほぼほぼ、試験問題に登場しています。
よって、選択肢に、「合金2ヶ」の合成樹脂管工事(CD管除く)、金属管工事、2種金属可とう電線管工事、ケーブル工事があれば、全部工事可能と即答できます。
合成樹脂管工事は、CD管ダメ
語呂の「合」は、「合成樹脂管工事」なわけですが、重要な条件があります。
「CD管を除く」のところです。
当該CD管は、「コンクリートの埋め込み配線」に用いられます。
言うなれば、コンクリート専用なわけで、よって、他の工事では使えないといった寸法です。
本試験では、当該CD管で出題されることもあるので、注意してください。
たとえば、「乾燥した場所に合成樹脂管工事(CD管)を行った」などと出ます。
合成樹脂管は、「すべてOK」ですが、例外的に、CD管はコンクリート専用なので、「×」となります。
すべてOKな合成樹脂管は、「PF管」「VE管」です。「CD管」は別、と整理して憶えましょう。
金属可とう電線管工事は、2種!
語呂の「2」は、「“2種”金属可とう電線管工事」に該当するわけですが、「2種」なので、注意してください。
当該には、「1種」と「2種」とがありますが、すべての場所で電気工事が可能なのは、「2種」のほうです。
本試験にて、ここが突っ込まれたことはまだないと思いますが、いつ出てもおかしくないので、押さえておくべきです。
このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、再確認してください。
補足リンク:特殊な場所
なお、似たような論点に「特殊な場所と工事種類」というものがあります。
やることは、ほとんど同じです。
「特殊な場所(爆燃性粉じん,可燃性ガス,可燃性粉じん,危険物)の工事と施行場所の語呂あわせとまとめ」にまとめているので、活用願います。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 2電工‐語呂合わせ, 2電工筆記, 2電工筆記・工事 | 2019年10月18日 11:12 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |