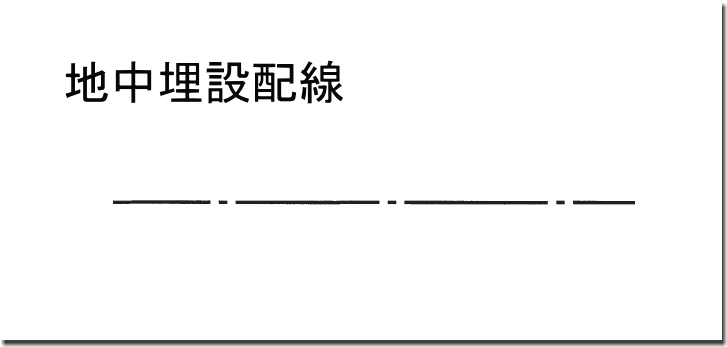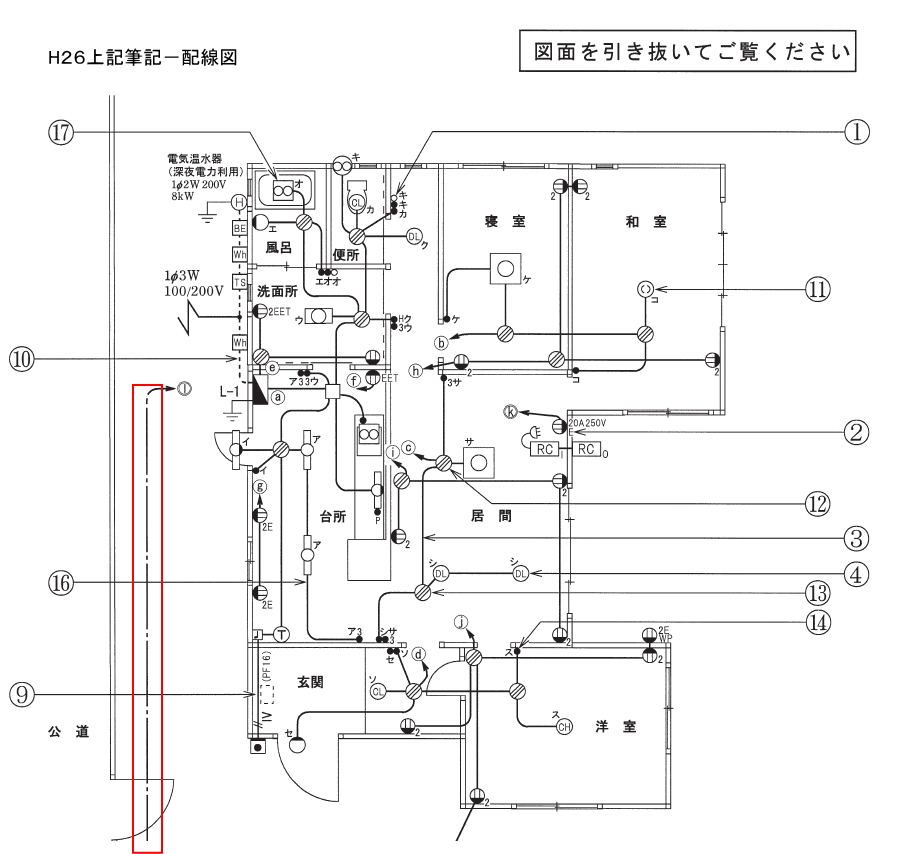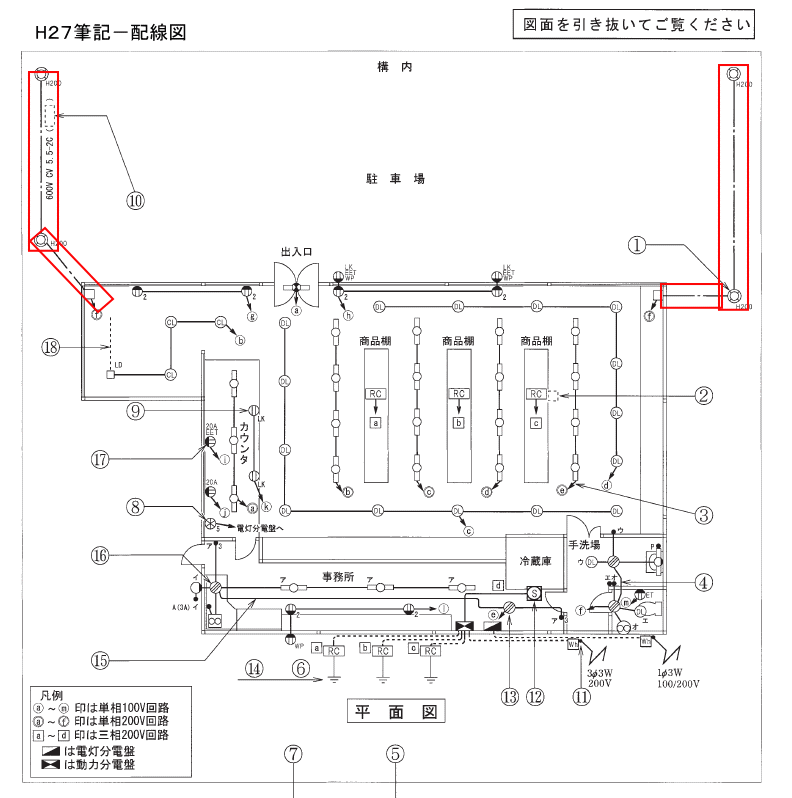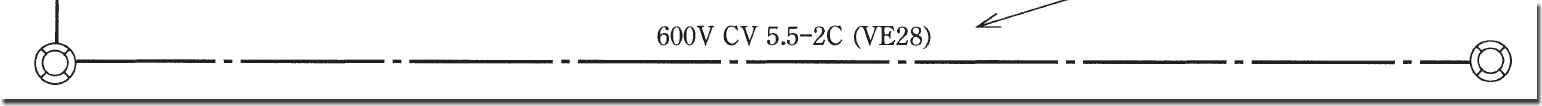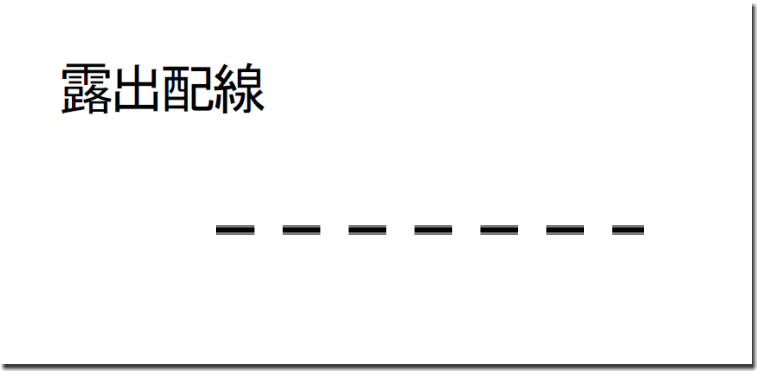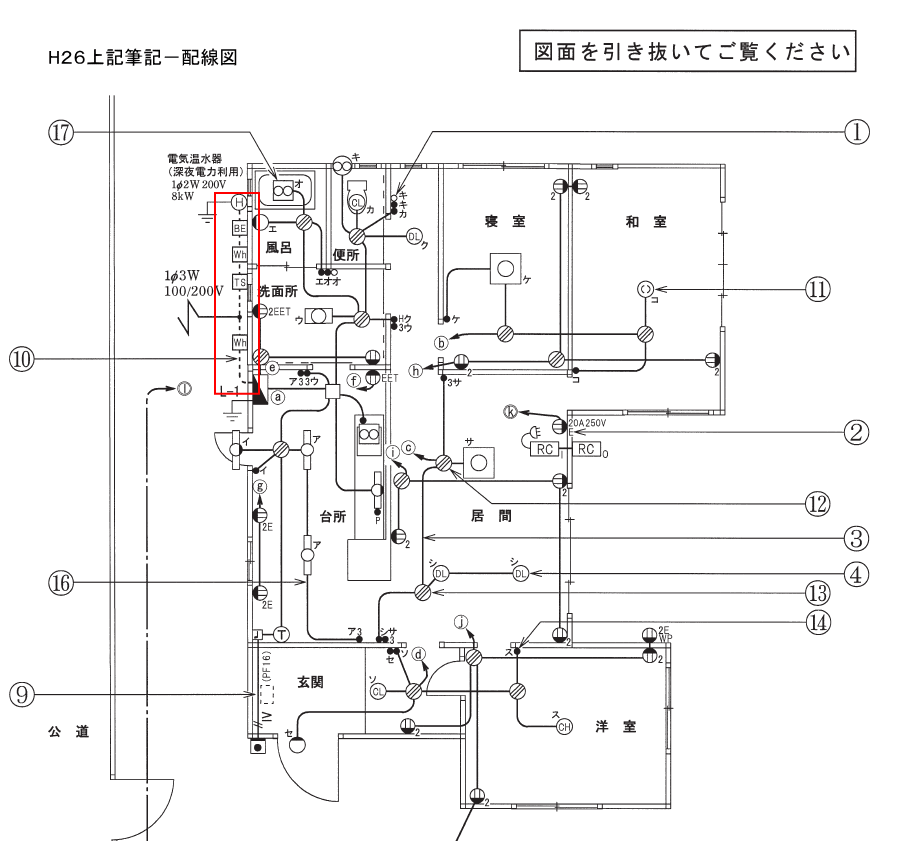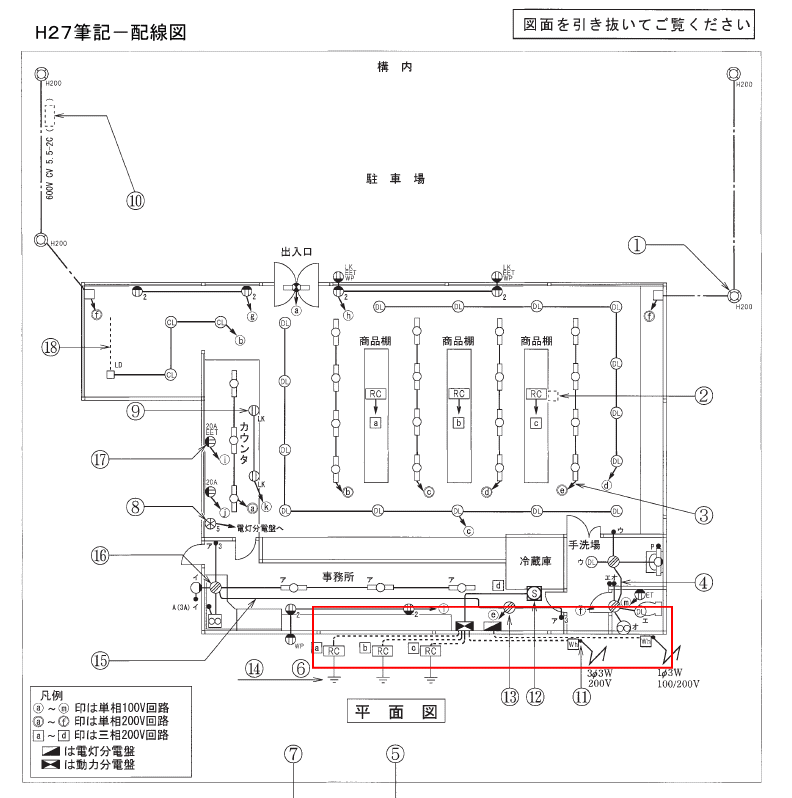地中埋設配線(かえる顔)の図記号の憶え方‐第2種電気工事士・筆記
このページでは、「地中埋設配線」の憶え方を述べています。
かなり“こじつけ”が入っているので、公言すると笑われます。試験用と割り切ってください。
他の配線の図記号は、「ブログ記事:配線用図記号」を、一読ください。
地中埋設配線
「地中埋設配線」ですが、「露出配線(点線)」と同様に、あまり使われない配線です。
「配線図」の資料を見てみましょう。
過去問の資料チェック
H26筆記試験の配線図です。
H27筆記試験の配線図です。
資料を一目見ればわかりますが、圧倒的に使われている「天井隠ぺい配線(実線)」と比べれば、「地中埋設配線」は、ほとんどありません。
しかし、試験では、実によく問われる図記号となっています。
あまり馴染みがないから、出題者は出しやすいかと思われます。
よって、「地中埋設配線」も、遺漏なく、憶えておく必要があります。
憶え方‐かえる顔
さて、「地中埋設配線」ですが、だいたい、下の画像のように、資料には現れます。
この画像から、一部だけ、抽出してみましょう。
じぃっと見てください。
もう一度、じぃっと見てください。
よーく見ると、「かえる」の顔のように、見えてきます。
見えてこない人は、見えてくるまで、眺め続けてください。
最後まで、見えない人は、病院に行ってください。
こうした次第で、憶え方としては、「地中埋設配線→冬眠で地中に埋まっている“かえる”の顔」ってな感じで、頭に入れます。
ひどい「こじつけ」と思われるでしょうが、かなり、記憶のノリはいいです。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記, 2電工筆記・図記号 | 2019年10月25日 1:12 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
露出配線(点線)の図記号の憶え方‐第2種電気工事士・筆記
このページでは、「露出配線(点線)」の憶え方を述べています。
かなり“こじつけ”が入っているので、公言すると笑われます。試験用と割り切ってください。
他の配線の図記号は、「ブログ記事:配線用図記号」を、一読ください。
露出配線(点線)
一口で言うと、先の画像のように、露出配線は、「点線」です。
過去問の「配線図」の資料を見てみましょう。
H26筆記試験の配線図です。
H27筆記試験の配線図です。
資料を一目見ればわかりますが、「点線」は、ほとんどありません。
先の資料でも、1箇所くらいしかありません。
(なお、H27筆記の⑱の点線は、LDの傍記があるので、「ライティングダクト」です。)
憶え方
憶え方としては、「露出配線は、点々としている」くらいに、憶えます。
基本、電気の流れる配線は、人の手が触れないように、「隠ぺい」されるのが、常です。
「露出配線」は、その名の通り、露出していて危険です。よって、滅多矢鱈に施工されず、先の資料のように、そんなに数がないです。んなもんで、「点々」としかないってな塩梅です。
こじつけですが、「露出配線→数少ない→点々としている→点線」くらいに、頭に入れましょう。
以上は、わたしの憶え方なので、公言はしないでください。恥をかきます。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記, 2電工筆記・図記号 | 2019年10月25日 1:10 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
ボイラーの検査(溶接検査,構造検査,落成検査,性能検査,使用検査,使用再開検査,変更検査,)のまとめ‐二級ボイラー技士の法令
「法令」の論点「ボイラーの検査」ですが、すべてを憶える必要はありません。
出るものに絞って、憶えて行きましょう。以下に、各検査について、見ていきます。
溶接検査・・・無用
「溶接検査」ですが、溶接作業に着手する前に行う検査です。
言うなれば、ボイラーの製造時の検査であり、運用側の二級ボイラー技士とは関係ないので、試験には出ません。
こういうのもある、くらいに押えておきましょう。
構造検査・・・無用
「構造検査」ですが、ボイラーを製造したときに行う検査です。
先と同じように、言うなれば、ボイラーのメーカーで行う検査のため、二級ボイラー技士とは、そう関係がありません。
よって、選択肢の一部くらいに出るのが関の山。
こういうのもある、くらいに押えておけばよいでしょう。
落成検査・・・重要
「落成検査」ですが、ボイラーの設置工事が終了した後に、受ける検査です。
二級ボイラー技士も関わってくるので、試験には出ます。
「落成」とは、「工事が完了して建築物などができあがること」を意味します。
「設置」とよく似ているので、「言葉の意味のつながり」で、「設置・・・落成検査」と憶えるといいでしょう。
さて、当該落成検査ですが、設置工事後の検査です。
んで、ボイラーの設置には、当該ボイラーが技術的基準に適っているかどうかの検査を、前もって、受ける必要があります。
それが、先に見た「構造検査」や、次に見る「使用検査」となっています。
んで、当該落成検査にパスすると、知事より、「ボイラー検査証」が交付されます。
使用検査・・・最も重要
一番よく出るのが、「使用検査」で、最も重要です。
「使用検査」ですが…、
「ボイラーを輸入した者。」
「構造検査または使用検査後、1年以上、設置されなかったボイラー(保管良好なら2年以上)を、設置しようとする者。」
「使用を“廃止”したボイラーを、再び設置し、または、使用する者」
…が受ける検査です。
使用検査キーワード
「使用検査」の最重要キーワードは、「廃止」です。
徹底して、「使用検査・・・廃止」を、ガチ暗記してください。
本試験のひっかけ問題で、「使用を休止したボイラーを設置するには、使用検査を受ける必要がある」などと、よく出題されるからです。
使用検査は、“廃止”したボイラーが対象です。
「ボイラーを輸入した者」も、よく出ます。
「ボイラーを輸入した者は、構造検査を受けなければならない」といった出題が典型例です。
「×」です。受けるのは、「使用検査」です。
「1年無設置」も、出ます。
「1年以上、設置されなかったボイラーを、設置しようとする場合は、使用再開検査を受けなければらない」などが、出題例です。
「×」です。受けるのは、「使用検査」です。
『使用検査・・・輸入・1年無設置・廃止』と、ガチで暗記してください。
使用再開検査・・・とても重要
「使用再開検査」ですが、「使用を休止したボイラーを、再び使用するとき」に、受けなければならない検査です。
キーワードは、「休止」です。
整理して憶えてください。
「廃止ボイラー」は、「使用検査」です。
「休止ボイラー」は、「使用再開検査」です。
ひっかけ問題で、定番なので、ガチで暗記です。
先に見た「使用を休止したボイラーを設置するには、使用検査を受ける必要がある」などと、出題されても、「休止=使用再開検査」だと、即答できるようになっておきましょう。
性能検査・・・とても重要
「性能検査」ですが、「ボイラー検査証の有効期間が満了する前」に、受ける検査です。
要は、ボイラー検査証の更新をするときに、受ける検査です。
キーワードは、「ボイラー検査証の有効期間」です。
ひっかけ問題で、「ボイラー検査証の有効期間を超えて使用する場合は、使用検査を受けないとならない」などと、出ます。
「×」です。
キーワードの「ボイラー検査証の有効期間」がある場合、「性能検査」です。
性能検査の他の論点
「性能検査」は、より突っ込んだ出題があります。
検査の前は、当然ですが、ボイラーと煙道を冷却し、掃除しておく必要があります。
そして、検査対象ですが、「ボイラー、ボイラー室、配管の配置状況、据付基礎、燃焼室、煙道の構造」について、行われます。
太線の「配管の配置状況、据付基礎」は、よくよく登場するので、正確に押えてください。
変更検査・・・それほど
「変更検査」ですが、「ボイラーの変更工事が終了したとき」に、受ける検査です。
当該変更検査は、あまり問われません。
「変更届」の方がよく問われるためです。
テキストを、ざっと読んでおけば、大丈夫です。
なお、「変更届」については、「変更届のまとめ+語呂合わせ」を、一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: ボイラー技士, ボイラー技士‐法令 | 2019年10月23日 9:26 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |