人体 一問一答
薬が働く仕組み 総論・前文
テキストのページは、「Ⅱ 薬が働く仕組み 総論・前文」です。
んでは、スタート。
『医薬品の作用には、有効成分が消化管などから吸収されて循環血液中に移行し、全身を巡って薬効をもたらす局所作用と、特定の狭い身体部位において薬効をもたらす全身作用とがある。』
正誤はこちら。
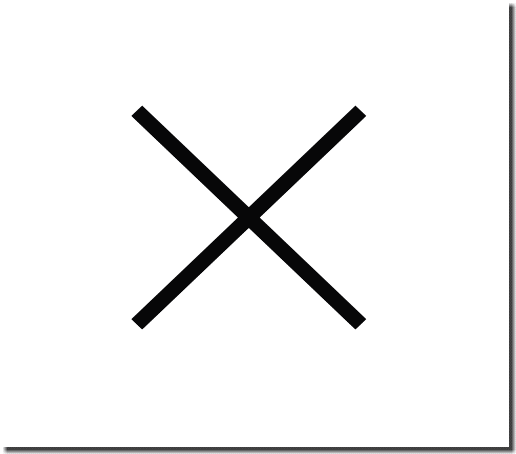
誤った記述です。
すぐわかる間違いですね。語句が入れ替えられています。
正しい記述は、「医薬品の作用には、有効成分が消化管などから吸収されて循環血液中に移行し、全身を巡って薬効をもたらす全身作用と、特定の狭い身体部位において薬効をもたらす局所作用とがある」です。
本節の基本用語なので、しっかり押えておきましょう。
さて、本節の「薬の働く仕組み」ですが、凝った出題があまりないところです。
テキストを読んでその内容を理解しておけば、大概は解けるかと思います。
『内服した医薬品が全身作用を現わすまでには、消化管からの吸収、代謝と作用部位への分布という過程を経るため、ある程度の時間が必要であるのに対し、局所作用は医薬品の適用部位が作用部位である場合が多いため、反応は比較的速やかに現れる。』
正誤はこちら。
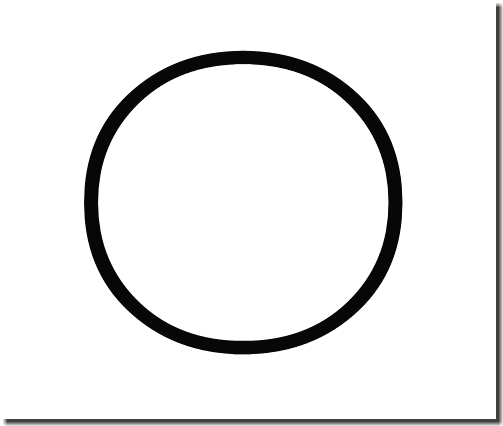
正しい記述です。
テキストそのまんまの記述です。
実体験からもそうかと思います。
かぜ薬などは飲んでから時間が経って効き始めますが、虫刺されとかは塗ったらすぐ効きますよね。
さて、こういう長文のメンドクサイ出題も見るようになっています。
出題の意図は、受験生の頭を疲れさせることです。徹底的にテキストを読み込んで、長い記述に慣れておきましょう。
『内服薬は全身作用を示すものが多いが、膨潤性下剤や生菌製剤等のように、有効成分が消化管内で作用するものもあり、その場合に現れる作用は局所作用である。』
正誤はこちら。
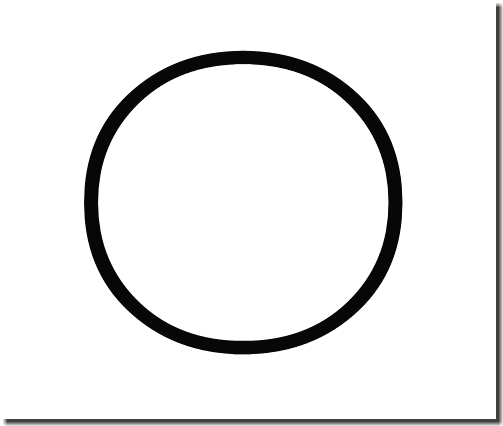
正しい記述です。
そうですよねーという問題です。
先述したように、本節では、そう凝った出題がなく、大半は、テキストの記述そのまんまが多いです。
だからこそ、なんでもない記述まで、出題される可能性が高いのです。
遺漏なく、テキストを精読しておきましょう。
『胃腸に作用する薬であっても、有効成分が循環血液中に入ってから薬効をもたらす場合には、その作用は全身作用の一部であることに注意が必要である。』
正誤はこちら。
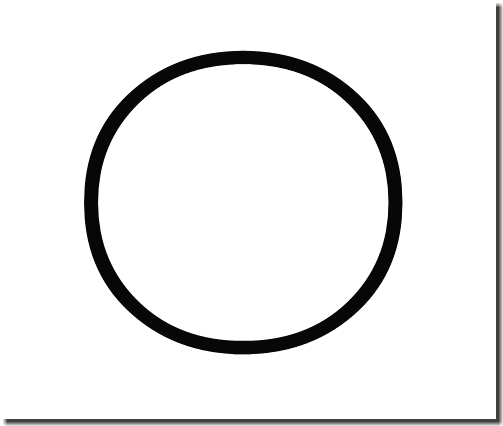
正しい記述です。
手引きそのまんまの記述です。
テキストを精読しておきましょう。
『内服薬の場合、適用部位に対する局所的な効果を目的としていることが多い。』
正誤はこちら。
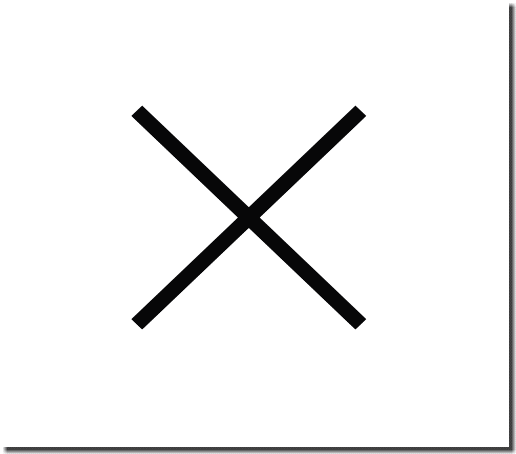
誤った記述です。
間違っているのは、「内服薬」のところです。
正しくは、「外用薬」です。
きちんとテキストを読んでいれば、問題文のおかしさに気づいたかと思います。
『坐剤、経皮吸収製剤等では、適用部位から吸収された有効成分が、循環血液中に移行して全身作用を示すことを目的として設計されたものも存在する。』
正誤はこちら。
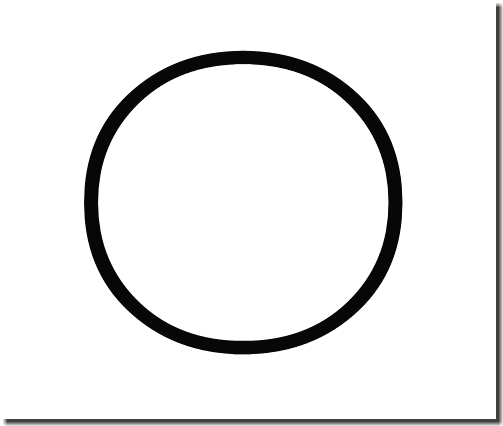
正しい記述です。
かぜ薬の坐剤とかをイメージして、“こういうもの”として押えておきましょう。
選択肢の1つに、ポコッと出そうですね。
『副作用には、全身作用によるものがほとんどで、局所作用によるものはない。』
正誤はこちら。
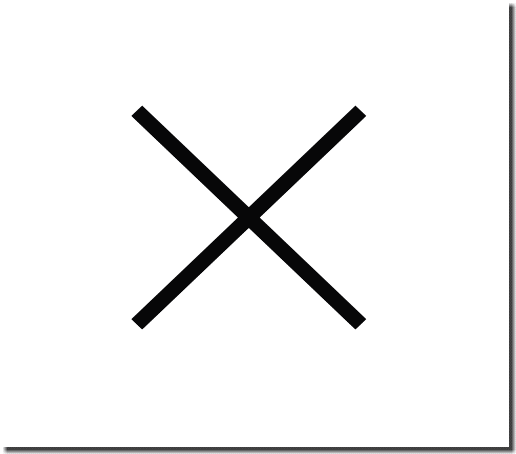
誤った記述です。
全体的に間違ってます。
正しい記述は、「副作用にも、全身作用によるものと局所作用によるものとがある」です。
たとえば、接触皮膚炎(かぶれ)なんかは、局所作用の副作用の典型ですよねー。
うーん、試験に出るとしたらこのくらいのレベルかなと思います。(問題作れない。)
『局所作用を目的とする医薬品によって全身性の副作用が生じたり、逆に、全身作用を目的とする医薬品で局所的な副作用が生じることもある。』
ページリンク
「一問一答:次のページ」へ。
補足リンク
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
本章インデックス・・・「人体 インデックス」
本節インデックス・・・「薬が働く仕組み インデックス」
こまごましたもの
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
★みんなとシェアする
薬の働き 一問一答
登録販売者
概要
独学シリーズ
対策シリーズ
勉強方法
過去問+解説
├チェック問題 過去問リスト
├漢方 過去問リスト
├生薬 過去問リスト
├全ブロック 試験問題 科目別
├「医薬品的な問題」過去問リスト
├「添付文書」過去問リスト
└「資料問題」過去問リスト
