人体 一問一答
剤形ごとの違い、適切な使用方法 (f)外用局所に適用する剤形
テキストのページは、「(f)外用局所に適用する剤形」です。
んでは、スタート。
『外用局所に適用する剤形には、軟膏剤、クリーム剤、外用液剤、貼付剤、スプレー剤等がある。』
正誤はこちら。
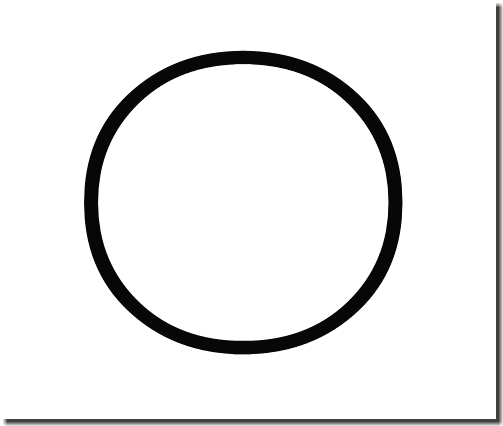
正しい記述です。
手引きそのまんまの記述です。
こういうストレートな記述が出ても、自信を持って答えられるくらいに、テキストを精読しておきましょう。
『基剤の違いにより、軟膏剤とクリーム剤に大別される。クリーム剤は、有効成分が適用部位に留まりやすいという特徴がある。』
正誤はこちら。
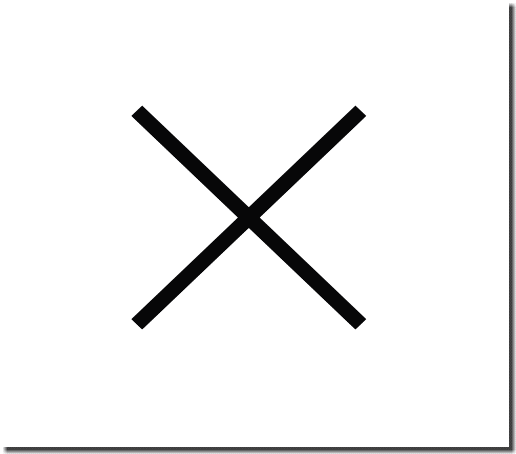
誤った記述です。
後半部分が間違っています。
「有効成分が適用部位に留まりやすいという特徴がある」のは、軟膏剤とクリーム剤に共通する特徴です。
手引きの記述は、「基剤の違いにより、軟膏剤とクリーム剤に大別される。有効成分が適用部位に留まりやすいという特徴がある」 としかないです。
こういうひねくれた出題もあります。
テキストを精読しておきましょう。
『クリーム剤は、油性の基剤で皮膚への刺激が弱く、適用部位を水から遮断したい場合等に用い、患部が乾燥していてもじゅくじゅくと浸潤していても使用できる。』
正誤はこちら。
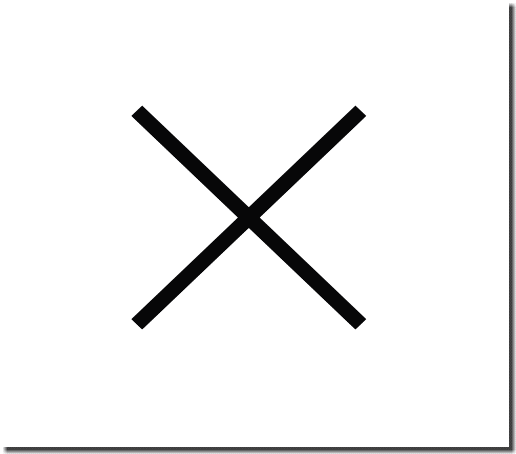
誤った記述です。
昔からの定番論点です。
間違っているのは、「クリーム剤」のところです。
選択肢の記述は、「軟膏剤」のものです。
手引きには…、
「軟膏剤は、油性の基剤で皮膚への刺激が弱く、適用部位を水から遮断したい場合等に用い、患部が乾燥していてもじゅくじゅくと浸潤していても使用できる」
…とあります。
軟膏剤とクリーム剤の入れ替え問題は、ド定番なので、ガチで押えておきましょう。
『軟膏剤は、油性基剤に水分を加えたもので、患部を水で洗い流したい場合等に用られるが、皮膚への刺激が強いため傷等への使用は避ける必要がある。』
正誤はこちら。
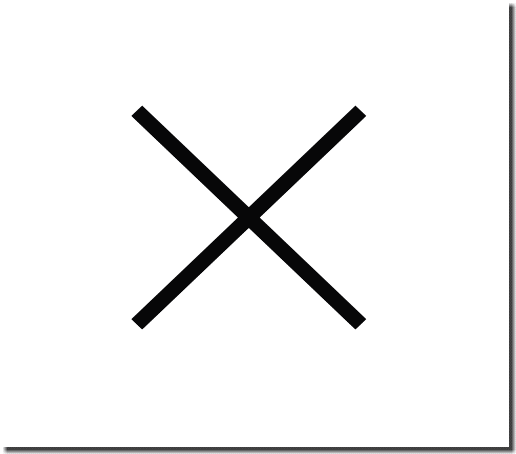
誤った記述です。
間違っているのは、「軟膏剤」のところです。
正しくは、「クリーム剤」です。
手引きの記述は、「クリーム剤は、油性基剤に水分を加えたもので、患部を水で洗い流したい場合等に用られるが、皮膚への刺激が強いため傷等への使用は避ける必要がある」です。
ド定番論点なので、何回も目を通しておきましょう。
『軟膏剤は、油性の基剤で皮膚への刺激が弱く、適用部位を水から遮断したい場合等に用いるが、皮膚への刺激が強いため傷等への使用は避ける必要がある。』
正誤はこちら。
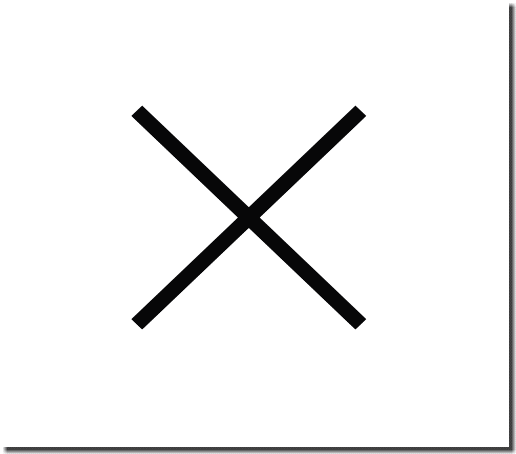
誤った記述です。
間違っているのは、「皮膚への刺激が強いため傷等への使用は避ける必要がある」のところです。
選択肢の避ける必要ウンヌンの記述は、「クリーム剤」のものです。
軟膏剤には、そのような記述はありません。
本問は、軟膏剤の記述とクリーム剤の記述をごっちゃにした問題です。
こういう出題にも慣れておきましょう。
ちなみに、軟膏剤の代表例には、「オロナイン軟膏」がありますが、これは、ヒビ・あかぎれ・切り傷などに使えます。
amazon参考:オロナイン軟膏
『クリーム剤は、油性基剤に水分を加えたもので、患部を水で洗い流したい場合等に用られ、患部が乾燥していてもじゅくじゅくと浸潤していても使用できる。』
正誤はこちら。
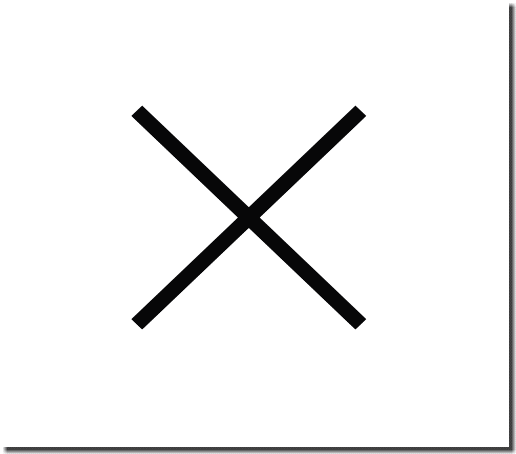
誤った記述です。
先と同趣旨の問題です。
間違っているのは、「患部が乾燥していてもじゅくじゅくと浸潤していても使用できる」のところです。
選択肢の後半の記述は、「軟膏剤」のものです。
クリーム剤には、そのような記述はありません。
剤形は、こういう「入れ替え」問題を想定して、テキストを精読しておきましょう。
『軟膏剤は、油性の基剤で皮膚への刺激が強く、適用部位を水から遮断したい場合等に用い、患部が乾燥していてもじゅくじゅくと浸潤していても使用できる。』
正誤はこちら。
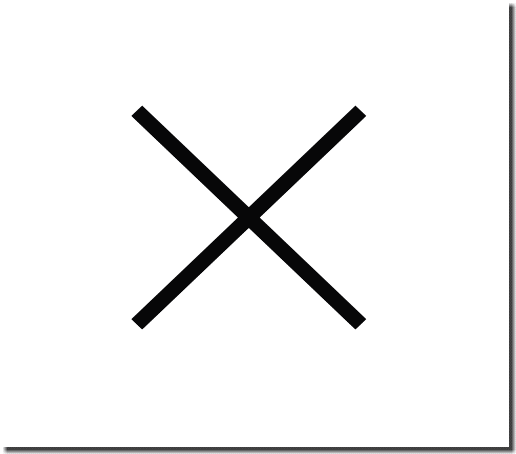
誤った記述です。
先と同趣旨の問題です。
間違っているのは、「刺激が強く」のところです。
正しくは、「刺激が弱く」です。
主語の軟膏剤・クリーム剤ばかりに目が行くと、こういうちょっとだけ変えた問題に足元をすくわれます。
油断せず、テキストを精読しておきましょう。
『クリーム剤は、水性基剤に油分を加えたもので、患部を水で洗い流したい場合等に用られる。』
正誤はこちら。
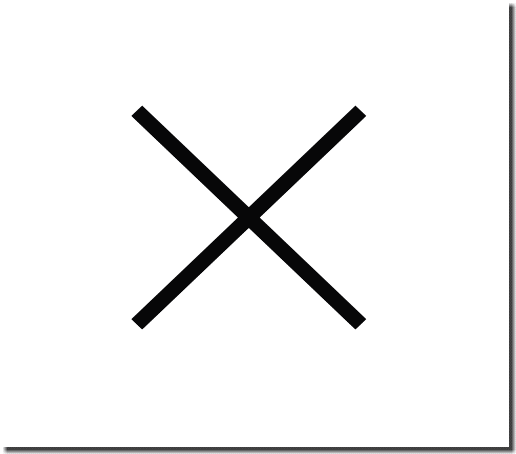
誤った記述です。
間違っているのは、「水性基剤に油分を加えたもの」のところです。
正しくは、「油性基剤に水分を加えたもの」です。
こういうところも、変えられます。
短い問題文に当たったときは、なにかあるんじゃ?と慎重になってください。
『軟膏剤やクリーム剤は、外用液剤に比べて、患部が乾きやすいという特徴がある。』
正誤はこちら。
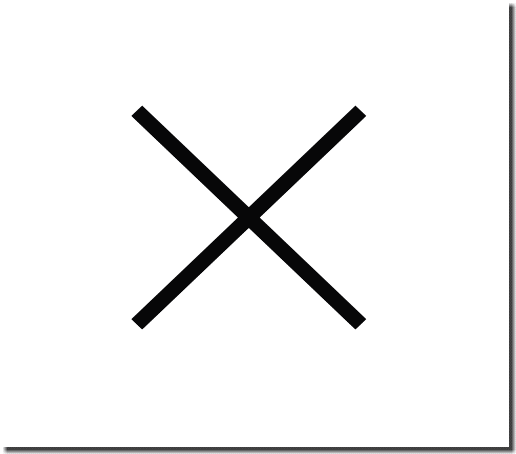
誤った記述です。
全体的に間違ってます。
正しい記述は、「外用液剤は、軟膏剤やクリーム剤に比べて、患部が乾きやすいという特徴がある。」です。
テキストを精読しておきましょう。
『外用液剤は、油性の基剤で皮膚への刺激が弱く、適用部位を水から遮断したい場合等に用いる。』
正誤はこちら。
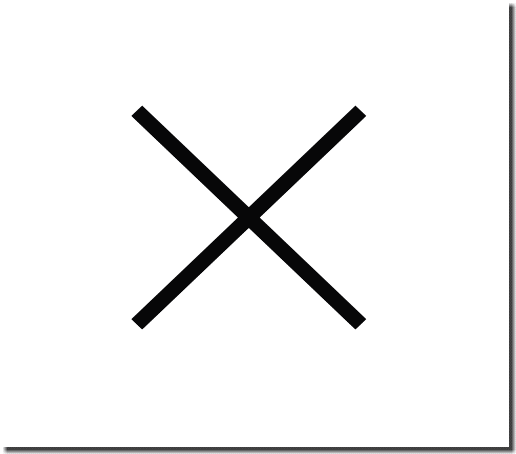
誤った記述です。
間違っているのは、「外用液剤」のところです。
選択肢の記述は、「軟膏剤」のものですね。
もうそろそろ、この種の「入れ替え」問題にも、慣れてきましたよね。
『外用液剤は、患部を水で洗い流したい場合等に用られるが、皮膚への刺激が強いため傷等への使用は避ける必要がある。』
正誤はこちら。
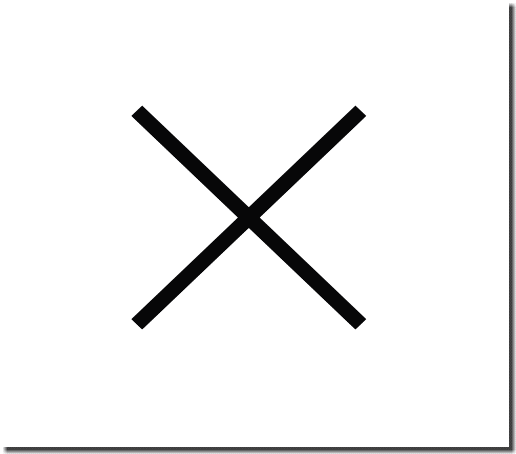
誤った記述です。先と同様の問題です。
間違っているのは、「外用液剤」のところです。
選択肢の記述は、「クリーム剤」のものですね。
『外用液剤は、軟膏剤やクリーム剤に比べて、患部が乾きやすいという特徴があり、適用部位に直接的な刺激感等を与える場合がある。』
正誤はこちら。
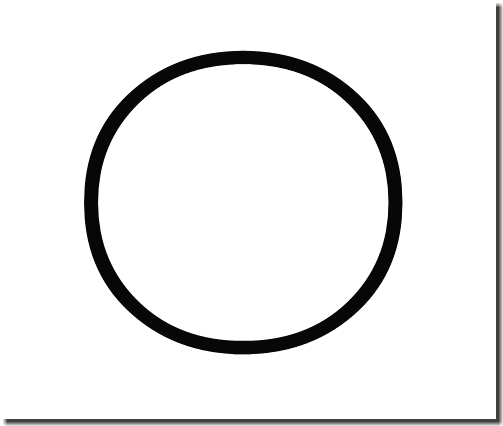
正しい記述です。
そのとおりの記述です。
ストレートな記述ですが、自信を持って答えられるようになっておきましょう。
『外用液剤は、軟膏剤やクリーム剤に比べて、患部が乾きにくいという特徴があり、直接的な刺激感等はない。』
正誤はこちら。
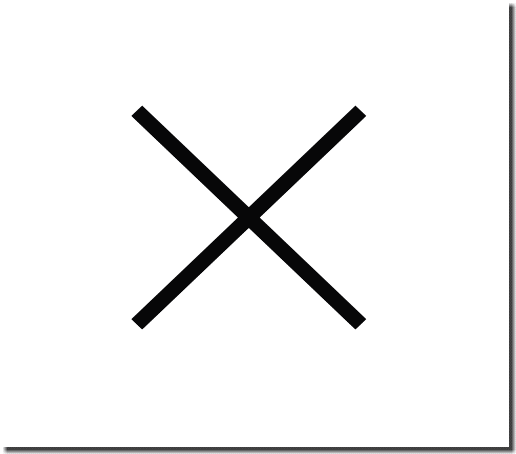
誤った記述です。
登録販売者試験らしい問題です。
全体的に間違ってます。特徴が逆になってますね。
正しい記述は、「軟膏剤やクリーム剤に比べて、患部が乾きやすいという特徴があり、適用部位に直接的な刺激感等を与える場合がある」です。
兎に角、剤形は、定番論点です。どんな問題が出ても、取れるようになっておきましょう!!!
『貼付剤には、外用液剤やテープ剤及びパップ剤がある。』
正誤はこちら。
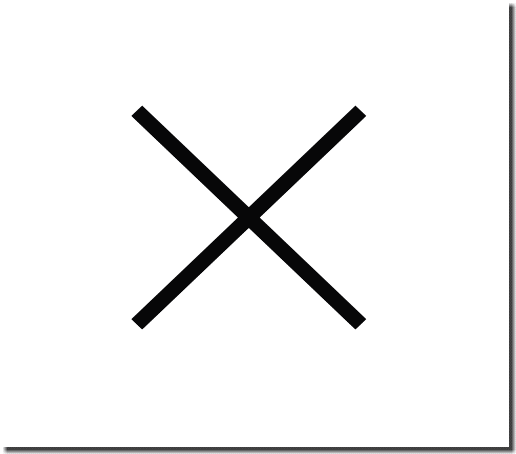
誤った記述です。
登録販売者試験らしい問題です。
間違っているのは、「外用液剤」のところです。
手引きには…、
「皮膚に貼り付けて用いる剤形であり、テープ剤及びパップ剤がある。」
…とあります。
外用液剤は、貼付剤にカテゴリされてませんね。液体のものを貼るというメチャクチャな問題ですね。
『パップ剤は、適用部位に有効成分が一定時間留まるため、薬効の持続が期待できる。』
正誤はこちら。
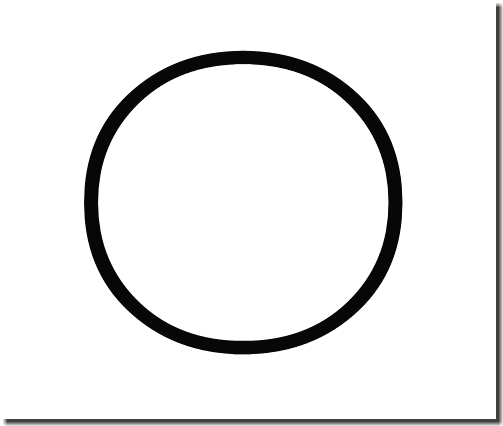
正しい記述です。
手引きには…、
「皮膚に貼り付けて用いる剤形であり、テープ剤及びパップ剤がある。」
「適用部位に有効成分が一定時間留まるため、薬効の持続が期待できる反面、適用部位にかぶれなどを起こす場合もある。」
…とあります。
パップ剤ですが、これは、湿布の一種です。
湿布をイメージすれば、即答できますね。
テキストを精読しておきましょう。
『テープ剤は、適用部位にかぶれなどを起こす場合もある。』
正誤はこちら。
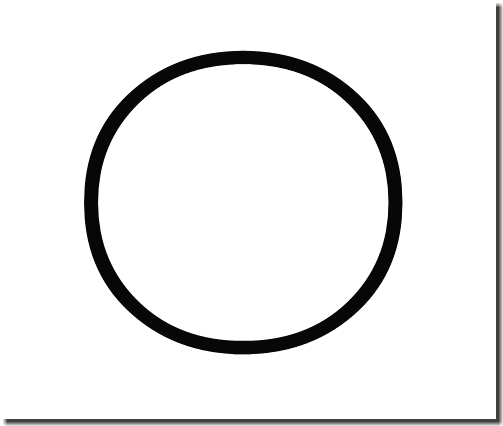
正しい記述です。
手引きには…、
「皮膚に貼り付けて用いる剤形であり、テープ剤及びパップ剤がある。」
「適用部位に有効成分が一定時間留まるため、薬効の持続が期待できる反面、適用部位にかぶれなどを起こす場合もある。」
…とあります。
副作用の記述は、まず出ます。
剤形での副作用も、必ず押えておきましょう。
『テープ剤は、有効成分を霧状にする等して局所に吹き付ける剤形である。』
正誤はこちら。
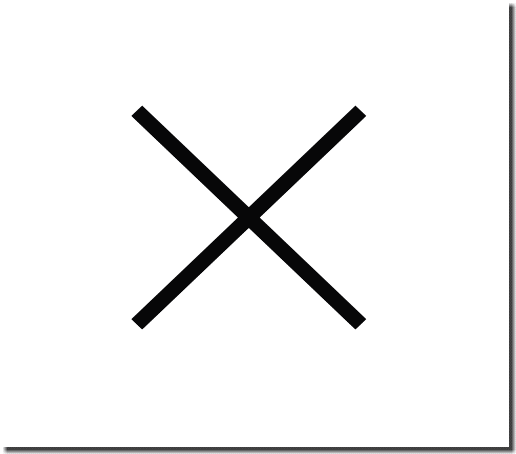
誤った記述です。
間違っているのは、「テープ剤」のところです。
正しくは、「スプレー剤」です。
当該スプレー剤ですが、身近なものなのか、これまで、あまり出題されませんでした。
しかし、だんだんと出てくるようになっています。
家にある実物のスプレー剤を元に、押えておきましょう。そうすれば、即答できますよ。
『クリーム剤は、手指等では塗りにくい部位や、広範囲に適用する場合に適している。』
正誤はこちら。
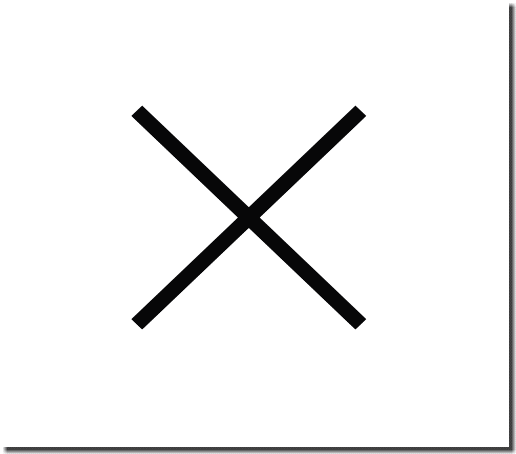
誤った記述です。
間違っているのは、「クリーム剤」のところです。
正しくは、「スプレー剤」です。
本問のように、他の剤形に入れ替えられると、途端に、アレレとなります。
スプレー剤の存在を忘れないよう、テキストを精読しておきましょう。
ページリンク
「一問一答:次のページ」へ。
補足リンク1
通読用・・・「剤形ごとの違い、適切な使用方法」
補足リンク2
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
本章インデックス・・・「人体 インデックス」
本節インデックス・・・「薬が働く仕組み インデックス」
こまごましたもの
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
★みんなとシェアする
薬の働き 一問一答
登録販売者
概要
独学シリーズ
対策シリーズ
勉強方法
過去問+解説
├チェック問題 過去問リスト
├漢方 過去問リスト
├生薬 過去問リスト
├全ブロック 試験問題 科目別
├「医薬品的な問題」過去問リスト
├「添付文書」過去問リスト
└「資料問題」過去問リスト
