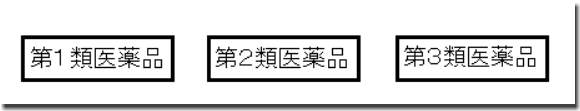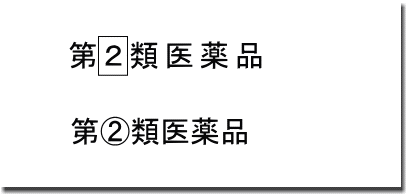副作用被害救済制度の対象外の憶え方+語呂合わせ‐軽度障害から精製水・ワセリンまで‐登録販売者
医薬品の中には、救済制度の対象とならないものがあります。
リスト化して挙げると…、
軽度の障害
不適切使用
製品不良など、製薬会社に賠償責任がある
無承認・無許可医薬品
健康食品
個人輸入された医薬品
要指導医薬品
殺虫剤・殺鼠剤
殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
一般用検査薬
一部の日局収載医薬品(精製水・ワセリンなど)
…といった塩梅です。
1つ1つ憶えるのは面倒なので、「そもそも系」「関係ない系」「医薬品系」の3つのグループで憶えましょう。
んで、「そもそも系」と「関係ない系」は、理屈で憶えましょう。
「医薬品系」は、語呂合わせで憶えましょう。
そもそも系
「そもそも系」ですが、その名の通り、「そもそも」を付けると、シックリくるものです。
この系統には…、
・軽度の障害
・不適切使用
…があります。
「軽度の障害」ですが、救済制度は、そもそもが「重度の障害」が対象です。
ちょっと気分が悪くなったがすぐ良くなった、入院する必要がなかった等は、救済制度の対象外です。
そもそも、軽度のものは、立証が難しいし、軽度まで含めると、制度がおっつかなくなる可能性もあります。
よって、対象外なのでしょう。
次に、「不適切使用」ですが、救済制度は、そもそもが適正な使用をしたのに障害が起きたケースを対象としています。
適正に使ったのに起きた副作用は、社会的な意味で、とても理不尽なので、救済制度があるってな寸法です。
んなもんで、逆の「不適切使用」の場合、被害が生じても仕方がないので、たとえば、検査薬を食べてお腹を壊したりするのは、救済制度の対象外となって然るべきかと思われます。
関係ない系
「関係ない系」には、公的な社会制度である副作用被害救済制度には、なじまないものが対象です。
・製品不良など、製薬会社に賠償責任がある
・無承認・無許可医薬品
・健康食品
・個人輸入された医薬品
…があります。
「製品不良など、製薬会社に賠償責任がある」ですが、これは、メーカーが責任を負うべきで、公的な救済制度が救ういわれがありません。
「無承認・無許可医薬品」と「健康食品」、「個人輸入された医薬品」ですが、そういう薬なり食品を使用する人の「自己責任」であったり、メーカーなり輸入業者、販売業者の「責」に負わせたりするのが、妥当かと思われます。
一口で言えば、「そこまで、面倒見られない」です。
医薬品系
さて、最も試験で問われるのが「医薬品系」で…、
・要指導医薬品
・殺虫剤・殺鼠剤
・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
・一般用検査薬
・一部の日局収載医薬品(精製水・ワセリンなど)
…が挙げられます。
すべて、出題実績があるので、必ず、押えておきましょう。
配偶者のように下らない語呂合わせですが、本・漫画・雑誌を捨てるときを思いつつ、「一冊、一冊が、要る」くらいに憶えましょう。
語呂の詳細は…、
一・・・“一”般用検査薬の「一」
冊(さつ)・・・“殺”虫剤・“殺”鼠剤の「殺(さつ)」
一・・・“一”部の日局収載医薬品の「一」
冊(さつ)・・・“殺”菌消毒剤の「殺(さつ)」
要・・・“要”指導医薬品の「要」
…となっています。
超絶注意!
注意喚起です。括弧書きの方が、問われています!!
「一部の日局収載医薬品」ですが、それよりも、「精製水・ワセリン」と、個別名で出題されることが多いです。
個別名称まで、キッチリ押えておきましょう。
amazon参考:精製水
amazon参考:ワセリン
次に、「殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)」ですが、過去問にて、「人体に直接使用する殺菌消毒剤を使用して生じた副作用は、救済制度の対象外である」などと出題されました。
「×」です。
「人体に直接使用する殺菌消毒剤」は、救済制度の対象です。
正確に文面を追うと…、
人体に直接使用“しない”殺菌消毒剤・・・救済制度の対象外
人体に直接使用“する”殺菌消毒剤・・・救済制度の対象
…です。
ここも、出題実績があるので、丁寧に押えておいてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 憶え方, 登録販売者 語呂合わせ, 登録販売者 適正使用 | 2019年11月12日 10:29 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
濫用等のおそれのある医薬品の憶え方‐エフェドリン,コデイン,ジヒドロコデイン,ブロモバレリル尿素,プソイドエフェドリン,メチルエフェドリン‐登録販売者
「法規」の頻出論点に「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」があります。
ただ、憶えるだけで、1点が取れるので、通勤・通学時に、憶えきってしまいましょう。
なお、本試験のほとんどの問題は、「名称」を問うだけです。くだらない語呂合わせもあるので、シッカリ押えておきましょう。
令和5年度(2023年度)の改正の反映済みです。憶えることが少なくなってラッキーです。
濫用おそれ一覧
「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」は、以下の「6つ」が…、
エフェドリン
コデイン
ジヒドロコデイン
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン
…あります。
下らない語呂合わせですが、「ここで、プチおしっこ」くらいに憶えます。
補足1‐語呂詳細
「ここで」は、「“コ”デイン」の「こ」と、「ジヒドロ“コ”デイン」の「こ」と相なります。
「プチ」ですが、これは、「“プ”ソイドエフェドリン」の「プ」と、「メ“チ”ルエフェドリン」の「チ」です。
「おしっこ」は、「ブロモバレリル尿素」の「“尿”素」に該当します。
ノーマルの「エフェドリン」は、自力で憶えてください。
我ながら、本当にくだらないですが、「ここで、プチおしっこ」で、意外に頭に残るので、試してください。
先も述べたように、試験では、「名称」を知っているかどうかを問うのが関の山です。
たとえば、「福島県 R4 午後第38問」のように、「以下の成分のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品はどれか?」というのが典型的な出題です。
先の下らない語呂の「ここで、プチおしっこ」で、十分に点が取れるかと思います。
補足2‐確認事項
「濫用等のおそれのある医薬品」ですが、ついに、販売授与時の「確認事項」が問われるようになっています。
「奈良県 R3 第51問」の問題です。
「若年者・・・氏名及び年齢」、「購入譲受け状況」、「買い込み・・・理由」は、押えておきましょう。
「氏名及び年齢」ですが、「若年者」だけが対象なので、注意してください。
ふつうの成年が買う場合は、氏名及び年齢の確認は、無用です。
「理由」は、「必要と認められる数量を超える」場合の確認事項です。ここも、注意してください。
つまり、ふつうの量を買うのであれば、理由を確認する必要はない、ってな塩梅です。
念のため、手引きの該当記述を抜粋すると…、
「ⅰ)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢」
「ii)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況」
「iii)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由」
「iv)(略)」
…となっています。
「濫用等のおそれのある医薬品」は、改正によって簡単になったので、今後は、ド定番論点となりそうです。ここまで押えておきましょう。
補足3‐該当する医薬品
「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の「医薬品」のページリンクを、以下にリストアップします。
成分に一抹の不安のある人は、復習に活用してみてください。
エフェドリン
「エフェドリン」は…、
…です。
メチルエフェドリン
「メチルエフェドリン」は…、
・鎮咳去痰薬‐アドレナリン作動成分‐メチルエフェドリン塩酸塩
・内服アレルギー用薬‐アドレナリン作動成分‐メチルエフェドリン塩酸塩
…です。
プソイドエフェドリン
「プソイドエフェドリン」は…、
・内服アレルギー用薬‐アドレナリン作動成分‐プソイドエフェドリン塩酸塩
…です。
ブロモバレリル尿素
「ブロモバレリル尿素」は…、
「風邪薬の鎮静成分」、
「解熱鎮痛薬の鎮静成分」、
「睡眠鎮静薬の鎮静成分」、
「鎮暈薬の鎮静成分」、
…です。
コデイン・ジヒドロコデイン
コデインとジヒドロコデインですが、風邪薬:鎮咳成分と、鎮咳去痰薬:麻薬性鎮咳成分に出てくる成分です。
かぜ薬のリンクは…、
…です。
鎮咳去痰薬のリンクは…、
…です。
補足4‐令和5年度改正
以下は、読む必要はありません。補足的に、改正について述べています。
当該論点ですが、令和5年度に改正され、括弧書きが削除されました。
かつては、「鎮咳去痰薬に限る」といった限定があったのですが、改正により、削除されています。
受験生の負担が減ったので、ラッキーな改正でした。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 憶え方, 登録販売者 法規 | 2019年11月12日 10:22 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
容器・外箱等への記載事項のまとめ 後編‐リスク区分から指定第2類医薬品まで‐登録販売者
「容器・外箱等への記載事項のまとめ 前編‐製造販売業者から要指導医薬品まで」の続きです。
(g) 一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示
「(g) 一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示」ですが、おなじみの「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字です。
下の画像のような…。
…ものです。
お手持ちの薬を見れば、まず間違いなく、先の「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」のどれか、表記がされているはずです。
指定第2類医薬品については、後述します。
(h) 日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量
「(h) 日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量」ですが、まあ、「有効成分の名称及びその分量」も、常識的に、必要だとわかるかと思います。
登場するのは、おおむね選択肢の埋め草ですが、出ることは出るので、押さえておいてください。
(i) 注意-人体に使用しないこと
「(i) 誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(殺虫剤等)における「注意-人体に使用しないこと」の文字」ですが、出題されています。
殺虫剤等には、「注意-人体に使用しないこと」が記載されます。
「ひっかけ」で、「“殺虫剤”と表記せよ」とか「“危険”と表記せよ」などと出ても、判断できるようになっておきましょう。
記載すべきは、「注意-人体に使用しないこと」です。
自宅のゴキジェットをチェックしてみてください。
amazon参考:ゴキジェット
なお、「厚生労働大臣」も、「ひっかけ」ポイントです。
「都道府県知事」などに変えられるおそれがあるので、注意してください。
使用の期限
「(j) 適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限」ですが、これは、別個の問題として、出ることが多いです。
出題されるのは…、
まず、数字の部分で、「3年」という数字が問われます。
2年とか5年とかじゃないです。
数字は常に狙われているので、要ガチ暗記です。
次に、使用期限は、「未開封」が対象です。
開封した物に、使用期限は適用されないので、キッチリ押えましょう。よく出ます。
最後に、「表示義務の当否」です。
先の規定は、「3年を超えて安定でない医薬品」で、これは、外箱等への記載義務があります
対して、「適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品質が安定であることが確認されている医薬品」は、「使用期限の法的な表示義務はない」です。
当該医薬品の安定性によって、義務の可否が異なるので、注意です。
たとえば、「すべての医薬品に、使用期限の表示義務がある」という趣旨の選択肢は、「×」です。
先に見たように、3年超安定医薬品は、使用期限の表示義務がないです。
なお、3年超安定医薬品の使用期限は、流通管理等の便宜上、外箱等に記載されるのが通常となっています。(配置販売される医薬品では、「配置期限」です。)
(k) 「店舗専用」の文字
「(k) 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字」ですが、こういうのもあるんだくらいに、ざっくり読んでおけばいいでしょう。
あまり出ないです。
指定第2類医薬品
「(l) 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字」ですが、これは、要チェックです。
「指定第2類医薬品」は、下の画像のような…、
…記載義務があります。
以上です。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 まとめ, 登録販売者 法規 | 2019年11月11日 10:36 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |