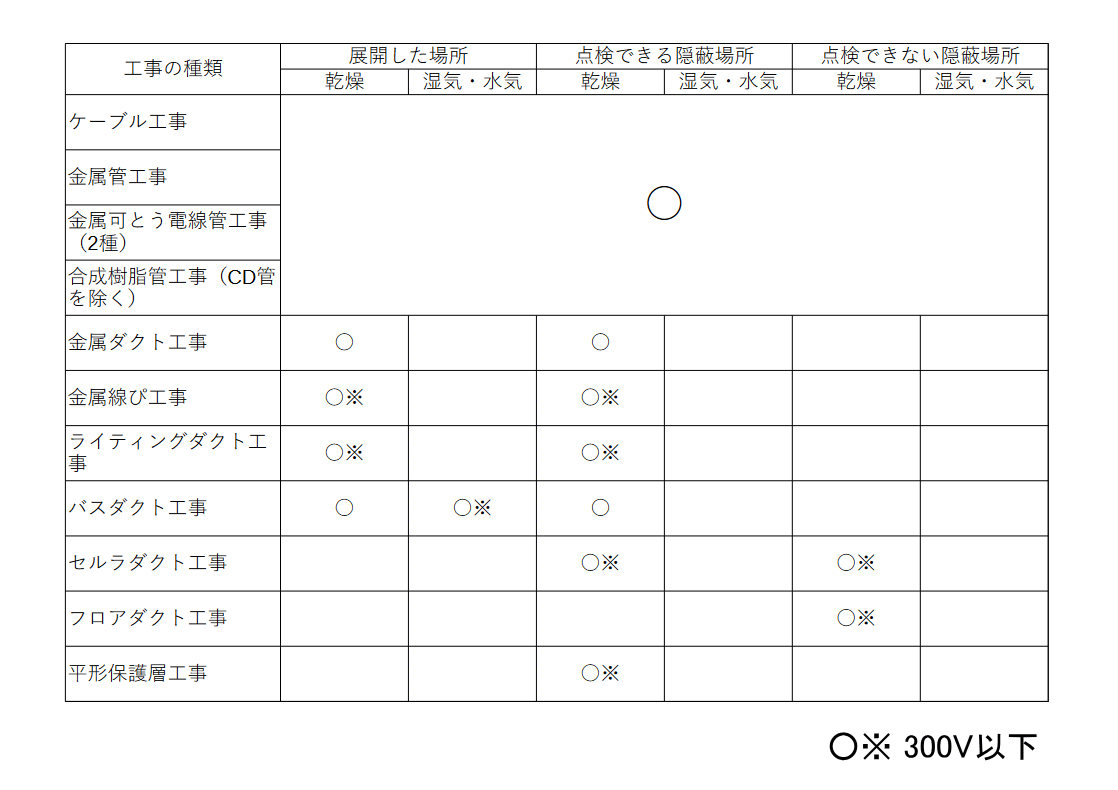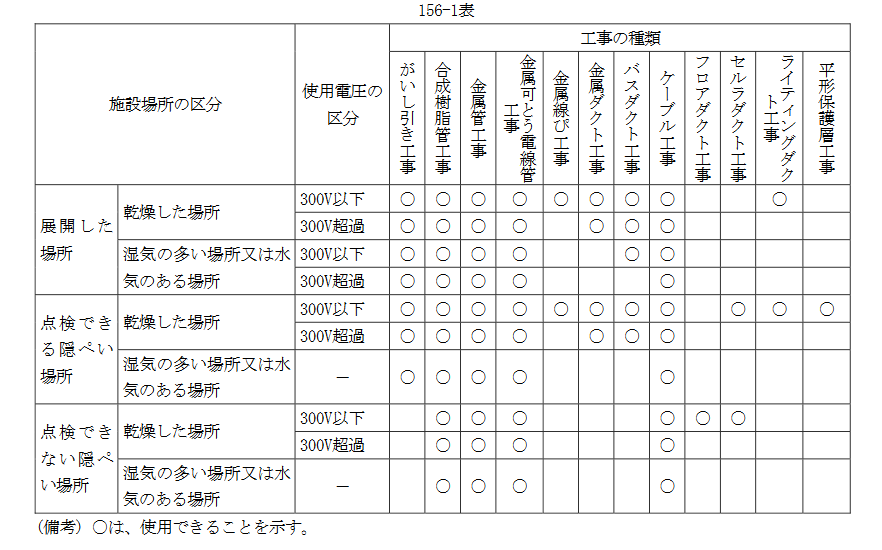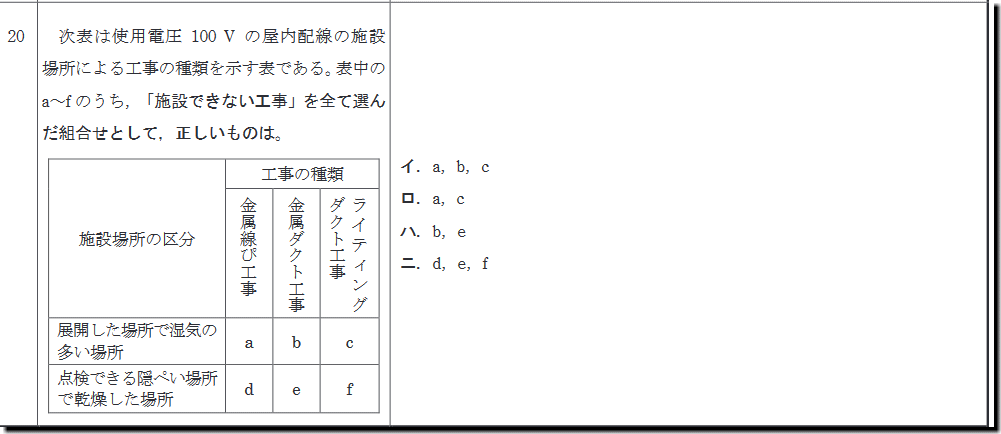施工場所と工事種類の「300V以下」の語呂合わせ:金属線ぴ工事・ライティングダクト工事・平形保護層工事の語呂合わせ‐2電工筆記
当ページの内容は、「施工場所と工事種類(金属ダクト工事、金属線ぴ工事、ライティングダクト工事、バスダクト工事、セルラダクト工事、フロアダクト工事、平形保護層工事)の語呂合わせとまとめ」に、まとめました。
300V以下の金属線ぴ工事・ライティングダクト工事・平形保護層工事等々の「電気工事」の試験対策は、先のリンクページを活用願います。
以下の記事は、アーカイブ的に残してます。読む必要は、あまりありません。
アーカイブ
(※ 以下の記事は、近年の傾向と、かなりかけ離れている内容です。参考にしなくていいです。)
「施工場所と工事種類」の論点ですが、金属線ぴ工事,ライティングダクト工事,平形保護層工事まで、問われるようになっています。
本ページでは、対策として、金属線ぴ工事以下の「300V以下」の論点を、まとめました。
なお、「展開した場所」とか「点検できる隠ぺい場所」ウンヌンについては、「施工場所と工事種類(金属線ぴ工事・金属ダクト工事・ライティングダクト工事・平形保護層工事)の語呂合わせとまとめ」を、一読願います。
300V以下について
上記画像の「表」を見れば一目ですが、金属線ぴ工事、ライティングダクト工事、平形保護層工事の3つは、「300V以下」という規定があります。
つまり、これら3つは、300V以下の工事なら工事可能ですが、300Vを超過すると工事不可となるわけです。
例題
本試験では、たとえば…、
①『乾燥した点検できる隠ぺい箇所に、対地電圧600Vのライティングダクト工事を行った』とか…、
②『乾燥した展開箇所に、対地電圧600Vの金属ダクト工事を行った』など…、
…といった出題が考えられます。
例題答え
答えを言うと、①は「×(不適切)」で、②は「○(適切)」です。
①のライティングダクト工事ですが、先に見たように、「300V以下」に限定されているので、対地電圧600Vの工事ではダメ、といった塩梅です。
対して、②の金属ダクト工事ですが、「300V以下」という規制がないので、600Vの工事でもOK、と相なるわけです。
当該「300V以下」も、昨今の事情から見るに、問われてまったく遜色がないので、押さえておくべきです。
「300V以下」の憶え方
くだらない語呂で、憶えてしまいましょう。
その語呂は、「300匹の平たいピラニア」です。
詳細ですが…、
・300匹・・・“300”V以下
・平たい・・・“平”形保護層工事
・ピ・・・金属線“ぴ”工事
・ラ・・・“ラ”イティングダクト工事
…といった塩梅です。
「300匹の平たいピラニア」の語呂があれば、先のような①の例題は、即効で判断が可能となります。
先述したように、当該300V以下の論点も、いつ問われてもおかしくないので、余裕があれば、押えておいてください。
個人的には、当該ページを「お気に入り」に入れて、本試験の移動時間や待ち時間で消化します。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工‐語呂合わせ, 2電工筆記 | 2020年11月24日 7:59 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
施工場所と工事種類(金属ダクト工事、金属線ぴ工事、ライティングダクト工事、バスダクト工事、セルラダクト工事、フロアダクト工事、平形保護層工事)の語呂合わせとまとめ‐2電工学科
第2種電気工事士の学科試験の「電気工事」の「低圧屋内配線の施設場所による工事の種類」の憶え方等についてです。
要は、上記「表」を憶える論点です。
本ページでは、金属ダクト工事、金属線ぴ工事、ライティングダクト工事、バスダクト工事、セルラダクト工事、フロアダクト工事、平形保護層工事について述べています。
対して、ケーブル工事、金属管工事、金属可とう電線管工事(2種)、合成樹脂管工事(CD管を除く)については、「施工場所と工事種類(合成樹脂管工事、金属管工事、2種金属可とう電線管工事、ケーブル工事)の語呂合わせ」の方を、参考にしてください。
当該ケーブル工事以下の「4つ」は、「すべて可能」なので、別枠扱いとしています。よって、このページからは、除外して考えます。
300V超過と300V以下
上記「電気設備の技術基準の解釈」によると、各電気工事は、300V超過と300V以下とで分けられています。
正確を期すために、このページでも、300V超過と300V以下について、記載しています。
しかし、です。
第2種電気工事士の本試験では、当該300Vの以下超過について問われることは、ほとんどないのです。
問題の設定は、100V~200Vなのが多く、各工事別に設定されている300V超過と300V以下の別について、厳密に押さえなくても、解答できてしまうのです。
以下の記述には、一応、300V超過と300V以下について記載していますが、試験勉強的には、無視して構わないです。
試験のレベル的にも、第2種電気工事士では、問われないと思います。
憶えるべきは、「点検隠ぺい乾燥」等々のところです。
カンタン:湿気の多い場所又は水気のある場所
最もカンタンなところから着手します。
先の「表」を見れば、「湿気の多い場所又は水気のある場所」で工事可能なのは、「300V以下のバスダクト工事」だけとなっています。
展開した場所・点検できる隠蔽場所・点検できない隠蔽場所に関係なく、「水気湿気・・・バスダクト工事のみ」です。
憶え方ですが、「バス(風呂)だけに、水気湿気は、“バス”ダクト工事のみ」とストレートに憶えてしまいましょう。
ほいで、です。
「湿気の多い場所又は水気のある場所」で工事可能なのは、「300V以下のバスダクト工事」だけならば、その「逆」も真なりとなります。
つまりは、残る電気工事は、つまり、「金属ダクト工事・金属線ぴ工事・ライティングダクト工事・セルラダクト工事・フロアダクト工事・平形保護層工事は、水気湿気では、工事不可」となるわけです。
過去問例題
当該2つの理屈を押さえていれば、上の画像の「R5 上期午後 第20問」ような問題を、即答できるようになります。
過去問例題では、「展開できる場所で湿気の多い場所」が問われていますが、先に見たように、「湿気の多い場所又は水気のある場所」で工事可能なのは、「300V以下のバスダクト工事」だけなので、「a」と「b」と「c」は、工事不可ってな塩梅です。
なお、憶え方の注意事項です。
先述したように、ケーブル工事・金属管工事・2種金属可とう電線管工事・CD管を除く合成樹脂管工事の「4つの電気工事」は、除いて考えてください。
当該4つの電気工事は、トランプのジョーカーと言えます。どこでも工事可能なので、「湿気の多い場所又は水気のある場所」でも、当然、工事可能と相なります。
さて、当該バスダクト工事のさらなる憶え方については、後述します。
カンタン:1個シリーズ
「表」を見ると、工事可能な箇所が1個しかないものがあります。
フロアダクト工事と平形保護層工事です。「表」の下から1番目と2番目のところです。これらは…、
・300V以下:フロアダクト工事:点検できない隠蔽の乾燥
・300V以下:平形保護層工事:点検できる隠蔽の乾燥
…となっています。
「フロアダクト工事」ですが、「フロア」という文言に着目しましょう。
フロア、少し強引ですが、フロアだけに「床下」をイメージします。
「床下」だけに「点検できない隠蔽」と押さえるといいでしょう。
次の「平形保護層工事」は、いい憶え方がないです。
「平形保護層工事・・・点検できる隠蔽」と、何度もブツブツ唱えて憶えるしかないです。
このページを「お気に入り」に入れておいて、空いた時間で何度も目を通しておいてください。
残る「乾燥」は、水気湿気で工事可能なのは、バスダクト工事だけなので、フロアダクト工事と平形保護層工事は、乾燥だけの工事となる、といった感じに、理屈を追って押さえるといいでしょう。
んで、繰り返しますが、先述したように、300V以下のところは、無理して憶えなくていいです。
ちなみに、「フロアダクト工事」ですが、「電線をフロアダクトに入れて床の中に埋め込む工事のこと。床下線工事とも呼ばる」とのことです。
んで、「平形保護層工事」は、「非常に薄い電線(平形導体合成樹脂絶縁体)をタイルカーペットの下に配線する工事」とのことです。
工事内容については、まず出ないと思うので、ざっくり見ておけばいいでしょう。
共通工事シリーズ‐金だ金ぴかライティング
「表」を見ると、工事可能な箇所が2個とも共通するものがあります。
・金属ダクト工事:300V超過と300V以下:展開乾燥と点検隠蔽の乾燥
・金属線ぴ工事:300V以下:展開乾燥と点検隠蔽の乾燥
・ライティングダクト工事:300V以下:展開乾燥と点検隠蔽の乾燥
…です。「表」の4つのジョーカーの下3つのところです。
金属ダクト工事と金属線ぴ工事とライティングダクト工事ですが、3つの工事とも、工事可能なのは、「展開乾燥と点検隠蔽の乾燥」となっています。
よって、当該3つは、まとめてセットで憶えるのがラクです。
「金だ金ぴかライティング」くらいの語呂で憶えてしまいましょう。語呂の詳細ですが…、
金だ・・・金ダ・・・“金”属“ダ”クト工事
金ぴか・・・金ぴ・・・“金”属線“ぴ”工事
ライティング・・・“ライティング”ダクト工事
…といった塩梅です。
語呂の「金だ金ぴかライティング」と「展開乾燥と点検隠蔽の乾燥」と憶えていきましょう。
なお、金属ダクト工事は、300V以下のほか、300V超過でも工事可能という点で、300V以下しかできない金属線ぴ工事とライティングダクト工事と異なっています。
ただ、先に述べたように、300V超過・300V以下のところは、無理して憶えなくていいでしょう。
バスダクト工事
「バスダクト工事」を憶えるのは、先に見た「金属ダクト工事:300V超過と300V以下:展開乾燥と点検隠蔽の乾燥」を憶えてからにします。
端的に言うと、「バスダクト工事」は、金属ダクト工事の工事場所に、「300V以下:展開した場所で、湿気の多い場所又は水気のある場所」が加わったものです。
表を見ると、「金属ダクト工事」で工事可能なのは…、
・展開乾燥(○‐300V超過・300V以下)
・点検隠蔽の乾燥(○‐300V超過・300V以下)
…となっています。
んで、「バスダクト工事」を見てみると…、
・展開乾燥(○‐300V超過・300V以下)
・点検隠蔽の乾燥(○‐300V超過・300V以下)
・展開した場所の湿気の多い場所又は水気のある場所(○※‐300V以下)
…となっています。
んなもんで、バスダクト工事は、金属ダクト工事に、展開・湿気水気を加えるだけ、といった感じで憶えればいいわけです。
ちなみに、「バスダクト工事とは、建物内に一括送電ができる大きなダクトを引き込む工事のことを指す」とのことです。当該工事内容は、第2種電気工事士ではまず出ないので、憶える必要は、あまりありません。
孤高のセルラダクト工事
最後に残るのは、「セルラダクト工事」です。
当該セルラダクト工事は、他の電気工事と共通点がないので、単独で憶えるしかないです。
当該セルラダクト工事ですが、「300V以下:点検できる隠蔽の乾燥と、点検できない隠蔽の乾燥」の2カ所となっています。
ゴリ押しの憶え方ですが、「点検できる・できない隠ぺい」に「乾燥」と憶えるしかないです。
このページを「お気に入り」に入れておいて、空き時間で何度も見ましょう。
ちなみに、当該セルラダクト工事は、「R5 下期午前 第20問」で出題実績があります。押えておきましょう。
なお、当該セルラダクト工事ですが、「セルラダクト配線とは、S造(鉄骨)などで床の材料として使われる「デッキプレート」の形を生かし、溝の部分を使って配線を通す方法」とのことです。あまり試験に出ないので、参考程度に見ておけばいいでしょう。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工‐語呂合わせ, 2電工筆記 | 2020年11月24日 7:46 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
令和2年度(2020年度)関西広域連合 登録販売者試験の科目別総評
「関西広域連合の令和2年度(2020年度)登録販売者試験」の「科目別」の総評です。
R2年度(2020年度)試験
試験科目のうち、最も難化しているのは、「医薬品」です。
そして、次いで、難化しているのは、「適正使用」です。
よって、当該2科目では、徹底して過去問演習に取り組み、そして、テキストの精読を行う、ってな次第です。
残りの「基本知識」「人体」「法規」ですが、少々難化しているも、従来の勉強で、点数は確保できます。
んでは、個々の科目の詳細を見ていきます。
各論:基本知識
第1問~第20問の計「20問」の「医薬品に共通する特性と基本的な知識」ですが、R2年度も安定した出題といえます。
しかし、変化は、そこそこにあります。
まず、「手引き」やテキストを、逸脱する選択肢が「3問:医薬品のリスク評価」で出ています。
選択肢のaとcなのですが、「???」となったかと思います。
最終解答には影響しないですが、こういう小難しい選択肢に、拘泥しないようにしましょう。
次に、「基本知識」にも、「ひっかけ」問題が登場するようになっています。
「14問:医薬品の品質」の選択肢bに、「保管期限」という“はったり選択肢”が出題されています。
テキストの読み込みが浅い受験生は、(???)となったはずです。
このように、「基本知識」は、従来の問題が大半とはいえ、“油断はできない問題”も問われるようになっています。
他の科目に比べたら、「基本知識」は、「得点源」です。
1問たりとも落とさない気持ちにで臨んでください。
各論:医薬品
第21問~第60問の計「40問」の「主な医薬品とその作用」ですが、当該年度は、点数的に、厳しくなっています。
「医薬品」の大きな変化として、「生薬の地位が下がり、漢方処方製剤の地位が上がった」です。
前年の試験では、「1問」丸ごと「生薬」の出題がありましたが、当該年度では、“丸ごと問題がなくなってしまいました。”
「生薬」は、“選択肢の一部”として問われるばかりです。
もっというと、「生薬」は、漢方処方製剤との「合同問題」として、選択肢の1~2個で問われるようになっています。
つまり、「生薬」を勉強すれば、選択肢の1~2つは確答できるも、「漢方処方製剤」の知識がないと、問題自体に正解できないという塩梅です。
こんな次第で、「生薬」は、かつてほどの費用対効果がなくなっています。
しかし、なのです。
出題者も然るもので、「生薬」さえ勉強していれば、その知識だけで選択肢が絞れて1点が取れる問題も、あるのです。
確かに、出題数が減って、「生薬」の地位は下がっていますが、勉強していれば、“格段に点数の可能性が上がる”のは、間違いありません。
このあたりの「コスパ事情」を念頭に、「生薬」をやるか、やらないかを判断してください。
漢方処方製剤対策が必須
対して、「漢方処方製剤」の出題が、前年比で微増(プラス1問)しており、漢方処方製剤を完全に捨てるのは、考え物になっています。
当該年度の「漢方処方製剤」の出題は、「10問」なのですが、これを全部落としたとすると、「40-10」で全「30問」で戦うことになります。
よって、カタカナ成分の問題をシビアに正解しなくてはならず、精神的に、かなり厳しいものがあります。
従来は、「漢方処方製剤」を完全に捨てても、「生薬」等である程度、カバーできていました。
しかし、最近の試験傾向からすると、「漢方処方製剤」を完全に捨てるわけにはいかないようになっています。
ここだけは、ちょっと大きな「変化」なので、注意してください。
新傾向問題
「38問:継続使用期間」に、ガチの数字問題が出ています。
「医薬品」でも、数字は問われていましたが、この種の「継続していい期間」が“横断的に”出題されたのは、初めてかと思います。
こういった問題も、出始めたので、「医薬品」でも、数字は、丁寧に押えていかねばなりません。
数字については、「数字対策インデックス」も、一読願います。
マイナー成分も出る
これまで問われたことのない、マイナーな成分が、出題されています。
「34問:胃薬」なのですが、「乾燥酵母」や「カルチニン」が出ました。
マイナー成分だからと言って、もう、油断できないようになりました。
テキストの成分は、どの成分でも、チェックを入れておきましょう。
こんな次第で、「医薬品」は、格段に点数が取れなくなっています。
当該変化を前提に、試験勉強に臨んでください。
各論:人体
第61問~第80問の計「20問」の「人体の働きと医薬品」ですが、R2年は、「少し、難しくなった」です。
まずもって、出題形式に、変化が見られます。
「横断問題」が出題されるようになっています。
問題の内容は、従来から問われているものなのですが、「問われ方」が変わってきています。
今後の定番様式となりそうなので、こういう出題形式に、慣れておきましょう。
次に、「副作用」に、多少の変化があります。
まず、肝に銘じて欲しいのは、「副作用は、すべてが出るようになっている」です。
これまでは、「間質性肺炎」など、メジャーなものばかりが出題されていたのですが、昨年度あたりから、精神神経障害など、「副作用」のすべての論点が、試験問題と化しています。
当該年度でも、この傾向が続き、消化器系副作用、循環器系副作用、泌尿器系副作用などが、マルッと問われるようになっています。
また、当該年度の特徴なのですが、超絶定番論点だった、SJSやTENが出題されていません。
出ない年度などないくらいに、よく出ていたSJSやTENですが、出ないときもあります。
定番事項に偏った試験勉強が危険になっています。
「副作用」のすべての論点を、押えておきましょう。
各論:法令
第81問~第100問の計「20問」の「薬事関係法規・制度」ですが、R2年では、「少しだけ難化している」です。
内容的には、過年度と大差は、ないのです。
しかし、やはり、ジワジワと、1問1問の問題の難易度が上がっています。
たとえば、「96問:広告規制1」などは、典型的に、難しくなった問題です。
とはいえ、「医薬品」と比べると、段違いで、点数が取りやすい科目です。
テキストを読み、過去問をシッカリ繰り返しておけば、大丈夫かと思います。
最後ですが、「82問:登録販売者」は、今後の定番と化しそうなので、テキストで念入りに見ておくべき論点かと思います。
各論:適正使用
第101問~第120問の計「20問」の「医薬品の適正使用・安全対策」ですが、「医薬品」に並に、要注意科目に変貌しています。
まずもって、「新傾向問題」です。
「106問:厚生労働省情報提供」なのですが、内容自体はそう変わってないのですが、こう問われると、格段に難易度が上がります。
次に、「新論点問題」です。
「108問:再審査制度」ですが、これまで問われなかった論点が、ドカッとメインで問われています。
次に、「難問」です。
「109問:副作用等報告の患者情報」や「113問:一般用医薬品の安全対策」は、解けた人は少ないと思います。
また、「107問:副作用等の報告」などは、「難問枠」の問題で、今後の定番と化しそうです。
これらの問題は、落とした人も多かったと思います。
このように、「適正使用」では、「点数の取り難い問題」が目立つので、「医薬品」に次いで、資源を投入する必要があります。
「医薬品的な問題」について
近年の「適正使用」の傾向変化の最たるものが、「主な使用上の注意の記載とその対象成分・薬効群等」の出題、つまり、「医薬品的な問題」の増加でした。
R2年では、当該医薬品的な問題の傾向が、「固まった」ように、見受けられます。
これまでの「医薬品的」な問題ですが、出題数に増減がありました。
しかし、当該年度の関西広域連合では、「使用しない(服用しない)が3問」で、「相談することが3問」の、合計「6問」となっています。
過去の試験では、“ちょっと多すぎるのでは?”と思っていましたが、今後は、「6問」前後を見ておくとよいかと思います。
なお、当該「医薬品的な問題」で、確実に押えるべきは、「医薬品」でも出題可能性のある「使用しない(服用しない)」です。
これは、3問全部、取るべきです。
対して、「相談すること」は、費用対効果が悪いです。
「相談すること」のうち、定番論点の1~2問を取れるようになっておけば、御の字かと思われます。
当該年度の関西広域連合 登録販売者試験は、ざっと斯くの如しです。
勉強方法や独学の進め方などは、「登録販売者の独学」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者試験 | 2020年11月19日 3:39 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |