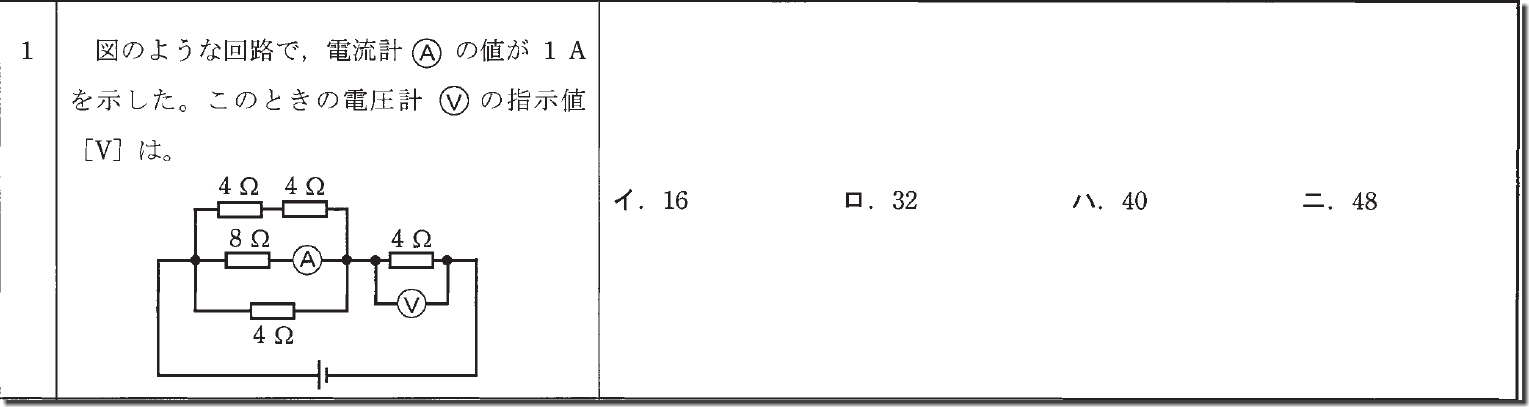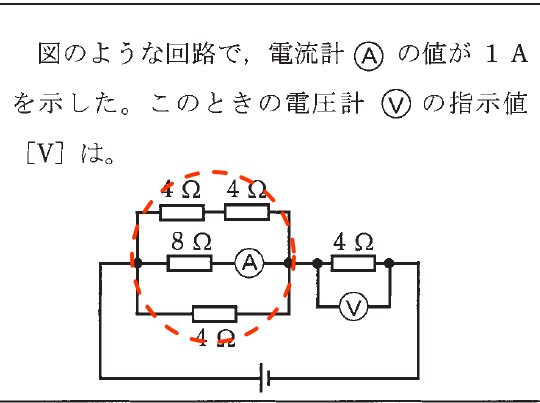2電工‐H28後期・筆記の総評‐新傾向問題「技能試験系の問題」とか「ガチ難問」とか
2電工の筆記試験は、心配するほど変わっていません。
本試験のほとんどは、定番問題で構成されています。
ですから、従来どおりの勉強をしていれば、つまり、「しっかりテキストを読んで、過去問を2~3回繰り返しておけば、筆記は“間違いなく”通る」ことに、変わりはありません。
ホント、電気理論、電気工事、配電設計、複線図のそれぞれは、例年通りの出題でした。
ただ、最近では、新しい傾向が顔を出しているのも事実です。本ページでは、当該新傾向について述べていきます。
新傾向その1‐技能試験系問題
筆記の新傾向としては、「技能試験系の問題」が登場していることです。
平成28年度の後期・筆記では、当該「技能試験系の問題」が、2問ほど出題されています。
その問題は、「第12問」と「第23問」です。
「第12問」では、「ボックスコネクタのねじ切り」が問題で、当該規定は「技能試験で登場する」ガチンコ規定です。
筆記のテキストに、当該技能の規定を載せた出版社は絶無なはずで、確実に解けた受験生はごく少数でしょう。
次の、「第23問」は、金属板張りの施工問題ですが、技能試験で定番の「メタルラス壁」の作業を知っていたら、難なく解ける内容となっています。
このように、「技能試験の勉強をしていたら取れるが、筆記の勉強だけでは取れない」問題が登場している、というのが最近の傾向となっています。
技能試験系問題は捨てる
さて、当該「技能試験系の問題」ですが、文系ド素人は、基本、『捨て問』とします。
というのも、技能試験系問題は、出ても1~2問くらいであり、この数問のために、100ページ近い技能のテキストを読むわけにも行かない、といった次第です。
それに、1~2問くらいなら、「捨て問」にしても、他の筆記ド定番の問題でカバーできますし、その時間を、厄介な「電気工事」等々に充てることで、いくらでも、失点を抑えることが可能です。
一口で言えば、「たかが1~2問のために、技能の勉強なんてやってられない(=費用対効果が悪すぎ)」といった次第です。
文系ド素人は、無理から、言うなれば、「筆記試験の段階から、技能の勉強はしなくてよい。技能試験系の問題は捨てる。」という次第です。
ただ、余裕があるならやっておく
しかし、なのです。
当該「技能試験系の問題」は、試験的には、とても『重要』なのです。
先に挙げた、H28年後期筆記‐第12問の「ねじ切り」は、技能試験での「軽欠陥ポイント」ですし、第23問のメタルラス壁の施工は「重大欠陥ポイント」となっています。
(現在では、両欠陥とも、即落ちの「欠陥」扱いとなっています。)
言うなれば、「筆記の段階から、勉強しておいても、全く損はない」内容となっています。
技能試験は、「重大欠陥」が「1つ」あれば即落ちで、「軽欠陥」が「3つ」で落ちる減点方式となっています。
このため、「どこで欠陥が取られるか」は、技能試験の重要な勉強となっています。
(注意:H29年(2017年)の試験より、以前の「軽欠陥・重大欠陥」という括りはなくなり、「欠陥」のみに統一されました。なお、欠陥1つで即落ちする、シビアな試験と変化しています。注意してください。)
ですから、時間に余裕のある人や、過去問を終わらた人は、技能の予習を兼ねて、「技能試験のテキストを読む」のも、損ではない、という次第です。
このあたりの塩梅は、皆さんの「取れる時間」で決めてください。ま、ふつうは、「4月勉強開始→6月受験」なので、そう時間に余裕のある人はいないと思います。
新傾向その2‐ガチ難問
さて、直近のH28年度の後期筆記では、「ガチ難問」が出題されています。
それは、「第11問」で、詳しくはリンク先に述べていますが、一口で言えば、「解きようがない問題」でした。
わたしが調べたところ、当該問題のテーマである「高速形漏電遮断器」と「高感度形漏電遮断器」の細かい数字に言及したテキストはありませんでした。
んなもんで、ほとんどの受験生は、答えられなかったはずです。
2電工筆記は、おおむね、どんな問題も、「勉強してさえいれば、解ける問題」が多かったのです。
しかし、当該ガチ問題のように、“重箱の隅を突くような、また、テキストには載ってそうにない選択肢で構成された、解きようのない問題”が出るようになっています。
対策は、一口で言えば、「できなくても、しゃーない」です。
で、大事なことは、こういうガチ難問で動揺しない、です。
解きようがない問題ですが、試験を全体から俯瞰すると、どこぞに、当該難問をカバーするような、やさしいド定番の問題があるからです。
難問ができなくても、他の問題で十分に点が取れます。
このように、「解きようのないガチ難問が登場しているが、それに動揺することなく、点の取れる問題をしっかりものにする」ことが、試験の心構えとなっています。
まとめ
一番最初に述べたように、2電工筆記の勉強方法「テキストを読んで、過去問を2~3回解いておく」は、大きく変わりません。
しかし、最近の筆記では…、
技能試験の内容が問われる「技能試験系問題」が1~2問…、
誰にも解きようがない「ガチ難問」が1問ほど、顔を見せています。
試験的に言えば、こういう問題は追及しない・拘泥しないのが一番です。んで、(あ、難問来たな)と思ったら、適当に好きな番号をマークすればよい、ってな塩梅です。
本試験にて、この種の問題に遭遇しても、さっさと見限って、従来の、定番・頻出問題に尽力してください。
以上、最近の筆記の「敵情偵察」でした。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月12日 10:37 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
捨て問候補一覧‐平成28年の後期の筆記試験
第2種電気工事士の筆記試験の合格ラインは「6割」です。
試験問題は「50問」出題されるので、「50×6」の「30問」を正解できれば、筆記はパスとなります。
逆を言えば、2電工は、「満点を取らなくてもよい」という次第で、手に負えない論点は「捨て問」にできる、といた塩梅です。
本ページでは、以下、文系ド素人なら「捨てても止むえない」問題を列挙します。
わたしが受験生当時に捨てていた問題、また、“今、再受験するにしても捨てる問題”を挙げていくので、試験勉強の指針にしてください。過去問に大きく「×」をしておくとよいでしょう。
逆を言えば、以下に述べる問題以外は、「すべて、取れるようになっておく」必要があります。
捨て問候補‐電気理論
「電気理論」は、おおむね8問ほど出題されるのが常です。
H28後期の筆記の電気理論で「難」なのは…、
第5問の「三相交流回路」と…、
第6問の「単相3線式回路」です。
当該2問の問題は、文系ド素人だと理解するのに時間がかかるため、ぶっちゃけ、費用対効果が悪いのです。
時間に余裕がない人は、「捨て問」にして、他の論点を憶えこむ方が絶対に賢明です。
参考:第5問
参考:第6問
なお、当該2問以外は、文系ド素人でも、ちょっとした勉強で点が取れる難易度なので、得点としてください。
捨て問候補‐電気工事系
「電気工事」の論点は、おおむね5~6問ほど出題されます。
H28後期の筆記の電気理論で「難」なのは…、
第11問の「漏電遮断器」と…、
第12問の「技能問題」と…、
第21問の「電磁的不平衡」となっています。
第11問には、テキストにはそれほど出てこない器具が出題されており、解くのは「難」です。取れなくても仕方がありません。
第12問は、「技能試験」に絡む問題で、筆記のテキストのみでは対応できない問題です。このため、取れなくても仕方がないといえます。
第21問は、技能の勉強で候補問題を解いていると、選択肢の“不自然さ”から、何とか判別は付くのですが、テキストのみの勉強では難しいでしょう。
これら3問は、『運』でしか正解できないので、わからなければ「捨て問」です。
参考:第11問
参考:第12問
参考:第21問
配線図の捨て問候補
配線図問題の捨て問は…、
第31問「3路スイッチ」と…、
第42問「複線図:コネクタの種類と個数」と…、
第43問「複線図:ケーブルの本数」と…、
第44問「複線図:リングスリーブの種類と個数」と…、
第48問「写真鑑別:工具」となっています。
「配線図」の問題では、「複線図」を理解していないと取れない問題が、多々出ます。
上記31問、42~44問がこれに該当し、文系ド素人なら、できなくても仕方がないといえます。
当該「複線図」は、理解するのに時間がかかる上、テキストのみの勉強では、ホント、理解しにくいものがあります。
ですから、「複線図」が苦手なら、上記問題群は「捨て問」にするとよいでしょう。どのみち技能でやるのですから、筆記で無理する必要はありません。
当該4つの問題が取れなくても、合格点は十分に確保できます。
参考:第31問
参考:第42問・第43問
参考:第44問
ちなみに、わたしが受験生当時は、複線図問題は「捨て問」で、問題文を読むや否や、即、3番にマークしていました。それでも、「42問」取れてパスできました。
さて、最後に、第48問の写真鑑別ですが、これは「難」でも、即「やさしい」になる問題です。
実物を知らないと間違えるが、実際に工具に触れたことがあるなら、間違えようのない問題です。
該当ページにも述べていますが、工具は筆記のときから買っておいて損はありません。
参考:第48問
まとめ
以上、「捨て問」候補を挙げました。
ぜんぶで「10問」を捨てるので、解くのは「40問」となります。
先も言ったように、合格基準は「正解30問」なので、まだまだ余裕はあります。
また、残る「40問」は、定番かつ頻出の問題で構成されており、きちんと過去問を解いていれば、まず、点数にすることが可能です。
つまり、文系ド素人でも、点の取れるオンパレードであり、また、ちょっと勉強するだけで点の取れる問題も多いです。
電気理論や配線図など、理解に時間がかかるものは、「捨て問」か「後回し」として、まずは、確実に点となる論点から消化していってください。
また、2電工は、競争試験ではありません。つまり、成績上位から一定人数を合格とする“調整”がない、といった次第です。
ガチで「6割」取れたら「合格」です。全受験生が6割取れば、全員合格です。ですから、まずは、6割取ることを念頭にがんばってください。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 11:11 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第1問:電圧の計算:電気理論‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第1問は、理論問題で定番の計算問題です。
基本的な公式と決まり事を覚えておけば、文系ド素人でも取れます。
本問のような抵抗の計算問題は、まず、「どこを求めるのか?」を見極めましょう。
でないと、無駄な計算をしてしまい、たとえば、並列回路の合成抵抗を計算したりで、混乱しかねません。
本問は、「右側部分の4Ωの抵抗にかかっている電圧」を求めるわけです。
「V=IR」です。Rは4Ωと判明していますから、残るは「I」を求めればいいわけです。
当該Iを、左側の並列回路で求めればよい、という次第です。
解説
本問のキーは、「並列回路」にかかっている電圧は同じ、であることです。
上の画像の赤点線で囲んだ並列回路の、真ん中の「8Ω」には、「1A」流れています。
ということは…、
「V=IR」ですから、「V=8*1」で「8V」がかかっているわけです。
当該「8V」は、並列回路の上の「4Ωと4Ω」のところにもかかっています。
直列なので足せばいいだけなので、「8Ω」に「8V」な塩梅です。
電流(I)は、「I=V/R」なので、「8/8」で「1A」となります。
並列回路の下のところも同じ要領で…、
「I=V/R」で「8/4」で「2A」となります。
これで、並列回路に流れるAがわかりました。
上から「1+1+2」で、合計「4A」です。
当該「4A」が出たら、答えは出たようなものです。
「4A」が「4Ω」のところに流れていますから…、
「V=IR」で、「V=4*4」の「16V」となります。
んなもんで、答えは「イ」となります。
まとめ
本問は、基本的な計算問題で、「オームの法則」と「並列接続には同じ電圧」さえ知っていれば、問題が解けます。
本試験では、おおむね第1問目に、本問のような計算問題がでます。
電気理論には、文系ド素人には厳しい問題が多々あります。
ですから、本問のような、少々の公式知識と、掛け算と足し算で解ける問題は、実に貴重です。
何度も練習して、必ず解けるようになっておきます。
また、本試験では、本問と似たような計算問題が出るので、オームの法則の使い方などを、本問でしっかり練習しておきましょう。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 11:03 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |