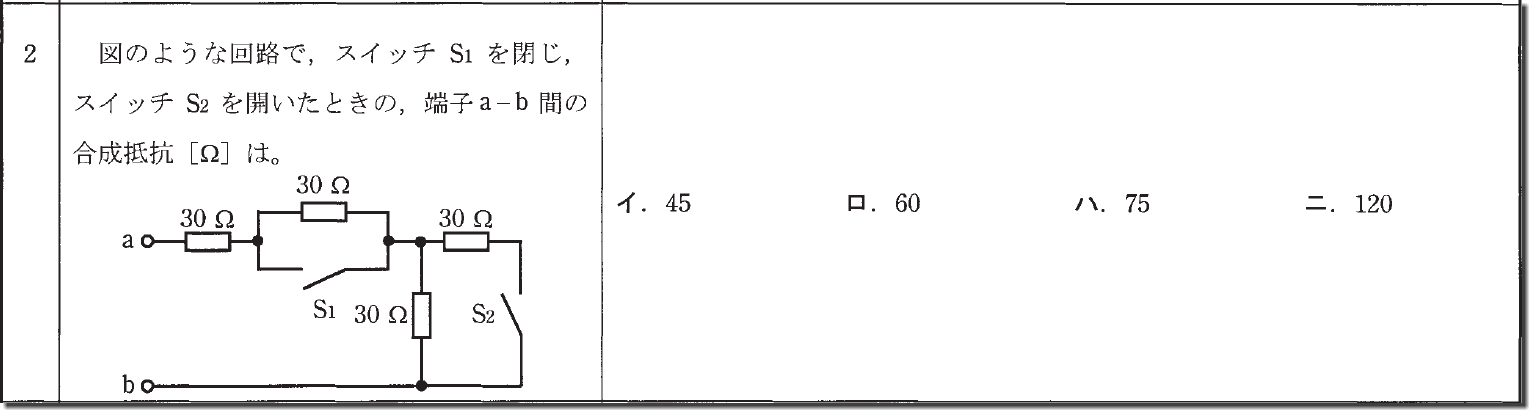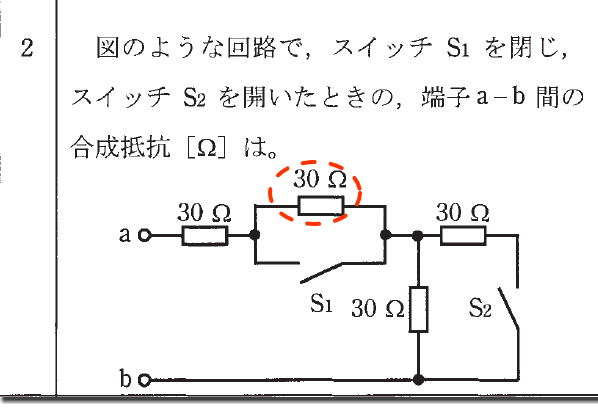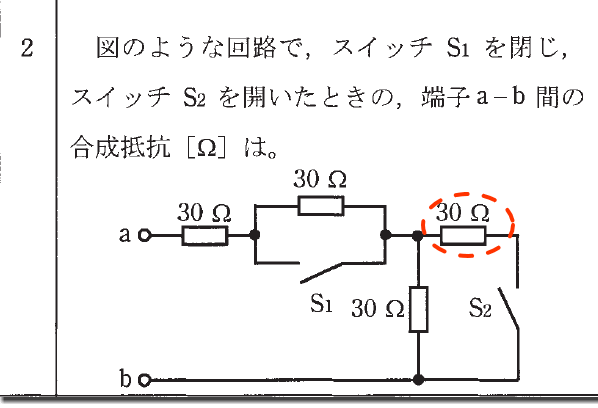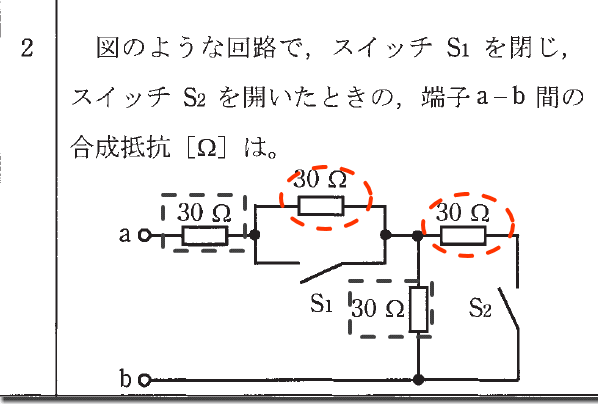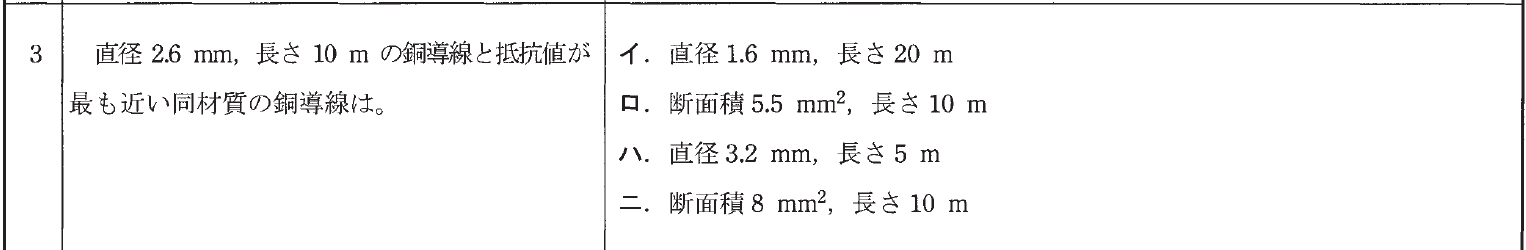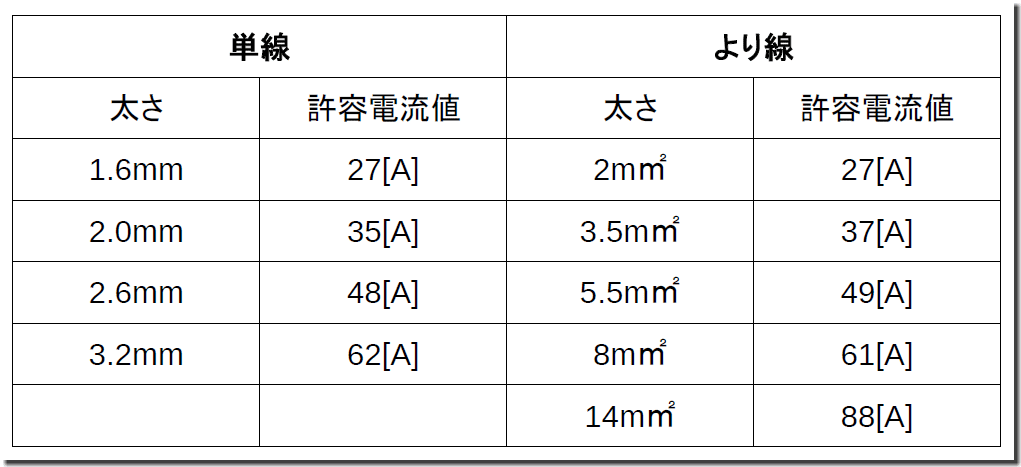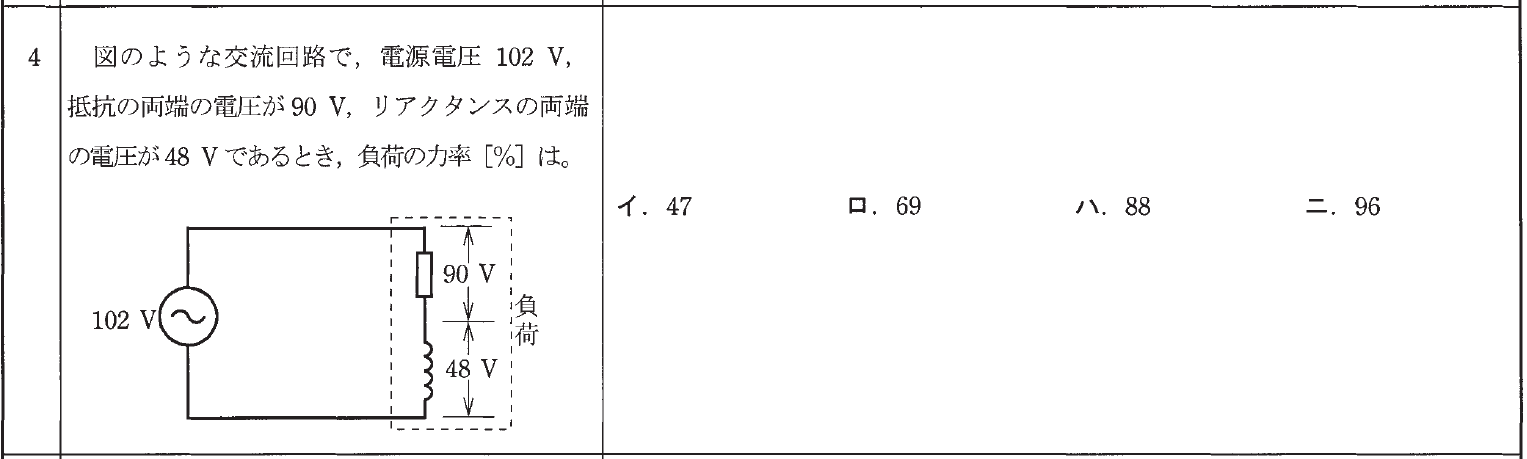第2問:電圧の計算:電気理論‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第2問は、「電気の基本的な知識」を問う問題です。
本問を解くには、電気の常識「電気は流れやすいところに流れる」を知っていることが必要です。
本問は、解説を読めば(なーんだ)の問題なのですが、緊張する本試験で本問が出たら、かなりの受験生が混乱して、上手に解けないはずです。
こういう問題の存在を、しっかり頭に叩き込んでおきましょう。
解説
スイッチ1(S1)を閉じると、電気は、下のスイッチのところを流れます。
反対に言えば、上記画像の赤点線で囲んだ「上側の30Ωの抵抗」のところに、電気は流れません。
先に言ったように、「電気は流れやすいところに流れる」からです。
んなもんで、「上側の30Ωの抵抗」は、無視できるという塩梅です。
さて、スイッチ2(S2)ですが、問題の指示では、「スイッチ2は開く」とあります。
要は、「電路がつながってない」わけで、電気は流れません。
んなもんで、上記画像の赤点線で囲んだ30Ωのところに電気は流れず、従って、無視できるという寸法です。
説明
ここまで到達すれば、後は、足し算だけです。
上記画像のように、赤点線部分は無視で、黒点線部分に電気が流れることになります。
本問だと、抵抗が直列で接続されていることになるので、「30Ω+30Ω」で「60Ω」となり、答えは「ロ」と相なる次第です。
まとめ
本問は、基本的な電気知識を問う問題です。
まあ、直列接続の合成抵抗の出し方がわからない人はそういないでしょう。
ただ、先述したように、本問は『出題がシンプルなだけ、難しく考え過ぎて、自滅する』傾向があります。
本試験では、こういうシンプルな問題もあると、頭の片隅に置いていてください。
本問も、文系ド素人でも取れる数少ない電気理論の問題です。
何度も練習して、必ず解けるようになっておきます。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 11:03 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第3問:電気抵抗:電気理論‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第3問は、「電気抵抗」の公式を使った計算問題です。
「電気抵抗」の公式とは…、
R=ρL/S
…です。
Rは抵抗(たぶん、レジストのR)で、「ρ」は「ロー」で抵抗率、Lは長さ(たぶん、レングスのL)、Sは断面積(たぶん、スクエアのS)となっています。
本公式は、銅銅導の太さが「断面積」の場合に、使います。
なお、銅銅導が「直径」の場合は…、
R=4ρL/πD2
…となります。
「D」は直径です。(たぶん、ダイアメタ:diameterのDです。)
解説
本問は、先の公式で計算するのですが、実は、「絶縁電線の許容電流」の表を憶えていると、計算せずに解けます。
ポイントは、問題文には、「ほにゃららに近い銅材質の銅導線」となっているところで、「近い数字」ならよいという塩梅で、反対に言えば、「一致しなくてもよい」といった次第です。
んなもんで、「絶縁電線の許容電流」の表でざっくり求めてよい、という次第です。
問題文の「直径2.6mm、長さ10mの銅導線」を、当該表に照らし合わせると、許容電流値は「48A」です。
当該許容電流値「48A」に“近い”のは、「より線の5.5mm2」の「49A」となります。
問題文の銅導線は「10メートル」で、選択肢「ロ」のそれも同じ「10メートル」なので、長さも問題ありません。
んなもんで、答えは「ロ」となります。
説明
先の公式を当てはめて、答えを求めることができますが、面倒なので各自でしたい人だけしてください。
なお、「イ」の選択肢は、「直径」なので、「R=4ρL/πD2」で計算します。
「ハ」も、「直径」なので、「R=4ρL/πD2」で計算します。
「ニ」は、「断面積」なので、「R=ρL/S」で計算します。
計算機を叩いてアレしてください。
まとめ
本問は、電気抵抗の公式を使わずとも、「絶縁電線の許容電流」の表で解くことができます。
試験的に言えば、公式の計算は面倒すぎるので、当該「絶縁電線の許容電流」の表で解くのがベターかと思います。
数字さえ憶えれば本問は解けるので、暗記に勤めましょう。
なお、先の公式は、単独で出題される公算が「大」なので、文系ド素人は、必ず憶えましょう。
文系ド素人でも取れる数少ない電気理論の問題なので、「表で解く」「公式で解く」で何度も繰り返してして、必ず解けるようになっておきます。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 11:01 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第4問:力率(抵抗とコイルの直列接続):電気理論‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第4問は、「抵抗とコイルが直列接続された回路の力率」の計算問題です。
文系ド素人だと、どっと冷や汗が流れますが、本問は公式さえ憶えていれば解ける問題で、しかも、計算そのものは実にカンタンです。
こういう問題こそ、文系ド素人は取らなくてはいけません。
食わず嫌いをせず、執拗に点の取れる問題を、追及してください。
解説
本問は、並列回路の力率の公式に、数字を当てはめるだけです。
公式とは…、
cosθ=Vr/V
…です。
本問の設定は、電源電圧は「102V」で、抵抗にかかる電圧は「90V」です。
そのまんま公式に当てはめて…、
cosθ=90/102
≒0.88
…と相なります。
んなもんで、答えは「ハ」となります。
まとめ
本問は、シンプルな問題です。ぜひとも解けるようになっておきたいです。
なお、本問の論点である「単相交流回路の電力と力率」は、たとえば、「有効電力」や「力率」、「力率の改善」など、「公式さえ頭に入っていればなんとなる」問題が多いです。
ぶっちゃけ、捨てても他でカバーできるので、当該論点は、ばっさり捨ててもいいです。
しかし、最近の本試験の傾向は、「計算問題がやや易しいのだけど、他の問題で、手ごわい問題が増えている」のです。
んなもんで、できる範囲で、少しずつ押さえていく方が、『安全』です。
文系ド素人には面倒かと思いますが、それでも、保険の意味で、少しずつ消化していきましょう。
ま、「理解」より「暗記」で、合格点は確保できます!
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 11:00 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |