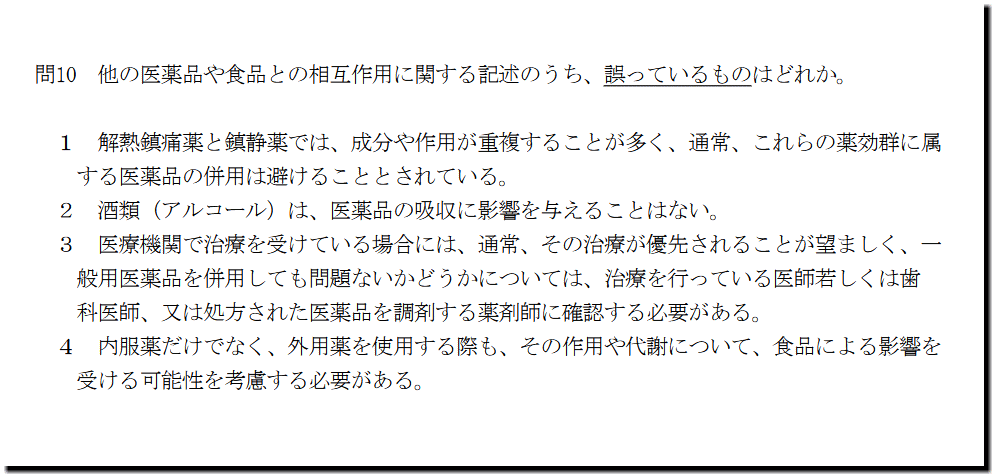登録販売者 香川県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)第10問
まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。
本問は、「基本知識」の「相互作用2」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
香川県 第10問‐相互作用2
(クリックして拡大。)
難易度コメント+こたえ
本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1
選択肢1の「解熱鎮痛薬と鎮静薬では、成分や作用が重複することが多く、通常、これらの薬効群に属 する医薬品の併用は避けることとされている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
常識的に判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2
選択肢2の「酒類(アルコール)は、医薬品の吸収に影響を与えることはない。」ですが、誤った記述です。
全体的に間違ってますね。
常識的に、薬を酒で飲んじゃダメと判断できると思います。
なお、手引きには…、
「酒類(アルコール)は、医薬品の吸収や代謝に影響を与えることがある。」
「アルコ ールは、主として肝臓で代謝されるため、酒類(アルコール)をよく摂取する者では、肝臓 の代謝機能が高まっていることが多い。」
「その結果、肝臓で代謝されるアセトアミノフェンな どでは、通常よりも代謝されやすくなり、体内から医薬品が速く消失して十分な薬効が得ら れなくなることがある。」
…とあります。
太文字部分がよく出ます。テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3
選択肢3の「医療機関で治療を受けている場合には、通常、その治療が優先されることが望ましく、一 般用医薬品を併用しても問題ないかどうかについては、治療を行っている医師若しくは歯 科医師、又は処方された医薬品を調剤する薬剤師に確認する必要がある」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
また、「適正使用」の「相談すること」を思い出してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4
選択肢4の「内服薬だけでなく、外用薬を使用する際も、その作用や代謝について、食品による影響を 受ける可能性を考慮する必要がある」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「外用薬や注射薬であっても、食品によって医薬品の作用や代謝に影響を受ける可能 性がある。」
…とあります。
なぜか全国的によく問われる記述なので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
答え
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
「誤っているもの」は…、
正解:2
基本知識
令和6年度 香川県
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
独学向け教材
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者 過去問題集 '26年版 (2026年版) 」を使えば支障ありません。
こまごましたもの
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
★みんなとシェアする
基本知識
登録販売者
概要
独学シリーズ
対策シリーズ
勉強方法
過去問+解説
├チェック問題 過去問リスト
├漢方 過去問リスト
├生薬 過去問リスト
├全ブロック 試験問題 科目別
├「医薬品的な問題」過去問リスト
├「添付文書」過去問リスト
└「資料問題」過去問リスト