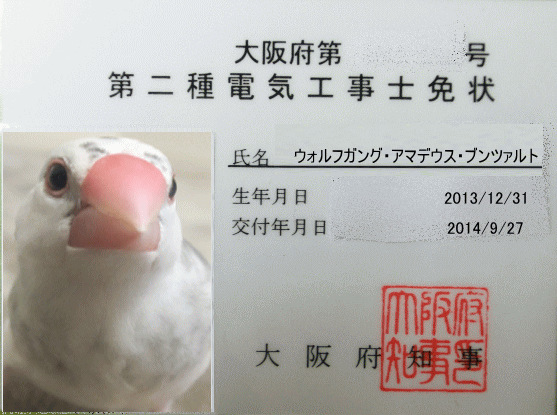第2種電気工事士の独学‐令和8年度(2026年度)試験対応
まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。
第2種電気工事士に独学合格するためのページです。独学に必要な教材の解説を文系理系に分けて述べたり、学科試験と技能試験の必須の独学ノウハウを提供する。そのほか、やってはいけないダメ勉強の紹介、過去問解説や再受験対策へのリンクも。CBT方式についても加筆。
第2種電気工事士の独学‐インデックス
【告知】令和8年度上期学科の受験生へ
上期試験の申込期間は、「3月16日(月)~4月6日(月)」です。早々に申し込みましょう。学科は何とでもなります。
CBT方式(パソコン試験)は、“申込期間”が「4月10日(金)~5月15日(金)」の「36日間」です。
そして、CBTの“受験期間”は、「4月23日(木)~6月7日(日)」の「46日間」です。
んで、筆記方式は、「5月24日(日)」です。
CBTだと、学科より1カ月強早く試験が受けられるのに加えて、学科より2週間遅れて受験でき(要は、14日間プラスして、試験勉強ができるようになった)、かなり時間の幅があります。
後述しますが、わたしは、技能が有利になるCBT方式の受験を勧めます。
まあ、どっちで受けるにせよ、さっさと申し込んで、学科の勉強を進めてください。学科は、ホント、過去問演習で何とでもなります。
最後に、独学だと公式情報に疎くなります。「当方のTwitter」で各種告知を行うので、心配な人は、フォローしておいてください。
んでは、本文です。
第2種電気工事士の独学ガイダンス
第2種電気工事士に独学合格するためのページです。
ブログ更新
最新ブログは、「第2種電気工事士の学科に複線図が出る背景」です。複線図を捨てる理由がこれです。
最新試験情報
直近の「学科試験 令和7年度(2025年度)下期試験」ですが、まあ新手の問題もあったりでしたが、全然対応可能でした。
「2電工筆記の要チェックの難問・奇問・珍問・ひっかけ問題リスト」に挙げた問題がそこそこ出たので、ぜんぶ解けるようになっておきましょう。
んで、前々回の「学科試験 令和7年度(2025年度)上期試験」に、考えさせる問題が出題されています。「第25問:絶縁抵抗器」です。
学科試験のほとんどは、暗記問題なのですが、突然、こういう思考系の問題が出るので、傾向把握として見ておきましょう。
次に、近年では出題されてなかった「小出力発電設備」が、再登場です。「一般用電気工作物」の選択肢イです。
かつての定番論点です。これから出そうな感じがプンプンします。テキストをチェックですよ。
最後に、資料をシッカリ読めば解ける問題が「第41問:図記号器具写真鑑別」で、再出題されています。これも、見ておきましょう。初見では絶対に解けないと思います。
教材は、こう買う。
学科用に買う教材は、文系か理系かで、そして、電気工事経験の有無で、異なります。
理系か、または、電気工事経験者‐お安く済ませる
理系の方や電気工事経験者は、学科のテキストは、好きに選んでいいです。
試験が試験なので、どれを使っても同じです。安いものか、amazonで高レビューのものを買えばいいでしょう。
選ぶのが面倒なら、文系用の「 ぜんぶ絵で見て覚える第2種電気工事士筆記試験すいーっと合格(2026年版) 」でいいです。これも、高評価です。
さて、過去問ですが、当方の「公式過去問+解説 インデックス」で、公式のPDF過去問に解説を付与しています。これを利用すれば、新たに買う必要はないです。
「問題番号科目対応表」を参考に、過去問演習をしてください。
2電工は、費用が掛かるので、支出は押さえましょう。
文系・電気ド素人‐金をかけて手厚く
テキスト選びで困るのが、文系の方や電気工事のド素人の人です。
わたしもそうでしたが、理系っぽい四角四面のものは、読み通すことすらできないです。
ですから、文系でも読めて、かつ、挫折しないものを選ばなくてはいけません。
わかりやすさを徹底してください。安物は厳禁です。教材費をケチってはいけません。
テキストに薦めるのは、「 ぜんぶ絵で見て覚える第2種電気工事士筆記試験すいーっと合格(2026年版) 」です。漢字が少なくて絵入りなので、文系でも読み通せます。
過去問で薦めるのは、「 すい~っと合格赤のハンディ ぜんぶ解くべし!第2種電気工事士 筆記過去問2026 」です。文系・電気ド素人だと、いきなりPDF過去問を解こうとしても、途方に暮れるだけです。本書で、ワンクッション入れる方がいいです。
教材の詳細は、「学科試験の教材」です。ここを読んで買うかどうか、決めてください。まあ、両方とも、2電工のド定番なんで損はないです。
技能の教材を買う
学科試験は、技能試験への橋渡し的な存在のため、技能試験で使う工具や材料が、よくよく学科でも問われます。
よって、技能の教材のうち、工具と材料は、文理ともども、そして、経験者・ド素人ともども、学科の段階で買っておく方が合理的です。
たとえば、ケーブルの「EM-EEF」や、コンセントの「EEF」と「20A 250V E」とかです。
工具では、「リングスリーブ用圧着工具」が、「R4 上期午前 第48問‐工具 写真鑑別」や「R2 下期午前 第50問‐写真鑑別」、「R2 下期午前 第42問‐接続作業」で、頻出工具となっています。
手元に実物があると、すぐ憶えられます。どのみち学科に受かれば買うのですから、先に買って学科に活かすべきです。
技能の教材は、「技能 教材レビュー」にまとめていますが、読むのが面倒な人は、定番メーカーの「ホーザン(HOZAN) 基本工具 DK-28
」
と、
「ホーザン(HOZAN) DK-52 2回セット
」で揃えればよいでしょう。
ちなみに、工具・材料は、いろんなシリーズがありますが、電気用品安全法の規制があるので、どれもいっしょです。
学科は気楽だが、技能は精神的にガチ。
一口で言うと、「第2種電気工事士は、技能が精神的にキツイ。学科は、勉強したらまず受かる。」です。
学科試験は、過去問を何回か解いておけば、落ちることはないです。テキストと過去問を消化すれば、まず、落ちません。正直、あんまり気にしないでいいです。
対して、技能は、欠陥1つで落ちる試験なので、キッチリ勉強していても、ケアレスミス1つで不合格になります。
ケアレスミスをゼロにはできません。よって、技能は、誰でも落ちる可能性があるわけです。注意すべきは、圧倒的に、技能の方です。
技能中心に考えよう
ところで、学科の受験方法に、「CBT方式」があります。
当該CBTを、試験開始の初日に受けると、最長で1ヶ月強、技能の勉強期間が延びるメリットがあります。
第2種電気工事士の独学では、技能に時間と手間を割きたいので、CBT方式をお勧めします。(好きな日に受けれるのも○。)
CBT方式の詳細は、「CBT方式(パソコン試験)とは?‐メリット・デメリット・最大活用法」を、一読願います。
なお、余談ですが、技能では、一切通電しません。よって、危険な作業は、ほとんどありません。老若男女、安心して受験してください。
学科の独学
学科試験は、暗記と記憶の試験です。
「最低限の暗記リスト」にあるものだけは、最低限度、すべて暗記してください。このページの公式・表を憶えるだけで、5点は固いです。
次に、語呂合わせや憶え方のブログがあります。「位置表示灯(H)と確認表示灯(L)の図記号の憶え方」といった感じで、多少は暗記に役立つかと思います。
こうしたサポートブログを「サイトマップ」に一覧化しているので、活用願います。
また、「学科の勉強方法」も、参考にしてください。
捨てるところ
文系・理系ともども、費用対効果の悪い「複線図問題」を、捨てていいです。「R5 上期午前 第34問:最少電線本数」といった問題は、捨てます。
複線図問題ができなくても、他で合格点を十分に確保できます。一抹の不安のある人は、「学科に複線図が出る背景」を、一読をば。
次に、文系の人は、挫折要因の「電気理論」を、とりあえず捨ててください。試験勉強の邪魔です。
当該電気理論は、学科をぜんぶ終えた終盤で、文系でも取れるものに絞って勉強するといいでしょう。
「令和4年度 上期午前 第2問:抵抗・許容電流」といった文章問題は、問いと答えを憶えたらいいです。
カンタンな計算問題や合成抵抗の問題も、取れます。「令和5年度 下期午後 第1問:消費電力」や「令和1年度 下期午後 第1問:合成抵抗計算」といった問題です。
過去問をパラパラ見て、こういう取れそうな理論問題に、手を付けましょう。最終得点にプラス1~2点できて、かなり合格に有利です。インピーダンスとかは捨てましょう。
過去問やれば受かる
学科試験は、過去問の使い回しが大半です。新規の出題は、2~3年に1回くらいなので、過去問さえシッカリ消化していれば、ほぼ合格点(6割得点:50*0.6の30問正解)を確保できます。
問いと答えを暗記するだけでもいいです。たとえば、「R3 上期午後 第22問」だとコンクリが答え、とかです。
「最悪の勉強方法」も、参考にしてください。
チェック問題リスト
学科試験は、奇問や難問すら使い回されます。
これまでの試験で出てきた、なんだこれ??問題を、「要チェックの難問・奇問・珍問・ひっかけ問題リスト」に、まとめています。
試験終盤に解いて、最終得点にプラス1~2点してください。
勉強の順番
学科の論点は、簡単にできて、消化しやすくて、即、点の取れる順でやるといいです。
文系の人なら、「図記号→写真鑑別→電気機器→検査→法令→配線設計・配線理論→電気工事」といった感じです。
法律に素養がある人(法学部卒・宅建持ち)なら、「法令」からやるのも一手です。
図記号は、正直、小学生社会のレベルで、すぐ得点源となります。「学科 一問一答」を活用して、暗記に努めてください。
電気理論とか配線設計・配線理論とか電気工事とか、一目見て嫌になるところは、「後回し」でいいです。
最新傾向
近年の過去問で、新傾向の問題を「学科試験 直前チェックリスト」にまとめています。
このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前に読んでください。
技能の独学
技能試験は、実技試験のため、かなり不安かと思います。わたしもそうでした。
しかし、技能最大のノウハウは、「暗記」です。技能も、「暗記」で受かります。
作業がヤヤコシイところは、組み方を暗記すればいいだけです。
「R8(2026)候補問題解説」に暗記ポイント指摘しています。活用願います。
なお、技能試験にでる問題は、毎年1月に公式が公開する「候補問題」と、“ほぼ”同じです。
(これまでずっと一緒です。ですから、これからも、一緒です。単に公式が「同じ問題を出す」と明言していないだけで、同じ問題が出てます。また、急に問題を変えると、今の受験生が過去の受験生と比べて、明らかに不利になるので、公平・公正の点からも、同じ問題を出し続けるように思われます。)
なお、技能の細かいことは、「技能の勉強方法」にまとめています。適宜に活用ください。
欠陥1つで落ちる
技能試験の最たる特徴は、「欠陥1つで落ちる」採点基準です。精神的にすごくキツイです。
肝に銘じてください。技能は、ケアレスミス1つで落ちるため、誰しも、不合格となる可能性があります。
候補問題を解くときは、どこに欠陥ポイントがあるか、ガチ把握してください。
候補問題を作っただけで満足しないでください!!!仕事は、その後の答え合わせ(欠陥の有無チェック)です。
お手本どおりにやる
技能試験の独学では、自己流は、厳禁です。
特に、電気工事経験者の人です。試験なので、試験のやり方を順守してください。“現場では・実務では”といった文言を封印し、試験が望むことをしてください。
すべての作業を、テキストのお手本に従って、行ってください。
お手本のやり方が、間違いのない安全なやり方です。
お手本のとおりにやれば、「欠陥」を取られることがありません。
お手本のやり方を省略するのも、お手本に付け加えるのも、ダメです。
お手本どおりに組めば、絶対合格です。“自分のやり方”なんて、犬も配偶者も食いません。技能に“個性”は、無用です。
必ず時間を計る
技能の勉強では、「必ず時間を計る」ようにしてください。
候補問題や個々の作業には、「目標時間」が設定されています。
たとえば、「輪作り」なら「90秒」といった塩梅です。
技能の勉強では、当該「目標時間」内に作業を完了させることを、「最優先目標」としてください。
なぜ、「目標時間」を守らないといけないかというと、その時間内にできないと、欠陥の「未完成」で落ちるからです。
技能の本試験は、「40分」です。
当該40分という時間は、すべての作業・施工を、設定された「目標時間」で作業できて、“ようやく”間に合うというのが、実感とするところです。
よって、練習のときに、個々の作業が「目標時間」内にできない場合、本試験では、まずもって時間が足りなくなり、「未完成」で落ちます。
技能は、時間との戦いです。のんびり考える時間は、一切ないです。
時間内にできたかどうかを把握するには、作業の時間を計測する必要があります。
スマホの時計アプリやストップウォッチで、必ず時間を計り、個々の作業に、どのくらい時間がかかっているかを把握してください。
そして、「目標時間」で完了できるように、余分な動作や余計な動作を洗い出してください。
測った時間は、1回目〇〇分、2回目××分といった感じで、テキストの余白なりにメモしておきましょう。復習や特訓の目安になります。
わざと失敗して直す
第2種電気工事士の技能独学の最大ノウハウです。
技能の終盤あたりで、わざと失敗して、それを直してください。これが、実に効き目があります。
詳細については、長くなったので、「最後の仕上げはわざと間違えて敢えて直す」にまとめています。
試験で最も怖いのが、ケアレスミスなのですが、当該作業で、ケアレスミスのカバーが可能になります。また、“あまりにもケアレスミスが怖くなる”ので、ケアレスミスの発生を最小限度に押さえられます。
プラスしかないです。ぜひ、「わざと失敗して直す」を、取り入れてください。
先に挙げた「R7(2025)候補問題解説」に、「わざと失敗するところ」を挙げているので、参考にしてください。
プチカンニング
技能試験の当日の超絶ノウハウです。
技能の本試験では、試験開始前に、試験に使う器具・ケーブル等がそろっているか、確認する時間が設けられています。
そのため、試験開始前に、どの候補問題なのか、“ある程度”把握が付くのです。
また、問題冊子が透けて中が見えることもあり、これまた、どの候補問題が出ているのか、“ほんのり”わかるのであります。
試験開始前に、どの候補問題なのか把握して、頭の中で複線図を書いていってください。
当該プチカンニングで、複線図を書く時間をかなり短縮できます。
技能試験は、時間との戦いで、1分1秒とも無駄にできません。
“合法的なプチカンニング”で、試験の始まる前の確認時間も、有効利用してください。
本試験直前
以下の記述は、本試験が近づいてからのものです。このページを「お気に入り」に入れておいて、本試験が近づいたら、一読願います。
試験の注意事項や復習ポイント、直前期でやることを述べたのが、「技能 直前チェックリスト」です。ダメ押しで見ておいてください。
そして、是非とも読んでおいてほしいのが、「持ち込める物・不可の物」です。特に、持ち込めないものを、確認してください。
補足1:文系ド素人が落ちるところ
文系ド素人の方が、技能で落ちる最たる要因が、「輪作り」です。
技能の数ある作業のうち、最も苦労するのが「輪作り」です。
わたしもそうでしたし、当該輪作りが余裕だったという人に、会ったことがありません。
「輪作り」で手間取って、時間切れになったり、見直し時間がなくなって落ちます。文系ド素人の鬼門です。
当該輪作りは、毎日必ず練習して、無意識でも、朝起きた直後でも、べろべろに酔ったときでも、配偶者が近くにいるときでも、短時間で完成できるよう、徹底練習してください。本試験前日まで練習しましょう。
次に、鬼門なのが、「ウォータレンチプライヤ」です。独学の盲点となりがちなところで、使い方が思っている以上に“違い”ます。
当該ウォータレンチプライヤを使う候補問題は、「11問:ねじなし管」と「12問:PF管」です。
文系ド素人の方で、ウォータレンチプライヤが初めての方は、必ず、正しい使い方を押さえておいてください。
補足2:複線図
学科では奇問だった複線図ですが、技能となると、言うほど、困りません。実戦がすぐ控えているので、理解は、とてもスムーズです。
テキストのやり方を真似すれば、問題ないですが、それでも、苦手な人は、文系ド素人向けの「R7(2025)複線図練習」を、参考にしてください。
やってはいけないダメ勉強
第2種電気工事士の不合格者に共通する「ダメ勉強」を挙げておきます。以下の…、
- 学科アルコール。
- ノートを作る勉強。
…を、“やらない”だけで、合格が近づきます。
ダメ1‐学科アルコール
まず、やってはいけない筆頭は、「アルコールを飲みながら、学科の勉強をする」です。
技能の勉強は、軽く一杯やりながらでも構わないのです。しかし、学科では、アルコールは、厳禁です。
技能は、“身体で憶える”勉強なので、ほろ酔いでも、そう支障ないです。逆に、冷静でない自分がどのようなミスをするか、“いい経験”にすらなります。
しかし、学科では、絶対に、飲みながら勉強してはいけません。
嫌な事があったときはお酒を飲みますが、それは、アルコールが「忘却剤」だからです。学科の勉強は、暗記なので、アルコールは相性が悪すぎます。
技能は少々はOKですが、学科では、絶対禁酒です。
ダメ2‐ノート
次に、「ノートを作る勉強」ですが、第2種電気工事士では、ノートを作るような論点は「ない」です。
作るのは“まとめメモ”や“暗記メモ”くらいです。
ほとんどの受験生は、ノートを作らず、合格しています。わたしも、作りませんでした。
ノート作りは、時間と労力の無駄です。
2電工の独学では、こうしたダメ勉強をしないでください。落ちる人は、だいたい、そうやっていました。
公式過去問+解説
本試験を実感するには、公式のPDF過去問を解くのが一番です。
PDF過去問は、「https://www.shiken.or.jp/construction/second/qa/」からダウンロードできます。
当該公式のPDF過去問ですが、問題と答えはあるも、解説がありません。
そこで、手前味噌ながら、解説を付与しています。以下の…、
「R5 上期 午前筆記」や「R5 上期 午後筆記」…、
「R5 下期 午前筆記」や「R5 下期 午後筆記」…、
「R4 上期 午前筆記」や「R4 上期 午後筆記」…、
「R4 下期 午前筆記」や「R4 下期 午後筆記」…、
「R3 上期 午前筆記」や「R3 上期 午後筆記」…、
「R3 下期 午前筆記」や「R3 下期 午後筆記」…、
…を使って、過去問演習をしてください。
なお、当該過去問のインデックスページは、「2電工過去問+解説」です。
再受験対策‐試験に落ちた人が読む
学科に落ちた人は、ひとまず「学科 不合格 再受験対策(チェックポイント+べからず集)」で、何がダメだったか、明白にしましょう。
なお、「学科 教材買い替え」でも述べていますが、学科のテキスト・過去問は、「再利用可能」なので、買い替える必要はないです。
次に、技能が不合格だった人は、「技能 不合格 再受験対策」で、ダメだったところを慎重に調査し、『自分が何のミスをしたか』を、特定してください。
まずは、反省から、です。欠陥の見落としが“かなり”あるはずです。
技能の教材ですが、テキスト・工具は続けて使えますが、ケーブル等を追加する必要があります。
「技能 教材買い替え」で、必要なものを早々に入手してください。
リンク集‐第2種電気工事士のこまごましたもの
勉強時間については、「第2種電気工事士の勉強時間」を参考をば。
難易度については、第2種電気工事士の難易度」を参考までに。
第2種電気工事士という資格については、「第2種電気工事士:独学資格ガイド」に、まとめています。
なお、すべての記事は、「サイトマップ」に挙げています。
★みんなとシェアする
第2種電気工事士
学科 過去問
技能 候補問題解説
学科対策
技能対策
├技能試験対策・練習ミス編
├技能試験対策・本試験レポート
├技能試験対策・本試験ミス
├技能 直前チェックリスト
├持ち込める物・不可の物
├技能 不合格 再受験対策
└技能 教材買い替え