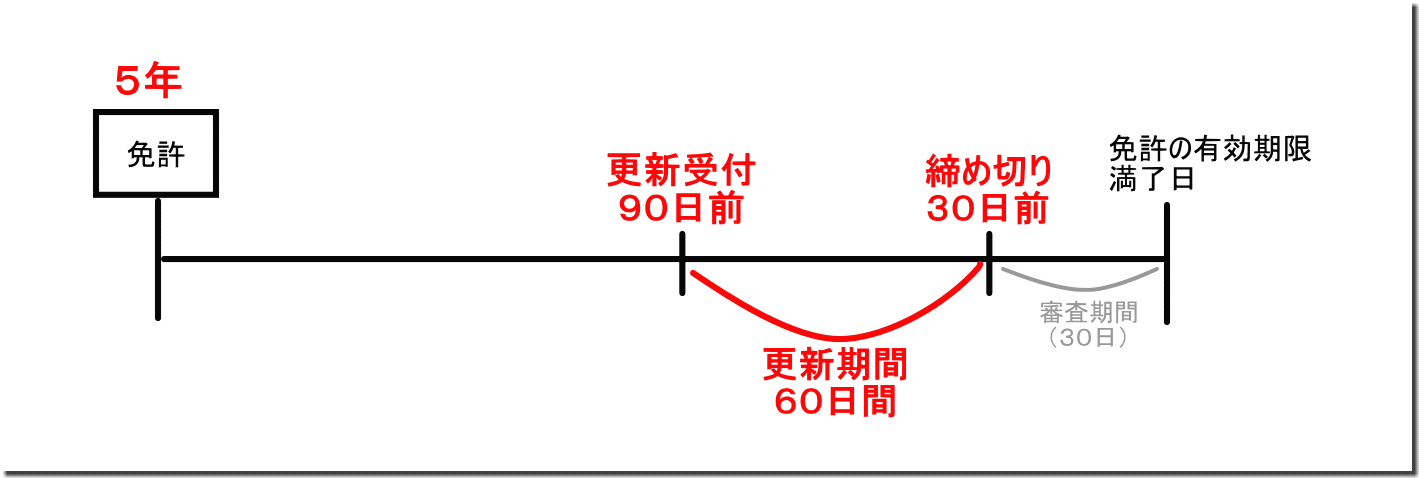宅建無料ノート:宅建業法‐免許区分と更新・・・重要ポイント直前チェック
「免許」の基本事項は、あまり試験には出ませんが、「ひっかけ」で登場する可能性が大なので、押さえておくべきです。
以下に、ポイントだけを列挙しておきます。有効期間と免許更新には、語呂合わせもあるので、復習や記憶の確認、テキスト読解の一助に。
免許区分
「免許区分」ですが、「2以上の都道府県」に、「事務所」を設置した場合に、「大臣免許」となります。
ひっかけ頻出地点なので、正確に憶えましょう。
キーワードは、「2以上の都道府県に、事務所を設置」です。
同一県内に2以上の事務所を設けるなら、大臣免許ではなく、「知事免許」です。
「事務所」にも、気をつけてください。
定義は、「継続的業務施設で、契約締結権限のある使用人(支店長等)が常時勤務するところ」です。
ですから、バイトやパートしかいない紹介所や案内所、受付所、簡易テントの営業なら、「事務所」には該当しない、ってな寸法です。
よって、それらを他県にいくつ設けても、「知事免許」でOK、ってな寸法です。
免許効果
端的に言うと、知事免許で、全国営業が可能です。
たとえば、大阪府知事免許で、東京都内で営業できます。神奈川知事免許で、群馬県で営業できます。
「知事免許・・・当該知事の都道府県のみ営業可能」で、「大臣免許・・・全国営業可能」ではないので、勘違いにご注意ください。
営業だけなら、知事免許で、日本全国、どの都道府県でも、可能です。
知事免許か大臣免許かは、県跨ぎの事務所数の違いだけです。
大臣免許申請
大臣免許は、「経由申請」です。
大臣免許を申請する際は、主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請することになります。
大臣に直接申請するのではないので、注意してください。
免許申請のみならず、「変更届」、「廃業届」も、「経由申請」です。
しかしながら、「書換え」「再交付」「返納」は、大臣に、直接行います。
これらは、「経由申請」ではなく、「直接申請」なので、要注意です。いつか、必ず、ひっかけ問題で出るはずです。
免許の有効期間と更新
免許の有効期間と更新には、語呂合わせがあるので、それで憶えるとよいでしょう。
有効期限は、「5年」。
更新の申請は、「期限切れの日の90日前から30日前まで」に行います。
つまり、申請期間は、「60日間」です。
んで、期間満了の「30日前」は、「審査期間」となっています。
図示すると…、
…となります。
数字の憶え方ですが、先の図を、左から見ていって、「免許更新、ごくろーさん(5・9・6・3)」です。
言うまでもなく、「5」は、有効期限の「“5”年」です。
「9」は、申請受付の「“9”0日前」に該当します。
「6」は、申請期間の「“6”0日」に該当します。
「3」は、受付締め切りの「“3”0日前」に該当します。
「免許更新、ごくろーさん(5・9・6・3)」で、即、数字は憶えられるはずです。
宅建業の免許更新の申請は、車の免許更新と違って、有効期限ギリギリまでではないので、注意しましょう。ひっかけ臭がプンプンします。
過去問ポイント
「免許」では、なんだか変なところが出るので、過去問のポイントを列挙しておきます。
業務停止中
免許の更新は、業務停止処分を受けていても、することができます。
過去問参考:H28 問35‐選択肢2
『法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。』
「×」です。先に見たように、申請可能です。
更新処分がない
規定どおりに申請しても、審査期間内に、免許が下りないときがあるようです。
この場合、車の免許と同じ感じで、前の免許は、有効期限を過ぎても、有効です。よって、営業可能です。
過去問参考:H29 問36‐選択肢1
『宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。』
「×」です。先に見たように、営業可能です。
なお、審査期間内に更新がなかったが、それ以後に、無事、免許が下りた場合、かつての免許の有効期限満了日の翌日より、5年間有効となります。
免許が下りた日から5年ではないので、注意してください。
まあ、問題のない業者なら、審査期間内に免許は下ります。下りないのは問題のある業者なので、わざわざ、有効期限を延ばす必要もない、ってな寸法かと思われます。
更新しなかった
免許を更新しなかった場合、当然、免許が失効します。
期間満了失効の場合、免許証を、返納する必要はありません。
過去問参考:H28 問35‐選択肢1
『個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。』
「×」です。期間満了失効のときは、免許証を、返す必要はありません。
ここは、バリバリのひっかけポイントです。
免許取消による失効、廃業による失効、免許換えによる失効だと、当然、免許証を返納します。
整理して憶えましょう!!
また、「宅建士証」との違いに、注意してください。
期間満了失効の場合、免許証は返納無用ですが、「宅建士証」だと、返納しなくてはなりません。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐免許, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年9月13日 11:46 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
宅建無料ノート:宅地造成等規正法‐届出(指定、除却工事、転用)・・・重要ポイント直前チェック
「宅地造成等規正法」では、なぜだか、各届出の出題が多いです。
試験に出るのは、「3つ」あって…、
「宅地造成工事規制区域の“指定”の際、すでに宅地造成を行なっている造成主の届出(指定届出)」
「一定の擁壁等の“除却”工事を行おうとする者の届出(除却届出)」
「宅地以外の土地を宅地に“転用”した者のする届出(転用届出)」
…となっています。
参考までに、過去問を挙げておくと、「H28 問20」の選択肢3や4です。
選択肢3『宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を険き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。』
選択肢4『宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。』
それぞれ、「○」と「○」です。そのとおりの規定です。
さて、当該論点は、数字は、語呂等があるので、そこそこ憶えやすいのですが、細かい規定が狙われているので、ていねいに憶えていってください。
んでは、個々の届出を見ていきましょう。
指定届出‐すでに宅地造成を行なっている造成主
宅地造成工事規制区域の指定の際、すでに宅地造成を行なっている造成主は、「指定のあった日から」、「21日以内」に、都道府県知事に届け出ることになっています。
要は、前までは、宅地造成工事規制区域ではなかったので、許可等を受けずに造成工事していたが、工事の途中で、当該工事現場が規制区域になってしまった(指定された)ケースです。
この場合、「許可」までは要しないが、「造成主」に「届出」の義務が課せられる、といった寸法です。
んで、当該届出の届出義務者は「造成主」で、届出先は「知事」です。
指定数字暗記
「21日以内」の覚え方ですが、1週間は7日ですから、「21日」は、「3週間」です。
当該規定のキーワードは、「宅地造成工事規制区域の指定の際」の『指定』です。
…もうおわかりですね。
指定→してい→3文字→3週間→21日
「指定は、していで、3文字、3週間、3週間は21日」といった感じで、憶えるってな塩梅です。
ひらがなで「してい→3文字」なので、注意してください。
指定注意点
起算日に注意です。「指定のあった日から」です。
たとえば、「指定される21日前までに届け出る必要がある」などと出るおそれがあります。注意してください。
除却届出‐一定の擁壁等の除却工事
次に、「一定の擁壁等の除却工事を行おうとする者の届出」です。
当該届出は、「工事に着手する日の14日前までに」、届け出る必要があります。
届出ですが、起算日に注意してください。
着手する日の「前」なので、正確に憶えてください。
「工事着手後、14日以内」ではありません!
なお、届出義務者は「除却工事を行おうとする者」で、届出先は「知事」です。
ところで、「擁壁(ようへき)」ですが、石垣みたいな物です。
参考:グーグル検索:擁壁
除却数字暗記
「14」の数字暗記です。
先と同じように、「週」で憶えます。
「除却」は、「除」と「却」の「漢字2文字」ですから、「漢字2文字で2週間、よって14日」と憶える、ってな寸法です。
除却工事が狙われて
除却工事の内容まで、狙われています
届出対象の工事は、「高さが2mを超える擁壁」の除却工事と、「地表水等を排除するための排水施設などの全部または一部」の除却工事です。
試験に出ているので、ここまで、押えておきましょう。
転用届出‐宅地以外の土地を宅地に転用
最後の「宅地以外の土地を宅地に転用した者のする届出」ですが、「転用した日」から「14日以内」に届出をすることになっています。
当該届出規定は、宅地に転用しただけで、宅地造成工事が伴わない(工事をしていない)ケースです。
造成工事をしていないので「許可」までは求めないが、代わりに、「届出」を義務付けている、ってな役所的塩梅です。
さて、先と同様に、起算日に注意です。
「転用した日」から、カウントされます。
「転用する日の14日前」ではないので、気をつけてください。
なお、届出義務者は「転用した者」で、届出先は「知事」です。
転用数字暗記
当該「14」という数字は、キーワードである「転用」を、もじって憶えます。
「転用→てんよう→テンヨン→10(ten)と4(よん)」
…もうおわかりですね。
「10と4(テンとヨン)」で「10+4の14日」です。
ひっかけポイント
さて、ひっかけ問題が出ています。
先の「除却」と「転用」の届出は、「宅地造成工事規制区域内」での話しです。
もし、出題の舞台が「宅地造成工事規制区域外」であれば、そもそもが、法の対象外なので、当然、先の届出も無用となります。
当該ひっかけは、いくらでも、考え付きます。
たとえば、「都道府県知事は、宅地造成工事規制区域外の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。」と、出題されてもおかしくない、といった寸法です。
規制区域外なので、当然、報告を求めることはできません。
本ページは、以上です。
ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐宅地造成等規制法 | 2019年9月8日 10:02 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
宅建無料ノート:宅地造成等規正法‐宅地造成の数字は、語呂で暗記・・・重要ポイント直前チェック
超絶頻出論点の「宅地造成」の「数字規制」を見ていきます。
本ページの内容は、各規定の説明と、数字の語呂合わせ「切り盛り兄さん、ごくろーさん」です。
さて、まずは、基本からです。
「宅地造成」には、「4つの数字規制」があり、以下の数字を満たす場合に、「宅地造成」に該当することになります。
4つの数字規制
とりあえず、数字規制の4つを、教科書的に挙げていくと…、
①‐『切土』で、切土部分の高さが「2mを超える崖を生ずる」もの。
②‐『盛土』で、盛土部分の高さが「1mを超える崖を生ずる」もの。
③‐『切土』と『盛土』を同時にする場合に、盛土部分は1m以下の崖を生じ、切土・盛土部分(全体部分)の高さが2mを超える崖を生ずるもの。
④‐上記に該当しない『切土』と『盛土』で、その切土・盛土の面積が「500㎡を超える」もの。
…となります。
ポイント1・・・③は後回し
まず、③は、「後回し」です。
あまり、試験に出ません。他の数字規定のほうが、圧倒的に出ています。
おそらく、③の規定がややこしいため、出題者の方も、問題を作り難いのだと思います。
正直、他の規定を混ぜ合わせたものなので、他を憶えてから、「違い」を押さえておけばよいでしょう。(盛土部分に1m以下の崖、切土・盛土の全体で2m超の崖)
ポイント2・・・超える
③の一部を除いて、数字規定は、「超える」なので、意識して憶える必要があります。
「超」ですから、その数字を、含みません。
「切土」で「2m」の崖の場合、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「2.1m」とかの場合です。
「盛土」で「1m」の崖の場合、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「1.1m」とかの場合です。
面積が「500㎡」の場合は、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「501㎡」とかの場合です。
閾値(しきいち)は、必ず、判別できるようになっておきましょう。
参考:以下・以上・未満・超える
語呂合わせ
語呂は…、
『切り盛り兄さん(きりもり、にいさん)、ごくろーさん』
…です。
「切り」は、「切土」です。数字は、「2m」でした。
「盛り」は、「盛土」です。数字は、「1m」でした。
「兄さん」は、「にいさん」で、「2・1さん」です。
「ごくろーさん」は、「“5”くろーさん」です。
…もうおわかりですね。
「切り盛り兄さん」は、「切り盛り 2・1さん」で、「切土:盛土」の「2:1」の対比を現します。
「ごくろーさん」は、「“5”くろーさん」で、言うまでもなく、③の面積規定の「“5”00㎡」に、該当します。
『切り盛り兄さん(きりもり、にいさん)、ごくろーさん』の語呂合わせで、先の数字は、即、暗記できると思います。
当該語呂を使って、過去問を1~2題、解いてみてください。そこそこ、解けるはずです。
たとえば、「H27 問19」の選択肢4です。
『宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。』
前者の「土地の面積が500㎡」ですが、数字定義は「超える」なので、「500㎡」は、含まれません。
んなもんで、「宅地造成」には、該当せず、許可は無用と相なります。ここは、OKとなります。
次に、後者の「切土をした部分に生じる崖の高さが1.5m」ですが、先の語呂「切り盛り兄さん(2・1さん)」からすると、「切土」の場合、2m超の崖のときに、「宅地造成」となります。
選択肢では、「1.5m」ですから、これまた、「宅地造成」には、該当せず、許可は無用と相なります。ここも、OKとなります。
前者・後者とも、間違いはないので、「○」と相なります。
当該数字規制は、ほぼ例年、選択肢の1つに顔を出すので、ガチで覚えてしまってください。
本ページは、以上です。
ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐宅地造成等規制法 | 2019年9月8日 9:53 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |