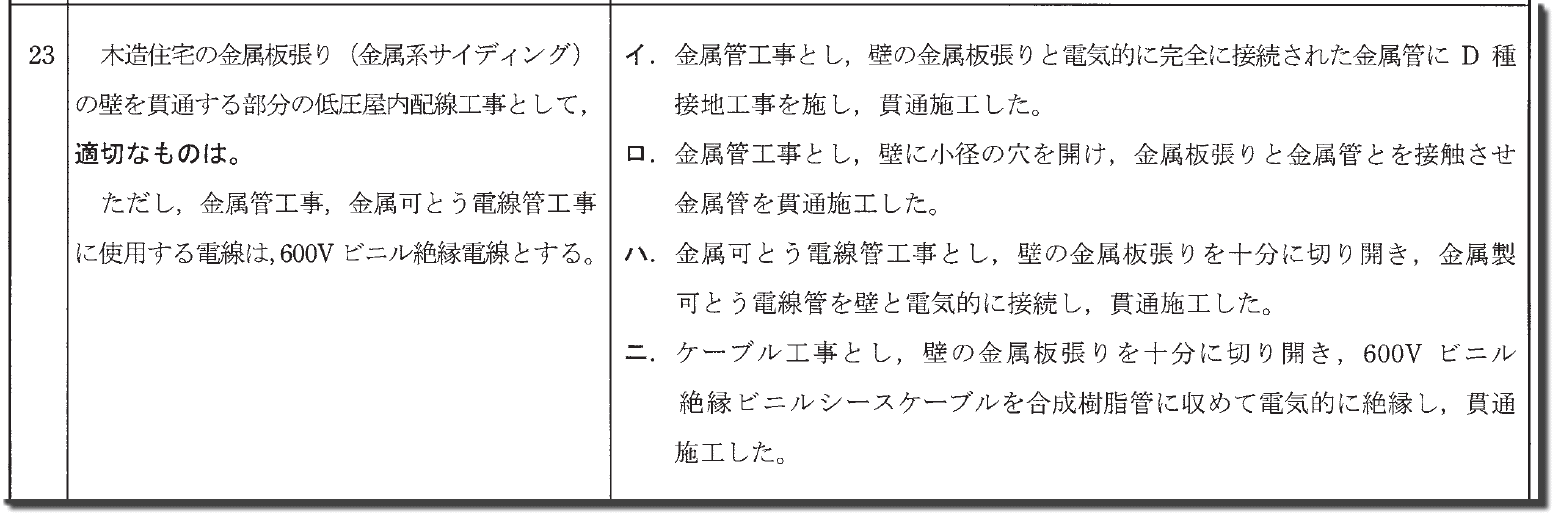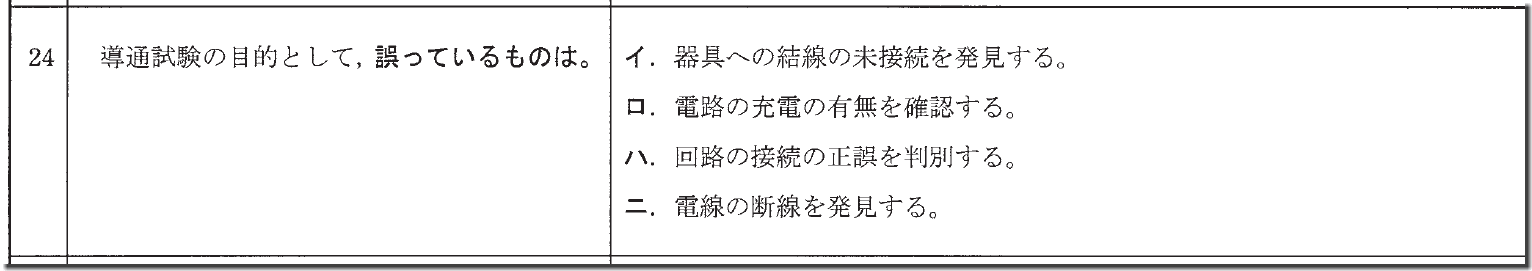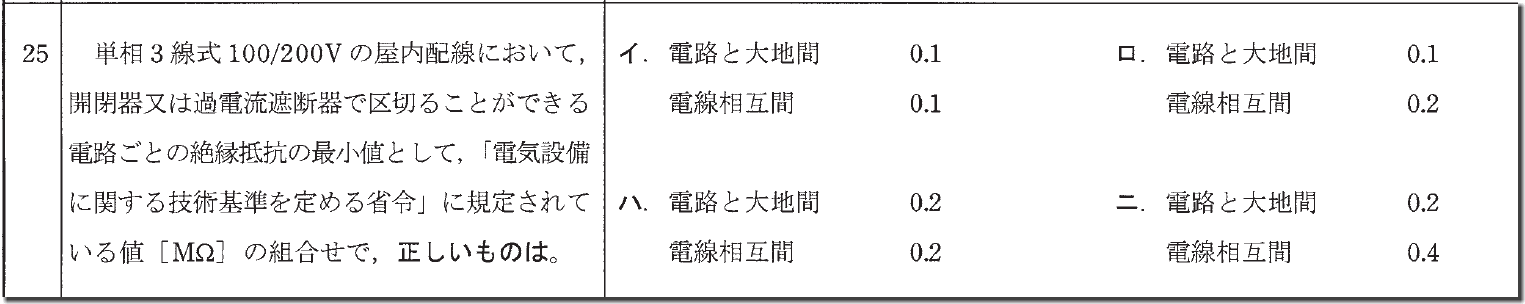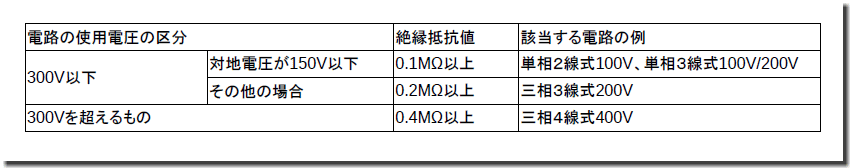第23問:常識問題‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第23問は、よく考えたらわかる「常識問題」です。
問題文にはいろいろ書かれていますが、常識を働かせてパスしましょう。
解説
先も言ったように、本問は常識的に考えれば、正解に到達できます。
本問のテーマは、木造住宅の金属板張りの壁の配線工事なわけですが、危惧すべきは、「漏電による出火」です。
このため、「電気的に接続」されていると、万が一の漏電の際に、金属入りの壁に電気が流れてしまい、当該電気の熱で出火しかねません。
んなもんで…、
「イ」は、「金属管工事」で「電気的に完全に接続」とあるので「×」です。
「ロ」は、「金属管工事」で「金属管と金属板張りとを接触」とあるので「×」です。
「ハ」は、「金属可とう電線管」で「電気的に接続」とあるので「×」です。
これで消去法で答えが「ニ」と相なります。
説明
答えは「ニ」なのですが、選択肢を読めばこれっぽいことがわかります。
「ケーブル工事」は、ごぞんじのように、『どんな工事でも可能』でした。
「金属板張りを十分に切り開いた」も、妥当な処置です。
「ケーブルを合成樹脂管に収めて」もOKで、「電気的に絶縁」も、これまた、妥当です。
こういった次第で、選択肢の内容からも、当該「ニ」を選べられるかと思います。
まとめ
本問は、一見すると“ぎょっ”としますが、よくよく選択肢を当たれば、「こら、まずいんでないかい」とわかるはずです。
落ちついて問題文を読んで、解答してください。今後、こういう問題が増えるはずです。
なお、当該問題のテーマは、「消防設備士」という資格の「乙種7類:漏電火災警報器」が対象としている試験です。
漏電火災警報器は、「木造作りで、鉄網入りの壁」がある場合、設置義務が生じる機器となっています。
消防設備士の乙7は、第2種電気工事士があると、「試験免除」をがっつり受けられるので、合格後、余裕のある方は受験を考えてみてください。
参考:消防設備士:乙7の独学
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 11:35 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第24問:導通試験‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第24問は、シンプルな「知識問題」です。
文系ド素人でも余裕で取れるので、しっかり点にしましょう。
解説
「導通試験」とは、器具への結線の「未接続」がないか、回路の「接続」が正しいか、電線が「断線」していないかを調べる試験です。
選択肢「イ」「ハ」「ニ」は、まさに、導通試験そのままの説明であり、問答無用で「○」です。
んなもんで、誤っている選択肢は、「ロ」の「電路の“充電”の有無を確認する」です。
なお、当該導通試験は、おなじみ「回路計(テスタ)」が使われます。
説明
おさらいとして、選択肢の「ロ」は、しっかり見ておいてください。
「電路の充電の有無を確認する」測定器は、おなじみの「検電器」です。(ネオン式や音響発光式があります。)
「検電器」は、測定器の論点では頻出ですので、「回路計(テスタ)」と併せて復習しておいてください。
反対に言うと、「ロ」の選択肢を読んだ時点で、(あれ、これ、検電器じゃん。検電器って導通試験に使ったけ?)と思い至れば、正解を導けるはずです。
まとめ
本問は、絶対に取らないといけない問題です。
知っていさえいれば取れるので、こういう問題こそ、文系ド素人は取らなくてはいけません。
間違えた人は、最低でも3回は解き直してください。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 11:29 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第25問:絶縁抵抗値‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第25問は、問題文も選択肢もコチャコチャ書かれていますが、「絶縁抵抗」を問うただけの「知識問題」です。
絶縁抵抗の表を暗記していれば、文系ド素人でも余裕で取れるので、暗記に励んでください。
解説
本問を解くには、一枚の表があればいいです。
この表に当てはめるだけです。
本問の屋内配線は、「単相3線式100/200V」です。
従って、表の使用電圧区分は「300V以下」の「対地電圧が150V以下」に該当します。
表の「絶縁抵抗値」は、「0.1MΩ以上」となっています。
んなもんで、答えは「イ」と相なります。
説明
選択肢の「電路と大地間」と「電線相互間」は、まあ、言ってしまえば、一種のフェイクで、出題者の罠といっていいです。
そもそも、「絶縁抵抗」という概念自体が、「電路と大地間」と「電線相互間」を対象としています。
んなもんで、先述したように、先の絶縁抵抗の表の絶縁抵抗値を、双方に適用する、といった塩梅です。
選択肢にはいろいろ数字が並んでいて、混乱しそうですが、出題者の“意図的な嫌がらせ”に引っかからないようにして下さい。
まとめ
本問は、「絶縁抵抗値の表」さえ憶えておけば、文系ド素人でも余裕で点が取れます。
ですから、絶対に取らないといけない問題です。
先の表は、本試験ではド頻出ですので、テキストを何度も見るなり、スマホ等に保存するなりして正確に暗記してください。
参考:絶縁抵抗値の表
本問を1問取れば、難問を1問捨てれます。
電気理論や電気工事、複線図では、難問がひしめき合って、芋洗い状態です。
こういう取れる問題を確保することで、先の難問の失点に備える次第です。
反対に言えば、電気の公式や理屈を勉強したくない人こそ、こういう問題を取りに行かねばなりません。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 11:27 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |