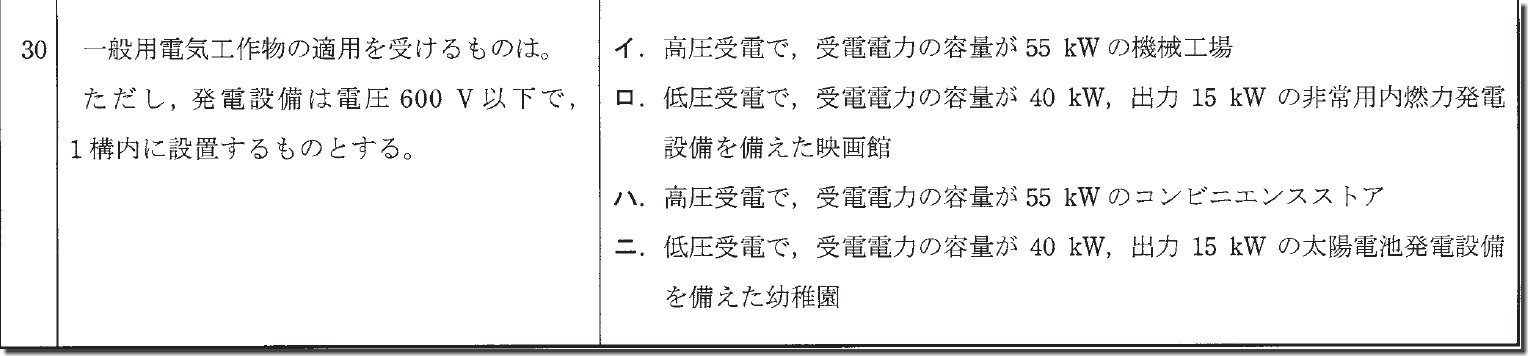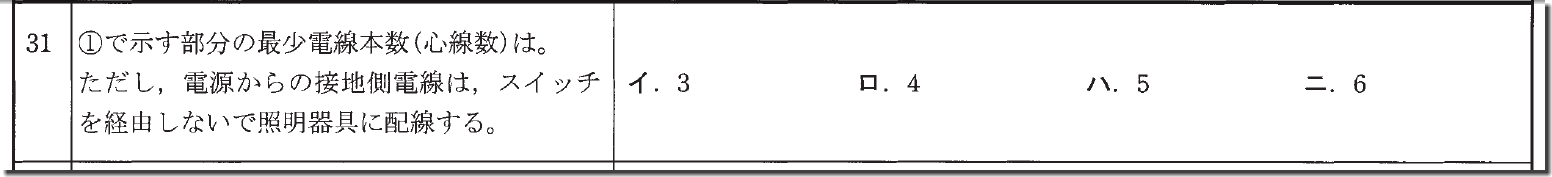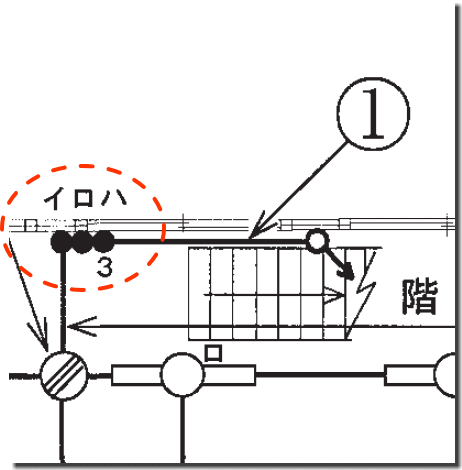第29問:電気用品安全法‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第29問は、文系ド素人の本領を発揮できる法令問題です。
「電気用品安全法」の定義は、ほぼ毎回出るといっていいです。
本問は「知識問題」なので、テキストの表を憶えておけば1点です。必ず1点取りましょう。
解説
「PSE」マークの四角か、丸かは、「特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品」にまとめているので、お目汚しください。
かいつまんで言うと、四角っぽい方が「格式ばってそう」なので「特定電気用品」で…、
丸のほうが「規制がやわい」風なので「特定電気用品以外の電気用品」ってな塩梅で、ニュアンスで憶えるってな寸法です。
選択肢を見ていくと、「イ」はテキストまんまの記述で「○」、「ロ」もそのままなので「○」、「二」もその通りで「○」です。
んなもんで、答えは「ハ」です。
電気用品安全法は、輸入したものにも適用がありますが、だからといって、「輸入したもの」に「<PS>E」と付す規定はありません。
説明
先の「ハ」の「<PS>E」と、「(PS)E」の表記について補足します。
当該山括弧と括弧は、『構造上表示スペースを確保することが困難な場合』に付される文言です。
まとめ
本問は、本試験ではド定番・ド頻出のテーマで、何度も何回も問われている論点です。
全くの基本・基礎なので、必ず取りましょう。
また、「何が特定電気用品か?」の問題もよく出るので、テキストの表は憶えておきましょう。
憶え方は「一般用電気工作物(600V)の憶え方のコツ」を参考にしてください。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 11:19 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第30問:一般用電気工作物‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第30問は、文系ド素人の本領を発揮できる法令問題です。
「一般用電気工作物」の定義は、ほぼ毎回出るといっていいです。
本問は「知識問題」なので、テキストの表を憶えておけば1点です。必ず1点取りましょう。
解説
「一般用電気工作物」ですので、「高圧受電」は除外されます。
従って、選択肢「イ」と「ハ」は、“わざわざ、問題文に高圧受電とお書き遊ばれておられる”ので、消去します。
これで、「50%」の確率で正解できるようになりました。
後は、お馴染み「小出力発電」で、選択肢を判別するだけであります。
「ロ」の選択肢には、「出力15kWの非常用“内燃力発電設備”」とあります。
当該「内燃力発電設備」は、「出力が10kW未満が一般用電気工作物」です。
本選択肢は「出力15kW」なので、一般用電気工作物ではありません。
従って、「×」となります。
んなもんで、「イ」「ロ」「ハ」が「×」なので、答えは「二」と相なります。
説明
念のため、「ニ」も見てみましょう。
「二」ですが、選択肢には、「出力15kWの非常用“太陽電池発電設備”」とあります。
当該「太陽電池発電設備」は、「出力が50kW未満」のときに一般用電気工作物となるので、「○」といった次第です。
コツ
「一般用電気工作物」の「小出力発電設備」の憶え方は、ブログにまとめています。
「小出力発電設備の憶え方のコツ」をばお目汚しください。
憶える負担がちょっとは減るかと思います。
まとめ
本問は、本試験ではド定番・ド頻出のテーマで、何度も何回も問われている論点です。
必ず、「小出力発電設備」の表は憶えておきましょう。
なお、「一般用電気工作物」は、低圧受電するものであり、当該「低圧」は「600V以下」を指すことも、ド頻出なので憶えましょう。
憶え方は「一般用電気工作物(600V)の憶え方のコツ」を参考にしてください。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 11:17 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第31問:3路スイッチの心線数‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第31問は、「3路スイッチ」の「複線図」問題です。
「複線図」の苦手な人は、「捨て問」でもいいでしょう。
が、“絶妙に間違ったゴリ押し”も可能なので、取りたい人は取りましょう。
解説
本問のキーは、「3路スイッチ」であることがわかるかどうか、です。
つまり、先の画像の赤点線で囲んだ「ハ」と「●3」の図記号が何か、知っているか否かを問うている次第です。
当該「ハ」の配線が、「3路スイッチ」からのものであることがわかれば…、
(3路なんだから、3本なんじゃねえの?)的な見当が付きます。
強引だし微妙に間違っていますが、答えは、「3本」で「イ」と相なります。
説明
基本的に、3路スイッチは、それぞれ、「1」と「1」、「3」と「3」とをつなぐのが定番です。
これで「2本」の電線が通ることになります。
そして、本問では、「電灯:ハ」に向かう「白線(接地側電線)」が、「1本」あります。
んなもんで、合計「3本」となる次第です。
ダメなら捨てる
個人的なことを言うと、文系ド素人は、複線図問題は「わからなくても仕方がない」ので、本問は「捨て問」にするか、先のように「細かいところはわからないけれども、3路なんで3本じゃない?」くらいの“強引な解答”でいいと思います。
テキストには、「3路スイッチ」の複線図の描き方が載っているでしょうが、たぶん、少しもしっくりこないはずです。
で、何回か挑戦してみて、ダメだったらダメでいいです。こういうとアレですが、「文系ド素人は、テキストという紙の上だけの勉強では無理」だからです。
何とかしたいのなら技能
当該3路スイッチの問題を何とかしたいのなら、技能の候補問題を“作る”ことに尽きます。
「3路スイッチ」は、技能のテキストを見ながら、複線図を描いて、実際に回路を組んで始めて、(あーこういうことなのね)と、「腑に落ちる」状態になります。
1回の組み上げは、10回のテキスト読解に勝ります。
かう言う私も、技能の勉強を始めて、わかったことが多々ありました。
反対に言うと、筆記のテキストだけで複線図がわかるなんて凄いなー、と思います。
こういう塩梅なので、本問を追求したいのなら、「技能」の「3路スイッチ」の候補問題に当たってみてください。
なお、技能の使用教材については、詳しくは「技能試験の教材」で述べていますが、読むのが面倒なら…、
工具は、定番メーカー:HOZANの「HOZAN 電気工事士技能試験セット S18」を…、
技能の材料には、候補問題の作り方を網羅したDVDの付く「準備万端(推奨・2回セット)」を使えば支障ありません。
まとめ
繰り返しますが、本問のような「複線図問題」は、できなくても構いません。
わたしは、受験生当時、「複線図」の問題は、基本的に『捨て問』にしていました。
個人的には、複線図は費用対効果が低いと思っているので、「やってみて」わからないなら、「捨てる」のが一手です。
ところで、本問は、「最少電線本数はいくつか?」という問題設定ですが、ここは深く考えなくていいです。
当該「最少電線本数」は、「世間一般的に、常識的に、合理的に施工するなら何本?」くらいの意味です。
反対に言えば、当該条件がないと、「わたしは、余るけど、10本使います!!」という輩が続出して、試験にならなくなってしまいます。問題文のこのところは、深く追求しなくていいです。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 10:19 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |