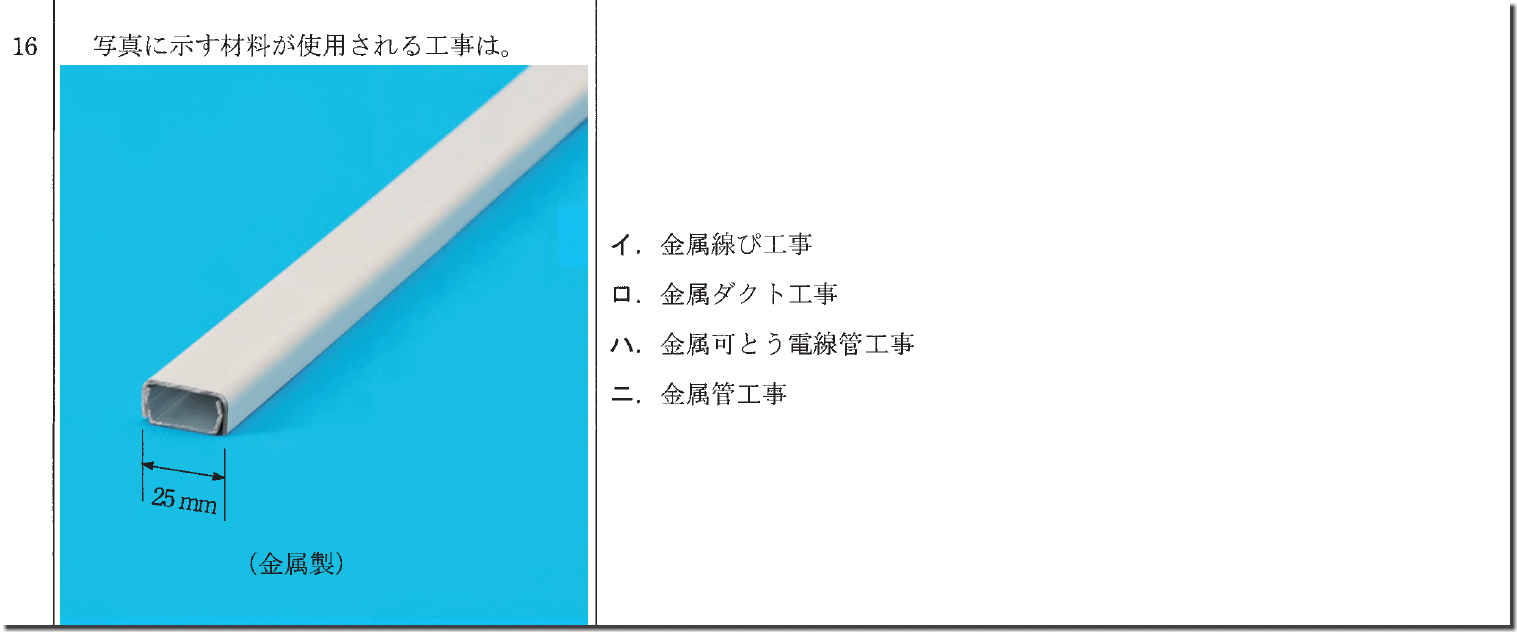第14問:ビニルコード‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第14問は、「ビニルコード」がテーマの問題です。
本問は、問題文に少々難があります。
問題文には、「移動電線」云々とあるので、「???」となりがちです。
しかし、ふつうの、身の回りにある「電気コード」を思い浮かべればそれでOKです。
「コード」は、小形機器の電源供給用の電線で、移動して使うために曲げやすくしたものです。
言うなれば、電気を通すもの(たとえば、ケーブルなど)は、基本、固定して使うわけですが、例外的に、「電気コード」は動けるようにしている、といった塩梅です。(後述しますが、逆を言えば、電気コードは固定してはいけないのです。)
「移動電線」とは、ふつうに目にする、たとえば、電気アンカや扇風機のコードを指しているだけです。
問題文の前提に引っかからず、ふつうに解答してください。
こんな回りくどい言い方になるのも、出題者側は、正確に用語を使わないと受験生からクレームが来るからです。
解説
本問は、「コード」のド定番論点「ビニルコードは、発熱する機器には使えない」を問うています。
ですから、選択肢から、「熱の出るもの」を除外すればよい、という次第です。
説明
先だって述べたように、「ビニルコードは、発熱する機器には使えない」ので…、
「イ」の「電気トースター」は、「×」です。
「ロ」の「電気コタツ」も、「×」です。
「ニ」の「電気コンロ」も、「×」です。
んなもんで、ビニルコードが使えるのは、「ハ」の涼しい「電気扇風機」と相なる次第です。
先の「イ」「ロ」「ハ」には、「ビニルコード」ではなく、「電熱用コード」を使用します。
補足
万が一、分からない場合、試験テクニックとして、「異色のものを選ぶ」があります。
先の選択肢を吟味すれば、「ハ」の扇風機だけ、用途が違うのがわかるかと思います。
んなもんで、「ハ」を選ぶ、といった次第です。
まとめ
本問のテーマの「ビニルコード」は、本当によく出るので、必ず正解できるようになってください。
また、当該論点は、「ビニルコードは、固定して使えない」も定番で、加えて、「ただし、ショウウィンドウ内は例外的に、固定できる」も、併せて憶えておきたいです。
ま、文系ド素人でもぜんぜん取れるので、押さえておきましょう。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 10:36 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第15問:電線管の加工工具‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第15問は、定番の「電線管の加工工具」です。
本問のような「工具」の問題は、ホームセンターで実物を触ってくるのが一番の勉強です。
紙の上だけの勉強は脆いです。テキスト片手に工具売り場をうろうろして、実物で勉強してください。
そして、帰りに歯ブラシかティッシュを買って、ホームセンターの売上に貢献してください。(学費の支払は必要です。)
解説
選択肢に出てくる工具は、すべて頻出なので、本問でマスターしてしまいましょう。
・リーマ・・・クリックボールに取り付けて、金属管内側の面取りをする。
・金切りのこ・・・金属管や太い電線の切断。
・パイプベンダ・・・金属管の曲げに使う。
・やすり・・・切断した際のバリ取り。
・パイプレンチ・・・カップリング等を取り付ける際に、金属管を回す。
・トーチランプ・・・硬質塩化ビニル電線管の曲げに使う。
特に、下線の付いた工具は要注意です。「名称」から用途が浮かばなかったり、馴染みが薄かったりで、試験でピンポイントに狙われています。
どう問われてもいいように、しっかり憶えておきましょう。
説明
本問は、「金属管」の工事です。
「トーチランプ」は、「硬質塩化ビニル電線管」に使う工具なので、当該工具の入っている選択肢は消去できます。
ですから、「ロ」と「ハ」が消えます。
次に、問題文の指定には、「金属管の切断および曲げ作業に使う工具」との指示があります。
んなもんで、金属管を回す「パイプレンチ」が「×」となります。切断と曲げには使わないからです。
ですから、「ロ」が消えます。
んなもんで、正解は「イ」と相なります。
補足
金属管工事に使う工具は、上記の選択肢群のほかに、「パイプバイス」と「パイプカッタ」「リード形ねじ切り器とダイス」なども、よく出るので押さえておきましょう。
「パイプバイス」の「バイス」は、「万力」の意味です。
金属管を切断する際に、固定するための工具です。
「パイプカッタ」は、金属管の切断に使います。
試験では、「合成樹脂管を切るときに使う」などと出るので注意です。なお、合成樹脂管を切る際は、「合成樹脂管用カッタ」を使います。写真鑑別でも出るので、テキストで要チェックです。
「リード形ねじ切り器とダイス」は、実感が沸かないためか、よく問われています。
ぜひとも、ホームセンターで実物に触れてみてください。
まとめ
本問のテーマの「電線管の加工工具」は、本当によく出るので、必ず正解できるようになってください。
これを落とすと、ヤバイです。
間違った人は、「ホームセンター巡礼」をしてください。行ってみると、なかなかに面白いです。
繰り返しますが、帰りは、電池でも何でもいいので買って、売上に貢献してください。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 12:09 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第16問:線ぴ(線桶)の写真鑑別‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第16問は、「金属線ぴ(線桶)」の写真鑑別の問題です。
本試験やテキストでは、「線ぴ」と表記されていますが、試験勉強的には、「線桶」で考える方が賢明です。
「線桶」のほうが、なまじ平仮名の「線ぴ」より、100倍はイメージが湧くからです。
言うなれば、「線」を入れた「桶(棺桶のおけ)」なわけで、「線桶」なら、この中に電線を入れるのだな、と見当が付きます。
解説
本問のコツは、「身近の配線を観察する」です。
テキストの紙の上の勉強ではなく、実地に、周りの配線を目ざとく見ていくほうが、よほどに頭に残ります。
本問の選択肢に採用されている工事(配線)は、かなり目にするんで、見つけるたびに、これが「○○工事」なのだな、と憶えていきましょう。
さて、本問の答えですが、本問は、その特徴のある形と、大きさが画像に「25mm」とあることから、「イ」の「金属線桶(線ぴ)工事」とわかるはずです。
当該「金属線桶(線ぴ)」ですが、結構目にします。
個人的には、会議室や倉庫などで、よくよく目にします。とりわけ、照明用のスイッチで、よく目にしました。
皆さんも、職場等々で目ざとく探してみて、頭に入れていきましょう。
なお、「金属線桶(線ぴ)」には、「1種金属線ぴ」と「2種金属線ぴ」とがありますので、それぞれを、テキストで確認しておきましょう。
説明
他の選択肢ですが…、
「ロ」の「金属ダクト工事」の「金属ダクト」は、工場やビルなど、多数の配線のあるところでよく見かけます。
わたし個人で言えば、「古いビル」でよく見ました。なお、ビルの床をよく見れば、「フロアダクト」が埋まってそうなところを見つけられるはずです。
さて、「ロ」ですが、「金属ダクト」には、「円形の穴」があるので、「×」と相なります。
「ハ」の「金属可とう電線管工事」ですが、これは、即、「×」とできるはずです。
「金属可とう電線管」の「可とう」は、曲がるように蛇腹状になっています。写真のものは、どう見ても曲がりそうにありませんし、うねうねしていません。
「ニ」の「金属管」も、同様の趣旨で、即断に「×」とできるはずです。どうみても、金属管ではありません。
まとめ
本問は、「金属線ぴ(線桶)」の写真鑑別です。
よく目にする工事なので、身の回りの有無を調べて、頭に入れてください。
写真鑑別は、テキストより、実物が一番です。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 12:06 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |