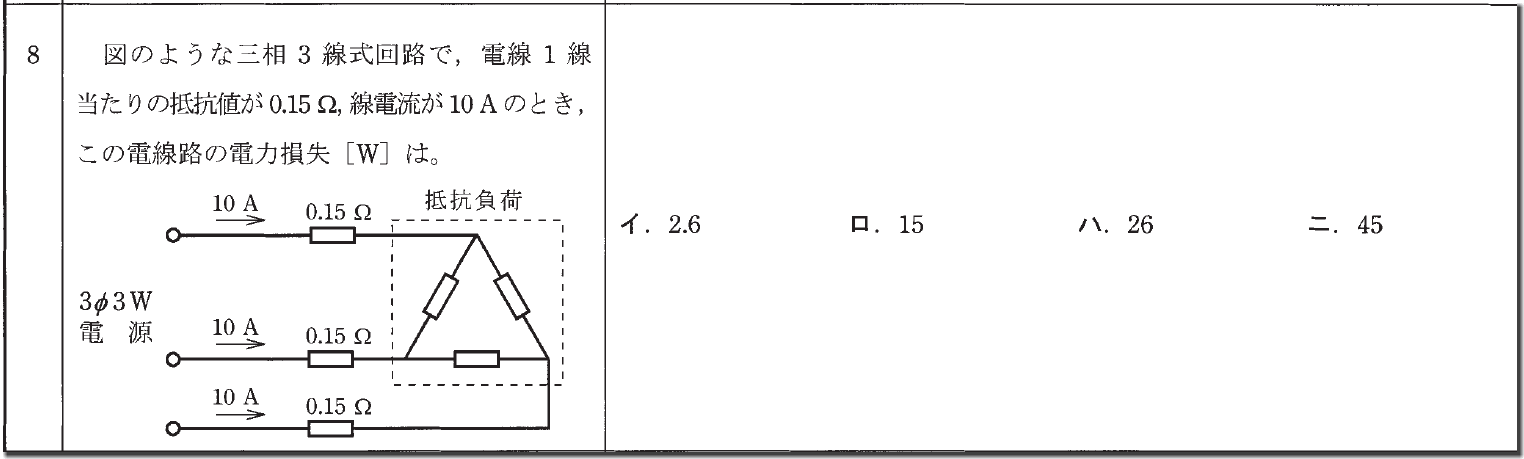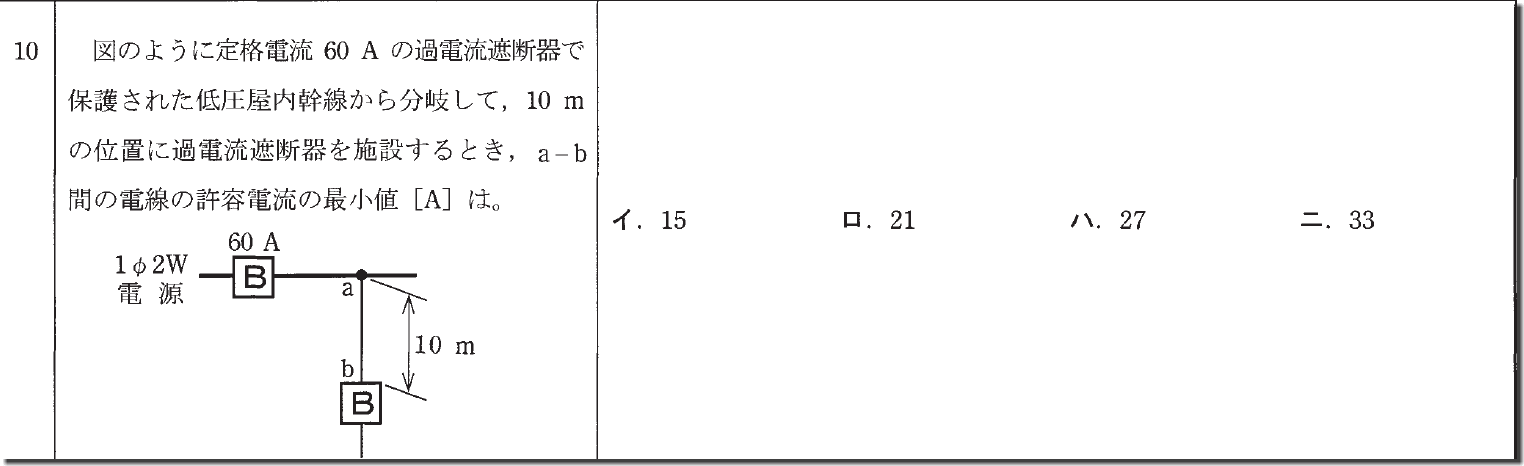第8問:電力損失‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第8問は、筆記で定番の「電力損失」の問題です。
ぶっちゃけ言えば、暗記と記憶の問題であり、テキストの「公式」を憶えておけば、穏当に1点取れます。
本問は、「三相3線式」の回路で、「電力損失」がテーマですから、使う公式は…、
3I2r[W]
…です。
ちなみに、「I2r」とは、お馴染みの「P=VI」に、「V=IR」を代入したものです。
「P=VI→P=IRI→P=I2r」な塩梅です。
文系ド素人の人は、理解は度外視して、公式だけでも暗記しておきます。
解説
先述したように、本問は、暗記と記憶がものをいう問題で、反対に言うと、憶えていないと手も足も出ません。
本問では、電線には「10A」の電流が流れており、電線の抵抗は「0.15」なので…、
3×10×10×0.15で…、
「15×3」の「45[W]」と相なります。
んなもんで、答えは「ニ」となります。
説明
電力損失の問題は、本問のような「三相3線式」以外にも登場します。
単相2線式だと「2I2r」です。
単相3線式だと「3I2r」です。
また、本問は、「電力損失」のほか、「電圧降下」も定番となっています。
単相2線式だと「2rI」で…、
単相3線式だと「rI」で…、
三相3線式だと「√3rI」です。(1.73のルート3です。)
これらの公式も、併せて憶えておきましょう。
まとめ
本問の「電力損失」は、公式さえ憶えていれば、文系ド素人でも憶えることができます。
長々とした理屈がテキストに載っているでしょうが、試験に出るのは、先の3・3の『公式』です。
どの公式も出る可能性があるので、しっかり憶えておきましょう。
文系ド素人で苦手なら、本試験の3日前くらいから、憶え込めばいいです。
何とか点を取りたいところです。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 10:53 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第9問:分岐回路‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第9問は、筆記で定番の「分岐回路」の問題です。
ぶっちゃけ言えば、暗記と記憶の問題で、テキストによく出てくる、下の画像のような表を憶えておけば、穏当に1点取れます。
注意すべきは、「電線の太さ」です。「断面積(mm2)」と「太さ(mm)」という「2つの単位」が混在しているので、こんがらないようにしてください。
なお、本試験では、「20A 配線用遮断器の分岐回路(上の表の太文字のところ)」が頻出です。
忙しくても、最低限度、ここだけは憶えておきましょう。
解説
先述したように、本問は、暗記と記憶がものをいう問題で、反対に言うと、憶えていないと手も足も出ません。
んなもんで、通勤・通学時に先の画像の表を何度も見て、頭に叩き込むのが試験勉強と相なります。
深く考えず、暗記に勤しんでください。
説明
選択肢の個々を見ていきます。
「イ」は、「20A」の配線用遮断器の分岐回路です。
「20A」の配線用遮断器の分岐回路では、電線の太さは「直径1.6mm以上(または2m㎡以上)」です。選択肢では「2.0mm」となっているので、電線の太さは「OK」です。
んで、コンセントですが、「20A」の配線用遮断器の分岐回路では、コンセントの定格電流は「20A以下」なので、これまた選択肢は「OK」となります。
従って、答えは「イ」となります。
なお、コンセントの『数』は受験生を戸惑わせる「フェイク」で、最終的な正誤に関与しません。
選択肢ロ
「ロ」は、「30A」の分岐回路です。表を見ればわかるように…、
電線の太さは「直径2.6mm以上(または5.5m㎡以上)」でなければならないのに、当該選択肢では「2.0mm」であり、細すぎます。
従って、電線の太さで「×」と相なります。
なお、コンセントの定格電流は、「30A」の分岐回路だと「20~30A」なので、当該選択肢の「20A」は「OK」です。
本選択肢は、電線の太さが「ダメ」で、コンセントは「OK」であり、従って、本選択肢は「誤り」と相なります。
選択肢ハ
「ハ」は、「20A」の配線用遮断器の分岐回路です。先の「イ」と同じです。
当該分岐回路の電線の太さは、「直径1.6mm以上(または2m㎡以上)」です。
んなもんで、電線の太さは「○」と相なります。
そして、コンセントの定格電流ですが、先述したように、コンセントの定格電流は「20A以下」です。
本選択肢は「30A」となっているので、「×」です。
従って、電線の太さは「○」でも、コンセントの定格電流が「×」なので、本選択肢は「誤り」となります。
選択肢ニ
「ニ」は、「30A」の分岐回路です。
電線の太さは「直径2.6mm以上(または5.5m㎡以上)」であり、当該選択肢は「2.6mm」なので「○」です。
次に、コンセントの定格電流ですが、「30A」の分岐回路だと「20~30A」です。
本選択肢は「15A」となっているので、「×」です。
従って、太さ「○」、コンセント「×」で、本選択肢は「誤り」となります。
まとめ
本問は、表を1つ丸ごと憶えなくてはいけないため、費用対効果が悪く思われるかもしれません。
しかし、当該分岐回路は、ほぼ毎回問われるド定番の論点であり、勉強さえすれば、100%取れる問題です。
文系ド素人にとっては、「やりさえすれば取れる問題」は、貴重な問題です。必ず、1点取れるようになっておきましょう。
なお、最近の本試験では、テキストには出ていない器具がでたり、技能に絡んだ問題が出題されたりと、文系ド素人には「向かい風」となっています。
ですから、本問のような、ド定番・ド頻出の問題は、必ず取るべきなのです。
試験に出ることは自明なのですから、一生懸命暗記して、1点としましょう。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 10:49 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第10問:分岐回路の開閉器・過電流遮断器‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第10問は、筆記で定番の「分岐回路の開閉器・過電流遮断器」の問題です。
「分岐回路」のド定番の問題に、先の第9問「分岐回路の種類」があります。
第9問の「分岐回路の種類」を正解するには、コンセントの定格電流やら電線の太さなど、細々した数字をたくさん憶えなくてはいけません。
参考:表:分岐回路の種類
しかし、本問の「分岐回路の開閉器・過電流遮断器」は、憶えることが少しで、2~3つしかありません。
んなもんで、「分岐回路の種類」はできずとも、本問の「分岐回路の開閉器・過電流遮断器」だけは、正解できるようになっておきましょう。
解説
本問のテーマ「分岐回路の開閉器・過電流遮断器」は、長々と書いているので難しそうですが、根っこは実にカンタンです。
まず、原則「分岐回路には、原則として、幹線の分岐点から、3メートル以内の場所に、分岐開閉器(開閉器・過電流遮断器)を設置しなくてはならない」を憶えましょう。
本試験で問われることは、この原則に関する『例外』です。
本来なら、常に、絶対に、必ず「分岐点から、3メートル以内の場所」に、開閉器・過電流遮断器を設置しないといけないのです。
しかし、開閉器・過電流遮断器は安いものではなく、無闇矢鱈に取り付けると、作業も増えるしお金もかかるしメンテも馬鹿になりません。
んなもんで、「こういう場合なら、問題もそうないので、規制を緩和する」、つまり、3メートルを超えて設置してもよい、という例外規定が生まれたという塩梅です。
例外規定とは、テキストでおなじみの…、
「分岐点からの電線の許容電流が、幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上であれば、3メートルを超え8メートル以下に施設」と…、
「分岐点からの電線の許容電流が、幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上であれば、距離に制限なく取り付けられる」といった次第です。
漢字が多く頭が痛くなりそうですが、まずは、コアとなる…、
「35%以上…3メートルを超え8メートル以下」
「55%以上…距離関係なし」
…を頭に入れましょう。
先の説明文がわかりにくいなら…、
…の表のように、言い換えた形で、憶えるといいでしょう。
説明
本問の舞台は、「幹線の過電流遮断器の定格電流」が「60A」です。
そして、分岐点から、分岐回路の過電流遮断器までの距離が「10メートル」となっています。
先の文言や表に当てはめると、「8メートルを超える」に該当するので、「55%以上」で施工することになります。
んなもんで、「60*0.55」で「33A」となり、答えは「ニ」となります。
まとめ
本問が厄介なのは、漢字が多く、意味がわかりにくいところです。
幹線やら、分岐回路やら、定格電流やら、過電流遮断器やらで、文系ド素人だと、目が回ります。
しかし、本試験で問われていることは、非常にシンプルです。
一度理解してしまえば、得点源となりますし、憶えることは少ないので、費用対効果は大です。
文系ド素人にとっては、貴重な問題です。必ず、1点取れるようになっておきましょう。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 10:46 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |