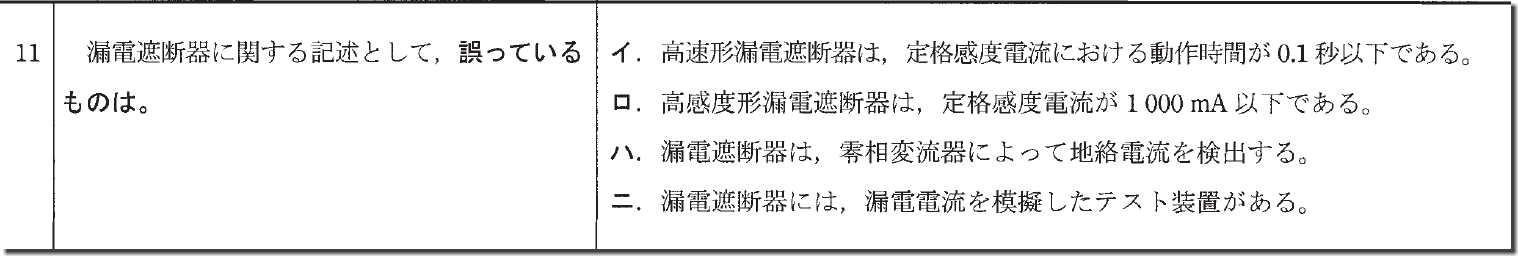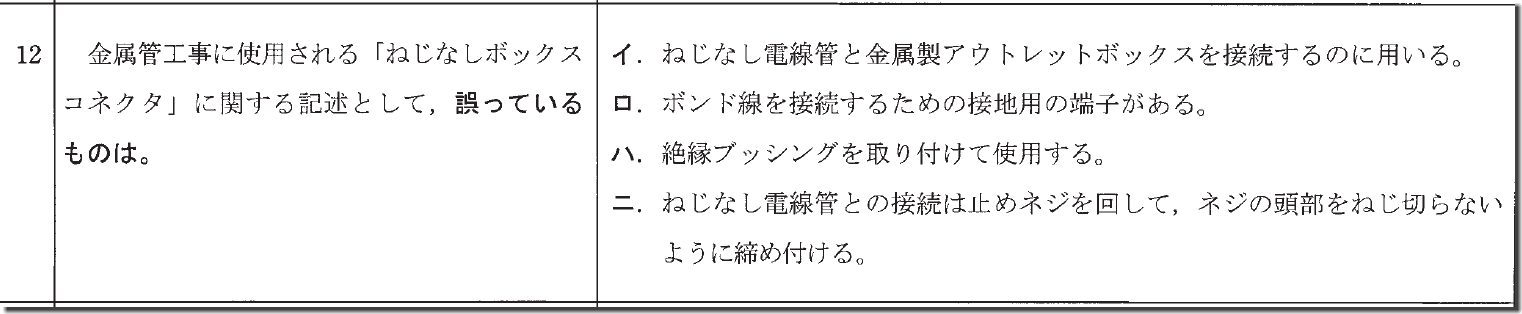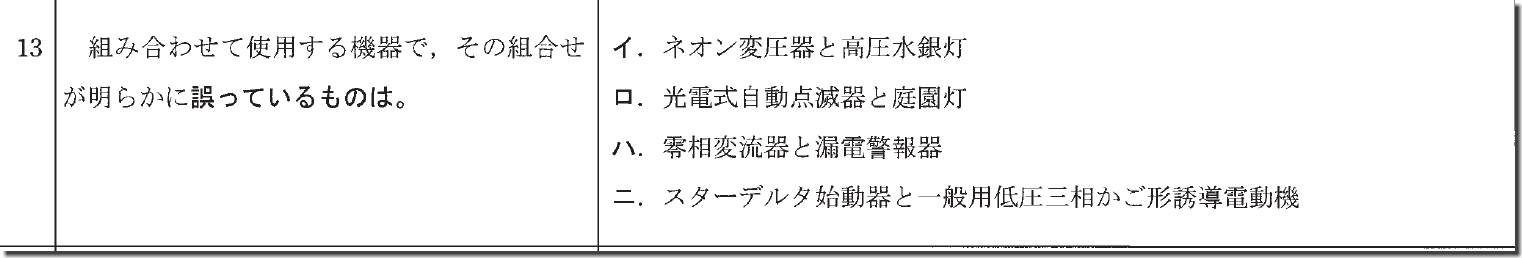第11問:漏電遮断器横断問題‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第11問は、「難」の問題で、テキストではあまり登場しない「高速形漏電遮断機」と「高感度形漏電遮断機」が出てくるので、「???」となりがちです。
ただ、問題を構成する選択肢は、定番のものがあり、言ってしまえば、本問は「当該頻出選択肢」をきっちり判別した後、運を天に任せるという次第です。
試験勉強的には、「ハ」と「ニ」だけ、答えられるようになっておけばいいでしょう。
解説
本問は、とりあえず消去できる選択肢を答えましょう。
まず解ける選択肢は、「ハ」です。
「ハ」の「漏電遮断器は、零相変流器によって地絡電流を検出する」ですが、まさに、そのまま、漏電遮断器の機能です。
んなもんで、「ハ」は「○」となります。
次に「ニ」です。
「漏電遮断器には、篭絡電流を模擬したテスト装置がある」ですが、まさに、その通りであります。
んなもんで、「ニ」も「○」と相なります。
なお、写真鑑別では、当該「テスト用ボタン」の有無で、漏電遮断器と配線用遮断器とを、区別するのがセオリーです。(試験問題の写真は小さいので、どうしてもこういうやり方となります。)
説明
残る「イ」と「ロ」ですが、知っていないとどうにもならないので、先の2選択肢「ハ」と「ニ」が判断できたら、50%の確率で、好きな方を解答、ってな次第です。
説明すると…、
「イ」の「高速形漏電遮断器」は、「定格感度電流の動作電流が0.1秒以下」のものです。
んなもんで、「イ」は「○」です。
「ロ」の「高感度形漏電遮断器」は、「定格感度電流が30mA以下」のものです。
問題の選択肢は「1000mA」となっているので、「×」となっています。
んなもんで、本問は「ロ」が答えと相なります。
まとめ
本問は、難問の類で、正解できなくても仕方がありません。
ただ、ド定番の選択肢である「ハ」と「ニ」だけは、答えられるようになっておきます。
反対に言うと、「ハ」と「ニ」を間違っているようじゃダメだ、であります。
「高速形なんたら」とか「高感度形なんたら」は、押さえ程度にアレしておきましょう。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 10:42 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第12問:技能問題‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第12問は、何気に「難」の問題です。
というのも、本問は、技能の勉強をしていないと、解けないからです。
技能の勉強を少しでもかじっていれば、解けるのですが、そうでないと全くわからないはずです。
本問は、筆記の勉強だけでは、対応できない問題で、一口で言えば、「捨ててもよい」です。
時間に余裕がある人は、技能のテキストを予習するのもいいですが、余裕のない人は、ぶっちゃけ『捨て問』にする、という次第です。
試験的に、技能がらみの問題は、出ても1~2問です。そのために、技能のテキストに手を付けるのは、費用対効果が悪いです。
ですから、まずは、筆記の定番を消化しきってください。
すべての論点が終わったら、点数を積み増すような感じで、本問のような、技能的問題に手を付けましょう。
「優先順位」をしっかり持ってください。
解説
本問は、知らないと、どうにもならない問題です。
答えは、ズバリ「ニ」で、「ねじ切らないように締め付ける」が誤りです。
正しい施工は、選択肢の真逆で、「締め付けた後、ねじを切る」となっています。
ちなみに、当該「ねじを切る」作業は、もし、そうしていないと、技能試験では「欠陥」を取られる作業です。
技能試験では、「欠陥」1つで即落ちますので、当該規定は憶えておいて損はありません。
説明
他の選択肢を見ていきましょう。
「イ」の「ねじなし電線管とアウトレットボックスを接続する」ですが、まさに、このままの作業です。
技能でも全くこのままの作業を行なうので、余裕のある人は、技能のテキストで確認するか、実際に組んでみましょう。
「ロ」の「ボンド線を接続する設置用の端子」うんぬんですが、これも、まさに、その通りです。
技能試験でも、当該ボンド線の設置作業を行なう可能性があります。(例年、ボンド線の作業は「省略」ですが、いつ指示が出てもいいよう、備えておくべきです。)
なお、当該ボンド線の作業は、作業そのものを忘れてやっていなかったり、不適切な取り付けだったりすると、「欠陥」で、即落ちします。
技能に備えて、頭の片隅に置いておきましょう。
「ハ」の「絶縁ブッシング」うんぬんも、その通りです。
なお、当該「絶縁ブッシング」も、技能試験での「欠陥」を取られるところで、取付を忘れていると、即落ちとなります。
一応は、頭に残しておきましょう。
まとめ
最近の試験では、本問のような「技能試験」に関ることも出題されるようになっています。
しかし、先も述べたように、技能試験がらみの問題は、出ても1~2問でしかありません。
ですから、まずは、筆記でド定番の論点を消化するほうが先です。
筆記の論点を消化した後で、点数を上乗せする、または、技能試験の予習をする感じで、当該論点を見ていくとよいでしょう。
なお、第2種電気工事士試験では、問題の使いまわしが、しばしば見られるので、本文が丸ごと、再利用される可能性はあります。
しっかり、復習しておきましょう。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 10:40 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第13問:器具・材料・工具‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第13問は、「器具・材料・工具」の横断問題です。
本問は、シンプルな知識問題なので「知ってさえいれば取れる」問題です。
文系ド素人は、率先して取るようにしてください。
また、本問を構成する選択肢は、どれも頻出事項なので、問題自体に正解するのみでなく、選択肢個々の正誤も完全にしておきましょう。
解説
「イ」の「ネオン変圧器」は、その名の通り「ネオン放電灯」の高電圧を作るための変圧器です。
従って、「イ」が「×」で、本問の正解となります。
説明
他の選択肢も、重要事項がいっぱいなので、チェックは必須であります。
本問の選択肢は、どれもが、形を変えて出続けているので、問題に正解するだけにとどまってはならず、追撃する必要を認めるものであります。
「ロ」の「自動点滅器」は「暗くなったら照明を点灯させるスイッチ」です。
んなもんで、「庭園灯」との組み合わせは「○」と相なります。
なお、「自動点滅器」の図記号は、「●A」で、筆記でも技能でも出るので、完全に憶えておきます。
ちなみに、「●A」の「A」は、「Auto(オート)」すなわち「自動」の意味であります。
ハ
「ハ」の「零相変流器(ZCT)」と「漏電警報機」は、ホントこのままのコンビです。
このまま、憶えるしかありません。
なお、これら2器具は、消防設備士の乙種7類の「漏電火災警報器」で必ず登場する機器であります。
第2種電気工事士の免状があると、乙7は、試験免除をガッツリ受けられるので、受験を考えてみてください。
参考:消防設備士:乙7の独学
ニ
「ニ」の「スターデルタ始動器」と「一般用低圧三相かご形誘導電動機」も、この通りの組み合わせです。
正直、文系ド素人にとっては、何がなんやらなのが実情でしょうが、このコンビはよく試験に出るので、せめて、名前だけでも押さえておきましょう。
まとめ
本問のような、「器具・材料・工具」の横断問題は、1問で多くの知識を試すので、定番の出題形式となっています。
1つ1つを甘く見ないで、しっかり憶えておきましょう。
ま、最初は一度にはできないので、“手に負える”ものから頭に入れていきます。
しっかり勉強しておけば、文系ド素人でもぜんぜん取れるので、ぜひ、1点にしましょう。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月7日 10:39 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |