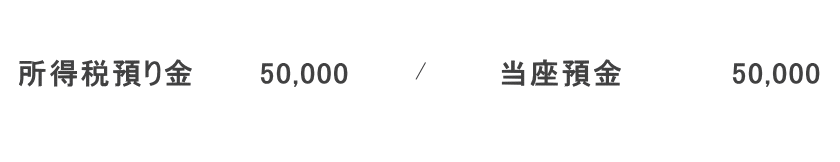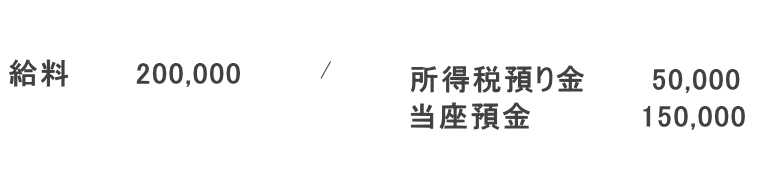大掃除に重曹が大活躍する掃除リスト
重曹は、手の荒れにくい食用グレードを推奨です。まあでも、弱アルカリ(pH = 8.3)なので、気にする必要はありません。隣で寝ている人のほうが有害です。
重曹は、ホームセンターやドラッグストアで売っています。値段はまちまちなので、安いところで買うといいでしょう。キロ単位で買うと割安です。
当方は、重い物を持ちたくないので、通販オンリーです。余った重曹は入浴剤や普段の洗濯に使うとスグ無くなります。
価格参考:アマゾン‐食用グレード重曹10キロ NICHIGA
重曹利用は簡単‐子犬でも配偶者でもできる
重曹の掃除利用は簡単です。
霧吹きを用意して、重曹を適当にバサバサ入れて、水を注いで振って溶かします。
当該重曹水を汚れに向けて、スプレーします。これだけで、汚れの落ち方が“劇的に”変わります。
なお、重曹はきつくないので、容量は気にする必要は全くありません。入れ過ぎたら霧吹きの底に残るだけ。
また、飲み込んでも害はなく、ノー手袋・ノーマスクで使用可能です。ですから、子供に使わせても安心です。(重曹は胃薬として市販されています。)
簡易窓拭きと窓のさん掃除
ほこりや土で手ひどく汚れている窓部分に、重曹水をざくざく吹き付けます。その時点で、配偶者のような黒い汚れが滴り落ちてくるはずです。
数分、時間を置いた方がきれいに汚れが取れるので、違う窓に吹き付けに行きます。なお、配偶者には吹き付けないでください。さすがに悪意を感じるからです。
さて、しばらく放置したら、ぼろ布で汚れを拭っていきます。こびりついた汚れは、更にスプレーすれば、するっと取れます。
窓のさんには、頑固な汚れが多いので、たっぷり重曹を使ってください。
なお、重曹の濃度や使用状況によっては、使用後に粉(塩)が出るときがあります。
このときは、いちいち拭くのも面倒なので、クエン酸水を吹き付けて中和させて除去します。
クエン酸を噴き付けると、水垢系の汚れが取れるので、重曹と併用しても構いません。
クエン酸も、ドラッグストアやホームセンターにあるはずです。
価格参考:ニチガのクエン酸1キログラム
台所油汚れ
軽い油汚れは、重曹水を吹き付ければすぐ落ちます。
しかし、換気扇や配偶者など、油汚れのひどいところは、重曹水ではなく、重曹を直に油に振りかけて、クレンザー風に“こそげ落とし”ます。お湯と併用すると落ち方は倍化します。
なお、重曹で手が荒れることはそうないですが、油が手に付くと面倒なので、ビニル手袋で掃除をするか、配偶者にやらせるとよいでしょう。
勝手は「換気扇の油汚れに重曹を」などを参考にしてみてください。油掃除に開眼するはずです。当方、半日仕事が2時間で終わるようになりました。
レンジ・冷蔵庫
食品系の汚れが目立つところです。食べ物系のべたつき汚れも、重曹が効きます。
軽い汚れは重曹水を拭きつけるだけで落ちます。
こびり付いてカピカピになったしつこい汚れは、重曹をかけてその上にスプレーをして、しばらく放置して拭います。
レンジは、臭いがこもりやすいので、掃除後は、重曹水に浸した布巾を入れて、数分加熱すると消臭できます。
なお、レンジや冷蔵庫の取っ手は、“かなり汚い”ので、大掃除を機に手脂をぬぐっておきましょう。
水筒
何かと汚れているのが水筒です。重曹をドバドバ入れて水を張ります。数時間、放置すれば、内壁にこびりついた汚れがドロっと出てきます。
夏に多用した方は大掃除を機に掃除です。
排水口
排水口には、ドバドバと重曹を入れまくります。次にクエン酸を入れます。水を注ぎます。
アルカリと酸がシュワシュワと反応して、臭いとつまりが格段に和らぐはずです。
年に1回こうしておくと、臭いに悩まされなくなります。
家中の排水口に処置しておきましょう。
クッション・ぬいぐるみ・座布団
洗えないクッション・ぬいぐるみ・座布団は、大き目のゴミ袋に入れて、重曹をばざばさ振りかけて、しばらく放置します。これで、臭いがなくなります。後は、重曹をはたいて天日で干せば完了です。
ついでの重曹消臭
重曹には、消臭効果があります。ビンに入れるだけの簡単な消臭剤ですが、そこそこ効き目があります。
押入れの整理、たんす・クローゼットの整理、玄関・くつばこの整理の際に、ビン入れした重曹を置いてみてください。
詳しくは「重曹で消臭」などの、一連の記事を参考までに。
重曹注意‐畳ダメ・熱ダメ
注意点をひとつ。
重曹はあまりに使い勝手がいいので、ついつい何にでも使ってしまいます。
が、「畳」には重曹を使ってはいけません。黒ずみの原因となります。
重曹は、こと「畳」だけはダメなので注意をしてください。重曹の数少ない「ダメ」の1つです。
次に、「高熱」は危険です。
沸騰したお湯を重曹にかけたり、重曹を加熱したりすると、焼成して「炭酸ナトリウム」という塩基性の高いものに化学変化します。
当該炭酸ナトリウムはアルカリ性が高く、薬傷のおそれがあります。
まあ、手に触れてもよい普通のお湯の「熱」なら、ぜんぜん大丈夫ですが、万が一のことを考えて述べておきます。(まあ、重曹を加熱することはまずないと思います。)
まとめ
重曹は、先述したように、「ほこり」「砂」「油汚れ」に甚大に有効です。
家具等の拭き掃除に使えます。
手垢の付きやすいところも、重曹が大活躍します。当方、キーボードやマウス、リモコンの手垢・手脂掃除に重曹を使ってます。市販のOA洗剤など目じゃありません。
ドアノブや電気のスイッチなどなど、どしどし使ってみてください。かなり、時間と手間を減らせられます。
っとまあ、こんな次第で、重曹があると格段に大掃除が楽になるので、試す価値は大です。
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: 重曹 | 2016年12月7日 11:41 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
所得税の源泉徴収税額の納付‐簿記3級仕訳
簿記試験の方針は、「実務重視」路線に切り替わっており、「実務で多用する取引」や「実務上、重要な処理」が、出題されるようになっています。
「所得税の源泉徴収税額の納付」も、こうした背景から、よく出るようになっています。
仕訳そのものは単純でも、源泉徴収制度について理解していないと、仕訳が切れないので、その目的と意味とを、しっかり理解しておく必要があります。
問題文
よくある問題文としては…、
「従業員の給与から差し引いた所得税の源泉徴収税額50,000円を銀行で支払った。」
…となっています。
答えの仕訳を先に挙げておきます。
前提
当該論点のポイントは、「前提」の理解です。
皆さん、重々、ご承知ですが、わたしたちに給料が支払われる際は、所得税が「源泉徴収」されています。
これを「支払側」からすると…、
…ってな仕訳が切られているわけです。
この仕訳が、当該論点の前提、ってな塩梅です。
処理はカンタン
「前提」が頭に入っているなら、処理はカンタンです。
一時預かり分の「所得税預り金」を減らすだけ、ってな次第です。
なお、勘定科目は、「預り金」の場合もあるので、柔軟に対応してください。
まとめ
「所得税の源泉徴収税額の納付」は、漢字だらけで頭が痛くなりそうですが、仕訳そのものはカンタンです。
しかし、どうして、このような仕訳をするのか、その『前提』を、つまり、源泉徴収制度を、きちんと理解しておいてください。
ざっくり述べると、給料を支払う際、事業者は所得税を徴収しなくてはいけません。
で、当該事業者が、期日が来たら当該源泉徴収した所得税を、銀行やコンビニで支払にいく、ってな塩梅です。
安易な暗記と記憶は、失点の元です。
当該論点は、社会人の方なら「当たり前」ですが、学生さんなら、いまいちピンと来ないため、しっくりこないはずです。
受験生を狩るのが趣味のブラディー出題者は、当該論点が「実務事項」であることもあり、ことさらに狙ってきそうです。
『心の軍師』に、『実務事項ゆえに、狙われることでしょう。』と、助言してもらってください。

なお、仕訳がうまく切れないという人は、「取引の8要素」が頭に刻まれていないからです。
「独学の簿記3級:商業簿記」を参考してください。当該8要素が頭に入ってないなら、無理して問題を解かなくていいです。
また、独学向け教材については「簿記3級の教材レビュー」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記3級, 簿記3級‐仕訳 | 2016年11月25日 10:37 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
危険物施設保安員は「監督の補助」で(語呂付き)‐危険物取扱者 乙種4類(乙4)の法令
乙4の法令で頻出なのが、「危険物施設保安員」です。
当該「危険物施設保安員」と似た規定に「危険物保安監督者」がありますが、両者を比べながら勉強すると、記憶に残りやすいです。
有体に言うと…、
「危険物保安監督者」は、「上司」で…、
「危険物施設保安員」は、「部下」といった寸法です。
「危険物施設保安員(以下、保安員)」は、言うなれば、「危険物保安監督者(以下、監督)」の「補助・補足」的な位置と考えておくと、本規定がカンタンになります。
このことを憶えるだけでも、混同や憶え間違えが、格段に少なくなります。
頻出‐設置義務施設
「危険物施設保安員」で、頻出なのは、「設置義務のある施設はどれか?」です。
憶え方ですが、先述したように、保安員は、監督の「補助・補足」的なものと言いました。
言うなれば、監督だけでは“手に負えない”から、補助なり補足なりが“必要”になるわけです。
このことを念頭に、『監督』を設置しないといけない施設を思い出してください。
「製造所の監督は、横文字のオク買いタンク」でした。
まず、保安員の設置義務のある施設は、これら監督の必要な施設の中にある、と憶えます。
このように憶えておくと、以下に述べる語呂をド忘れしても、監督の中から選べばいいので、格段に正解率が上がります。
語呂は「せいい」
保安員の必要な施設は、適当な語呂ですが、「せいい」と憶えます。
まあ、「危険物施設保安員は、せいい(誠意)」を持って仕事をしないといけない、風に考えれば、頭に入るかと思います。
さて、「せいい」の内容は…、
「せ」は、「製造所」で…、
「い」は、「一般取扱所」で…、
「い」は、「移送取扱所」で…、
…といった次第です。
指定数量の憶え方
さて、「せいい」ですが、注意点があります。
製造所と一般取扱所には、指定数量の規定があるからで、両施設は、「指定数量の倍数が100以上」あるときに、保安員の設置が義務付けられています。
当該倍数の「100」の憶え方を敢えて言うと…、
「危険物施設保安員」→「きけんぶつしせつほあんいん」→「ほあんいん」→「ほあん」→3文字→3ケタ→「100」
…てな具合に考えると、わたしは憶えられました。
まあ、「せいい」が「3文字」なので、「3ケタの100倍」と連想してもいいです。
このようにして、製造所と一般取扱所の「100倍」の数字を暗記するといいでしょう。
移送取扱所
さて、「移送取扱所」は、指定数量に関係なく、保安員の設置が義務付けられています。
これについては、「移送取扱所」が、言うなれば、「パイプライン」に当たることを考えれば、すんなり記憶に残るかと思います。
事故が起きたら大惨事なので、「指定数量に関係なく、保安員を配置する」と憶え込みましょう。
ない・ない
さて、最後のポイントは、「資格」と「届出」です。
「危険物施設保安員」は、「ない・ない」です。
保安員になるための要件は、法令に載ってないので、規制はありません。
つまり、「危険物取扱者の免状も要らないし、実務経験の必要ない」といった次第です。ですから、バイト君でもなれるわけです。
また、保安員を選任したとき・解任したときの報告義務もありません。
おさらいですが、監督だと、「甲か乙の免状+実務経験」が必要で、「選任・解任の届出は義務」でした。
これは、一番最初に述べた「監督」が上司で、「保安員」は部下と考えれば、納得できます。
つまり、上司で「やったこと」を、いちいち部下にまで拡大しなくていいだろう、的な手合いです。
イメージとしては…、
新人「保安員って免状が要るんすかね?」
ベテラン「監督が持ってるから、要らないんじゃね?」
新人「ですよねー」
…ってな寸法です。
新人「保安員って届けましたっけ?」
ベテラン「監督だけでいいんじゃね?俺ら下っ端だし。」
新人「ですよねー」
…ってな寸劇です。
ま、こんな風に考えていけば、失点は免れるように思います。
ところで、本試験では、「危険物施設保安員となるには、危険物取扱者の丙種免状が要る」という、割かし凝った問題が出るので、要領をキッチリ押さえて、確実に点にしてしまいましょう。
言うまでもなく、保安員に免状は要りません。上司の監督が持ってるからです。
なお、以上のことは、「試験向けの考え方」であり、実情を述べたものではありません。あくまで「試験用」なので、公言しないでください。恥をかきます。
まとめ
乙4の法令には、似たような規定が多いです。
「危険物施設保安員」の重要ポイントは、そうありません。
しかし、「危険物保安監督者」の規定と混同しやすいため、よくよく試験には出る論点です。
対策としては、まず、一番重要な「危険物保安監督者」をキッチリ憶えることです。
監督の方をキッチリできてから、補足的に、保安員の方を勉強するといいでしょう。
『心の軍師』に、『危険物施設保安員は「せいい」』と、助言してもらってください。

なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物取扱者 | 2016年11月18日 11:07 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |