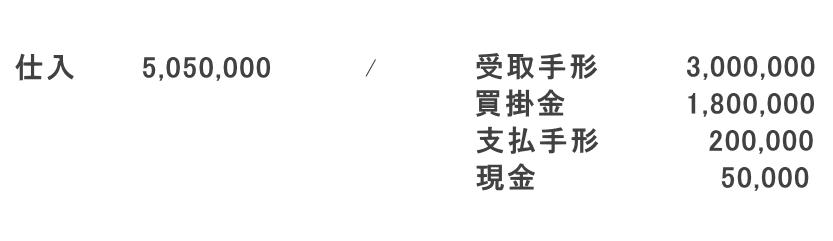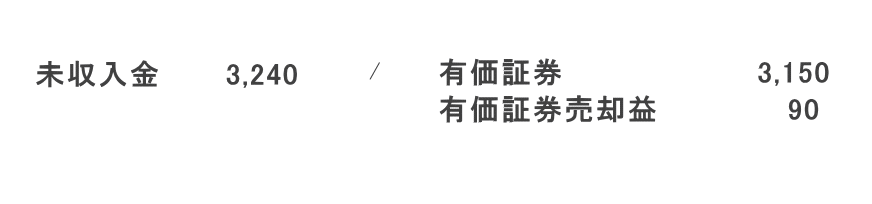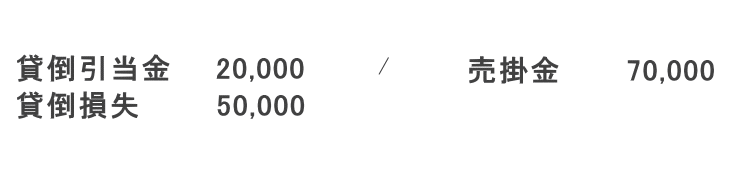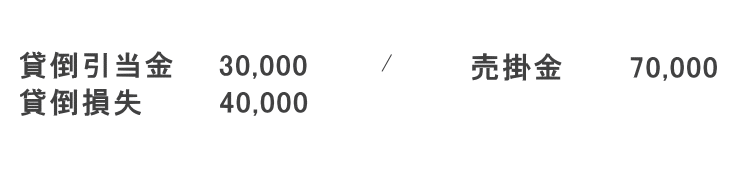仕入の応用問題‐簿記3級仕訳
昨今では、普通の仕訳は、まず出題されず、応用問題が大半です。
当該「仕入」の仕訳も、あの手この手で論点が付け加えられて、格段に“複雑化”されているので、「慣れ」が必要です。
ま、1つ1つの論点は手に負えるので、慎重に解答すれば1点取れます。
問題文
よくある問題文としては…、
「商品5,000,000円を仕入れた。代金のうち、3,000,000円は手形を裏書譲渡し、1,800,000円は掛けに、200,000円は手形を振り出した。当方負担の運賃50,000円は現金で支払った」
…となっています。
答えの仕訳を先に挙げておきます。
手形の裏書譲渡
陰険な出題者の1つ目のいやがらせが、「3,000,000円は手形を裏書譲渡」部分の「手形の裏書譲渡」です。
ご存知のように、手形の裏書譲渡は、「受取手形」を減らす処理です。
底の浅い受験生だと、「手形」という文言に釣られて、「仕入で手形…支払手形っ!」と仕訳を切るはずです。
ゆえに、出題者は狙ってくる、という次第です。
買掛金
邪悪な出題者の2つ目のいやがらせが、「1,800,000円は掛」部分です。
難しく考える必要はありません。
単に「買掛金」で仕訳を切ればいいだけです。
「買掛金」を差し込んでくるのは、問題を複雑化して、受験生に手間を食わせたいだけです。
基礎・基本どおり、「買掛金」で処理しましょう。
(…これ、買掛金だよなー。なんか別の処理があったけ?)などと、思い悩んではいけません。
それが、出題者の罠(意図)だからです。
手形振り出し
陰湿な出題者の3つ目のいやがらせが、「200,000円は手形を振り出した」部分です。
言うまでもなく、「支払手形」で仕訳を切ります。
普通の処理ですが、この部分は、受験生の疑心暗鬼を発生させるための処置です。
そう、先に手形の裏書譲渡で「受取手形」が顔を出しており、「あれ、手形に手形?手形が2つも出てくる?」などと、思わせたいわけです。
先述したように、(支払手形でいいよなー。なんか別の処理があったけ?)などと、思い悩まないでください。
カンタンな仕訳でも、受験生の目を惑わすことに使えるのです。
運賃現金
かび臭い出題者の4つ目のいやがらせが、「当方負担の運賃50,000円は現金」部分です。
「当方負担」という指示があるので、当該運賃は、取得原価、つまり、「仕入」に含めます。
このとき、出題者は、必ず、使用勘定科目群に、「送料」や「運賃」、「運送料」といった文言を挿し込んできます。
これだけ論点がてんこ盛りだと、ついつい、注意が向かず、下手を打ってしまいます。最後まで、注意してください。
「付随費用は、取得原価に含める」です。
商品の取得原価計算
先述したように、「付随費用は、取得原価に含める」です。ホント、頻出論点です。
「仕入」は、「5,000,000円」に運賃「50,000円」を足して、「5,050,000円」で仕訳を切ることになります。
まとめ
ド定番の「仕入」でも、出しようによっては、ここまで複雑な問題ができてしまいます。
1つ1つが単独で出されたら解けるでしょうが、いっぺんに来られるだけで、たちまち苦戦してしまいます。
こんな問題を出されたら、底の浅い受験生は一気に狩られてしまうでしょう。
出題者は、徹底して受験生の弱いところを狙ってきます。いい「的(まと)」にならないよう、しっかり勉強しておきます。
ま、1つ1つの処理は、基礎・基本レベルなので、勉強した受験生なら、苦戦はするでしょうが、点数は取れるはずです。
『心の軍師』に、『各個撃破ですな』と、助言してもらってください。

なお、仕訳がうまく切れないという人は、「取引の8要素」が頭に刻まれていないからです。
「独学の簿記3級:商業簿記」を参考してください。当該8要素が頭に入ってないなら、無理して問題を解かなくていいです。
また、独学向け教材については「簿記3級の教材レビュー」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記3級, 簿記3級‐仕訳 | 2016年10月7日 10:49 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
有価証券の期中売却‐簿記3級仕訳
有価証券の期中売却は、仕訳問題で頻出です。
狙われる理由は、「損益計算がめんどくさいのと、取得原価の論点(付随費用の処理)があるのと、勘定科目の未収入金も試せるから」です。
出題者からすると“ドてんこもり”の論点で、おっちょこちょいの受験生など、当該有価証券の仕訳で一掃されてしまいます。
問題文と答えの仕訳
よくある問題文としては…、
「株を30株、108円で売った。売却金額は来月受け取る。この株は、先月、1株100円で100株買ったもので、購入の際、手数料が500円かかっている。」
…という、期中売却の問題です。
答えとなる仕訳は…、
…です。
たった2行ながら、その“影に”計算量はそこそこあります。だから、「いやらしい」のです。
取得原価でミス多し
有価証券を売却する場合は、その元値となる「取得原価」を計算しなくてはいけません。
ここが第1の関門です。
購入手数料などの「付随費用」がかかった場合、当該費用を取得原価に加算します。
先の「1株100円の株を100株買った。購入の際、手数料が500円かかった。」の場合、株の代金は100円×100株の10,000円に、付随費用の手数料500円を足した「10,500円」となります。
取得原価は「10,500円」で、この際、1株の価格は、「10500÷100株」の「@105円」となり、当該金額で損益計算することになります。
うっかりすると、購入時の「100円」で、売却益なり売却損を計算しかねません。
こんな次第で、『有価証券の売却」では、「取得原価」に注意です。陰湿な出題者は、まず出してきます。
損益の計算
先の述べたように、有価証券の売却は、「取得原価」を算定してからになります。
損益の計算をミスをする人は、はしょらず、過程を計算用紙に書き出しましょう。わたしは、よく間違えるので、紙上計算派です。(自分の脳を信じていません。)
先の例で行くと、取得原価は、「一株あたり@105円」です。
これを30株売ったのですから、「30株×105」で「3,150(買い)」が、元の値段です。
単価108円で30株売ったのですから、「30株×108」で「3,240(売り)」が、入金予定額です。
「3240(売り)-3150(買い)」で「90」が、「有価証券売却益」となります。
なお、「108-105」で差額を計算して、「3×30株」でも計算できます。好き好きでやってください。
損益計算は、特に凝ったところもないのですが、何気に計算ミスを犯しやすいところです。(経験者は語る。)
先の(売り)(買い)の表記も、時折、どっちの数字で買って売ったのか、わからなくなったときがあるので、整理のためにそういうメモをしていました。
単純な計算で間違えるとショックなので、落ち着いて、丁寧に電卓を打ちましょう。
受け取り来月 未収入金
まだまだ、油断はできません。
問題文には「売却金額は来月受け取る。」とあるからです。
ついウッカリいつもの癖で、「現金」や「当座預金」で処理しそうになるので、本当に問題文は注意して読まなくてはいけません。
営業“外”で未入金のものは「未収入金」で処理します。
あまり使わない仕訳なので、受験生の盲点となっており、邪悪な出題者が突いてくる可能性が大です。
「未収入金」という勘定科目の存在を、忘れないようにしましょう。
ちなみに、営業“上”の未入金は「売掛金」です。
まとめ
こんな次第で、「有価証券の期中売却」は、見かけと違って処理が多く、底の浅い受験生をさくさく狩れる、ブローニングM2重機関銃的な論点となっており、昔も今も、たびたび出題されています。
言うまでもなく、第1問の仕訳問題のみならず、第3問の総合問題、第2問の個別論点問題にも出題されるので、しっかり勉強しておきましょう。
本試験で目にしたら、御尻の穴をキュッと締めて、取り組んでください。そこかしこに、失点の可能性があります。
なお、「有価証券の期中売却」の要領は、簿記2級でもわんさか出題されるので、3級の時点で、完全に理解しておくと後々楽です。
なお、仕訳がうまく切れないという人は、「取引の8要素」が頭に刻まれていないからです。
「独学の簿記3級:商業簿記」を参考にしてください。当該8要素が頭に入ってないなら、無理して問題を解かなくていいです。まずはここからです。
また、独学向け教材については「簿記3級の教材レビュー」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記3級, 簿記3級‐仕訳 | 2016年10月6日 11:22 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
貸倒損失と貸倒引当金‐簿記3級仕訳
貸倒損失と貸倒引当金の処理は、仕訳問題で頻出です。
狙われる理由は、「知らないと絶対に解けないから」で、底の浅い受験生を狩る、格好の論点となっています。
当該貸倒損失の処理は、「費用収益対応の原則」などの、崇高かつどうでもいい会計学の理屈が背後に控えています。
犬も食わない会計学です。
善良なわたしたちは、そんなものをうっちゃておいて、当該論点の処理だけを憶えましょう。
問題文
よくある問題文としては…、
「ツブレ堂が倒産した。前期に発生した売掛金は20,000円で、当期に発生した売掛金は50,000円である。貸倒引当金の残高は30,000円である。」
…といった塩梅です。
先に答えを挙げておくと…、
…です。
なお、推定問題では、貸倒引当金の残高が問われたりもします。この場合、残高は「10,000」です。
基本論点
まず、債権が貸し倒れたときは、「貸倒損失」で処理します。
で、この際、「貸倒引当金」が計上されているなら、当該「貸倒引当金」を当該損失に充てる、といった塩梅です。
で、引当金で不足するなら、当該残額を「貸倒損失」で処理します。
ま、教科書をよく読んでください。
昔は「これ」で点が取れましたが、最近は、もう少し突っ込んだ出題となっています。
去年のは去年、今年のは今年
端的に言うと、貸倒引当金の処理は「去年は去年、今年は今年」といった次第で、『それはそれ、これはこれ』方式です。
計上されている貸倒引当金は、「前期の債権」に“ひも”づけられています。
ですから、今ある貸倒引当金は、「今年の債権」とは、関係ありません。
処理の方法‐まず当期分
「去年は去年、今年は今年」です。
確実に攻めて行きましょう。
先述したように「去年は去年、今年は今年」です。
当期に発生した売掛金50,000と、前期に計上された貸倒引当金は、対応関係にありません。
ですから、当期分は、即、「貸倒損失」で処理します。
処理の方法‐次に前期分
前期の処理を行ないます。
前期に発生した売掛金は20,000円ですが、これには、前期計上の貸倒引当金と「対応」しています。
ですから、貸し倒れた前期分の20,000は、貸倒引当金で処理できるという塩梅です。
まとめ
もう一度、正解の仕訳を挙げます。
当該貸倒損失のポイントは、繰り返しますが、「去年は去年、今年は今年」であることです。
よくある間違いの仕訳を挙げておきます。
ついウッカリすると、貸し倒れた売掛金の全額70,000を、貸倒引当金で処理しかねません。
いや、多くの受験生は、貸倒引当金の全額を、当期発生分の債権に充てることでしょう。そして、間違うことでしょう。貴重な1点を失うことでしょう。
また、先述したように、貸倒引当金の残高を問う出題も、大いに考えられるので、念入りに見ておきましょう。
こんな次第で、貸倒損失の論点では、「前期計上した貸倒引当金は、前期の債権にのみ使う。当期分はそのまま貸倒損失にする」ということを憶えておかないと、絶対に正解できない論点となっています。
2級の総合問題でも出ています。処理の要領をしっかり憶えておきましょう。
なお、仕訳がうまく切れないという人は、「取引の8要素」が頭に刻まれていないからです。
「独学の簿記3級:商業簿記」を参考にしてください。当該8要素が頭に入ってないなら、無理して問題を解かなくていいです。まずはここからです。
また、独学向け教材については「簿記3級の教材レビュー」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記3級, 簿記3級‐仕訳 | 2016年10月5日 11:46 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |