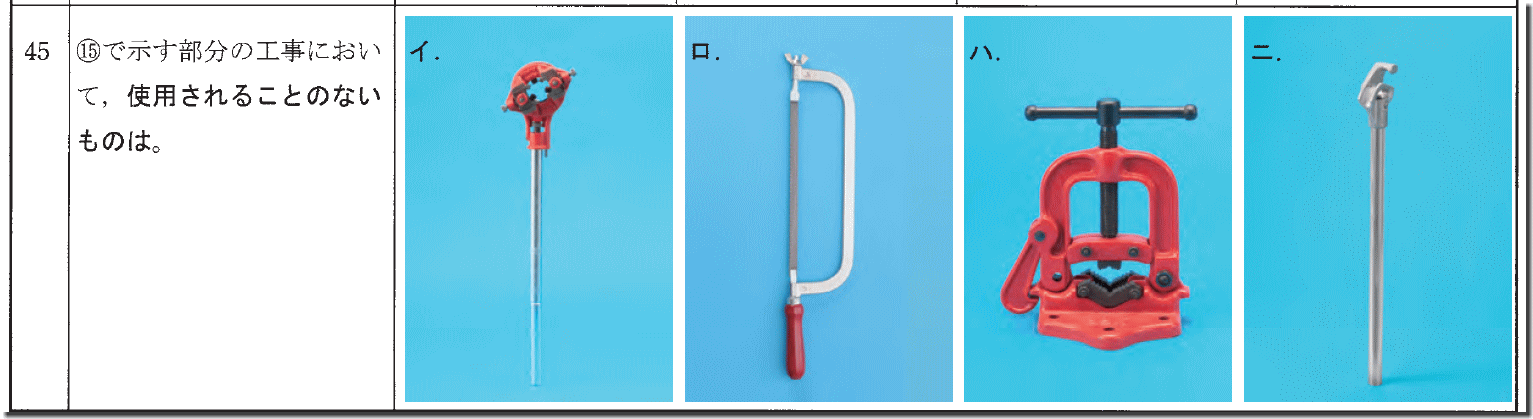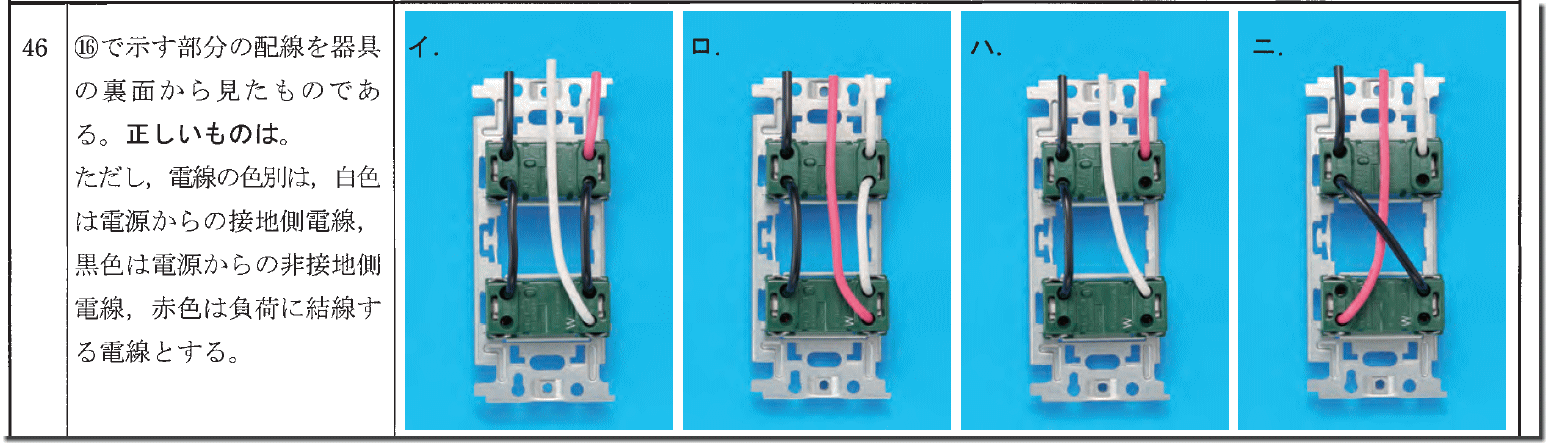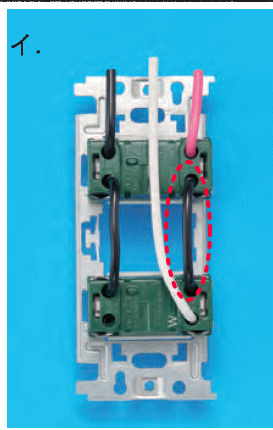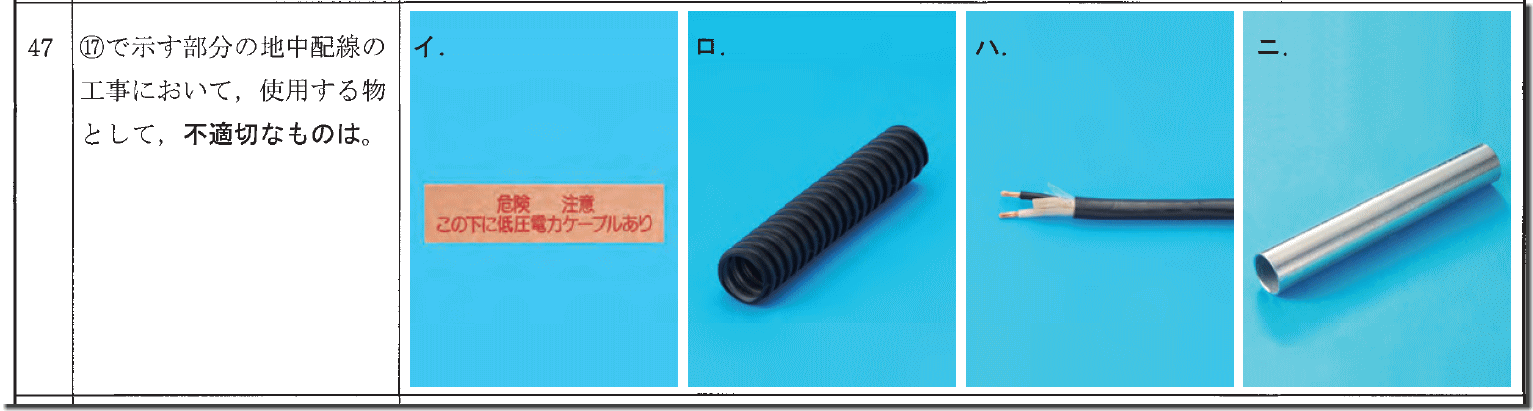第45問:図記号Eと工具写真鑑別‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第45問は、「知識問題2問分」といった次第です。
問題文の指示「⑮」には、「IV1.6 E19」との記号が付されています。
「E」が示すのは、「ねじなし金属管」です。
まず、ここがわからないと、正解には到達できません。ここが知識問題の1問分です。
ほいで、工具の写真鑑別です。
どの工具が何をするのか、正確な工具知識がないと、間違えます。んなもんで、「1問で2問分」といった寸法です。
整理して選択肢を判別すれば、取れます。
解説
本問のポイントは、「E」が「ねじなし管」であると判断できるかどうか、です。
先も言ったように、ここがわからないとどうにもならないので、しっかり憶えましょう。ド頻出事項です。
なお、当該「E(ねじなし管)」憶え方については、「電線管の種類と記号の憶え方‐薄鋼電線管・ねじなし電線管・2種金属製可とう電線管」の方を参考にしてみてください。
次に、画像の工具を見ていくと…、
「イ」は、「リード型ねじきり器」です。
「ロ」は、「金切りのこ」です。
「ハ」は、「パイプバイス」です。
「二」は、「パイプベンダ」です。
…それぞれの名前を挙げるだけで、答えが出ました。
本問の答えは、「イ」の「リード型ねじきり器」です。
その名の通り、当該器具は「ねじを切る器」なので、本問の「ねじなし金属管」には用いない、といった次第です。
補足
本問の問題に採用されている器具は、すべて、その用途と名前を憶えておきましょう。
ぜんぶ、試験問題として登場しています。
「ロ」の「金切りのこ」は、金属管や太い電線を切断するために使います。
「ハ」の「パイプバイス」は、金属管を切断する際に、金属管を固定するために用います。
ちなみに、「パイプバイス」の「バイス」とは、「万力」のことです。
参考:アマゾン‐バイス・万力
「二」の「パイプベンダ」は、金属管を曲げるときに用います。
コツは「ホームセンターに急げ」
本問のような、工具の写真鑑別は、実物を手にするのが最大のコツです。
反対に言うと、文系ド素人にとっては、テキストの写真だけでは、実にわかりにくい、といった次第です。
数センチの写真を眺めるより、ホームセンターにて、何十倍もの大きさをした実際の工具を手にする方が、よほどにわかります。
1問でも、器具の写真鑑別で間違ったなら、土日に時間を取って、ホームセンターの工具売り場で、テキスト片手に時間を潰してみてください。
(あーこれがねじ切り器ね)といった風に勉強する方が、絶対に早いし、間違わないです。
ほいで、ホームセンターの帰りには、洗剤かティッシュでも買って店の売上に貢献するのを忘れないようにしてください。(勉強の御礼はしなくてはいけません。)
まとめ
本問で出てくる「E」の「ねじなし金属管」は、配線図の問題ではド定番なので、きちんと憶えておきましょう。
また、工具の写真鑑別は、テキストのみに頼らず、実物に手にしましょう。文系ド素人は、実地教育が一番です。
本問も「取れる」問題です。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月4日 10:25 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第46問:配線の写真鑑別‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第46問は、一見すると(うわっ!?)となりますが、そう難しくはありません。
本問は、『問題文さえよく読めば、正解できる』問題です。
本問では、「赤色は負荷に結線する」とあり、ここさえ理解できれば、正解できます。
解説
先述したように、本問のポイントは、「赤色は負荷に結線する」の理解に尽きます。
ここで言う「負荷」とは、「蛍光灯」のことです。
つまり、「蛍光灯」と「蛍光灯のスイッチ」は、「赤色」でつなぐ、塩梅です。
ここまで把握できれば…、
「ロ」と「二」は「スイッチ」に結線されていないので、「×」となります。
両選択肢とも、「コンセント」に「赤色」が結線されています。これじゃあダメです。
「電気工事」は、手前勝手にやってよいものではなく、「指示通り」にできるかどうかが大事です。
本問は、このことが守れるかどうかを、試しているように見受けられます。
なお、文系ド素人が陥りやすい罠として、「電気的に通じている・通じていない」を考えがちですが、そんなこと考えなくていいです。
大事なことは、指示通りに施工するだけです。
「余計なことはやらない」「余計なことは考えない」は、どの仕事でも通じる真理です。
説明
さて、正解の選択肢ですが、答えは「ハ」です。
「イ」は、「無用な渡り線」があるので「×」です。
当該渡り線に意味はなく、電線の無駄であり、ガチで「×」です。
補足
問題文には「配線の器具の裏側」となっています。
間違える人はそういないと思いますが、念のために言うと、「上がスイッチで、下がコンセント」です。
配線図の“図記号の置き方”どおりに組むことになるので、間違えないでください。
なお、コンセントには「極性」があり、本問のように、「接地側電線」は「W」または「N」の表記されたところに結線します。
当該極性は『技能試験で重大欠陥ポイント(間違えると即落ち)』なので、筆記のときから頭に叩き込んでおいてください。
まとめ
2電工の筆記は、定型・定番の問題が多いので、問題文を読まなくても、解答できたりします。
しかし、それこそ盲点で、出題者は逆手を取るように、「問題文を読まないと解けない」ものを繰り出してきます。
本問は、まさに、「問題文をよく読んでいないと解けない」問題の典型です。問題文を飛ばし読みしないで、しっかり読む訓練をしておきましょう。
反対に言うと、「問題がうまく解けないときは、問題文を再度、読み直してみる」という塩梅です。
本問は、文系ド素人でも「取れる」問題です。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 過去のススメ | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月4日 10:19 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第47問:地中配線工事の写真鑑別‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第47問は、平成28年後期の筆記試験で、最もカンタンな“取れる”問題となっています。
少々頭を使えば、正解を導ける問題です。
2電工の筆記では、こうした“常識的な問題”もあるので、絶対に落とさないようにしましょう。
本問は、一種のボーナス問題です。
解説
本問の「地中配線工事」は、小難しく考える必要はありません。
『金属管を埋めちゃ、錆びるからダメだろ』と、常識的な判断ができればそれでOKです。
言うまでもなく、答えは「二」の「金属管」です。
説明
念のため、選択肢の写真それぞれを述べると…、
「イ」は、「ケーブル標識シート」です。
「ロ」は、「FEP管(波付硬質合成樹脂管)」です。
「ハ」は、「CVケーブル」です。
「二」は、「金属管」です。
補足説明
「イ」の「ケーブル標識シート」は、何気にアレレとなりかねない盲点事項です。
テキストの該当ページには、重要な工具が目白押しなため、そちらにばかり目が行ってしまい、この標識シートを見落としがちです。テキストの写真はどれも出る可能性があるので、丁寧に見ておきましょう。
言うまでもありませんが、当該標識シートは、「この下に」の文言どおり、地中埋設工事に使います。
「ロ」の「FEP管」は、何気に身近で見かけます。
マンション住まいの人は、建物に付属する「植え込み」を探してみてください。ぽろっと埋まっているFEP管を、野良猫のフンと一緒に見つけることができるでしょう。
なお、FEP管については、「電線管の種類と記号の憶え方2‐PF管とCD管・VE管・HIVE管・FEP管」も、参考にしてみてください。
また、当該FEP管は、頻出事項なので、必ずその姿形と名前と用途とを押さえておきましょう。
「ハ」の「CVケーブル」は、実物を見れば、(ああこれか)となるのですが、本試験ような、数センチ大の写真では、何が何やらわからないはずです。
本試験では、当該選択肢のCVケーブルがわからなくても、仕方ありません。ルーペでもないとわからんですわ。
当該CVケーブルも地中埋設工事に使います。
まとめ
本問は、正面から解くよりも、「電気工事の当たり前」を前面に押し出したほうがいいです。
先述したように、「地中に金属管は、錆びるからダメだろ」で、常識的に考えれば、正解できるはずです。
ただ、本試験では、いつもと違う精神状態になっているので、深追いしないこと・難しく考えないことが大事です。
たとえば、わたしなんかは、「イ」の「ケーブル標識シート」に引っかかってしまい、(こんなもん使ったけ?)と思った口で、危うく間違うところでした。
“普段は判断できることでも、本試験では、うまく判断できないこと”もあります。
油断大敵です。本試験での精神状態も踏まえて、しっかり復習しておきましょう。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月4日 10:16 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |