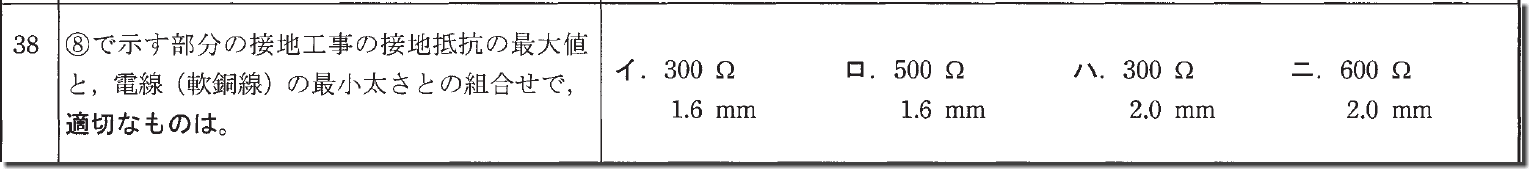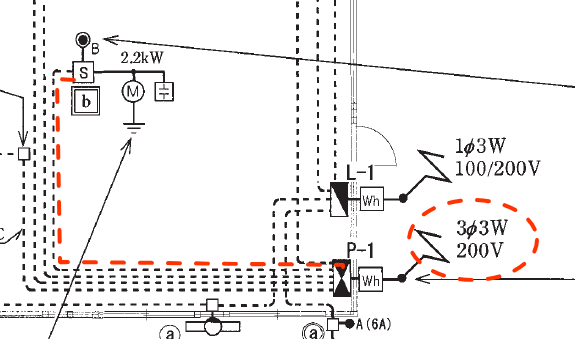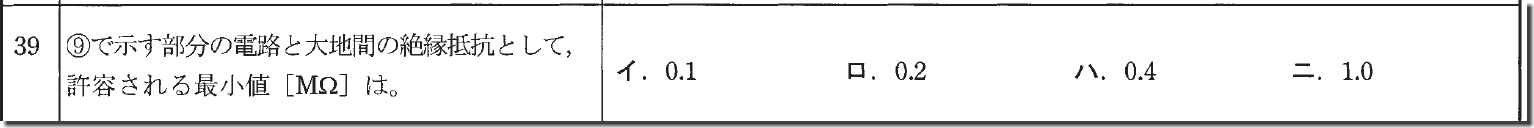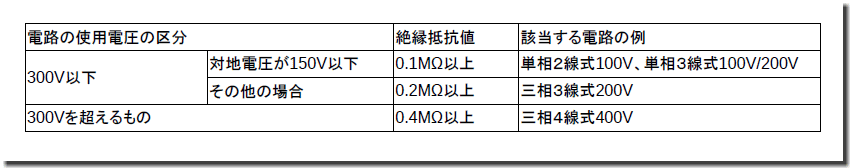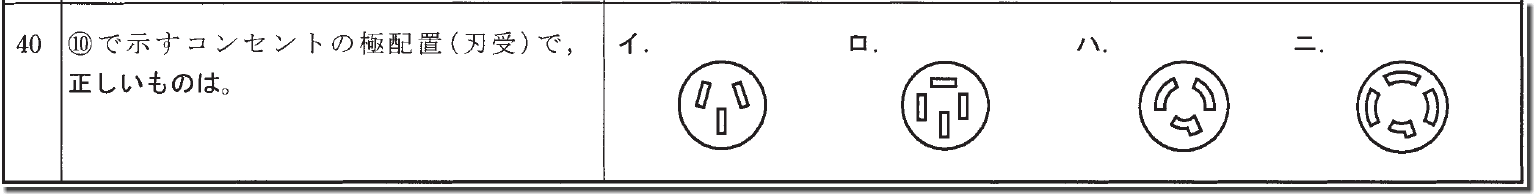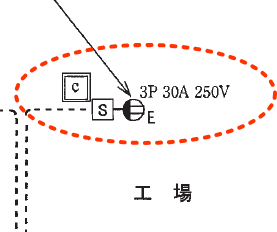第38問:D種接地工事‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第38問は、ぶっちゃけ「知識問題」で、“規則でそう決まっているので、そう憶えるしかない”のであります。
「Ω」云々の記号が出るので計算でもするかと思いきや、「D種接地工事」の定番の表を憶えるだけ、という塩梅です。
当該表は、通勤や通学時に何度も目を通せば頭に残ります。
文系ド素人でも取れるので、確実に点にしましょう。
また、当該「D種接地工事」の論点は、ほぼ例年、問われる論点となっています。本試験では、本問が“即答”できるくらいになっておきましょう。
解説
先述したように、本問は「絶縁抵抗」の定番の表を憶えるだけです。
その表とは…、
…です。
おそらく、皆さんが使っているテキストにも、同様の表があるはずです。(ないなら、先の画像をスマホ等に保存して利用してください。)
後述しますが、この表を憶えて、言葉を当てはめるだけです。
問題冊子の余白部分に、先の表がスラスラ書けるようになっておきましょう。うろ覚えじゃダメです。
説明
配線図を見ると…、
…この部分の接地を施す電動機は、「三相3線式200V」を電源とする機器であることがわかります。
後は、先の表に当てはめるだけです。
使用電圧は「300V」以下となので、「D種接地工事」となります。
で、ここが本問の独自のところですが、「配線図」の問題文の注意事項に目を通します。
見るべきは、〔注意〕の「3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用してる」です。
ここを見ていないと解答できません。
先の表を見れば、「0.5秒以内に動作する漏電遮断機を施設する場合、500Ω以下」とあるので、「500Ω」まで許容されるという次第です。
説明
先の時点で、答えは出ています。
接地抵抗値の最大値は「500Ω」なので、ズバリ「ロ」と相なる次第です。
このように、先の定番の表を暗記していれば、さっくり解けてしまうという寸法です。
さて、電線の太さですが、これまた、先の表を憶えていれば、解答できるはずです。
太さは、表にあるように「1.6mm以上」です。
んなもんで、「ロ」で、間違いないといった寸法です。
なお、本規定には「移動して使用する電気機械器具の接地線で、多心コードまたは多心キャブタイヤケーブルの1心を使う場合は0.75mm2以上」という例外規定がありますが、2電工ではまず問われることはないでしょう。
まとめ
本問の「D種接地工事」の問題は、「知ってさえいれば解ける問題」です。
先述したように、余白にスラスラ展開できるくらいに、表を暗記してください。
また、本問は、「注意書き」を読んでいないと正解できない問題なので、こうした問題のあることを知っておいてください。
ま、本問は、文系ド素人でも正解できるので、確実に点にしましょう。
こういう問題をとることで、電気理論や電気工事、複線図といった難問の備えをする、といった寸法です。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 9:05 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第39問:絶縁抵抗値‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第39問は、ぶっちゃけ「知識問題」で、“規則でそう決まっているので、そう憶えるしかない”のであります。
「Ω」云々の記号が出るので計算でもするかと思いきや、「絶縁抵抗」の定番の表を憶えるだけ、という塩梅です。
当該表は、通勤や通学時に何度も目を通せば頭に残ります。
文系ド素人でも取れるので、確実に点にしましょう。
また、当該「絶縁抵抗」の論点は、ほぼ例年、問われる論点となっています。本試験では、本問が“即答”できるレベルになっておきましょう。
解説
先述したように、本問は「絶縁抵抗」の定番の表を憶えるだけです。
その表とは…、
…です。
おそらく、皆さんが使っているテキストにも、同様の表があるはずです。(ないなら、先の画像をスマホ等に保存して利用してください。)
後述しますが、この表を憶えて、言葉を当てはめるだけです。
問題冊子の余白部分に、先の表がスラスラ書けるようになっておきましょう。うろ覚えじゃダメです。
説明
配線図を見ると、「動力分電盤P-1」の「d」に接続されているのが分かります。
んで、当該「d」の電源側をたどっていくと、「3φ3W200V」との表記が見られます。
んなもんで、問題の電路は「三相3線式200V」と相なります。
ここまで来たら、先の暗記すべき表に当てはめるだけです。
使用電圧は「300V以下」で、対地電圧が「200V」、「三相3線式」なので、絶縁抵抗値は「0.2MΩ以上」となる塩梅です。
んなもんで、解答は「ロ」の「0.2」と相なる次第であります。
ちなみに、「3φ3W」は、「3φ」が「三相」を表し、「3W」は「3線」を表しています。んなもんで、「三相3線式」という寸法です。
なお、「φ」は、「ファイ」と呼びます。
まとめ
本問の「絶縁抵抗値」の問題は、「知ってさえいれば解ける問題」です。
先述したように、余白にスラスラ展開できるくらいに、表を暗記してください。
文系ド素人でも正解できるので、確実に点にしましょう。
こういう問題をとることで、電気理論や電気工事、複線図といった難問の備えをする、といった寸法です。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 8:59 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第40問:コンセントの刃受け‐平成28年後期筆記‐第2種電気工事士の過去問解説
第40問は、「コンセント種類」を問う問題で、ぶっちゃけ、「知識問題」です。
知ってさえいれば取れるので、確実に点にしましょう。
とりわけ本問は、種類の少ない「三相200V」なので確実に点としたいところです。
ところで、本問は、知ってさえいれば“即答”できます。こういう単純な知識問題こそ、「計算問題の解答時間」の源泉です。
すぐ解けるレベルに到達しておきましょう。
解説
本問の図記号は…、
…のように、「3P 30A 250V」に「E」となっていることから、「三相200V用30A接地極付コンセント」です。
…言うまでもなく、「E」は「接地極」の「“E”arth」です。
本問のコツは、「暗記にするに限る」です。
といいますか、「コンセントの刃受け」の形を憶えていない限り、解答のしようがありません。
んなもんで、テキストの図を何度も目を通して、憶えるしかありません。
反対に言えば、「憶えていれば、文系ド素人でも余裕で点が取れる」です。
んで、解答ですが、「接地極付」の「三相200V用30Aコンセント」なので、「ロ」と相なります。
説明
「イ」は、「三相200V用コンセント」です。接地極がないコンセントです。
「ハ」は、「三相200V用コンセント」ですが、「引掛形」です。なので「T」がある場合のコンセントとなります。
なお、「T」は「twist(ツイスト)」の「T」です。
「二」は、「三相200V用コンセント」の「接地極付」で「引掛形」です。なので「E」と「T」がある場合のコンセントとなります。
まとめ
本問は、「知ってさえいれば解ける知識問題」です。
また、刃受けコンセントの論点では、2つしかない「三相200V」でカンタンな部類です。
即断に解答して、計算問題の解答時間を捻出してください。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 筆記H28後期, 2電工筆記‐過去問 | 2017年4月6日 8:57 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |