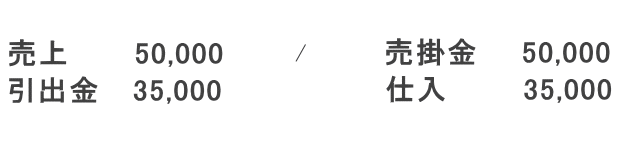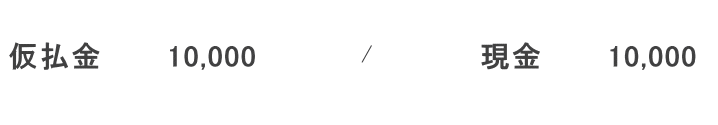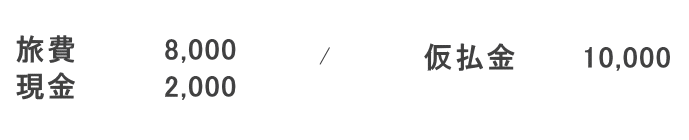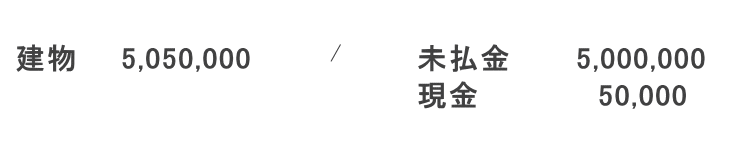商品の自家消費‐簿記3級仕訳
仕訳問題で狙われるのが、「商品の自家消費」です。
当該論点が頻出なのは、「使い慣れない勘定科目」で処理するからです。
「資本金」勘定や「引出金」勘定を使うのですが、「ほとんど姿を現さないレア勘定科目」なので、仕訳を切る機会がなく、このため、受験生が手薄になっています。
故に、喫茶店のようじを全て持って帰る出題者は、ことさらに、出題してくる、といった塩梅です。
第1問の仕訳問題のほか、第2問の個別論点で問われたり、第4問あたりで帳簿記入まで求められることが考えられますが、基本は、この「仕訳」ですので、きっちり、見ておきましょう。
問題文
よくある問題文としては…、
「掛で販売した原価7,000円のメロン100個(売価10,000円)のうち、5個が返品された。仕方ないのでジャムにした。(引出金で処理)」
…となっています。
答えの仕訳を先に挙げておきます。
ポイント1‐訂正仕訳
お馴染みの頻出論点「訂正仕訳」が、試されています。
普通の訂正仕訳ですが、「売価」と「原価」に注意します。
「売った商品」の返品ですから、返品の仕分けには、「売価」です。
5個返品の処理は…、
「売上 50,000 / 売掛金 50,000」
…と、返品の分だけ、「売上」をなかったことにする仕訳を切ります。
繰り返しますが、「売上」をなかったことにするから「売価」計算です。
ポイント2‐自家消費の仕訳
「自家消費」については、必ず指示があるのでそれに従います。
問題文では、「引出金」と指示があるので、それに従います。
仕入れた商品を自分とこで処分したので、「原価」で計算します。
「仕入」をなかったことにする仕訳は…、
「引出金 35,000 / 仕入 35,000」
…と、相なります。
なお、「引出金」は、漢字に注意してください。
「引 当 金」と、かなりの確率で書き間違えるので、注意が必要です。
また、「引出金」ではなく、「資本金」を使うよう指示があるので、丁寧の問題文を読んでください。
まとめ
「売上 50,000 / 売掛金 50,000」と…、
「引出金 35,000 / 仕入 35,000」の仕訳を合体すると答えの仕訳と相なります。
「売価」と「原価」が入り乱れるので、混乱しやすい問題です。
1つ1つはカンタンなので、確実に取れるようになっておきましょう。
『心の軍師』に、『売価と原価だけですな』と、助言してもらってください。

ところで、当該論点には「資本の引き出し」というものもあるので、併せて確認しておきましょう。
なお、仕訳がうまく切れないという人は、「取引の8要素」が頭に刻まれていないからです。
「独学の簿記3級:商業簿記」を参考してください。当該8要素が頭に入ってないなら、無理して問題を解かなくていいです。
また、独学向け教材については「簿記3級の教材レビュー」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記3級, 簿記3級‐仕訳 | 2016年10月14日 11:02 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
概算払いの仮払金‐簿記3級仕訳
仕訳問題で頻出なのが、「概算払いの仮払金」です。
当該論点が狙われるのは、「正確に問題文が読めて、正しい勘定科目が使えるか」を試すことができるからです。
また、「概算払い確定時の仕訳」も、おまけに付いてくるといった次第で、なかなかに“出題パフォーマンス”の高い論点となっています。
処理そのものはカンタンですが、甘く見ていると、血に飢えた出題者に狩られます。
勘定科目は正確に記憶しましょう。ぶつぶつ何度も唱えてください。
問題文1‐基本
よくある問題文としては…、
「従業員の出張の際、旅費の概算額10,000円を前渡しした。」
…となっています。
答えの仕訳を先に挙げておきます。
ポイント1
ポイントは2つ。
問題文の「概算」と「前渡し」です。
しっかり憶えてください。
「概算払い」は、「仮払金」を使います。
問題文の「前渡し」に囚われて…、
「前払金」とか、「前渡金」とか、「前払費用」とか、「立替金」とか…、
こういった勘定科目を使ってはいけません。
血まみれの出題者は、使用勘定科目群に、「前渡し」から連想される勘定科目を、ふんだんに挿し込んでくるはずです。
これに引っかかって、多くの受験生は失点します。
繰り返しますが、「概算払いは、仮払金」です。
勘定科目の憶え方
「仮払金」は、仮に払った金です。金は払ってしまったので減っています。
ですから、「現金」を減らす仕訳になり、現金は貸方に来ます。
んなもんで、対応する「仮払金」は借方に来る、といった塩梅です。
問題文2‐追加論点
「仮払金」が出たら、まず間違いなく、「確定時・判明時」の処理が出るはずです。
よくある問題文としては…、
「従業員の帰社により、旅費の概算額10,000円のうち、実費が8,000円だった報告を受け、残額を現金で受けとった。」
…となっています。
答えの仕訳を先に挙げておきます。
ポイント2
「借方」に計上していた「仮払金」を減らす(なくす)仕訳を切ればよいだけです。
「仮払金」を取り崩して、確定なり判明なりした費用について、適切な勘定科目で計上する、といった次第です。
まとめ
「仮払金」の論点は、理解してしまえばそう難しくありません。
ポイントは、「勘定科目」です。
問題文中に「前渡しした」とあると、ついつい、勘定科目を間違ってしまいます。
概算払いの際は、仮払金を使うとしっかり頭に叩き込んでください。
『心の軍師』に、『概算払いは仮払金と100回唱えろ』と、助言してもらってください。

なお、仕訳がうまく切れないという人は、「取引の8要素」が頭に刻まれていないからです。
「独学の簿記3級:商業簿記」を参考してください。当該8要素が頭に入ってないなら、無理して問題を解かなくていいです。
また、独学向け教材については「簿記3級の教材レビュー」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記3級, 簿記3級‐仕訳 | 2016年10月12日 10:09 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
固定資産の期中購入‐簿記3級仕訳
固定資産の購入は、仕訳問題で頻出です。また、第3問の総合問題でも顔を出すので、丁寧に見ておかねばならない論点です。
狙われる理由は、「付随費用の処理」が絡むのと、「期中購入だと減価償却費」にひと手間かかるからです。
仕訳のそのものはカンタンですが、だからといって甘く見ていると、“ころっ”と処理を“ド”忘れして採点時に身体が震えるので、注意してください。
また、絶妙な「問題文」のときがあるので、読解力も磨いておく必要があります。
問題文
よくある問題は…、
「5月1日に、建物5,000,000円(残存価額10%、定額法、10年)を買った。代金は翌月に払う。登記料の収入印紙30,000円と仲介手数料20,000円は現金で支払った。当期の会計期間は1/1から12/31である。」
…といった塩梅です。
正解の仕訳は以下。
付随費用は取得原価
まず、「取得費用」は、取得原価、つまり、建物に含めて計算します。
問題文は、実に“イヤらしく”、付随費用だけ、現金で支払っているので、注意です。
邪な出題者は、問題の使用勘定科目に、「支払手数料」とか、登記料は収入印紙で払うので「租税公課」といった勘定科目を挿入してくる筈です。
まず、「付随費用は取得原価」を、きっちり憶えておきましょう。
建物価額に、各種手数料を合算して、「5,050,000」で計上します。
単純なだけに、忘れがちです。ついうっかり、付随費用を「支払い手数料」などで処理しかねません。
取得原価は、最後に述べる「減価償却費」にも関ってくるので、ここを間違うと、工場を閉鎖したジャムおじさんになってしまいます。
未払金
次に注意なのが、代金の処理です。
問題文では、「代金は翌月に払う。」となっているところを、読み落としてはいけません。
普通の問題では、「小切手を切った」で「当座預金」で購入することが多いので、ついウッカリ、忘れてしまいます。
営業『外』の未払いは「未払金」で処理します。
目ざとい出題者は、受験生が固定資産の処理ばかりに目が行っているのをいいことに、こうした心の間隙を付く問題を好んでいます。
「代金は翌月に払う。」なので、必ず、「未払金」で処理します。
減価償却費
固定資産を期中購入すると、期末の減価償却の計算では、「月割」をすることになります。
他の取得済みの固定資産とは、別に計算しないといけないので、注意です。
会計期間は1/1から12/31で、5月1日に購入したので、「8ヶ月」分を計上することになります。
なお、減価償却は「月割」です。たとえば、「5月31日」という末日購入でも、「1ヶ月」とします。
忘れてはいけないのが「付随費用を含めた金額」にするところです。
建物は、建物単体の「5,000,000」ではなく、付随費用を含めた「5,050,000」で計算します。
減価償却費は、「5,050,000×90%÷10年」に「8/12」をかけた「303,000」といった次第です。
受験生の1~2割は、付随費用を忘れて「5,000,000」で計算して、減価償却費を「300,000」で解答することでしょう。
また、何人かは、減価償却の月割りを忘れて、「年」で計算して、ばってんをもらうはずです。
ヒャハ、引っかかってるよとつぶやく、意地の悪い出題者の笑顔が浮かびます。
まとめ
こんな次第で、「固定資産の期中購入」は、何気についウッカリ間違える可能性をはらんだ論点となっています。
言うなれば、当該論点は、「普段の練習のときは間違えないけど、緊張する本試験というときでは、つい間違う」傾向の強いものとなっています。
この種の問題を落とすと、「黄色信号」どころか「黄疸信号」でかなりやばいです。
最近の簿記3級は、「解ける問題を確実にとっておかないと、失点が追いつかない」傾向となっています。
「固定資産の期中購入」は、1つ1つをきっちり処理していけば、点が取れます。しっかり練習しておきましょう。
なお、仕訳がうまく切れないという人は、「取引の8要素」が頭に刻まれていないからです。
「独学の簿記3級:商業簿記」を参考にしてください。当該8要素が頭に入ってないなら、無理して問題を解かなくていいです。まずはここからです。
また、独学向け教材については「簿記3級の教材レビュー」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記3級, 簿記3級‐仕訳 | 2016年10月11日 11:56 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |