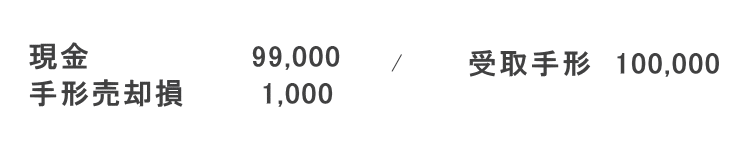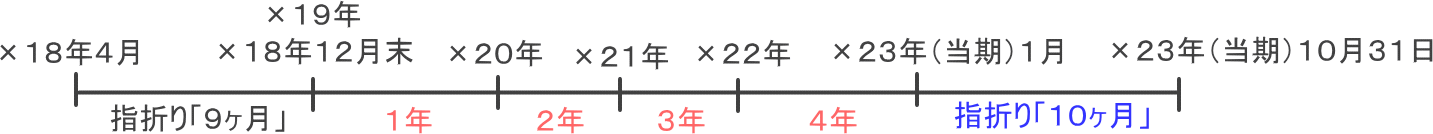手形の割引‐簿記3級仕訳
手形の割引は、仕訳問題で頻出です。
狙われる理由は、「手形の割引は、実務上重要な取引なのだが、受験生はよく知らないから」です。
受験生の大半は、おおむね1個人ですので、手形など見たことがないというのが大半です。
しかし、手形の割引は、実務上、メジャーな決済手段となっています。
出題者にとっては、実務上の要請にも適ううえに、受験生の選別にも使えるので、当該論点が頻出になっている、という塩梅です。
問題文
問題文の典型としては…、
「約束手形100,000円を銀行で割引き、割引料1,000円を差し引いた残りを現金で受け取った」
…です。
先に、答えの仕訳を挙げておきます。
テキストでしっかり確認
先に、「受験生は手形に疎い」といいました。
そら当然で、商売をしている人ならまだしも、学生や社会人など、一般の人にとって手形など、知る由もありません。
このため、テキストの読み込みを怠っていると、「約束手形100,000円を銀行で割引き」部分の“約束手形”で、「???」となります。
支払手形か受取手形か、わからなくなるからです。
加えて、性格の悪い出題者は、受験生の無知に乗じるため、語群(使用勘定科目群)に、不渡手形や割引手形など、手形の文言が付いた勘定科目を挿入して、さらなる嫌がらせを図ります。
こんな次第で、「手形の割引」という商行為をきっちり理解しておかないと、仕訳をきちんと切れません。
仕訳を暗記するのではなく、当該取引の意味と目的とを、今一度、テキストで確認してください。
割引料も罠だらけ
次に、「割引料」です。
当該「割引料」は、「手形売却損」で処理するのですが、陰湿な出題者は「支払手数料」などの混同しやすい勘定科目を、語群の中に挿入してくるはずです。
「割引料」という文言から、「手形売却損」という文言が連想しにくいため、ことさらに、狙われます。
「手形売却損」という独立した勘定科目を使うことを、きちんと頭に入れておきます。
ぼんやりとしか憶えていないと、本試験問題の前で、「支払手数料?手形売却損?どっちだっけなあ」と脂汗を流すことになります。
まとめ
繰り返しますが、仕訳の暗記と記憶の前に、「手形の割引」が、どういう意味と目的があるのかを、テキストで理解してください。
手形の割引は、企業の代表的な資金繰りの一環であり、財務活動の1つです。
ぴんと来ない人は、銀行に行ってみて下さい。看板に「手形割引」の文言があるはずです。
また、時折、「手形売却損」を、日割りで計算させるときもあるので、丁寧に問題文を読んでください。
日数計算については、「にしむくさむらいで日数計算」を一読をば。
なお、仕訳がうまく切れないという人は、「取引の8要素」が頭に刻まれていないからです。
「独学の簿記3級:商業簿記」を参考にしてください。当該8要素が頭に入ってないなら、無理して問題を解かなくていいです。まずはここからです。
また、独学向け教材については「簿記3級の教材レビュー」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記3級, 簿記3級‐仕訳 | 2016年10月4日 4:04 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
固定資産の期中売却‐簿記3級仕訳
固定資産の期中売却は、仕訳問題で頻出です。
狙われる理由は、「減価償却が絡んでくるため、計算が複雑になるから」です。
先によくある仕訳を挙げておくと…、
「×18年の4月に購入した機械(取得原価1,000,000円、残存価額10%、耐用年数10年、定額法)を、×23年の10月31日に100,000円で売却した。代金は後日受け取る。当期は×23年で、会計期間は1/1から12/31である」ってな塩梅です。
はい、まず、この問題文の長さに“辟易”します。
一度に読むと眩暈がするので、大きな意味をまず把握しましょう。
要は、機械を売っただけで、その機械の売り時をごちゃごちゃしているだけなので、ウルセーウルセーテメェガヤレヨバカと毒付きながら、処理していくまでです。
仕訳には3計算でド手間
当該取引の仕訳を切るには、
①過年度の減価償却累計額を計算し…、
②当期(今年)の減価償却費を計算し…、
③算出した額から、売却損益を計算する…、
…こんな次第で、計算の量が複雑で、量も多いため、受験生は往々にしてミスする、従って、陰険な出題者が殊更に狙ってくる、という次第です。
答えの仕訳は以下。
減価償却累計額の計算は必ず線上に
原価償却に絡んだ問題は、必ず、「線の上」で、年月日を記入した上で考えます。
頭で考えると、必ず計算ミスをするからです。
こんな感じに、まず、線の上に、年月日を書き出します。
繰り返しますが、「線上」で考えます。簿記3級なら頭の計算で可能ですが、どのみち2級ともなれば、複雑な問題になるので、「線」を引くことになります。今、線上で処理した方が練習になります。
さて、×18年の減価償却費は、「9か月分」です。(4、5、6・・・と、指折り計算しましょう!)
「100,000×0.9÷10年」に「9/12」をかけた「67,500」が、購入した年度の償却費です。
次に、×19年、×20年、×21年、×22年です。
それぞれ通期ですから4年分を計上することになります。
「100,000×0.9÷10年」の「×4」で「360,000」が、当該4年間の減価償却費です。
ようやく、過年度の「減価償却累計額」が計算できます。
「67,500+360,000」の「427,500」が、「減価償却累計額」です。
…この時点で、多くの受験生が、計算ミスを犯していそうです。
次に、当期の減価償却費を計算します。
当期の減価償却費を忘れない
大事なことを言いますが、固定資産の期中売却は、「当期の減価償却費」を忘れないことです。
ここが最も大事な論点です。
最初に述べたように、「固定資産の期中売却」が頻出なのは、「当期の減価償却費」を忘れがちだからです。
そう、過年度の減価償却費の計算で、一安心したためか、多くの受験生が「当期の減価償却費」を、ころっと忘れてしまうのです。
売却した固定資産は、当期も使ったのですから、その分を費用化して、税金を安くしなくてはいけません。
問題文では「10月31日」に売っています。
会計期間は「1/1から12/31」までなので、1月から指折り計算して、「10ヶ月」分の減価償却費を計上することになります。
なお、減価償却の計算は「月割」です。
で、当期分を計算すると、「100,000×0.9÷10年」に「10/12」の「75,000」が、購入した年度の償却費です。
やっと、役者がそろいました。
売却損益の計算
売れた金額は「100,000」です。
減価償却累計額は「427,500」です。
当期の減価償却費は「75,000」です。
合計「602,500」です。
売った機械の元値は「1,000,000」ですから、差額「397,500」が「売却損」だと、“ようやく”判明しました。
売却代金の処理にも注意
まだまだ、ほっとしてはいけません。
邪悪な出題者は、もうひとつ、罠を仕掛けています。
問題文をよく読んでください。
「…100,000円で売却した。代金は後日受け取る。…」となっています。
この問題文の場合だと、「未収入金」で、売却代金の100,000を処理しなくてはいけません。
よくある「現金で受け取った」や「当座預金に入金した」につられないでください。
ついつい、現金や当座預金で処理しかねません。
『営業以外で、未だ受け取っていない金銭は、未収入金』という、未収入金の論点も同時に出題しているという塩梅で、非常に手が込んでいます。
なお、「未収入金」の反対は「未払金」です。
まとめ
固定資産の期中売却が、どうして、頻出論点になるのか、肌でお分かりでしょう。
まず、過年度の減価償却累計額の計算が煩雑です。
例では、「定額法」でしたが、問題の難易度が上がると、「定率法」で攻めてきます。
繰り返しですが、当該累計額の計算は、必ず「線上」で年月日を展開した上で計算しましょう。頭でやるとド混乱します。
次に、「当期の減価償却費」を忘れがちなので、要注意です。
減価償却累計額を計算したら、脳が「はい、償却終わり~」てな感じになるので、意識的に、「期中売却には当期分あり」などと、「釘を刺しておく」ことが必要です。
次に、「売却の損益計算」です。
おおむね「売却損」ですが、ごくまれに「売却益」のときがあるので、処理に戸惑わないでください。
最後に、売却代金の処理です。
おおむね「当座預金」か「現金」なのですが、「未収入金」で攻めてくることもあるので、最後の最後まで、気を抜いてはいけません。
まず、『固定資産の期中売却は、他の論点とは違って、手ごわい』ことを、頭に刻んでおきましょう。
当該論点が、他の論点とは違って、かなり「やばい」ことに鼻が利くだけで、格段に間違わないようになります。
仕訳問題以外に、第3問でも問われる公算があります。本試験で遭遇したら「…来たな」くらいの心持で解答してください。
なお、仕訳がうまく切れないという人は、「取引の8要素」が頭に刻まれていないからです。
「独学の簿記3級:商業簿記」を参考にしてください。当該8要素が頭に入ってないなら、無理して問題を解かなくていいです。まずはここからです。
また、独学向け教材については「簿記3級の教材レビュー」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記3級, 簿記3級‐仕訳 | 2016年10月3日 2:03 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
「にしむくさむらい‐西向く侍」で日数計算
結論から言うと、「にしむくさむらい‐西向く侍」という語呂を覚えておくと、日数の計算が正確になる、といった次第です。
日割計算は、多くの試験で出題されます。
たとえば、簿記試験の端数利息などです。
よくある形式としては、「4月1日から6月12日までは、何日あるか?」といった手合いです。(答えは最後。)
当該日数計算がメンドクサイのは、「月」によっては、「30日」と「31日」の月があるためです。
で、この解決法が、先に挙げた「にしむくさむらい」という語呂です。
にしむくさむらいは「31日」じゃない
要点から言います。
「にしむくさむらい」は、31日ではない月を指します。
反対に言うと、「に」を除いた「にしむくさむらい」は「30日」の月、といった塩梅です。
「に」は、「2月」で、2月は「28日か29日」しかありません。
「し」は、「4月」で、4月は「30日」までしかありません。4月(しがつ)の「し」です。
「む」は、「6月」で、6月も「30日」までしかありません。「む」が「6」なのは「むっつ」という読みからです。
「く」は、「9月」で、9月も同様に「30日」までしかありません。9月(くがつ)の「く」です。
「さむらい」は、少し手が込んでいるので後述。
さむらいは11月
頓知の優れた小学生なら、「さむらい」が「11月」に当たるのがすぐわかるのですが、成人となると、なかなかピンと来ないので解説します。
「さむらい」は「侍」です。
「侍」は「武士」です。
「武士」は「士」です。
「士」という漢字は、「十」と「一」に分けれます。
「十」と「一」で、「十に一」で「11月」ってな塩梅です。
11月も、先の4月・6月・9月と同じように、「30日」までしかありません。
まとめ
こんな風に、「にしむくさむらい」と語呂を憶えておけば、「30日」の月が区別できるので、正確な日数を計算できる、ってな塩梅です。
先に挙げた、「4月1日から、6月12日」なら…、
「にしむくさむらい」で、4月は「30日」。
5月は「にしむくさむらい」に含まれないので、「31日」。
んで、6月12日なので「12日」。
「30+31+12」で、当該期間は「73日」といった塩梅です。
「にしむくさむらい」は、結構、使える語呂なので、憶えておいて全く損はありません。
「31日じゃない月」という反語表現なので、最初はややこしいですが、すぐ慣れます。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 建設業経理士, 簿記2級, 簿記3級 | 2016年10月2日 12:45 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |