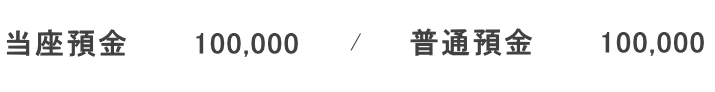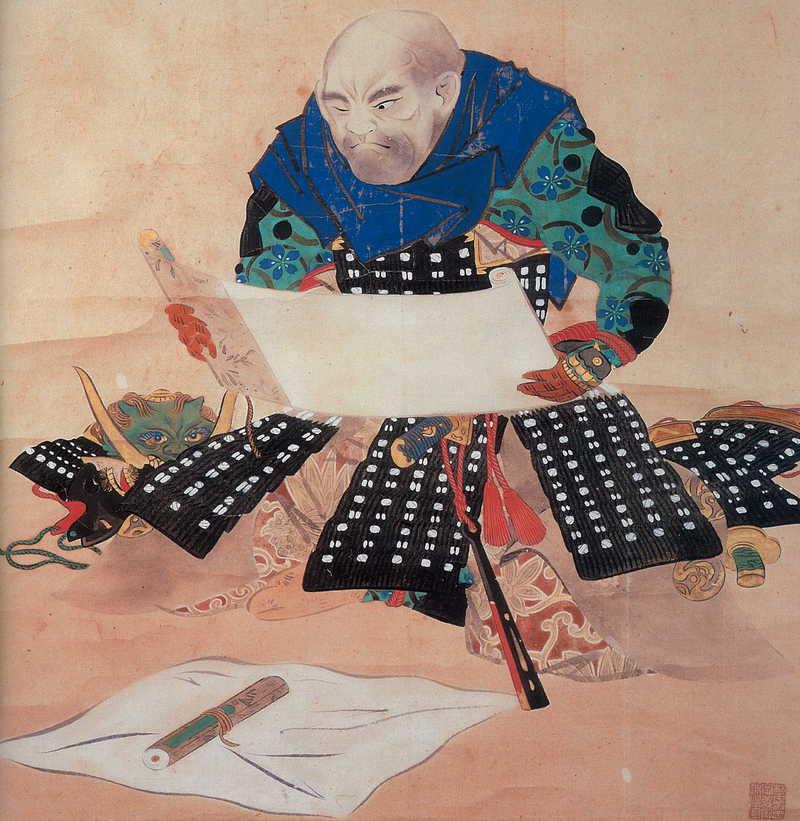当座預金の開設‐簿記3級仕訳
仕訳問題で狙われそうなのが、「当座預金の開設」です。
ぶっちゃけ言うと、頻出ではありません。
しかし、簿記3級の性質上、“実務的な可能性”があるので、出題されることはあります。
簿記3級は、個人事業者や中小事業主の経理・会計を対象としています。
試験勉強では、超メジャーな「当座預金」ですが、事業者の全てが、最初から「当座預金」を持っているわけではありません。
「当座預金」の開設には、結構、信用が要るからです。
実務の想定事態として、「商売が軌道に乗った→当座預金の開設」ということも、考えられます。
こんな次第で、実務事項として出る可能性があるので、しっかり押えておくべき論点です。
問題文
「当座預金の開設」で、よくある問題文としては…、
「普通預金の口座は開設していたが、このたび、当座預金の口座を開設した。この際に、普通預金から100,000円を預け入れた。同時に、当座借越契約500,000円を結んだ。」
…となっています。
答えの仕訳を先に挙げておきます。
普通預金
普通預金とは、皆さん個人がお持ちの口座です。
給料の入金や公共料金の支払、養育費の支払の際に振り込む口座です。
対して、「当座預金」とは、決済専門の口座です。
当座預金は、普通預金とは違って、銀行がつぶれても、社会経済上の理由から、全額が保護されます。
ちなみに、普通預金は、現行法では、最大1,000万円までしか保護されません。
この点が、普通預金と当座預金との違いで、ま、「商売専用の口座が当座預金」と憶えておけばいいでしょう。
答え
仕訳そのものは、なんてことはありません。
普通預金から、当座預金へ、振り替えるだけです。
当該論点は、テキストの読み込みが浅い受験生だと、問題文が何を書いているのか理解できないため、失点しがちです。
しっかりと、テキストの記述に目を通しておきましょう。
さて、本仕訳には、もう1つ、注意点があります。
問題文後半の「同時に、当座借越契約500,000円を結んだ。」のところです。
ここは、契約を結んだだけで、なんら簿記上の取引は発生していません。
仕訳は「なし」です。
「当座借越契約」という文言で混乱して、たとえば、「当座預金○○ / 借入金○○」といった、へんちくりんな仕訳を切らないようにしてください。
今一度、「当座借越」が、どういう意味と目的とがあるのかを、テキストで確認しておきましょう。
まとめ
「当座預金の開設」は、仕訳が簡単ですが、金融についての知識が不足していると、何がナンやら、堅焼せんべいがナンやら、わからなくなってしまいます。
昨今の簿記試験は、「実務重視」路線ですので、こういった実務に関係した問題が狙われます。
猫舌なのに鍋奉行の出題者は、メジャーでないが故に狙ってくることが、大いに考えられます。
こういう「処理」もあるので、しっかりテキストの記述を読み込んでおいてください。
『心の軍師』に、『油断大敵で臨みましょう。』と、助言してもらってください。

なお、仕訳がうまく切れないという人は、「取引の8要素」が頭に刻まれていないからです。
「独学の簿記3級:商業簿記」を参考してください。当該8要素が頭に入ってないなら、無理して問題を解かなくていいです。
また、独学向け教材については「簿記3級の教材レビュー」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記3級, 簿記3級‐仕訳 | 2016年11月11日 5:27 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
すぐ憶えられる乙種の液体・固体‐危険物取扱者 乙種4類(乙4)の法令
乙種には、1類から6類まであって、それぞれ、液体状のものと固体状のものがあり、類によっては、両方のものがあります。
当該「固有か液体か、両方か」が、本試験では頻繁に問われるのですが、試験勉強の序盤だと、それぞれが不明なために、なかなか憶えられません。
文系の人には、特にそれが顕著です。
しかし、当該論点は、法令のみならず、性消でも問われることがあるので、しっかり憶える必要があります。
また、当該論点は、乙4のみならず、甲種や他の類(乙種1類~6類)でも出るので、先々の試験を受ける予定なら、殊更に頭に叩き込まないといけません。
で、以下に、かなり“お世話になる覚え方”を述べていきます。
憶え方
次に述べるのは、わたしのオリジナルではありません。
出展は「チャレンジライセンス」です。兎にも角にも、『有用』なので、以下の憶え方を推薦します。
個人的には、「いいくに(1192)作ろう鎌倉幕府」なみの、優れた語呂だと評価します。
さて、この語呂は、2つの過程で憶えていきます。
憶え方1‐9文字の語呂
まず、以下の「9文字」の語呂を覚えます。
「こ・こ・こ・えき・えき・えき」
ひらがなのそれぞれは…、
「固・固・固・液・液・液」
…を指しています。
聡い方はもうおわかりでしょう。
そう、「1類・2類・3類・4類・5類・6類」が…、
それぞれ、「固体・固体・固体・液体・液体・液体」と対応している、ってな塩梅です。
憶え方2‐乙4の前後に1工夫
4番目の「液体」は、乙種の4類です。
「固・固・固・液(乙4)・液・液」
乙4は、ご存知のように、超メジャーな、ガソリンや灯油、軽油を対象とした類です。
ですから、乙4は「液体」だと、即解できるかと思います。
んなもんで…、
で、当該一番頭に入りやすい「乙4」を基準に考え、乙4の前後は、「固体と液体」と、憶えます。
先に見た…、
「固・固・固・液(乙4)・液・液」
…乙4の前後は、“固体と液体”と、こじつけるといった塩梅で…、
「固・固・固・液・液(乙4)・固・液・液」
…と、このような脳内処理を行なう、ってな塩梅です。
文字からすると、凄くかったるいのですが、慣れると、すっと憶えられるので、この憶え方をお勧めです。
まとめると…、
「こ・こ・こ・えき・えき・えき」を、まず憶えて…、
乙4の「えき」の前後の類は、固体又は液体とこじつける、ってな塩梅です。
また、乙4の前後は、「それぞれ反対のものがある」と憶えても、つまり、「固体なら液体がある」とか「液体なら固体がある」という手合いでもOKです。
それか、「乙4の前後は、両方」でも、しっくりくるかと思います。
おさらい
おさらいです。
乙種の第1類の危険物は、「酸化性固体」です。
乙種の第2類の危険物は、「可燃性固体」です。
乙種の第3類の危険物は、「禁水性・自然発火性物質(固体または液体)」です。
乙種の第4類の危険物は、「引火性液体」です。
乙種の第5類の危険物は、「自己反応性物質(固体または液体)」です。
乙種の第6類の危険物は、「酸化性液体」です。
多くのテキストでは、第3類と第5類の表記が「物質」となっていますが、当該物質は「固体または液体」を指します。
おおむね「物質(固体または液体)」と表記されているはずですが、念のために。
まとめ
乙種の分類は、本当によく出ますので、きっちり・かっつり憶えこんでおきましょう。
お使いのテキストでは、たぶん、語呂が載っているかと思いますが、それでいけそうなそれで憶えて、しっくり来ないなら本ページにある憶え方で、頭に“刻んで”おいてください。
出展参考:「チャレンジライセンス」
先に紹介した憶え方は、「こ」が3つで、「えき」も同様に3つと、大変、テンポがよく、通勤や通学時のわずかな時間ですぐ覚えられるはずです。
ところで、「乙種の類ごとの性質」については、「語呂と理屈で憶える乙種の○○性」を参考にしてみてください。
『心の軍師』に、『こここえきえきえき。乙4前後は両方。』と、助言してもらってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令 | 2016年11月10日 1:32 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
語呂と理屈で憶える乙種の○○性‐危険物取扱者 乙種4類(乙4)の法令
危険物取扱者の法令の中で、ド頻出な論点が「1類から6類までの、それぞれの○○性」です。
当該論点は、乙4の「法令」のみならず、甲種試験でも、また、なぜか、1~6類の「性消」でも姿を現すことがあり、「ド頻出」にウソ偽りがありません。
試験の出題者的には、「点を取らせる問題」として、当該論点を採用しているきらいがあります。
確実に憶えて、1点を確保して、難問奇問に備えてください。これを間違えると、苦戦は必定です。
当該論点の対策は2つあって、「語呂」か「理屈」で憶えられます。
おさらい
まずは、各危険物のおさらいからです。
乙種の第1類の危険物は、「酸化性固体」です。
乙種の第2類の危険物は、「可燃性固体」です。
乙種の第3類の危険物は、「禁水性・自然発火性物質」です。
乙種の第4類の危険物は、「引火性液体」です。
乙種の第5類の危険物は、「自己反応性物質」です。
乙種の第6類の危険物は、「酸化性液体」です。
多くのテキストでは、第3類と第5類の表記が「物質」となっていますが、当該物質は「固体または液体」を指します。念のために。
対策1-語呂暗記
語呂は「サガット、失禁、しかも時差」です。
ポイントは、自明の「乙種4類は引火性液体」を、除いているところです。
当該「引火性」は、「物化」で定番の論点なので、無理に憶えようとしなくても、「物化」の試験勉強で自然に頭に入ります。
知っていることを、わざわざ語呂に入れる必要はない、といった次第です。
んなもんで、先の「サガット失禁、しかも時差」には、乙4の引火性液体は、入ってない語呂となっています。
なお、「サガット」は、別段、「佐賀」とか「サガ」でも構いません。
ちなみに「サガット」とは、昔の格闘ゲーム、ストリートファイターのキャラクターです。ライバルのリュウに昇竜拳を食らって、時間差で失禁している姿を想像してください。
語呂の説明
語呂のそれぞれは…、
さ・・・1類の「酸化性」の「さんかせい」の「さ」。
が・・・2類の「可燃性」の「かねんせい」の「か」に濁点で「が」。
(っと)・・・この部分に、語呂はありません。
し・・・3類の「自然発火性」の読みは「しぜんはっかせい」の「し」。
(っ)・・・この部分に、語呂はありません。
きん・・・3類の「禁水性」の「きんすいせい」の「きん」。
(しかも)・・・この部分に、語呂はありません。
じ・・・5類の「自己反応性」の「じこはんのうせい」の「じ」。
さ・・・6類の「酸化性」の「さんかせい」の「さ」。
…語呂の説明は以上です。
そこそこ「サガット失禁、しかも時差」は、いい語呂だと思います。
対策2-理屈で憶える
語呂で憶えにくいなら、1つ1つをクソ理屈で憶えていきます。
当該理屈では、3つの過程で憶えられます。
理屈1‐乙4の引火性
まず、一番憶えやすい「乙4」は「引火性」です。
当該「引火性」は、「物化」で定番の論点なので、無理に憶えようとしなくても、「物化」の試験勉強で頭に入ります。
(補足しますが、乙4の危険物は、表面燃焼ではなく、引火性の蒸気が燃える蒸発燃焼です。これは、物化で超絶定番なので必ず憶えましょう。)
理屈2‐1類と6類の酸化性
さて、次に、1類と6類の「酸化性」です。
ちょうど、乙種の最初と最後が「酸化性」なので…、
「最初と最後に参加(さんか→酸化)」くらいの語呂で、会議の最初と最後だけ参加するイヤらしい上司を頭に浮かべながら、憶えます。
鏡を覗けば、イヤらしい人の顔のサンプル顔が、目に入るかと思います。
これで、「3つ」済みました。
理屈3‐5類の自己反応性
残るは「3つ」ですが、5類から行きます。
5類は、「自己反応性物質」です。
ひらがなにします。
「ごるい」は、「じこはんのうせいぶっしつ」です。
「ごるい」の「ご」と、「じこはんのう」の「じ“こ”」をこじつけて…、
5類の「ご」は、自己反応性物質の「こ」と、“カ行のこ”つながり、ってな感じで頭に入れます。
理屈4‐3類の禁水性・自然発火性
3類の禁水性・自然発火性は、語呂で一発です。
「しぜんさんすい」です。
漢字で言うと、「自然山水」か「自然散水」です。
ひらがなにします。
「しぜんさんすい」
説明すると…、
「しぜん」は、言うまでもなく、自然発火性の「しぜんはっかせい」の「しぜん」。
「さん」は、3類の「さん」。
「すい」は、禁水性の「きんすいせい」の「すい」。
…という手合いです。
旅行好きな方は「自然山水」で、無趣味のつまらない人は「自然散水」で憶えましょう。
理屈5‐2類の可燃性は無理だった
第2類の「可燃性」は、いい憶え方が浮かばなかったので、そのまんま、ブツブツと「2類は可燃」と唱えてください。
強引に「2類は可燃。2類は可燃。2類は可燃。」と、ブツブツ会議中に唱えるのがよいでしょう。
すぐに暇を出されるはずです。
なお、第2類危険物には、「“引火性”固体」というものがあります。
当該品目の「引火性」を、定義の「可燃性」と、混同しないようにしましょう。
まとめ
以上、危険物の性についての、語呂と理屈の2対策でした。
乙種の1~6類の「性」は、本当によく出ますので、きっちり・かっつり憶えこんで、「1点」を確保です。
なお、「類ごとの液体・固体の別」については、「すぐ憶えられる乙種の液体・固体」を参考にしてみてください。
『心の軍師』に、『語呂か理屈で、間違いのない1点ですな』と、助言してもらってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物取扱者 | 2016年11月10日 1:31 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |