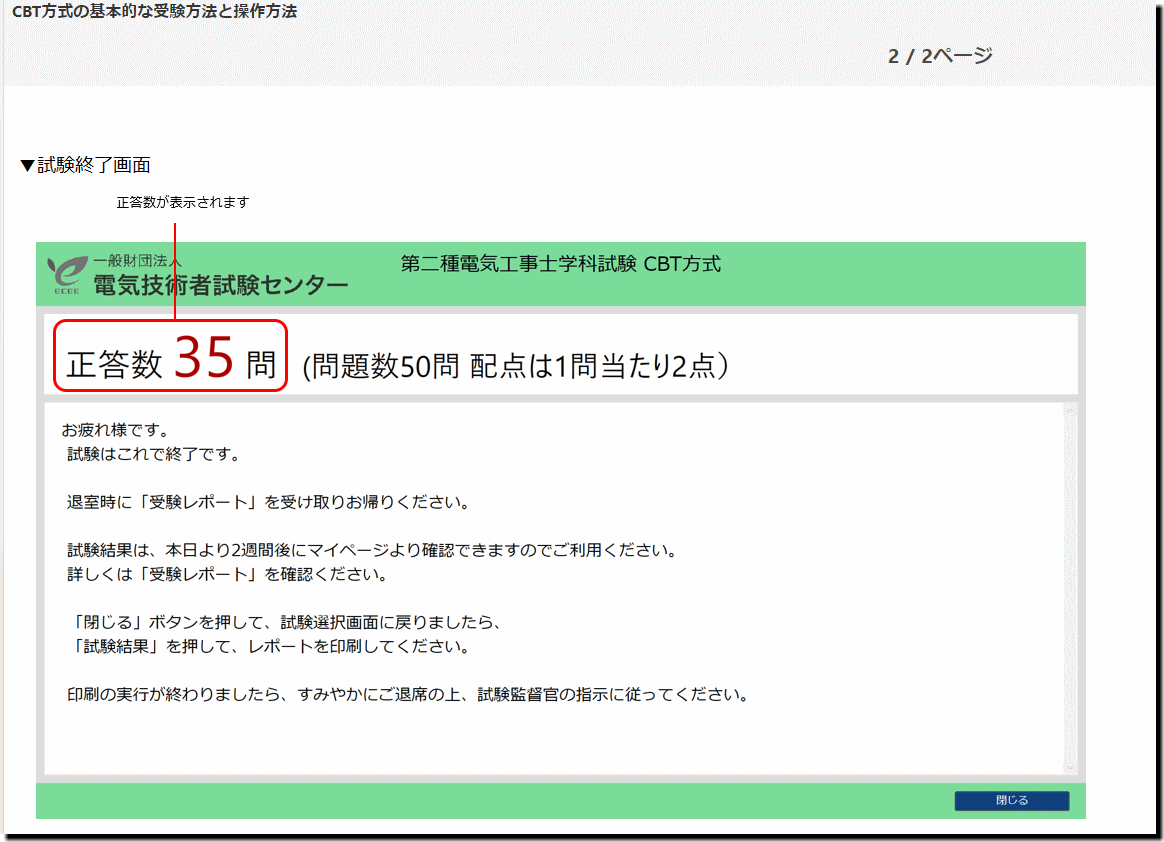C型肝炎訴訟のポイントまとめ‐登録販売者
当該ページでは、「C型肝炎訴訟」について見ていきます。
令和4年度の改正事項です。遺漏なく押えておきましょう。
C型肝炎訴訟
「C型肝炎訴訟」ですが、手引きには…、
『出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したことに対する損害賠償訴訟である。』
…となっています。
太文字下線部分が、当該訴訟のキーワードです。ほぼ出ると言っていいです。
「C型肝炎訴訟・・・フィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤」と、正確に押えておきましょう。
語感がよく似た“アルブミン製剤”とかに変えられますよ!
最後に、「血液凝固第IX因子製剤」ですが、ローマ数字の「IX(9)」は、無理して押えなくていいでしょう。
ざっくり、「血液凝固因子製剤」くらいに把握していれば、試験的には十分かと思います。
まさか、「血液凝固第“IV”因子製剤の投与を受けたウンヌン」といった、ギリシア数字を変えてくる問題は、さすがに出ないと思います。
配偶者のように性根の腐った出題者とはいえ、こんなクソ問題は作らないと、信じたいです。
補足-人体
「フィブリノゲン製剤」の「フィブリノゲン」ですが、「人体」の「肝臓」のところでは「血液凝固因子」と、表記されています。
んで、「血小板」のところでは…、
「血漿タンパク質の一種であるフィブリノゲンが傷口で重合して線維状のフィブリンとなる。」
「フィブリン線維に赤血球や血小板などが絡まり合い、血の凝固物(血餅)となって傷口をふさぎ、止血がなされる。」
…となっています。
これを契機に、カタカナ語句の方も、復習しておきましょう。
参考:人体 カタカナ語句 フィブリノゲン・アルブミン(肝臓)
参考:人体 カタカナ語句 フィブリノゲン・フィブリン(血小板)
下線の大量出血とC型肝炎ウイルス
次に、試験に出そうなのが下線部分の「大量出血」と「C型肝炎ウイルス」です。
何のための投与かが定番出題なので、「大量出血」は、チェックしておきましょう。
最後に、「C型肝炎ウイルス」ですが、これは、当該訴訟の基本的な語句なので、“そのまんま”が選択肢に出る公算が高いです。基本中の基本の語句なので、押えておくべきです。
C型肝炎訴訟の特徴
C型肝炎訴訟の被告は、「国・製薬企業」です。
サリドマイド訴訟・スモン訴訟・HIV訴訟と同じ、「国・製薬企業」が被告です。
被告が、「関西広域連合 R6 第20問」にガチ出題されています。少し慌てます。チェックです。
ちなみに、CJD訴訟だけは、「国、輸入販売業者及び製造業者」となっているので、整理して憶えておきましょう。
次に、重要ポイントですが、C型肝炎訴訟は、まだ和解されていません。
手引きには…、
『国では、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、現在、和解を進めている。』
…とあり、「進めている」段階であり、最終的な和解が、なされていないことが読み取れます。
他の薬害訴訟は、和解が完了しているので、「C型肝炎訴訟・・・和解まだ」と、整理して憶えねばなりません。
対策・制度創出
「C型肝炎訴訟」を契機とする制度創設ですが…、
『医師、薬剤師、法律家、薬害被害者などの委員により構成される医薬品等行政評価・監視委員会が設置された。』
…と、手引きにあります。
キーワードは、言うまでもなく、「医薬品等行政評価・監視委員会」です。
制度創設は、ガチで出るので、「C型肝炎訴訟・・・医薬品等行政評価・監視委員会」と、ガチで押えておきましょう。
憶え方ですが、C型“肝”炎訴訟の“肝”の「かん」と、医薬品等行政評価・“監”視委員会の監視の“監”の「かん」とを繋げて、「かん繋がり」くらいに憶えるといいでしょう。
議員立法が出た!
試験の難化を象徴する問題が、「関西広域連合 R6 第20問」に登場です。
「議員立法」が問われました。穴埋め問題なので、文章の前後関係から解けなくもないですが、厳しい出題です。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、チェックしておきましょう。
まとめ的なもの
こういうとアレですが、「C型肝炎訴訟」は、憶えるものが少ないので、テキストの細かい記述が出る可能性が高いです。
とはいえ、試験的には、テキストの記述が“そのまんま”選択肢に出るくらいが関の山かと思われます。
たとえば…、
「国及び製薬企業を被告として、5つの地裁で提訴されたが、言い渡された判決は、国及び製薬企業が責任を負うべき期間等について判断が分かれていた。」とか…、
「C型肝炎ウイルス感染者の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、特別措置法(平成20年法律第2号)が制定、施行された。」
…といった感じの出題になるかと思います。
先述したキーワード以外の記述も、念のため、精読しておきましょう。
言うまでもないですが、キーワード部分は、ガチで出るので、ガチで押えておきましょう。
なお、他の薬害訴訟との横断的な勉強には、「登録販売者 薬害訴訟(CJD訴訟,HIV訴訟,スモン訴訟,サリドマイド訴訟,C型肝炎訴訟)の横断学習のページ‐論点整理とまとめ
」の方も、活用してください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 基本的知識, 登録販売者 薬害訴訟 | 2023年1月11日 9:38 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第2種電気工事士 学科試験のCBT方式(パソコン試験)とは?‐メリット・デメリット・最大活用法
第2種電気工事士の学科試験に「CBT(Computer Based Testing)方式」が令和5年度(2023年度)に新しく導入されました。
当該CBT方式ですが、一口で言えば、「パソコン試験」です。
マークシートに代わって、主催者の指定する試験会場にて、パソコンで解答するといった体です。(自宅でのオンライン受験ではないので、注意してください。)
さて、当該CBT方式ですが、結論から言うと、以下に…、
・筆記方式の試験日に、どうしても受験できない人。
・実力者(直近過去問でコンスタントに8~9割取れる人、過去に2~3回受験経験があって“もはや”手慣れた人など。)
…該当する方は、CBT方式を受ける価値が大いにあると思います。
ところで、「わたし」の意見ですが、事情が許すなら、CBT方式を受けることを“推奨”します。
理由は、後述するように、「技能試験の勉強に、“最大1か月”早く着手できるので、技能試験のリスクを下げることができるから」です。
以前は、わざわざCBTなんて受けなくていいじゃんと思ってましたが、上記メリットに気づいてからは、「推奨」するようになってます。
なお、とっとと本ページの要約を知りたい人は、当該ページ最後の「CBT方式最大活用法」をお読みください。
第2種電気工事士 CBT方式のメリット1‐利便性
CBT方式(パソコン試験)のメリットは、公式の資料が言うように、試験に関する場所・時間の利便性が増すところです。
これまでの筆記試験は、「○月×日 △時~。〇〇ビル××階△△室」といったように、試験日・試験時間・試験場所が『一律固定』されていましたが、CBT方式だと、ある一定の期間内なら、日時・場所を『選択可能』になります。
公式の資料に拠ると…、
「・予約枠に空きがあれば、全国どのCBT会場でも予約をすることができます。」
「・CBT 方式は、試験日の3日前まで試験会場及び試験日時の変更が可能です。」
…となっています。
身体の空いた日・時間、都合の良い場所で受験できるので、格段にスケジュール管理が楽になります。
出張等の多い人でも、安心して試験に臨めます。
第2種電気工事士 CBT方式のメリット2‐技能に早く着手できる
第2種電気工事士のCBT方式の第2のメリットですが、「技能に早く着手できる」ところです。
当該CBT方式の開催期間ですが、令和7年度(2025年度)試験だと…、
「上期試験:4月21日(月)~5月8 日(木)(18日間)」
「下期試験:9月19日(金)~10月6日(月)(18日間)」
…となっています。
これに対して、通常の学科試験(つまり、筆記方式)は…、
「上期試験:5 月 25 日(日)」
「下期試験:10 月 26 日(日)」
…となっています。
よって、CBT方式だと、筆記方式に比べて、「2~4週間強(17日~33日)」ほど、早く試験を受けることになります。
CBT方式の場合、試験後に正解数がわかるので、そこで、即、受かったかどうかが判明します。(正解数は、マイページでも確認できます。)
よって、受かっていれば、その日から、本腰を入れて技能試験の勉強ができる、ってな塩梅です。
「第2種電気工事士の独学」でも述べているのですが、技能試験は、1つもミスのできない試験のため、精神的にきついです。
正直、学科試験と技能試験、どっちが厳しいかと言うと、後者の技能試験です。欠陥1つ(ミス1つ)で即落ちするの試験だからです。
学科は、こういうとアレですが、4割も間違ってもいいので、てきとーでも受かる可能性があるのですが、技能は、てきとーだと絶対に受かりません。よって、技能試験の方に、時間を大きく割くべき、といった塩梅です。
また、技能は、“実技”の試験なので、練習時間が多くある方が絶対的に有利です。
技能の勉強時間が最大で1ヶ月伸びるのは、圧倒的なメリットかと思います。
受験経験者として、余裕をもって技能を勉強できるのは、“精神的”にとても大きいと思います。
CBT方式のデメリット
CBT方式のデメリットは、先に挙げたことの「反対」です。
CBT方式のデメリットは、学科の試験日が繰り上げられる(時間的に、早くなってしまう)点です。
CBT方式だと、通常よりも、「約2~4週間強(約17日~33日)」ほど、試験日が早くなるので、その分だけ、学科試験の勉強期間が短くなってしまいます。
学科の勉強が進んでない人、遅れがちの人にとっては、試験勉強期間の短縮は、大きなリスクです。
第2種電気工事士のCBT方式まとめ‐CBT方式をどうしたらいいのか?
最初に述べたように、通常の日程では本試験が受けられない人や、学科マスターの実力者は、積極的にCBT方式を選びましょう。
学科試験ですが、こういうとアレですが、ある程度まで行くと、実力は、頭打ちとなります。
先述したように、直近のPDF過去問で40問前後を正解しているなら、穏当に受かります。よって、CBT方式でさっさと学科試験を済ませて、余った時間で技能試験の勉強を開始するというのが、現時点で、最も効率がいいです。
(直近のPDF過去問は、こちら→第2種電気工事士 公式過去問+解説 インデックス)
対して、別に技能試験を急ぎたくない人、学科の勉強が遅れがちな人・苦手な人、そのほか、嫌なことは先送りしたい人は、これまで通りの筆記方式を選べばいいでしょう。
無理からCBT方式を選ぶ必要はないです。
わたし的には、先述したように、実力や時間が許すなら、CBT方式で受けて、さっさと技能に臨むべき、と考えています。
しかし、先述したように、学科の勉強が遅れがちな人が、わざわざ学科の勉強期間が短くなるCBT方式を選ぶ理由はありません。
皆さんの状況に応じて、CBT方式で受けるかどうか、考えてみてください。
補足‐期間内なら筆記にできる
CBT方式は、何気に自由度が高く、たとえ、CBT方式を選んで試験会場等を予約しても、申請期限内ならば、その予約を解除して、元の「筆記方式」に戻ることも可能です。
「令和6年度第二種電気工事士上期 学科試験(CBT方式)‐https://cbt-s.com/examinee/examination/r6_ecee_denko2-1_cbt」によると…、
「筆記方式への変更方法・・・改めて筆記方式へ変更する場合は、受験者マイページ「筆記方式へ変更」ボタンより申請してください。」
「※筆記方式へ変更すると、予約したCBT方式の席は予約解除されます。試験申込の取消ではありませんのでご注意ください。」
「※CBT方式への変更期間中の申請が必要となります」
…とあります。
こんな次第で、一度、CBT方式を選ぶと、絶対にCBT方式でないとダメってなわけではないです。(繰り返しますが、CBT→筆記への変更できる期間(申請期限)は、“7日間”と短いので、注意してください。)
このあたり、結構柔軟なので、頭を柔らかくして、考えてみてください。
CBT方式最大活用法
ざっくり、現時点での結論を言うと…、
「CBT方式だと、筆記方式より、最大1カ月早く技能の勉強を始めることができるので、技能試験の練習時間を多く取れる。練習的に余裕が生まれ、精神的にけっこうラクになる。」
「CBT方式には、はやめ試験を受けないといけないデメリットもあるが、学科の試験勉強を、上期なら2~3月から(下期なら6~7月から)始めれば、勉強時間を十分に確保できるので、デメリットを帳消しにできる。」
「初めて第2種電気工事士を受ける人は、可能ならば、2~3月から(下期なら6~7月から)、学科の勉強を始めて、CBT方式を選べばよい。」
「受験経験者など、ある程度の実力者(直近のPDF過去問で7~8割は取れている人)なら、CBT方式のデメリットは、ほとんどないので、CBT方式を選ぶ。」
「学科の着手に出遅れた人、学科の進捗が遅い人等々は、無理して、CBT方式にしなくてよい。」
…ってな次第です。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記 | 2022年12月13日 10:46 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
登録販売者 人体 腎臓の糸球体,ボウマン嚢,腎小体,ネフロンの語呂合わせと憶え方
登録販売者試験の「人体」の論点のうち、「腎臓」は、例年1問が出題されています。
優先して押さえるべき費用対効果の高い論点となっています。
本試験では、「腎臓」の語句の理解を問う問題が多く、「糸球体」、「ボウマン嚢」、「腎小体」、「ネフロン」が最頻出語句です。
以下に、当該4つの語句の語呂合わせと憶え方を述べるので、活用してみてください。
手引き抜粋
まずもって、手引きの記述ですが…、
「腎臓に入る動脈は細かく枝分かれして、毛細血管が小さな球状になった糸球体を形成する。」
「糸球体の外側を袋状のボウマン嚢が包み込んでおり、これを腎小体という。」
「ボウマン嚢から1本の尿細管が伸びて、腎小体と尿細管とで腎臓の基本的な機能単位(ネフロン)を構成している。」
…となっています。
試験的には、以下のように…、
・腎小体・・・糸球体とボウマン嚢
・ネフロン・・・腎小体と尿細管
…を、憶えるってな次第です。
なお、これらの語句がどんなものか、いまいちピンと来ない方は、「ネフロン」等で検索を掛けてみてください。
製薬会社の絵入りページがあるので、一見すれば、即解すると思います。糸球体・・・なるほどーってな塩梅です。
参考:グーグル検索:ネフロン
語呂合わせ
「糸球体」、「ボウマン嚢」、「腎小体」、「ネフロン」ですが、語呂合わせがあります。
その語呂は、「始球式で暴投したしょうた君。」と「しょうた君、ニュー細君からボディブローをくらう」の2つです。
始球式で暴投したしょうた君
「始球式で暴投したしょうた君」の語呂の詳細ですが…、
「始球式」は、「“糸球”体」の「しきゅう」です。
「暴投」は「“ぼう”とう」で、「“ボウ”マン嚢」の「ボウ」に該当します。
「しょうた君」の「しょうた」は、「腎小体」の「じん“しょうた”い」です。
当該語呂で、「糸球体とボウマン嚢で、腎小体」が憶えられるかと思います。
しょうた君、ニュー細君からボディブローをくらう
次に、2番目の語呂の「しょうた君、ニュー細君からボディブローをくらう」ですが…、
「しょうた君」の「しょうた」は、「腎小体」の「じん“しょうた”い」です。
「ニュー細君」は、「尿細管」の「“にょ”う“さいかん”」を適当にもじったものです。
「ボディブロー」は「ブロ」のところが語呂で、「ネ“フロ”ン」の「フロ」に濁点を付けたものです。
当該語呂で、「腎小体と尿細管で、ネフロン」が憶えられるかと思います。
憶え方
「始球式で暴投したしょうた君。」と「しょうた君、ニュー細君からボディブローをくらう」で、先のヤヤコシイ組み合わせを暗記できるかと思います。
個人的には、悪くない語呂だと思います。
しかし、少々長いのが欠点です。
憶えるに越したことはないのですが、語呂自体は頭に残りやすいので、本試験の直前にブツブツ唱えて、「人体」の試験が始まったら、問題冊子の余白に語呂をメモすればいいでしょう。
それか、試験会場の移動時間に、ブツブツ唱えてみてください。
過去問
先の4つの語呂が問われている、典型的な過去問を挙げておきます。
・福岡県 R1 第25問…人体では珍しい穴埋め問題。
・福岡県 H28 第25問…先の語呂で解ける。
・東京都 R3 第25問…本問も先の語呂でOK。
・茨城県 R3 第48問…先の語呂でOK。
おおむね語句の知識を問う物なので、先の語呂で、テキストの内容を押さえていってください。
さて、ネフロン等のカタカナ語句が苦手な人は、「ボウマン嚢・ネフロン(腎臓)‐登録販売者 人体 カタカナ語句対策」も、参考にしてください。
んで、試験勉強の詳細ついては「登録販売者の独学」を、独学向け教材については「登録販売者の教材レビュー」を参考をば。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 人体, 登録販売者 憶え方, 登録販売者 語呂合わせ | 2022年9月5日 9:17 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |