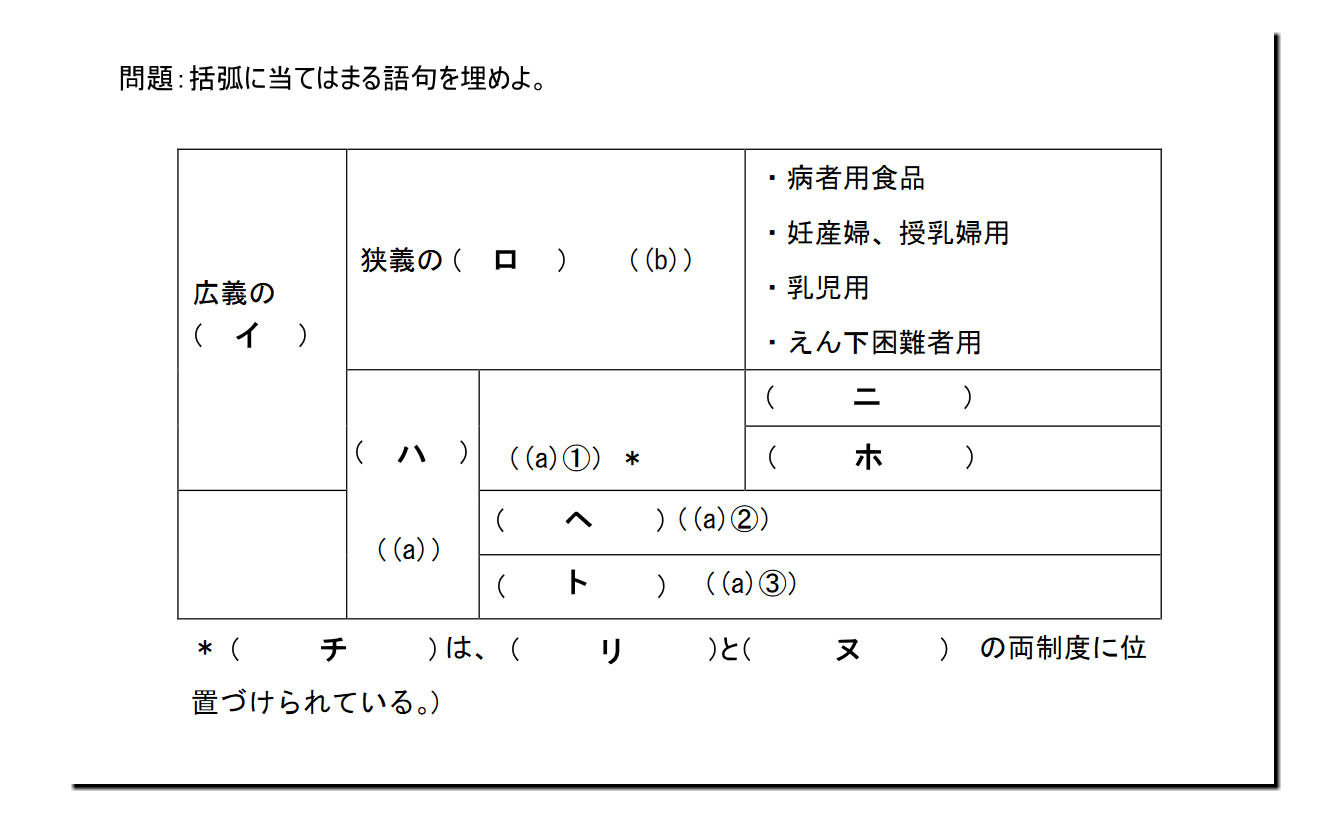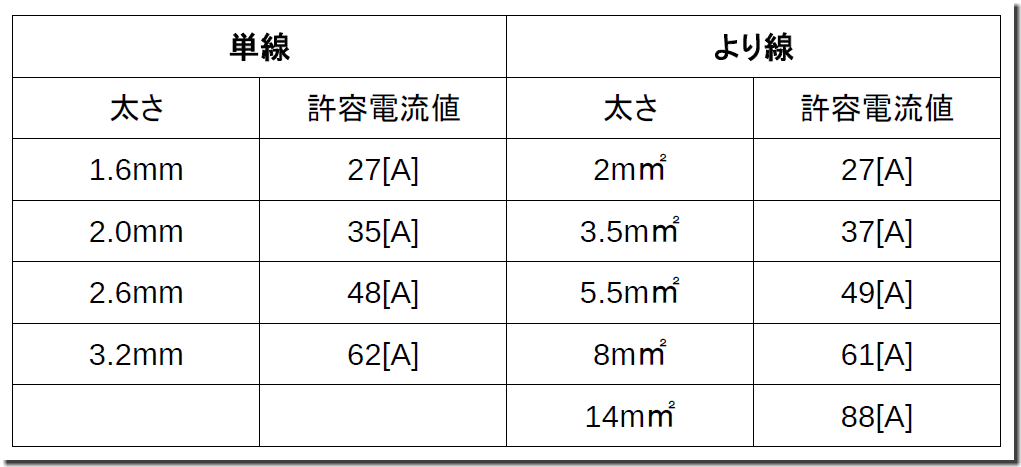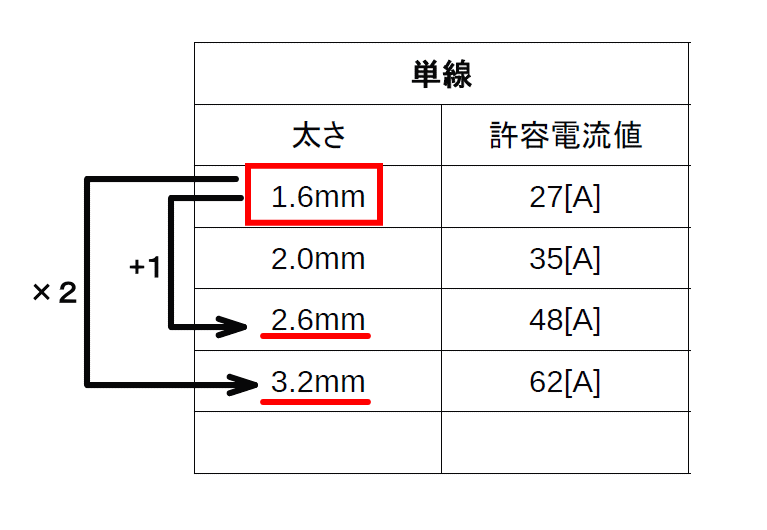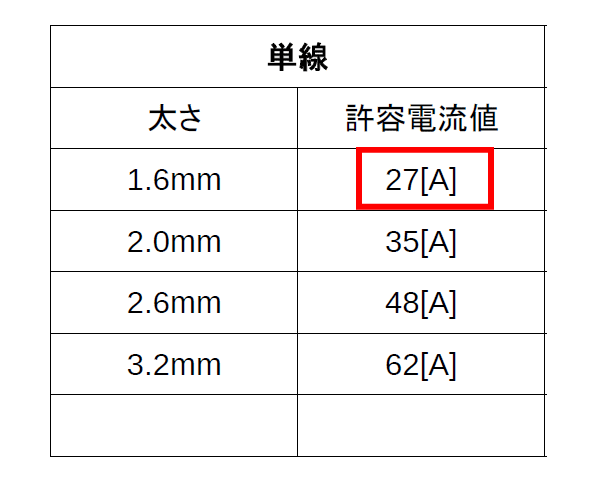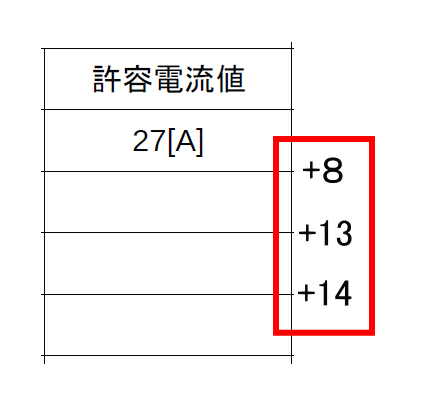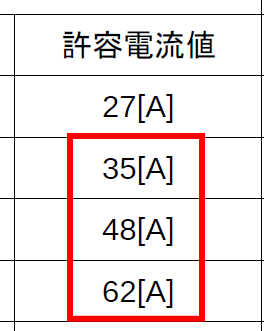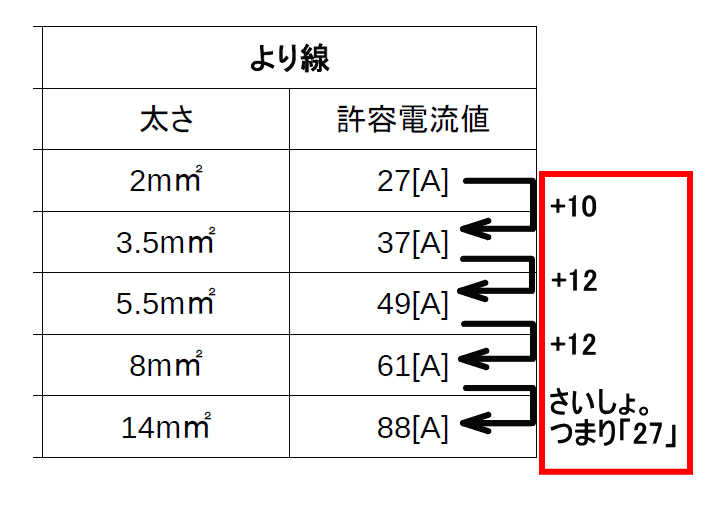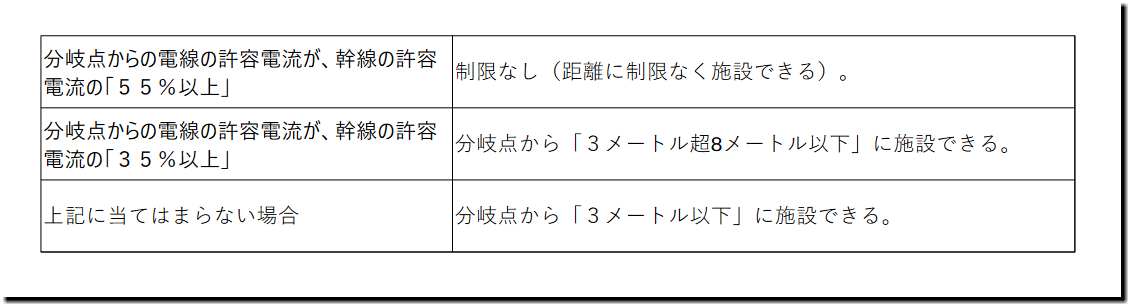登録販売者 「保健機能食品等の食品」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題3
「法規」の【保健機能食品等の食品】に「表」があります。
当該表の「穴埋め問題」を作りました。
知識の整理にもなるので、解いてみてください。
正直、実に難しいです。
本試験では、ここまでガチで問われないので、安心してください。
解説
念のため、“お気に入り”にでも入れておいて、最低3回は、チェックしてください。
括弧イ・ロ
(イ)には、「特別用途食品」が入ります。
そして、(ロ)にも、「特別用途食品」が入ります。
括弧の前にある「広義の」と「狭義の」で、憶えるといいでしょう。
括弧ハ
(ハ)ですが、ここには、「保健機能食品」が入ります。
「表」を見てもわかるように、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」と「機能性表示食品」の3つが、当該保健機能食品に分類されています。
この辺り、それぞれの語句が似通っていて、本当にわけがわからなくなります。
機械的に暗記してください。考えるだけ無駄です。
括弧ニ・ホ
(ニ)には、「特定保健用食品」が入ります。
そして、(ホ)には、「条件付き特定保健用食品」が入ります。
「特定保健用食品」は、ふつうの「特定保健用食品」のものと、“条件付き”の「特定保健用食品」のものとがあると、把握しておいてください。
この辺りも、試験後半あたりで???と、記憶の混同が起きます。
何も考えず、無念無想で、括弧が埋められるようになっておきましょう。
括弧ヘ
(ヘ)には、「栄養機能食品」が入ります。
当該栄養機能食品は、「1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合」したものです。
クソわけわからなくなるので、一度憶えても、再度、チェックしておきましょう。
括弧ト
(ト)には、「機能性表示食品」が入ります。
当該機能性表示食品は、「一定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできる」ものです。
当該語句も、後々で、ゲシュタルト崩壊(=わけがわからなくなる)ので、チェックしておきましょう。
括弧チ・リ・ヌ
括弧チ・リ・ヌですが、「表」の注記的な文言です。
試験に出しやすいところなので、押えておきましょう。
(チ)には、「特定保健用食品」が入ります。
(リ)には、「特別用途食品“制度”」が入ります。
(ヌ)には、「保健機能食品“制度”」が入ります。
当該注記は、そのまんまが、選択肢の1つとして出題されそうです。
例題としては、「特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけられている」と、そのまんまが選択肢に登場、ってな塩梅です。
常識のある出題者なら、上記のように、そのまんまを選択肢に出すと思われます。
しかし、クソの出題者なら、「“機能性表示食品”は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけられている」などと「ひっかけ」をしてきそうなので、注意してください。
まとめ
以上、【保健機能食品等の食品】の「表」の穴埋め問題です。
当該論点は、頻出論点です。
語句にも似たものがあり、受験生が“際立って”間違えやすくなっています。
先述したように、記憶の混同も起きやすいです。
意味を考え出すと、本当に???となってくるので、機械的に暗記していってください。
また、繰り返しますが、一度憶えても安心せず、本試験までは、知識の再確認・再記憶を行ってください。
本当に、忘れやすく、憶え間違いをしやすいところです。だから、毎回、試験に出るのです。
| カテゴリー: 未分類, 資格こもごも | Tags: 登録販売者 法規, 登録販売者 法規 オリジナル問題 | 2022年7月11日 9:26 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
絶縁電線の許容電流の憶え方‐第2種電気工事士 筆記対策
「絶縁電線の許容電流」ですが、ほぼ毎年出ている論点です。
ほぼ同じ出題で、「表」の暗記だけで点が取れます。以下に、「表」の数字の憶え方を述べていきます。
憶える対象
憶えるべきは、上記「表」のすべての数字です。
しかし、個々の数字をそっくりそのまま憶えるのはメンドウです。
よって、単純な形で憶えていきましょう。
単線の太さ
まずもって、「単線」の「太さ」から憶えていきます。
結論から言うと、憶え方は、「自力と、+1,×2」」です。
最初の2つの「1.6㎜」と「2.0mm」は、自力で憶えます。
当該「1.6㎜」と「2.0mm」の電線は、技能試験の教材のケーブル内にあるので、それらに触れて「1.6」と「2.0」の数字を憶えましょう。(絶妙に太さが違います。)
参考:技能試験の教材
次に憶えるべきは、「2.6㎜」の「2.6」と、「3.2㎜」の「3.2」です。
これらは、「1.6」に足し算(+1)と掛け算(×2)をすることで憶えます。
つまりは…、
「2.6」は、最初の「1.6+1」の「2.6」で憶える…、
「3.2」は、「1.6×2」の「3.2」で憶える…、
…ってな次第です。
図にすると、下の画像のように…、
…なります。
ふつうに「2.6」と「3.2」を憶えるよりも、単純な「+1,×2」の方が憶えやすいはずです。
単線の許容電流値
次は、「単線」の「許容電流値」を憶えていきます。
結論から言うと、憶え方は、「+8,+13,+14」です。
まずもって、最初の「1.6㎜」の「27A」は、自力で憶えてください。
当該「27」が憶え方の基準となるので、正確に憶えましょう。
次に、それ以降の「35A」と「48A」と「62A」ですが、ここは、足し算「+8,+13,+14」を行うことで憶えます。
要領ですが、図にすると…、
…となります。要は…、
最初の「27」に「+8」で「35」を…、
「35」に「+13」で「48」を…、
「48」に「+14」で「62」を…、
…求めるってな次第です。
個々の数字を憶えるよりも、「+8,+13,+14」の方が憶えやすいと思います。
細切れ時間に、「プラ8・プラ13・プラ14…」や、「プラス8・プラス13・プラス14…」とか、「8,13,14…」などと、唱えてみてください。そこそこ頭に残るかと思います。
より線の太さ
次に、「より線」の「太さ」を見ていきます。憶え方は、先と同じです。
結論から言うと、「+1.5,+2.0,+2.5,合計」です。
最初の「2m㎡」の「2」のところは、自力で憶えます。
後の数字は、先に見た「+1.5,+2,+2.5,+合計」で足し算して求めます。
図にすると…、
…ってな塩梅です。
つまりは…、
「2+1.5」で「3.5」を…、
「3.5+2.0」で「5.5」を…、
「5.5+2.5」で「8」を…、
…求めるってな次第です。
最後の「14m㎡」ですが、これは、先に足し算した値の合計値「1.5+2.0+2.5」の「6」を足し算します。
よって、「8+6」で「14」と相なります。
「+1.5,+2,+2.5,+合計」の意味は、こうした次第です。
個々の数字を暗記するよりも、(プラス1.5,2、2.5の合計)と唱える方が楽だと思います。
より線の許容電流値
「より線」の「許容電流値」ですが、要領的には先と同じです。
憶えるべきは、「+10,+12,+12,最初」というフレーズです。
当該フレーズを図にすると…、
…といった塩梅です。要は…、
最初の「27」に…、
「27+10」で「37」を…、
「37+12」で「49」を…、
「49+12」で「61」を…、
…押えるってな次第です。
そして、最後の「最初」ですが、これは、最初の「27」Aを意味します。
よって、「61+27」で「88」を求める、ってな次第です。
まとめ
憶え方の語呂をまとめると…、
単線太さ・・・「+1,×2」
単線許容電流・・・「+8,+13,+14」
より線太さ・・・「+1.5,+2,+2.5,+合計」
より線許容電流・・・「+10,+12,+12,最初」
…です。
試験が始まったら、試験問題の余白に先の語呂を殴り書きして、問題に遭遇したら、「表」に作り変えるとスマートです。
なお、単線の太さですが、これは、「直径」で「mm」です。
対して、より線の太さは、「断面積」で「m㎡」です。
単位が異なっているので、注意してください。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記 | 2022年7月8日 10:04 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
分岐回路の過電流遮断器の施設の憶え方‐第2種電気工事士 筆記対策
「分岐回路の過電流遮断器の施設」は、近年は出題がそうありませんが、かつては、毎回出るド頻出論点でした。
過去の論点は、しばらくすると、再出題されるので、押えておきましょう。
暗記表
試験で問われるのは、上記「表」です。
使うテキストによって、アレコレ書かれていますが、上記のように憶えるのが一番効率がいいかと思います。
解説
憶えるべきは…、
・分岐点からの電線の許容電流が、幹線の許容電流の「55%以上」であれば、「距離に制限なく」施設できる。
・分岐点からの電線の許容電流が、幹線の許容電流の「35%以上」であれば、「3メートル超8メートル以下」に施設できる。
・上記に当てはまらない場合は、「3メートル以下」に施設する。
…です。
よって、暗記すべき数字は、「55%」と「35%」、「3メートル超8メートル以下」の数字と相なります。
一番カンタン‐55%
「55%」の数字が一番憶えやすいので、先に消化してしまいましょう。
くだらないですが、「制限なし、GOGO(55)」くらいの語呂で、数字を頭に入れてください。
35%…3m超8m以下をいじる
先に見たように、分岐点からの電線の許容電流が、幹線の許容電流の「35%以上」であれば、「3m超8m以下」に、施設することになります。
当該「35%」の憶え方ですが、「3m超8m以下」をいじって憶えます。
「35%」の「3」は、「“3”m超8m以下」にあるので、そのまんまです。
次に、「35%」の「5」です。
これは、「3m超8m以下」を引き算っぽく加工して、「8-3=5」といった感じで、憶えてしまいます。
無理から「5」を憶えるよりも、「3m超8m以下」を引き算に加工する方が楽と思われます。
こうした次第で、「35%」という数字を憶えるってな次第です。
補足…「逆」も可能。
先の引き算の憶え方ですが、「35%」の方から、「3m超8m以下」を憶えることも可能です。
「3m超8m以下」の「3」は、「“3”5%」です。
残る「8」ですが、これは、「35%」を足し算風に直して、「3+5=8」くらいに憶えることが可能です。
要は、数字が頭に入っていればいいので、頭に残る方法で憶えていってください。
まとめ
以上、「55%」と「35%」の憶え方でした。
当該論点は、問題の「解き方」も、押えておきましょう。
過去問の典型的な出題として…、
…といった問題があります。
また、「逆」の出題もあります。
たとえば…、
「分岐点から5メートルのところに過電流遮断器を施設した。分岐回路の定格電流はいくつにしたらいいか?幹線のそれは、100Aである。」
…といった塩梅です。
例題では、もうすでに過電流遮断器が5メートルのところに施設されています。
この場合、「3m超8m以下」に該当しますから、「表」を眺めて、「35%」以上にしたらいいことがわかります。
幹線の定格電流は「100」Aですから、「100*0.35」で「35A」以上にしたらよい、ってな塩梅です。
当該論点は、基本の「表」の暗記に加えて、問題文の読み方や解き方も、チェックしておきましょう。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記 | 2022年7月8日 9:34 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |