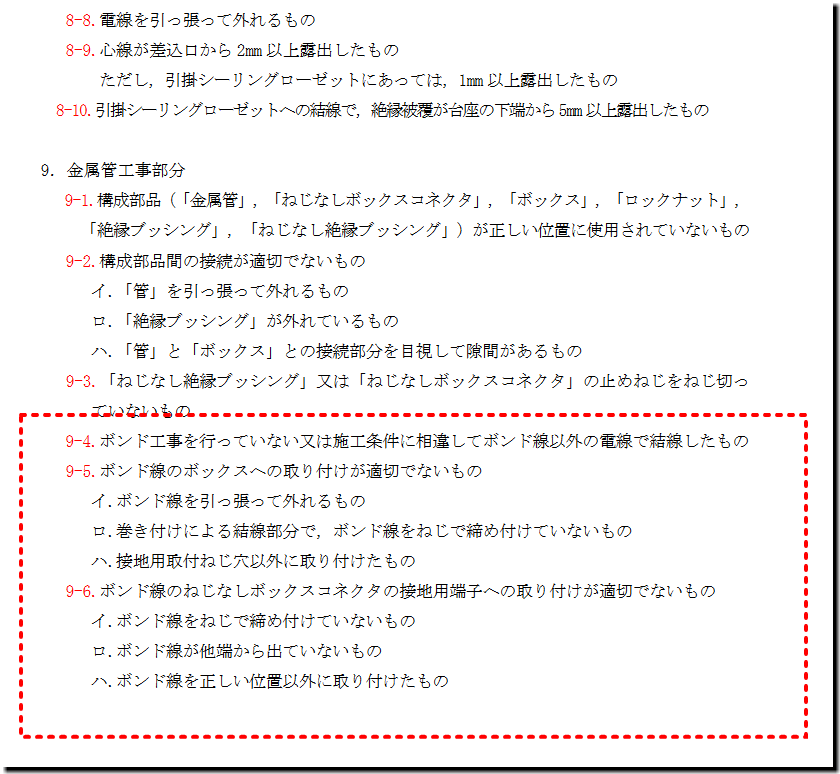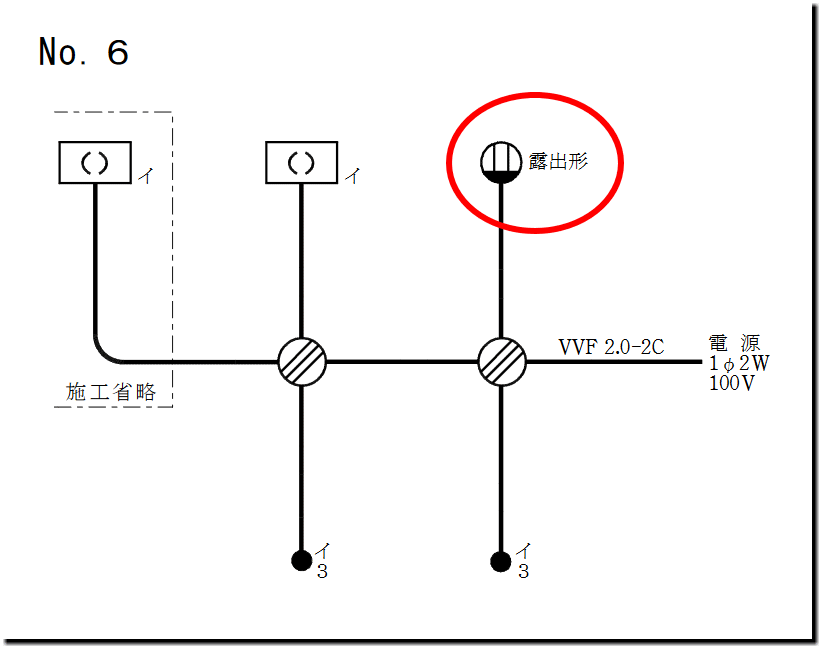固有部分(ボンド線・ロックナット・露出形コンセント)を2~3度練習:第2種電気工事士の技能試験の勉強
技能で行う作業・施工には、候補問題で「共通するもの」と、共通しない「固有のもの」があります。
前者の「共通するもの」とは、たとえば、ケーブルの採寸、ランプレセクタプルやコンセント、リングスリーブの接続や圧着などです。
これら「共通するもの」は、ある候補問題で練習すれば、当該練習がそっくりそのまま、他の候補問題の練習にもなるという次第で、自然と練習量が確保できているのです。
ですから、候補問題を作っていれば、「共通するもの」は、ドンドコと上達していくので、神経質になる必要はありません。
対して、文系ド素人が用心しないといけないのは、候補問題で共通しない、後者の「固有のもの」の方です。
試験勉強の中盤あたりから、以下の「固有のもの」を徹底練習しておきましょう。
固有のもの
当該「固有のもの」ですが、そのすべてを徹底練習する必要はないです。
「固有のもの」には、たとえば、3路スイッチ・4路スイッチや確認表示灯、端子台などの作業が該当します。
しかし、これらは、似ているというか、要領的に同じことが多いです。
たとえば、端子台の作業は、言ってしまえば、被膜を剝いてねじ締めするだけであり、ほとんど“同じ”作業です。
よって、「固有のもの」であっても、先の「共通するもの」と同様に、候補問題を作っていくうちに、ドンドコ上達するのです。
こういうものは、そう神経質になる必要はないのです。
しかし、「固有のもの」の中には、1~2つの候補問題にしか出てこないものもあるのです。
これらを本当に注意しないといけないのです。
ガチの固有
「固有のもの」のうち、最も注意すべきが…、
①ボンド線の取り付け
②ボックスコネクタのロックナットの取り付け
③露出形コンセント
…です。
これらの作業は、特定の候補問題にしか出ないため、練習の絶対数が絶対的に不足するのです。
文系ド素人だと、練習不足から「欠陥」を犯しかねません。
よって、別枠で時間を設けて、個別的に練習をしておく必要があります。
①ボンド線の取り付け不良
①のボンド線は、金属管とアウトレットボックスを接続する際に、『出題の可能性がある作業』です。
2022年度の候補問題では、「第11問:ねじなし管」です。
当該ボンド線の装着は、昨今では『省略』が主流ですが、突然、試験の傾向が変わって、出題される可能性は、厳然としてあります。
公式が公表している「欠陥基準」では、毎年のごとく、当該ボンド線の記載があります。
当該ボンド線の取り付けは、「アウトレットボックス+金属管」の候補問題にしか出ないために、練習量が絶対的に不足し、本当に手薄になります。
出題者からすれば、当該ボンド線作業は、「当該作業を課すだけで、難易度を引き上げられる、便利な調整項目」なので、試験的に、無視できません。
試験勉強の中盤あたりに、2~3回は、当該ボンド線の作業を、個別的に練習しておきましょう。慣れていない作業のため、かなり手間取るはずです。
わたしのケースですが、当該ボンド線の作業を苦手にしてました。
本試験では、いの一番に当該ボンド線作業の有無を確かめ、“なかった”ので、難関1つクリア!!と、安堵した思い出があります。
当該「ボンド線」は、おおむね『省略』でしょうが、いつ試験に出てもいいよう、保険の意味で、練習だけはしておきましょう。
②ボックスコネクタのロックナットの取り付け不良
当該②ボックスコネクタのロックナットの取り付けは、「ねじなし管」を使う候補問題でしか顔を出しません。
2022年度の候補問題では、「第11問:ねじなし管」だけです。
このため、練習量が不足して、ついついうっかり、ロックナットの“取り付けそのもの”を忘れてしまいます。
本試験は、本当に独特の空間なので、ケアレスミスの発生率は、“超絶に高い”と思っていてください。
練習中は、明白に「ボックスコネクタのロックナットの取り付けは、欠陥!!!」と意識して作業に臨みます。
試験勉強の中盤以降に、2~3回、ボックスコネクタにロックナットの取り付けて、「ここが欠陥だ!」という風に、記憶に刻み付けておきましょう。
なお、ロックナットの「向き」も注意してください。
ロックナットには「向き」が設定されており、少し窪みのある方が金属壁側になっていないと、「欠陥」を取られて、即落ちします。
③露出形コンセント
③露出形コンセントですが、これは、おおむね「3路スイッチ」の候補問題で登場します。
2022年度の候補問題では、「第6問:3路スイッチ」です。
写真だと…、
…のところです。
当該露出形コンセントは、先述したように3路スイッチの問題しか出ないため、練習量が圧倒的に不足しています。
そして、露出形コンセントの作業は、他に似たものがないため、これ1個のためだけに、独自の練習をする必要があります。
採寸の仕方や作業の仕方を、意識して押えてください。
また、当該露出形コンセントのところは、そこそこ「欠陥」が取られるので、本当に要注意です。
「不合格となる危ないところ」だと、意識して作業に臨んでください。
中盤のまとめ
まとめです。
①ボンド線の取り付け
②ボックスコネクタのロックナットの取り付け
③露出形コンセント
上記3つの作業は、他の候補問題に共通しない「固有のもの」です。
練習量が圧倒的に不足するところなので、意識的に時間を設けて、練習してください。
試験勉強の中盤以降、最低でも「3回」は、組んでおきましょう。
補足‐追加教材
技能試験の教材については「第2種電気工事士・技能試験のテキスト・教材・工具」に述べているのですが、文系ド素人にとって、あると便利なものを紹介しています。
たとえば…、
「ホーザン 合格クリップ」や、
「ホーザン 合格ゲージ P-925」や、
「ホーザン 合格配線チェッカー Z-22」です。
絶対に必要かというとそうではありませんが、「手助け」にはなるので、万全を尽くしたい方は参考にしてみてください。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工技能 | 2016年6月16日 10:14 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
技能試験は減点方式‐採点基準:欠陥をまず理解:第2種電気工事士の技能試験の勉強
第2種電気工事士の技能試験は、ガチの『減点方式』であることを、いの一番に、頭に入れてください。
技能は、「欠陥」がたった1つでもあると、不合格です。
候補問題がそこそこ組めていたら合格なのではありません。
美しく回路を作ったら合格なのではありません。
見た目がひどい出来上がりでも、「欠陥」がないなら、合格です。
素人丸出しのあたふた回路でも、「欠陥」がないなら、合格なのです。
反対に、どれほど上手く・プロ風にできていても、「欠陥」が1つあれば、そこで落ちます。
ここを取り違えてはいけません。
全工程の99%ができていても、「欠陥」が1つあればダメなのです。
技能の合格率は70%台。高合格率であります。
しかし、「1つでも間違えると不合格」となる採点基準のために、全く油断のできない、精神的に厳しい試験となっています。
技能は、7割合格とはいえ、わたしには、神経を使いに使った、しんどい試験でした。手が震えました。
「欠陥」を、まず知るべし
技能試験の試験勉強を始めたら、まず、テキストの最初の方にある「欠陥」の章を、『3回』は目を通しましょう。
テキストのページには…、
「未完成」
「回路間違い」
「器具配置違い」
「使用電線違い」
「電線の心線・被覆の著しい損傷」
「電線の色違い」
「寸法違い」
「連用枠の取り付け違い」
「極性違い」
「接続間違い」
「ねじの締め忘れ」
「被覆の噛み」
「被覆の剥き過ぎ」
「心線のはみ出し・抜け落ち」
「コネクタの施工不良」
「破損(欠け)」
…などなど、個々の「欠陥」の指摘と説明とがあるはずです。
このページに、「合格」の情報が詰まっています。
技能試験とは、これら「欠陥」をしないだけ、です。
「欠陥」を犯さないだけ
繰り返しますが、「欠陥」を犯さないことが、技能合格の最大のポイントです。
最初のうちは、候補問題を組むことに集中しているため、どこが「欠陥」なのか、意識が希薄です。
そのため、候補問題を最後まで組めただけで、そこそこ満足しがちです。
しかし、一口で言うと、『それではダメ』です。
わたしたちが神経の大半を割かねばならないのは、「欠陥」の有無です。
各候補問題に設定されている「欠陥」をパスしてこそ、“実のある”試験勉強になるのであって、「作れたからよし」では、まるでダメなのです。
回路がそこそこ組めたことに満足してはいけませんし、やった感に浸ってもいけません。
「欠陥」の有無を確かめ、それが「ゼロ」で始めて満足していいのです。
まとめ
2電工の技能試験は、「欠陥」が1つでもあれば不合格となる、ガチの「減点方式」です。
受験生が注意すべきは、「欠陥」の有無です。ここが『合否の境目』です。
日々の練習では、候補問題ごとに設定されている「欠陥」を意識して臨んでください。
回路の出来不出来以上に、「欠陥」を犯していないかどうかを、“答え合わせ”してください。
なお、回路の仕上がりなんてものは、全候補問題を1~2周繰り返せば、劇的に上達するので、気にする必要はありません。最初は皆へたくそです。
そして、最後ですが、「欠陥」を極端に恐れる必要はありません。
先述したように、技能試験の合格率は約70%ですから、7割の人は「欠陥」をしていない塩梅で、7割も防げるなら、これをお読みの皆さんも、確率的に「欠陥」の発生を防げます。
何回も練習して、はやる心を抑え、慎重に作業に臨めば、「欠陥」を犯しません。
ホント、技能は、「欠陥」をしないだけです。
逆に言うなら、「欠陥」以外のことは、てきとーにやってもよい、という塩梅です。
全部が全部の作業に神経を張り詰めると、逆に、ケアレスミスを犯しかねません。
独学では、先生や講師がいないので、1つ1つのミスが気になるかもしれません。
しかし、細かいミスは、それが「欠陥」に該当しないなら、笑って済ませばいいのです。
補足‐追加教材
技能試験の教材については「第2種電気工事士・技能試験のテキスト・教材・工具」に述べているのですが、文系ド素人にとって、あると便利なものも、紹介しています。
たとえば…、
「ホーザン 合格クリップ」や、
「ホーザン 合格ゲージ P-925」や、
「ホーザン 合格配線チェッカー Z-22」です。
絶対に必要かというとそうではありませんが、「手助け」にはなるので、万全を尽くしたい方は参考にしてみてください。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工技能 | 2016年6月15日 11:33 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
ヨーグルトメーカーの容器の洗い物に重曹を
ヨーグルトメーカーで納豆やヨーグルトを作る利点は、『たくさんできる』に尽きます。
量を気にせずガッツリ食べられますし、何よりも、買い物の量が減るので、日々の買い物の手間がだいぶ省けます。
しかし、ヨーグルトメーカーによる自作で問題なのが、『洗い物』です。
当該空き容器には、納豆のネバネバや、ヨーグルトの残りかすが付着しており、洗う際は、手は元よりスポンジまでがぬめってしまうという塩梅で、配偶者並に手のかかるという次第です。
これらの汚れの解決に登場するのが、おなじみの重曹です。
即効性はありませんが、普通に水に浸けておくよりも、格段に汚れが落ちます。
重曹使用は例に漏れず、実に簡単です。
容器に水を入れる際に、粉末状の重曹をだばだばと、持ち前の“大雑把さ”と、人の口に上がっているだろう“雑さ”を活かして投入するだけです。(○○さんって結構雑よね的な。)
どのくらいの量を入れたらよいか?とかは、一切考えなくて結構です。
どばっなり、ざくっなりで、重曹を振り掛ければ、いいだけです。
容器に水を張り、そこに重曹を入れて、しばらく放置すれば、ぬめりの強度はかなり落ちています。
容器内の水を捨てれば、多くのネバネバ・べとべとは落ちていますので、後は、スポンジで洗い落とせばよい、という次第です。
当該「ネバネバ・べとべとに重曹」の欠点は、時間がかかる点ですが、容器が空いてすぐ洗い物をするような繊細さを持ち合わせてはいないでしょうから、大丈夫かと思われます。
わたしの場合は、納豆なりヨーグルトが残り少なくなると、サラダボウルなどの小皿に移してしまい、率先して容器を開けるようにしています。
こうすると、容器を水につける時間が確保できるからです。
重曹を振りかけておくだけで、厄介な洗い物が減ります。
納豆やヨーグルトの自作をされている方は、ぜひ、試してみてください。
なお、口にするものなので、念のため、食用グレードの重曹を使ってください。
配偶者なら掃除用の重曹でさえ贅沢ですが、対して、家族と自分に関わるものは、より安全な食用グレードを使うべきであります。
| カテゴリー: 調理・料理・軽食 | Tags: ヨーグルティア, 糖質制限, 納豆, 重曹 | 2016年6月14日 9:59 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |