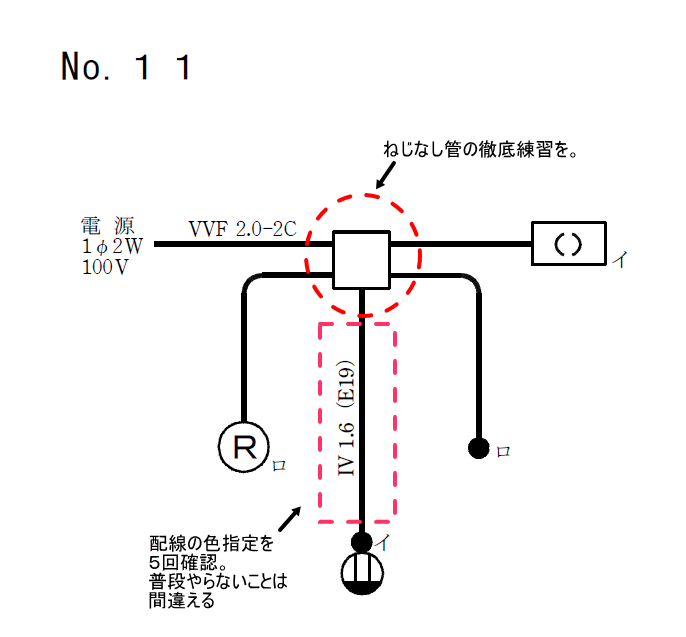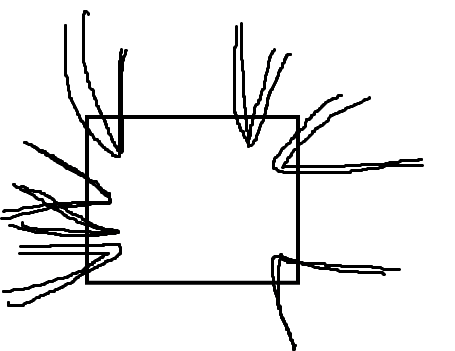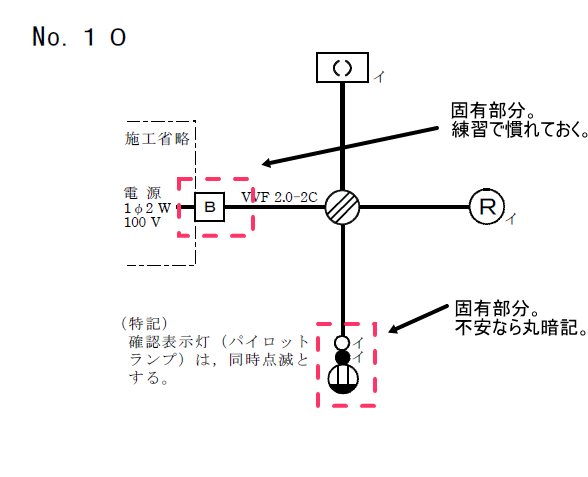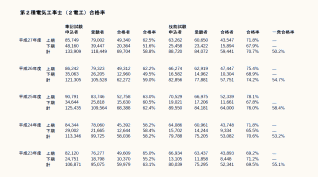候補問題11の独学ノート【画像あり】‐第2種電気工事士・技能試験(平成29年度‐2017年度)の攻略、手順、注意事項
平成29年度(2017年度)の、第2種電気工事士の技能試験の「候補問題11」の独学者向けポイントを見ていきます。
問題攻略の前に、「電源線で準備運動‐こころとゆびを慣らす」に、ざっくり目を通してください。
11は「最難関」
候補問題11は、全候補問題中で「最難関」となっており、心してかかる必要があります。
本問は、独自論点の宝庫で、「ねじなし電線管(E19)」「色付きIV線」と、他では出ない作業があるため、しっかり練習しておく必要があります。
とりわけ、凶悪なのは、「ねじなし電線管(E19)」で、ここは、欠陥の判定が「6つ」あるところで、ここができないだけで即落ちします。
本問では、まず徹底して、当該「ねじなし電線管(E19)」を練習しなくてはいけません。
ねじなし電線管(E19)の欠陥ポイント
「ねじなし電線管(E19)」は、先も述べたように、欠陥をたくさん取られるところです。
まず、欠陥ポイントを挙げると…
「ボックスコネクタのロックナットの取り付け忘れ」と…、
「ボンド線の不適切な取り付け」と…、
「ロックナットの向きの間違い」と…、
「絶縁ブッシングの取り付け忘れ」と…、
「絶縁ブッシングが外れている」と…、
「ねじ切り忘れ」となっています。
ここは本当に“やばい”ので、必ず、何回も何度も練習しなくてはいけません。
対応策
「知は力なり」です。
まず、「欠陥」の取られるところを憶えましょう。
「ロックナット」は落ちます。
「ボンド線」も落ちます。
「絶縁ブッシング」も落ちます。
「ねじ」で落ちます。
どこで『欠陥』がとられるかを知っていると、作業が慎重になるので、それだけ、ミスしなくなります。
本問の練習の前に、当該欠陥ポイントをド暗記しましょう。
ねじなし管攻略は5つ
ねじなし管の作業の前に、「5」という、ねじなし管の作業数を憶えておきます。
①金属管にボックスコネクタを差込んで、ねじ切り。
②ロックナット・絶縁ブッシングを取る。
③金属管をボックスに差し込み、ロックナットで固定。
④絶縁ブッシングの取り付け。
⑤ボンド線の取り付け。
どれも、「やることを忘れていたり」「間違っていたり」すると、欠陥をとられます。
工程数を明白にしていると、「抜け落ち」に気づくので、劇的に欠陥を避けることができます。
練習の際は、数字を口に出しながら、作業してください。
①のねじ切り
①のねじ切りは、おおむね「2つある」ので、絶対に忘れないようにしてください。
金属管の両端にボックスコネクタを付けたのに、うっかりすると、ボックス側のねじ切りしかやってない場合があります。
ねじは2つあるので、両方やるように、意識付けてください。ついつい、ウッカリします。
練習では、繰り返して練習するために、ねじ切りができないことでしょう。
しかし、ウォータポンププライヤを手に持ち、ねじをはさんで軽くねじを回し、『やったつもり』と一声だけ発しておきます。
こう「意識付け」ておけば、本試験でも2つのねじ切りを忘れないはずです。
なお、施工条件で、片方のボックスコネクタが「省略」されることもあります。この場合、「どっちに、ボックスコネクタをつけるか」の指示があるはずなので、それに従います。ま、おおむね、アウトレットボックス側です。
②のロックナット・絶縁ブッシング取り
次に、②のロックナット・絶縁ブッシング取りですが、ポイントは、「両方とも取る」と「置き場所を決めておく」です。
時折、目立たないロックナットを取り忘れることがあり、「あれ、ない、ないぞ!」とあたふたする事があります。確実に、ねじなし管から取り外しましょう。
そして、両部品を取り外したら、あらかじめ決めておいた、『定位置』に置きます。
練習でも本試験でも、作業スペースは限られており、かなりごちゃごちゃしています。
両部品とも細かいので、適当なところに置くと見失って、「探す」という要らざる時間を費やす羽目になります。
あらかじめ、どこに置くかを、たとえば、色が濃くて太くて目立つ「電源線の近くに置く」などと、決めておきましょう。
③のロックナット固定
金属管をアウトレットボックスに差し込んで、ロックナットで固定する作業です。
本作業は、「欠陥」ポイントなので、丁寧に行ないます。
ロックナットには『向き』があり、少し膨らんでいる方をボックスに向けて取り付けなくてはいけません。
④の絶縁ブッシング
④の絶縁ブッシング付けですが、気が急いていると、『付け忘れる』という大ポカをしかねません。
というのも、先の③のロックナット付けで、「なんだか管が固定されたような気分」になるためです。
このため、絶縁ブッシングの存在を綺麗さっぱり忘れてしまい、そのまま提出となりかねません。
わたしは練習時に、付け忘れという大ポカを、1度やっています。
絶縁ブッシングの付け忘れも欠陥で即落ちします。気をつけましょう。
⑤のボンド線は“超”最難関でまさに災難
最後の⑤のボンド線の取り付けは、かなり手間取るはずです。
ボンド線の取り付けは、輪作りもあり、「先端が出るように切る」といった細かい規定もあり、技能試験の中でも、最高ランクの難作業です。
まさに、「ボンド線」は、最難関の「災難」です。
最低5回は練習しておいて、スムーズに、手間取らず、短時間でできるレベルに到達しておきましょう。わたしも、本当に、手を焼きました。
本試験では、省略されることを『祈りたい』ですが、「いつ付けるよう指示されるか」はわからないので、「できる」ようになっておくことは必須です。
ちなみに、当該ボンド線ですが、平成29年度(2017年度)では、『取り付けの指示』の可能性があるので、念入りに見ておいてください。
例年、ボンド線は『省略』でしたが、本年度は、わかりません。
というのも、今年の技能試験では、ド定番だった「メタルラス壁」という作業が削除されているからです。
「メタルラス壁」がなくなった分だけ、どこぞにしわ寄せの来る危険性があります。
その筆頭が、毎年、省略されていた「ボンド線」といった寸法です。
ボンド線は、公式で、高らかに「欠陥判断ポイント」だと明記されているので、「無視」せず、万が一に備えて、できるようになっておきましょう。
参考:公式‐電気工事士技能試験(第一種・第二種)欠陥の判断基準:PDF
なお、ボンド線は、市販のを買うのもアレなので、使用済み電線から絶縁を取り除いた銅線で、代用するといいでしょう。少し硬いですが、練習はできます。
色付きIV線
本問では、おおむね「黒」「赤」「白」「黄」のIV線が登場します。
電線“単独”で出るのはごく少数で、本問のほか1問だけです。ですから、手間取らないよう、意識して練習しておきます。
本試験では、色ごとに、どの器具と接続するか指定されるので、必ず、その通りにします。
本問に遭遇した場合は、問題文を「3回」読んで、当該指定について、把握してください。問題文を読む際は、色指定のところに大きく『丸』をするといいでしょう。
そして、接続するときは、文系ド素人最強の技「指差し確認」をして、色と部品とが合っていることを確認してから、ガッチャンコと接続します。
なお、テキストにもよりますが、電線管に電線を差し込む場合、寸法のとり方が微妙に違っていることがあるので、必ず、お使いのテキストのやり方に従ってください。
アウトレットボックスは、180度曲げ
アウトレットボックスにケーブルを突っ込むと、ホント、ごちゃごちゃします。
んなもんで、差し込んだケーブルは、お馴染みの「180度曲げ」をします。
上記ひどい図のように、ケーブルを入れたら180度曲げて、ボックス上空をすっきりさせます。
こうすると、接続するケーブル・電線だけを選んで作業できるので、効率が格段にアップするはずです。
その他はふつう
「ねじなし管」と「色付きIV線」以外は、至極普通の作業なので、手間取らないはずです。
ただ、リングスリーブは注意です。そう顔を見せない「中」で接続するところがあるので、スリーブの種類と刻印(圧着マーク)とを「指差し確認」したうえで、ガチャンとしてください。
先述したように、本問は、最難関です。
固有部分は最低3回は練習しましょう。
また、本試験の1週間前には、必ず1度、通しで練習してください。
なお、念のため、本試験での注意を述べたいのですが、長くなるので「問題文は命取り‐絶対的注意事項」に述べています。併せて、お目汚しください。
最後に、技能試験の教材については「第2種電気工事士・技能試験のテキスト・教材・工具」に述べているのですが、文系ド素人にとって、あると便利なものを紹介しています。
たとえば…、
「ホーザン 合格クリップ」や、
「ホーザン 合格ゲージ P-925」や、
「ホーザン 合格配線チェッカー Z-22」です。
絶対に必要かというとそうではありませんが、「手助け」にはなるので、万全を尽くしたい方は参考にしてみてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 2電工技能, 2017技能 | 2017年1月23日 10:36 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
候補問題10の独学ノート【画像あり】‐第2種電気工事士・技能試験(平成29年度‐2017年度)の攻略、手順、注意事項
平成29年度(2017年度)の、第2種電気工事士の技能試験の「候補問題10」の独学者向けポイントを見ていきます。
問題攻略の前に、「電源線で準備運動‐こころとゆびを慣らす」に、ざっくり目を通してください。
10の難易度は「やや難」
結論から言うと、候補問題10は、「やや難」です。
「確認表示灯(同時点滅)・スイッチ・コンセント」があるためです。
しかし、後述するように、「結線のやり方を丸暗記すれば」、劇的に難易度は下がります。
また、本問では、「配線用遮断機(ブレーカー)」が出ます。先の画像の「B」の部分です。
当該器具は、本問にしか登場しない、言うなれば、“レア”器具となっています。接続に慣れておく必要があります。
ここも、後述する対策を採れば、到って穏当に合格できる問題となっています。
本問は、受かる問題なので、遭遇したら小躍りしてもいいです。「ミスゼロ」で臨んで、確実に合格しましょう。
確認表示灯(同時点滅)は暗記
結論から言うと、「確認表示灯(同時点滅)・スイッチ・コンセント」の部分は、「結線を丸暗記」です。
当該作業は、“考えれば、”できますが、本試験では、「いちいち考えていると時間がなくなる」ため、考えてはいけません。
うーん、どうしたっけ?と、トロトロやっていると、見直し時間がなくなってしまいます。
ちなみに、組上げ後の見直し時間は、“最も重要な時間”で、大概1つは、見直し時に致命的なミスを発見し、事なきを得るケースが多々です。
つまり、見直し時間がない=ミスを発見できない=欠陥で不合格、という塩梅です。
試験的には、同時点滅の結線を、つまり、わたり線の通し方、わたり線の色、その他諸々を、丸暗記するのが一番です。
なお、同時点滅については、一度、自分で考えて、同時点滅の理屈を理解してから、暗記に入ります。
丸暗記だけだと、施工条件が変えられた時点で落ちるからで、万が一の“担保”です。
そんなに難しい理屈じゃないので、押さえるだけ押さえます。
なお、丸暗記は、組む練習を5回もやれば憶えますが、憶えられなかったら「憶えるまでやるだけ」です。
ホント、ここだけを組むだけなので、数分でできます。晩酌前なり、寝る前の儀式として、ちゃちゃと組み立てて、憶えてしまいましょう。(言うまでもありませんが、使用済みケーブルで練習してください。新たにケーブルを切るのは手間です。)
配線用遮断機は、NO油断
さて、本問には、本問にしか出ない「配線用遮断機(B)」が登場します。
普通の端子台の作業と同じなので、そう手間取ることはないでしょう。
しかし、『極性』だけは、要注意です。
極性の間違いは「欠陥」なので、本問で落ちるとしたらここです。
本問では、最難関の「同時点滅」の回路に、神経の大半が行ってしまうため、ついうっかり、遮断機の極性を忘れてしまうことがあります。
ケアレスミスが出ないよう、「極性~よしっ!」の指差し確認を推奨します。
当該固有部分も、4~5回は練習して、身体を慣れさせておきましょう。
残るは「中」
本問では、リングスリーブの「中」を使います。
「中」の出番はそうないので、ついつい、いつもどおりに「小」「極小」でガチャンコとしそうになるので、本当に注意してください。
本問は、落ち着いて作業すれば、まず合格できる問題です。
絶対に合格しましょう!
なお、念のため、本試験での注意を述べたいのですが、長くなるので「問題文は命取り‐絶対的注意事項」に述べています。併せて、お目汚しください。
最後に、技能試験の教材については「第2種電気工事士・技能試験のテキスト・教材・工具」に述べているのですが、文系ド素人にとって、あると便利なものを紹介しています。
たとえば…、
「ホーザン 合格クリップ」や、
「ホーザン 合格ゲージ P-925」や、
「ホーザン 合格配線チェッカー Z-22」です。
絶対に必要かというとそうではありませんが、「手助け」にはなるので、万全を尽くしたい方は参考にしてみてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 2電工技能, 2017技能 | 2017年1月23日 10:25 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第2種電気工事士「下期」の筆記は「夏・注意」-合格率の低い理由
結論から言うと、「下期筆記」の試験勉強は、「8月の暑さ」に注意する、といった次第です。
ご存知のように、2電工は、「上期」と「下期」に試験が行われます。
「上期」受験は、気候的に問題ないのですが、「下期」に受験予定の方は、「夏の暑さ」に、留意しなくてはいけません。
「下期」の筆記の合格率は、「上期」と比べて、明らかに低いからです。
上記PDFを見てもらえば、一目瞭然です。
上期は60%台になることが多いのに、下期は40~50%台と、「下期」の筆記は、「上期」に比べて、明白に低くなっています。
理由は暑さ
「下期」の筆記の試験問題は、基本的には、「上期」と同じレベルです。当たり前ですが、上期と下期とで、大差はありません。
下期筆記の合格率の低い原因は、「夏の暑さ」かと思われます。
「下期」の筆記試験は、おおむね「10月の第1週の土・日」に行なわれます。
ぱっと見、(10月かー)くらいにしか、思わないはずです。わたしもそうでした。
しかし、ここに巨大な落とし穴があります。
10月に本試験があるのなら、試験勉強は、8月の暑い最中に行うことになる、ってな寸法です。
ぶっちゃけ、「8月」なんて、勉強できません。いくら空調を効かせようと、やはり、日中の暑さで、体力を消耗しています。
特に、仕事を抱えている人で、現場仕事なら、勉強なんてできない相談です。
暑い最中仕事して、帰ってきて、ビールを飲もうものなら、もう、テキストなんて頭に入りません。
暑い最中仕事して、帰ってきて、風呂に入ったら、もう、問題集を開く気など起きません。
こうした次第で、8月の試験勉強は、能率が半分くらいに落ちると、想定しておくべきです。
下期を受ける方は、「下期の筆記には、暑さという大敵」が存在していることを、頭の片隅に置いてほしく思います。
はやめはやめに手を付ける
結論から言うと、下期試験の筆記は、6月~7月の間に、テキストと過去問とを、ざっくりでいいので、一通り、やっておくのがベストです。
「8月」は、1日当たり、テキストは1~2単元を精読し、過去問を3~5問ずつ、消化するくらいのペースが賢明かと思います。
で、「9月」ともなれば、暑さも和らぐので、弱点や未消化論点、間違えたところの復習に充てる、ってな寸法です。
「8月」を当てにしない、学習計画を作りましょう。
下期筆記のまとめ
はじめて2電工の下期試験を受けられる方は、筆記試験の勉強に「暑さ」という強敵が潜んでいるなんて、気づくはずがありません。
しかし、当該「暑さ」は、数字の上で、猛威を振るっています。
繰り返しますが、下期受験の方は、本格的に暑くなる8月になる前に、論点すべてを済ませられるような学習計画を練ってください。
「8月」なんて「ない」くらいに考えておく方が無難です。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士 | 2017年1月21日 1:42 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |