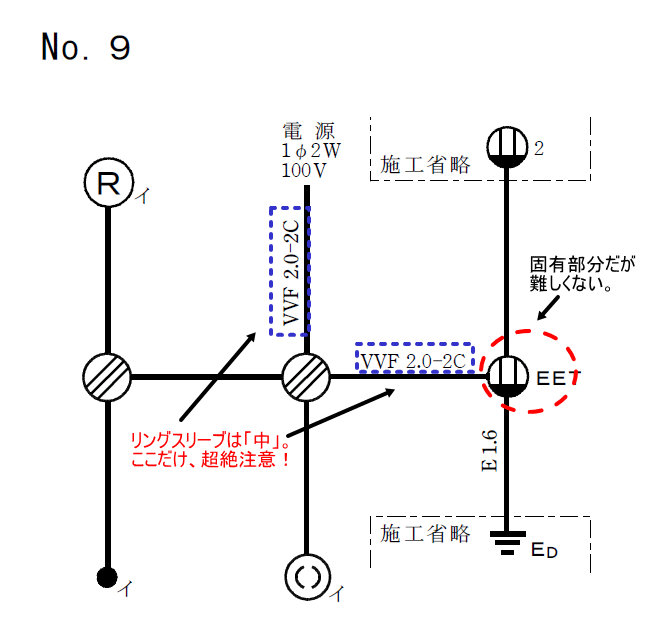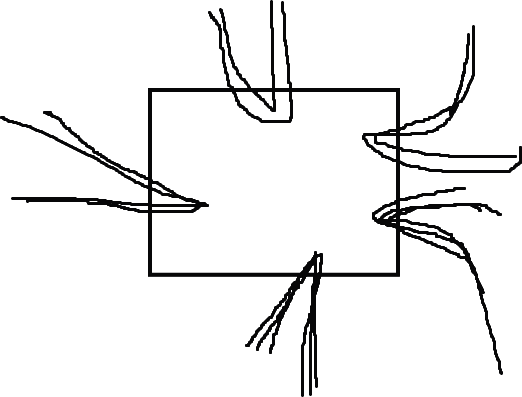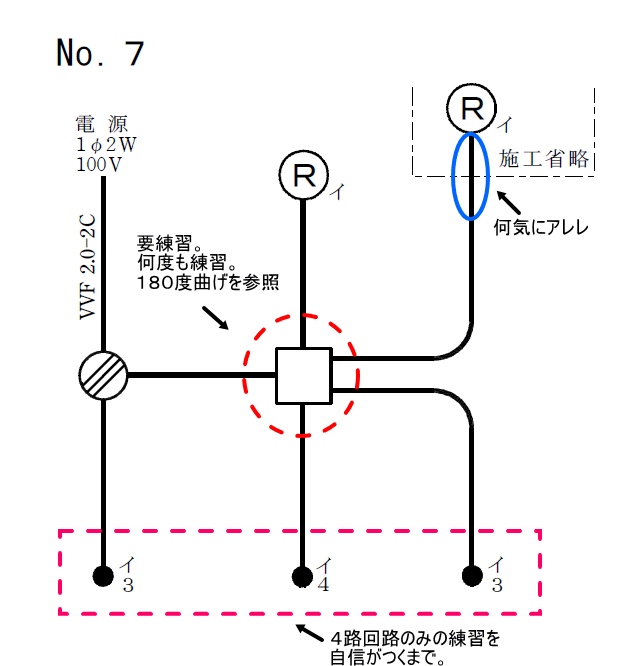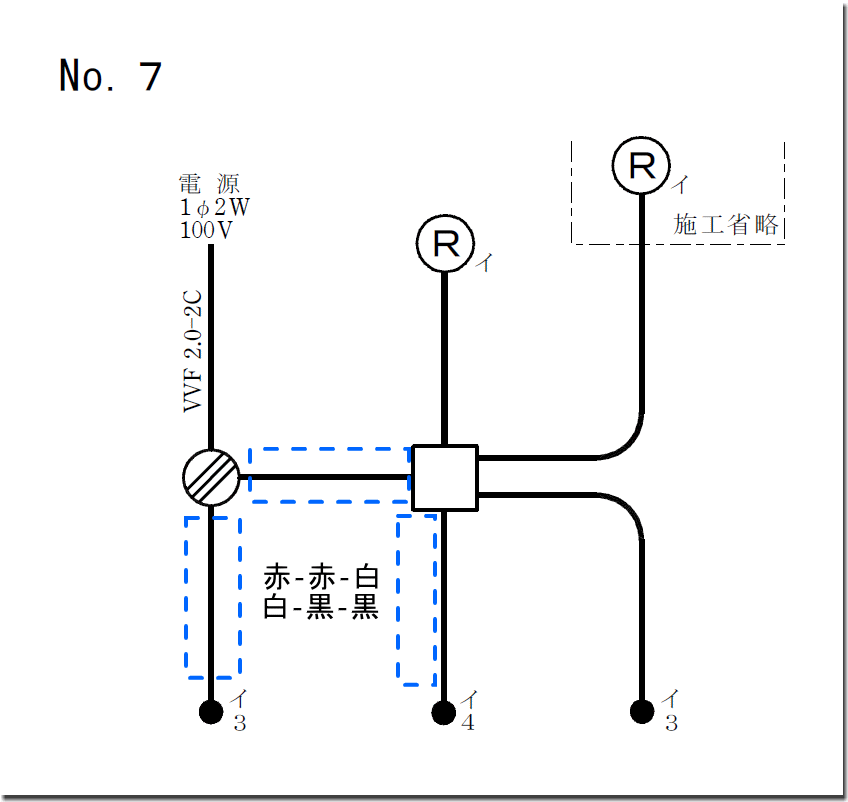候補問題9の独学ノート【画像あり】‐第2種電気工事士・技能試験(平成29年度‐2017年度)の攻略、手順、注意事項
平成29年度(2017年度)の、第2種電気工事士の技能試験の「候補問題9」の独学者向けポイントを見ていきます。
問題攻略の前に、「電源線で準備運動‐こころとゆびを慣らす」に、ざっくり目を通してください。
9の難易度は「やさしい」
結論から言うと、候補問題9は、「やさしい」です。
本問に当たると、「ラッキー」です。かっちり仕上げて合格してください。
さて、本問の固有部分は、「EET(接地極付接地端子付コンセント)」と「丸型の引掛けシーリング」ですが、両方とも、難しくありません。
“普通に”挿し込むだけなので、お手本を見て2~3回作業すれば、文系ド素人でもまずできます。
また、本問では、「VVF 2.0-2c」が2つ使われるところに特徴があり…、
『2.0と2.0の接続は、リングスリーブの「中」で接続される』ことに、注意をしなくてはいけません。
言うなれば、注意点はここだけです。
EETは落ち着くだけ
「EET(接地極付接地端子付コンセント)」ですが、こういう簡単なものほど、ケアレスミスをしやすくなっています。
単に、電線を突っ込むだけですが、「極性」だけは、注意です。落ちるとしたら、ここだけだからです。
いつも通りの自分の力を発揮してください。
丸型の引掛けシーリングも同様
「丸型の引掛けシーリング」は、本問にしか出ません。
しかし、作業は器具部品中でもカンタンな部類なので、問題はないでしょう。
先のEETと同じように、「極性」だけを注意してください。
まあ、他の候補問題を消化していれば、間違うことはないでしょう。
VVF 2.0-2cの接続
先述したように、本問で一番の注意点は、「VVF 2.0-2c」同士の接続です。
VVF 2.0-2cとVVF 2.0-2cを接続する際は、リングスリーブの「中」で、刻印(圧着マーク)も「中」で行ないます。
「中」の出番はそうないので、ついつい、いつもどおりに「小」「極小」でガチャンコとしそうですが、本当に注意してください。
リングスリーブの接続を間違うと、修正に3~5分かかります。
(中だよいいね?中だよいいね?)と、指差し確認を2回した後で、接続してください。
そのほかは、問題ないでしょう。ま、「施工省略」でやる作業を、おさらいしておいてください。
本問は、作業が単純なので、たいてい、時間が余るはずです。焦らなくても、時間は十分にあります。心を落ち着けて、作業するようにしてください。
絶対に合格しましょう!
なお、念のため、本試験での注意を述べたいのですが、長くなるので「問題文は命取り‐絶対的注意事項」に述べています。併せて、お目汚しください。
最後に、技能試験の教材については「第2種電気工事士・技能試験のテキスト・教材・工具」に述べているのですが、文系ド素人にとって、あると便利なものを紹介しています。
たとえば…、
「ホーザン 合格クリップ」や、
「ホーザン 合格ゲージ P-925」や、
「ホーザン 合格配線チェッカー Z-22」です。
絶対に必要かというとそうではありませんが、「手助け」にはなるので、万全を尽くしたい方は参考にしてみてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 2電工技能, 2017技能 | 2017年1月21日 10:49 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
候補問題8の独学ノート【画像あり】‐第2種電気工事士・技能試験(平成29年度‐2017年度)の攻略、手順、注意事項
平成29年度(2017年度)の、第2種電気工事士の技能試験の「候補問題8」の独学者向けポイントを見ていきます。
問題攻略の前に、「電源線で準備運動‐こころとゆびを慣らす」に、ざっくり目を通してください。
8の難易度は「ふつう」
結論から言うと、候補問題8は、あまり難しくありません。
本問に当たると、「ラッキー」とは行きませんが、「しめしめ、強敵ではないですぞ、西住殿」と秋山風に再現してみてください。
まず、本問は、左側の方にくちゃくちゃと図記号が固まっているので、一見難しそうですが、試験には影響ありません。
というのも、当該リモコンリレーは、端子台で代用されるからで、作業そのものは、難しくありません。
次に、アウトレットボックスですが、これも、単に「間違わないで組むだけ」なので、他の候補問題を消化していれば、間違うことはないでしょう。
ただ、本問は、アウトレットボックスに、ケーブルを都合7本、突っ込むことになるので、「180度曲げ」は必須です。
あとは、リングスリーブで「中」を使うのと、「VVR 2.0-2c」の施工があるくらいが、留意点です。
リモコンリレー対策
リモコンリレーは、本試験では、おおむね、端子台で代用されます。
ですから、「端子台」の作業の練習をしておけば、それで事が済みます。
ここだけを、使用済みケーブルで、最低3回は、組んでおくとよいでしょう。
なお、リモコンリレーの理屈は、念のため、テキストで確認しておいてください。万が一、試験問題を変えられると、暗記では対応できないからです。
“端子台の背景には、このような理屈があるのだなーふーんー”程度でいいので、担保として、見ておきましょう。
手間取るアウトレットボックスは180度曲げ
本問の特徴は、リモコンリレー代用の端子台からのケーブル・3本を、ボックスの「1つの穴」に入れるところです。
文字だけならなんてことはないですが、実際にやると、かなりキツキツで、硬いケーブルが互いに干渉して、接続にかなり手間取ります。
ですから、恒例の必殺技「180度曲げ」をやってみてください。
上記ひどい図のように、ケーブルを入れたら、“くっ”と180度曲げて、へんな言い方ですが、元に戻すみたいに、曲げてしまいます。
こうすると、電線を格段に把握しやすくなるので、接続間違いが、劇的に少なくなるはずです。
ところで、リモコンリレーからの3本のケーブルですが、狭い1つの穴に突っ込むことになるので、雑にやるとゴムブッシングが取れたりします。
ゴムブッシングが取れていると、「欠陥」で即落なので、注意しましょう。イライラするのはわかりますが、丁寧に施工します。
接続は、指差し確認
本問の特徴は、先述したように、ボックス内で、「7本」ものケーブルを接続するところです。
かなりの量となるので、落ち着いて、1つ1つ、確実に接続します。
何回も言いますが、あわてて接続を間違えると、修正には2~3分もの時間がかかります。
40分しかない本試験では、2~3分のロスは致命的なものとなります。
「ミスゼロ」の1回で終わらせられるよう、「指差し確認」しながら、接続してください。
ちょっぴり注意3点
本問で、強いて難儀と言えるのは、「VVR 2.0-2c」ケーブルです。
VVRケーブルは、外装をはぐのに、結構神経を使います。
中にある電線の絶縁皮膜に大きな傷がつくと、『欠陥』を取られて即落ちです。
テキストでは電工ナイフを使っていますが、わたしは、ストリッパでギリギリっと裂け目を入れて、後はペンチで外装を引っ張っていました。
こうすると、中の絶縁皮膜に傷がつきようがありません。
要は、絶縁皮膜に傷がなければいいので、各自、自分がうまくいくようにやってみてください。
次に「リングスリーブ」です。
本問では、あまり顔を見せない「中」が登場します。
つい、いつもの調子で、「小」や「極小」で接続しないようにしましょう。
他のページでも言っていますが、電線を接続するときは、必ず、リングスリーブの大きさと刻印(圧着マーク)を「指差し確認」して、さらに「もう一度、指差し確認」をして、がちゃんと接続します。
『リングスリーブを間違うと、修正がクソ面倒。3~5分かかる。』です。
最後に「端子台のねじ」です。
最後の最後に、端子台のねじを増し締めしてください。
というのも、見直し時に、端子台をいじる可能性があるからです。つまり、ねじを緩めて、ずれた接続を再接続したはいいが、そのまま忘れてしまった、という危険がある、ってな次第です。
本試験ではかなり緊張しているので、ねじを緩めたことを忘れる、と仮定してください。
ねじがきちんと締まっていないと「欠陥」で即落ちです。
ですから、念のため、最後の最後で、締まっているとは思うけれども、ねじを増し締めする、といった寸法です。
ここまで意を払えれば、まず、合格です。
なお、念のため、本試験での注意を述べたいのですが、長くなるので「問題文は命取り‐絶対的注意事項」に述べています。併せて、お目汚しください。
最後に、技能試験の教材については「第2種電気工事士・技能試験のテキスト・教材・工具」に述べているのですが、文系ド素人にとって、あると便利なものを紹介しています。
たとえば…、
「ホーザン 合格クリップ」や、
「ホーザン 合格ゲージ P-925」や、
「ホーザン 合格配線チェッカー Z-22」です。
絶対に必要かというとそうではありませんが、「手助け」にはなるので、万全を尽くしたい方は参考にしてみてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 2電工技能, 2017技能 | 2017年1月21日 10:47 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
候補問題7の独学ノート【画像あり】‐第2種電気工事士・技能試験(平成29年度‐2017年度)の攻略、手順、注意事項
平成29年度(2017年度)の、第2種電気工事士の技能試験の「候補問題7」の独学者向けポイントを見ていきます。
問題攻略の前に、「電源線で準備運動‐こころとゆびを慣らす」に、ざっくり目を通してください。
7の難易度は「やや難」
最初に大事なことを言うと、候補問題7は、難しい部類に入ります。
上の画像を見てもらえばわかるように、本問は、「4路スイッチ」という「難易度の高い」論点があります。
本問は、徹底して、当該「4路スイッチ」の練習をしておく必要があります。
「40分」しかない本試験では、考える時間などありません。考えるよりも、先に手が動くまで、練習あるのみです。
なお、本問には、「アウトレットボックス」が登場しますが、そう気に病む必要はありません。
ケーブルを突っ込むだけだからです。
しかし、接続の際に、ケーブルが思っている以上に、ごちゃごちゃするので、後述する「180度曲げ」に慣れておいてください。
4路スイッチ攻略‐暗記する
端的に言うと、「4路スイッチ」は、結線の手順を暗記します。
本試験では、考えている時間はないので、「この線とこの線をつなぐ」と決めてかかってください。
3路スイッチは黒0
まず、3路スイッチの「0」には、黒を結線することを、頭に叩き込みます。
要は、3心の黒の電線を、3路スイッチの「0」に差し込む、という寸法です。
言うまでもありませんが、3路スイッチは2つあるので、両方とも、「0」に黒です。
当該「0黒」の作業は、4路スイッチの作業の一番最初にやりましょう。
というのも、当該「0黒」は、極性の指示があるからです。
おおむね、本試験の施工条件では、3路スイッチの「0」に、黒が指定されています。
なので、「0」をいの1にやれば、採点部分の(接地極)はクリアできるので、気が楽になる、という次第です。
なお、残る「1」と「3」は、色の指定がないのが通例です。
とにかく、「0」に「黒」を最初にやるよう、『手順化』しましょう。
結線の色を決めておく
さて、先述したように、3路スイッチの「1」と「3」は、例年、色の指定がありません。
しかし、本試験で迷わないために、どの色にどの色を組むかを、練習時に決めておきます。
わたしは、3路スイッチの「1」には白の電線を、「3」には赤をつなぐように、『手順化』していました。
んで、上の画像の青の点線部分(『左』の3路スイッチとアウトレットボックスに向かう3心ケーブル)のところは…、
赤と赤
白と黒
…をつなぐように、『手順化』していました。
同色の赤を繋いで、残った同士、ってな塩梅です。
番号を丸暗記
うんざりしますが、取り合えず、言葉で述べます。
3路の右側の「1」は4路の「1」で、3路の「3」は4路の「3」です。
残りの、3路の左側の「3」は4路の「2」で、3路の「1」は4路の「4」です。
文字にするとウンザリしますが、要は、右は「1-1、3-3」で、左は「3-2、1-4」と丸暗記して、スイッチ間を接続する、という塩梅です。
右は同じ番号同士と憶えればすぐですが、左の方は「3・2、1・4」と無規則なので、ブツブツ唱えて憶えましょう。
また、試験が始まったら、下の画像のような「絵」を書いておくと良いでしょう。
こう憶えて「手順化」して憶えてしまえば、本試験では迷いなく作業できます。
上記のように、1つ1つの作業を『手順化』して身体に憶えこませておけば、本試験では、まず失敗しません。
とにかく、ここも「練習あるのみ」なので、4路スイッチ部分だけを、何回も何回も、最低3回は組む練習をしましょう。
アウトレットボックスの基本
本問では、アウトレットボックスが出てきますが、本試験では、穴が既に空いている筈です。
本試験では、向かって上が北として、北側に穴1、東に穴2、南に穴1、西に穴1の状態で、ボックスが配られるはずです。
まず、当たり前なのですが、穴が空いている以上、ケーブルを入れるところが決まってしまうので、正確に、ボックスにケーブルを挿入します。
反対に言うと、適当にケーブルを入れてはいけない、ってことです。
なお、間違ったところに入れると、「誤接続」で即落ちします。
また、ほとんどいないと思いますが、勝手に穴を開けると、欠陥の「損傷」で即落ちします。
本試験では、まず穴が空いているので、余計なことはしないように!
180度曲げ
各ケーブル類を正確に差し込んだ後の、一工夫を述べておきます。
「180度曲げろ」です。
下手な図ですが、この画像のように、接続の際は、ケーブルを“くっ”と、180度、曲げてしまいます。
アウトレットボックスにケーブルを、5本も入れると、まあもう、配線だらけで混乱のきわみです。
ですから、先のひどい図のように、180度曲げて、へんな言い方ですが、元に戻すみたいに、曲げてしまいます。
こうすると、ごちゃごちゃせず、電線を手で配線を追いやすくなるので、作業効率が上がります。
別に、ケーブルを曲げたからといって、欠陥をとられるわけではないので、やりやすいようにやりましょう。
最後に、ゴムブッシングの加工・取り付けですが、問題ないでしょう!
電工ナイフは、普段の練習でもほとんど使わないので、十字線を割くときは、手を切らないよう気をつけてください。
でもまあ、大丈夫でしょう。
指差し確認で確実正確
4路スイッチでの接続は、文系ド素人最強の技「指差し確認」を2回した後で、行ないます。
要領は、候補問題6の3路スイッチと同じです。
複線図の接続しようとする箇所を、(これとこれをつなぐ、よござんすね?)といった感じで、指でなぞり…、
次に、ケーブルの線と線とを指差しして…、
「このスイッチの○色の電線→真ん中3心ケーブルの○色電線をつなぐ、ヨシッ!」という過程を、
2回確認してから、リングなりコネクタなりで、ガッチャンコと接続します。(3回やるとめんどくさいので、わたしは2回してました。)
こうすると、ミスをしなくなりました。
なお、指差し確認を2回しても、ほとんどの練習では時間が余ったので、時間のロスにはならないはずです。
接続で失敗をしたことのある人は、ぜひとも、「指差し確認」を導入してみてください。
その他の箇所
4路スイッチ以外は、ふつうなので、問題はないかと思います。
また、接続のリングスリーブは、おおむね、「小」と「極小」を使うはずです。
他のページでも言っていますが、電線を接続するときは、必ず、リングスリーブの大きさと刻印(圧着マーク)を「指差し確認」して、さらに「もう一度、指差し確認」をして、がちゃんと接続します。
というのも、『リングスリーブを間違うと、その修正がクソ面倒だから』です。
間違った接続部分を切り取り、ケーブルの外装を剥いで、電線の被膜を取るという“時間ロス”の権化です。
おおむね3分は、下手をすると5分は時間を取られます。
本試験は『40分』ですので、当該ミスが、いかに危ないか、お分かりかと思います。
指差し確認の時間は、間違ったことを考えれば、『絶対に、あり』です。
なお、「施工省略」のところは、ちょっとだけ注意しておきます。
テキストの指示通りの「施工省略」作業を徹底してください。
てきとーにやっていると、本試験の最中に(アレ、施工省略ってどうしてたっけ?!)と、軽くパニックに陥ります。
なお、念のため、本試験での注意を述べたいのですが、長くなるので「問題文は命取り‐絶対的注意事項」に述べています。併せて、お目汚しください。
最後に、技能試験の教材については「第2種電気工事士・技能試験のテキスト・教材・工具」に述べているのですが、文系ド素人にとって、あると便利なものを紹介しています。
たとえば…、
「ホーザン 合格クリップ」や、
「ホーザン 合格ゲージ P-925」や、
「ホーザン 合格配線チェッカー Z-22」です。
絶対に必要かというとそうではありませんが、「手助け」にはなるので、万全を尽くしたい方は参考にしてみてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 2電工技能, 2017技能 | 2017年1月21日 10:40 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |