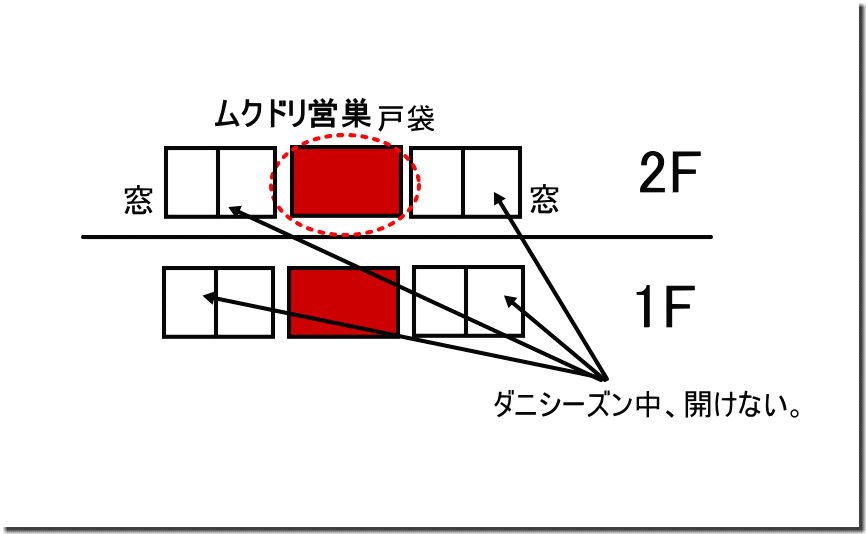ダニ(イエダニ)対策3‐閉鎖編
本ページでは、ダニはダニでも、イエダニ対策の「閉鎖」について、見ていきます。
一口で言えば、イエダニの沸いた部屋には、梅雨のシーズン中に、入退室を禁止するといった塩梅です。
なお、他のダニ対策としては、「イエダニ対策1‐ダニスプレー編」や「イエダニ対策2‐避難編」も、併せて参考ください。
閉鎖して入らない
イエダニが沸いた部屋は、ダニスプレーを撒くときや、よほど必要なものを取りに行くとき以外は、『原則として、閉鎖』します。
ダニシーズン中は、人の出入をしない、といった寸法です。
換気もしません。当方、1~2ヶ月、締め切っています。
なぜなら、イエダニに換気は効かないからです。
当方、一日中、開けっ放しにしていましたが、イエダニの被害が減ることは“一切”なく、『換気』はイエダニに無効と判断します。
逆に、イエダニが外から侵入したり、部屋に湧いたイエダニが拡散する恐れがあるので、窓を開けないほうがいいくらいと考えます。
こういった次第で、イエダニ部屋は閉鎖してしまいます。
いうまでもなく、掃除もしません。
ダニスプレーを満遍なく撒いたら、イエダニの活動は、ほぼ沈静化します。
掃除をしたら、さらに何倍もイエダニが死ぬ、というわけでもないので、掃除機等の作業は必要ないでしょう。
アレルギー体質の人で、ダニの屍骸がダメなど、相応の理由がない限り、掃除する必要はありません。当方は、1ヶ月以上は、ほったらかしです。
閉鎖部屋への入退室は注意
さて、いくらダニスプレーを撒いているといっても、イエダニが根絶したわけではありません。
人は、イエダニのエサで、吸血対象です。部屋に入った際に、「部屋に入った人間」に引っ付く可能性がないわけではありません。
んなもんで、何か用事があって、イエダニ部屋に入る際は、ダニスプレーを撒いたときに着用した、頭巾付きのビニル製の服を装備し、アレルゲン対策用のマスクも併せて装着します。
同様に、専用スリッパで入退出します。地肌や靴下が、イエダニ部屋と接触することは、避けるべきです。
言うまでもなく、これらの処置は、「2次感染」を防ぐためです。
神経質すぎるかもしれませんが、「イエダニ」の猛烈な痒みと不快感を思えば、「打てる手はすべて打つ」のが賢明かと思います。
イエダニは、咬んだ際に吸血します。吸血したイエダニは、数日以内に卵を産んで、次世代のダニを産生するとのこと。つまり、咬まれたら、新たなダニの発生という塩梅で、イエダニの発生ループは、確実に断つべきです。
イエダニ部屋への入退出をしっかり管理することで、イエダニの被害の拡散を防止できます。
イエダニの沸いた部屋は、閉鎖して、入らない。
入るときは、万全の注意をしてから、入室する。
上記2つを、徹底してみてください。イエダニの発生率と、心の重荷がかなり減るはずです。
イエダニ側は、窓開けない
結論から言うと、イエダニ発生源周辺の開口部は、つまり、窓は閉鎖する、といった塩梅です。
窓が開いていると、イエダニが入ってくると考えられるからです。
先述したように、当方のケースは…、
野鳥の「ムクドリ」が「戸袋」に「営巣」し、雛が生まれた。当該雛が巣立った後、巣に寄生していた「イエダニ」が移動し、当方の生活圏に侵入してきた。
…となっています。
何回かイエダニの被害を蒙ることになってわかったのは、「イエダニは、日光がそう怖くない。直射日光で死ぬわけではない」です。
イエダニが湧いたところは、「南側」で、とても日当たりがよいところなのです。1日中、日が当たっています。
最初は、「あんだけ日に照らされるところだから、ダニが移動しようとしたら、直射日光で即死だろう」と思っていたのです。
しかし、イエダニ対策を執っても咬まれ続ける日々が続き、あるとき、ふと、(窓から入ってるのかもしれない?)と思い到ったのです。
それがビンゴでした。
2階の窓はいうまでもなく、1階の窓も完全に締め、ほいで、窓のさんの部分に消毒液を撒いておくと、イエダニの被害が減ったという寸法です。
当方の実感ですが、窓からイエダニが侵入する可能性は大、と結論付けています。
ちなみに、この「窓の締め切り」を行なった年は、イエダニ発生は「2回」で、咬まれたのは「8箇所」で済んだ次第です。例年と比べると、激減しました。
窓を閉め切ると少々暑苦しいですが、イエダニのシーズンはおおむね6月なので、まだ我慢できます。また、反対側の窓は開けられるので、換気的には大丈夫です。また、早めに空調を入れることもできます。
先の画像を参考に、一度、窓の閉鎖を試してみてください。当方は、“かなり有効”であると考えます。
言うまでもないですが、イエダニが沸いた側で、洗濯物を干すのも止めたほうがよいでしょう。
予想以上にイエダニは移動しますし、また、野鳥が飛ぶ際に、ダニが拡散している可能性も否定できません。
洗濯物にイエダニが付着する可能性もゼロではありません。干す場所を変えたり、部屋干しにしたりして、試してみてください。ダニが減れば御の字です。
まとめ
以上、「閉鎖」についてみてきました。
当方、イエダニの発生した部屋に、無闇に出入りしたため、他の部屋にもイエダニを拡散させた苦い思い出があります。
イエダニが屋内で拡散すると、ダニ対策も倍々なため、肉体的、時間的、そして、精神的に、追い込まれます。
ダニスプレーを撒くなど、対策を執ったなら、その部屋には入らないようにしましょう。
入室禁止は、梅雨の1~2ヶ月です。そのくらいなら、入らなくても何とかなります。
また、イエダニが沸いた側の窓の「締め切り」も、意外に有効だと思います。
できることは何でもやって、皆さんと配偶者以外の家族のイエダニの被害を抑えてください。あいつのは天罰。天網恢恢。
なお、他のダニ対策としては、「イエダニ対策1‐ダニスプレー編」や「イエダニ対策2‐避難編」も、併せて参考ください。
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: イエダニ | 2017年8月24日 10:15 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
臭う洗濯物は、電子レンジで加熱するか、お湯で煮る
結論から言うと、重曹で洗っても臭う洗濯物は、①電子レンジで加熱する(注意事項あり)か、②お湯で煮た後で、重曹洗濯すると、かなり臭いが取れる、という塩梅です。
ベースは重曹洗濯
重曹で洗濯すると、洗濯物の生乾き臭やアカ染みた臭い、汗臭さ、雑菌臭を押さえることができます。
従って、配偶者のいる家では、重曹をかなり重宝するはずです。
しかし、向こうもさるもので、“洗濯したにもかかわらず、獣並みの異臭がする”ケースが多々生じます。
被害が多い洗濯物は、ハンカチ、ハンドタオル、タオル、シャツなど、肌に直に接するものが多いです。
おそらく、洗濯物に雑菌が湧き過ぎて、洗濯しても、日光に晒しても、雑菌が居続けているのかと思われます。配偶者由来の雑菌は、あのバイキンマンですら嫌な顔をして、温厚なアンパンマンすら舌打ちするくらいですから、仕方ありません。
こうした、臭いが取れなくなった洗濯物は、先述したように、レンジで過熱したり、お湯で煮たりすると、格段に臭いが取れる、という次第です。
【重要】レンジ加熱は危険な作業
洗濯物の電子レンジ加熱は、重大な注意事項があります。必ず守ってください。
遵守すべきは、洗濯物は水で濡れた状態で加熱する、です。
乾いた状態の洗濯物を加熱すると、「火災」が生じる危険があります。
当方、乾いた状態のTシャツを加熱したところ、異臭と煙が生じ、Tシャツが炭化して真っ黒に焦げていました。
即、レンジを停止したので、事なきを得ましたが、1つ誤れば、火事でした。もし、台所に煙感知器があったら、即、作動して、えらいことになったはずです。
そもそも、洗濯物を、電子レンジで加熱することは、電子レンジの目的外の使用です。
「ヤバイ」ことをやっていると、意識してください。
洗濯物の湿り気の目安は、洗濯機の脱水後くらいの水分量です。このくらい水ッけがあると、加熱時に水蒸気が発生して、雑菌を蒸し焼きできます。
また、電子レンジの加熱時は、レンジから離れないでください。異変があった場合、つまり、異音や異臭がした場合、即、機械を停止できるようにするためです。
言うまでもなく、ファスナー等の金属部品のあるものを、電子レンジで加熱しては行けません。
また、一度に大量の洗濯物を、加熱してはいけません。電子レンジのモーターが消耗して、故障の原因となります。
レンジによる加熱は、タオルなら1枚、シャツも1枚、ハンカチ・ハンドタオルなら2~3枚が限度です。
このように、レンジ過熱は、注意事項が多いので、必ず守った上で、加熱してみてください。
劇的に臭いが取れます。
煮沸はお湯に注意
沸騰したお湯で5分、弱火で洗濯物を煮れば、ほぼ雑菌は滅失しています。
パスタをゆでるときに使う、大きめな鍋で、臭う洗濯物をぐつぐつしてください。
先のレンジ加熱と同様に、格段に臭いが減ります。
さて、洗濯物を煮る場合は、徹底して、「火傷」に注意してください。
大き目の鍋で煮るため、予想以上の湯量です。
加えて、鍋で衣類等を煮るのは、“慣れない作業”のため、予想外の事故がありえます。
“危険な作業をしている”と意識しながら、臭う洗濯物を煮てください。なお、配偶者も煮たくなりますが、配偶者を煮ると鍋がひどく汚れるのでやめましょう。配偶者は、煮ても、焼いても、揚げても、蒸しても食えないことを思い出してください。
また、鍋で煮た洗濯物を取り出す際は、『重量』に注意してください。衣類はかなりお湯を吸うので、想像以上に重いです。
「トング」を利用し、しっかり洗濯物をつかんでください。菜ばしだと、お湯を吸った洗濯物の重量に耐え切れず、落としたりして熱湯に接触する可能性があります。
そこそこ危険な作業なので、作業中は、子供を近づけてはいけません。居るだけで邪魔な配偶者はケージに入れておくか、エサをたくさんあげて気だるくしておくとよいでしょう。
こうした次第で、お湯で煮ると、格段に臭いは減ります。大量の洗濯物の臭いに悩んでいる方は、お試しください。
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: 洗濯物, 消臭, 重曹 | 2017年7月3日 12:38 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
第2種電気工事士の技能試験は下手に予想しない
結論から言うと、「2電工の技能は、下手に予想して山勘で作業するより、難しい候補問題に絞って練習するほうがよい」という塩梅です。
候補問題には、難易度の差がある
「要注意リスト-2017年(平成29年度)2電工・技能候補問題のまとめと整理」でも述べていますが、全13問の候補問題の難易度には、ばらつきがあります。
“ものすごくヤバイ候補問題”もあれば、そうでないのもあります。
先のリンク先のページでも述べていますが、本年度の候補問題のうち、 ガチ難問は「1つ」で、要注意の問題は「4つ」となっています。
わたしは、下手に(これとこれとこれ)的に予想して、当該予想した候補問題だけを練習するより、先の「1つ」と「4つ」の“ヤバイ候補問題”に絞って練習するほうが、格段に受かりやすくなる、と考えます。
難易度が「ふつう」や「やさしい」問題は、先の難問題を繰り返しておけば、何とか解けて(ミスなく組めて)しまうのです。
対して、“ヤバイ候補問題”は、どうしても、それ相応の練習をしない限り、どこぞでポカをしてしまうため、受からないのであります。
理想は、「全候補問題を、等しく練習すること」です。しかし、現実には、時間という問題があります。
んなもんで、時間に余裕のない人は、根拠のない予想より、先の“ヤバイ候補問題”に尽力するほうが、「合格の可能性はまだしも上がる」といった次第です。
すべてをやらずとも
候補問題を、丸々組み上げる必要はありません。
難しい作業と複雑な施工は、「固有部分」にあります。大事なのは「全体」ではなく「部分」です。
「固有部分」に絞った練習なら、たとえば、3路スイッチの問題なら3路スイッチだけ組むとか、ねじなし管の取り付けだけをするとかなら、1回当たりの試験勉強を、『15~20分程度』に収めることができます。
ほいで、時間のある休日に、“通しで全部を組み立てる”ようにすれば、少ない時間を有効に活用できるかと思います。
技能は、どうしても、ある程度の練習量が必要です。
忙しくて時間と体力が不足気味でも、やりようはあります。
優先順位の高い候補問題の、優先順位の高い固有の難作業から消化して行けば、最低限度の“受かる”練習量を確保できるかと思います。
また、序盤・中盤で、難しい奴を倒していると、気が楽です。「やさしい」「ふつう」系の候補問題も、難しいのができたら、まあ作れます。
配偶者等の妨害に耐えつつも、少しでも実のある勉強をしてみてください。
(なお、技能の勉強は、少しアルコールが入っていても大丈夫です。ほとんどの試験勉強は、勉強中の飲酒は厳禁ですが、話が技能だとまあOKです。晩酌のアテにやるのもよいでしょう。わたしはビール片手にやってました。酔っていても、正確かつ確実に組み立てられるほうが、本試験では心丈夫です。なお、工具由来の怪我には注意してください。)
最後に、技能試験の教材については「第2種電気工事士・技能試験のテキスト・教材・工具」に述べているのですが、文系ド素人にとって、あると便利なものを紹介しています。
たとえば…、
「ホーザン 合格クリップ」や、
「ホーザン 合格ゲージ P-925」や、
「ホーザン 合格配線チェッカー Z-22」です。
絶対に必要かというとそうではありませんが、「手助け」にはなるので、万全を尽くしたい方は参考にしてみてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 2電工技能, 2017技能 | 2017年6月16日 10:06 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |