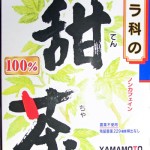甜茶で花粉症由来の鼻づまりがなくなっていることに気づいた
「花粉症」については、わたくし自身が既往歴:4分の1半世紀を誇りますので、適当に「効いている」ものを雑文にまとめさせていただいております。
そこで、毎年の如く言っているのが、「花粉症には甜茶」で主張です。
甜茶は、何分にも漢方系のお茶でありますので、個人差はあるように思われますが、少なくとも、わたくしの花粉症を抑えることには成功しております。
当該甜茶ですが、飲むとしばらくは、花粉症の諸症例は収まるのです。
しかし、飲んで時間が経てば、目もかゆくなるし、くしゃみも出るようになります。鼻水も出ます。
しかし、最近になって、「鼻づまりが全く起きなくなった」ことに、わたくしは気づいたのであります。
気づくのが遅くなったのは、まさに、ここずっと、「鼻づまり」がなかったからであります。
花粉症で鼻づまりの人と話していて、(そういや、以前は鼻づまりになってたのに、最近は全く鼻が詰まらなくなったなあ)と思い為したのであります。
小中高と、大概、鼻が詰まってたのになアと、のんきに往時を思い出したくらいであります。
あれこれ調べてみると、甜茶は「鼻づまり」に効くようなのであります。
そして、甜茶の対鼻づまりに対しては、かなり効いている人間が、ここに1人ございます。
鼻が詰まると、何とも隔靴掻痒で、じれったいものがあります。鼻水が出だすとかみにくくなって、往生するものであります。
先も言いましたように、甜茶を飲んだからといって、花粉症の諸症例のすべてを抑えられるわけではありません。
そして、ずっと効くわけでもありません。
しかし、「鼻づまり」に関しては、結構な威力と長時間の効能があるように、体感している次第です。
わたくしは、朝一杯飲んで、日中こまめに口を潤していますが、丸一日、鼻づまりになっておりません。だからもう、鼻づまりの存在を忘れるくらいです。
花粉症由来の鼻づまりで往生しておられる方は、ぜひ、甜茶をお試しくださればと存じます。
わたしの作り方はごくごくカンタンで、2パックをボールに入れて、熱湯を注いで一晩置くだけです。
甘いのが好きなので、熱湯は2パックで800ccほど注いでいます。これで、一日は持ちます。
数千数万円もかかるわけでもないので、薬局かドラッグストアにて購入して、お試しくださればと存じます。
効けば、ホント儲けものです。
なお、わたくしは、例年、山本漢方製薬株式会社の甜茶を飲んでおります。
ドラッグストアで大概取り扱っているので、お困りの方はお試しをば。
価格参考amazon:山本漢方製薬の甜茶
| カテゴリー: 日々の暮らし | | 2013年3月12日 7:02 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
帽子をかぶって花粉が髪の毛に付くのを防ぐ
「帽子」が、何気に花粉症の諸症例に効くという、わたくしの体験記でございます。
タイトルそのまんまで恐縮ですが、花粉症対策の一手に加えてくださればと存じます。
花粉症対策といいますと、薬を飲むとかマスクをするとかメガネをかけるというのが一般的であります。
多くの方が、『マスク』でとどまっております。
しかし、今年はぜひとも、「帽子」を加えてくださればと存じます。
屋内や室内なら別に帽子は要りませんが、外出する際は、可能な限り、帽子を被るべきでございます。
帽子を被っていると、帰宅なり帰還後の、花粉症の症例がかなり抑えられるのであります。
その理由を愚考するに、おそらく、「帽子が髪の毛に花粉が付くのを防ぐから」ではないかという次第でございます。
わたくしは、幼少のころからの花粉症者なのですが、「帽子を被って帰宅すると、くしゃみが出にくい」ことを発見したのであります。
帽子をかぶらなかった以前は、外から帰宅すれば、くしゃんくしゃんと大きなくしゃみをしておりました。
しかし、先述したように、外出の際は帽子を被るようにすると、如実にくしゃみの回数が減ったのです。
何しろ、依然は血が滲むくらいに、毎日多数のくしゃみをしていたのです。それこそ、脳震盪でふらふらするくらいです。
それが、かなり激減したのです。むずむずで終わるのです。
帽子をかぶってなかったときは、さぞかし、花粉が髪の毛に付着の上に付着して、それを屋内に運んでいたんだなあと、実感した次第です。
髪の毛みたいな繊維たっぷりのところには、花粉が絡みやすいもの。
手術をするときは、切る周辺の毛を全部剃るといいますが、それは、毛には細菌なりゴミなりが多数存在している、つまり、「小さいものが居やすいところ」とも言えるわけでございます。
当該小理屈を髪の毛と花粉に当てはめたところ、“ビンゴ”という次第です。
単に、外出の際に帽子を被で、結構な差があると思われます。
普段帽子を被らない人は、ぜひとも、花粉作用対策の一環として、帽子をお試しください。
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: 花粉症 | 2013年3月7日 2:02 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
間違いは、「はよ気づいてよかったわ」で行く
お勉強というのは、「間違い」があって当然の作業でございます。
そもそもが、できないことや知らないことを学習しているのですから、「できる方がおかしい」のであります。
お勉強に間違いは不即不離のものでありまして、それほど、大騒ぎするものでも、悲嘆に暮れるものでもないのでございます。
そこで、間違いの対処法としては、タイトルにありますように、「はよ気づいてよかったわ」の心持にて向かい合うべきかと思います。
間違いというのは、そのときは何だか気分の悪いものです。
しかし、その間違いは、本試験で犯したものではありません。
つまり、今、その間違いをすることであって、下手をすれば本試験時にやっちゃったかもしれない間違いを知ることができた、と考えるのでございます。
「今」は、いくらでも間違ってもいいときであります。
なぜなら、「本試験」を受けているわけではないからです。
間違いというのは、「はやく知れば知るほど」、その間違いに対して対処法と対応策を練ることができます。
そして、いち早く間違いを知って手当てをするほどに、「他の間違いをつぶす」時間的余裕を持つことができます。
間違いをつぶせば、もうその間違いは間違いという“失点”ではなくて、“得点”となるのはいうまでもありません。
間違いをつぶすと、点数が伸びるのも自明の理なのであります。
間違ったからといって、ウダウダしたり落ち込んだりする前に、その間違いをいかに活かすかに、思いを致すべきです。
合格者といいますのは、勉強ができる人というのではなくて、、「間違いをたくさん知っている人」と言い換えることができるように存じます。
| カテゴリー: 勉強ワンポイントアドバイス | Tags: 失敗 | 2013年2月25日 1:58 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |