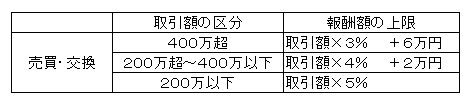不動産3資格(宅建、管業、マン管)の違い
代表的不動産資格の宅建、管業、マン管には受験資格がないので、独学で挑戦しやすい資格です。
とはいえ、一見だけでは、どの資格がどんな塩梅なのかよくわかりません。
そこで、当該3つの不動産資格の資格の価値や優先順位、求人数や難易度など、その違いを見ていきたいと思います。
優先順位
結論から言うと、取得すべき優先順位は、『宅建→管業→(マン管)』です。
マン管を“括弧掛け”しているのは、別段、取らなくてもいいからです。
マン管はコンサルタント資格であるため、“腕に憶えのある人”以外は、取得しても、まあ活きません。
だから、『宅建→管業』と取って、腕なり力なりを蓄えてから、括弧掛けに挑戦するとよい、という寸法です。
難易度
かいつまんで言うと、マン管はコンサル資格であるため、一番「難しい」資格となっています。
次に難しいのは宅建ですが、きちんと勉強したら取れるので、「普通」といっていいでしょう。
管理業務主任者は、先の2資格と比べると「易しい」ですが、“運”で取れる資格ではないので、甘く見てはいけません。
難しい順で並べると、『(マン管)→宅建→管業』です。
合格率
マン管は、おおむね「8%」台です。
9割近くが落ちるので、難関資格といっていいでしょう。
宅建と管業はおおむね「20%」台と、マン管に比べると数倍の合格率ですが、それでも8割前後が落ちます。
楽して取れる資格ではありません。
勉強時間
マン管はおおむね「500~600時間」で…、
宅建は「300~400時間」くらいで…、
管業は「200~300時間」といったところです。
とはいえ、被っている試験科目が多いのが3資格の特徴です。
たとえば、民法は、上記3資格全てで出題されます。
民法以外にも、区分所有法は管業とマン管で多数が、宅建でも少数が出題されます。
出題形式も似たようなものが多く、業者規制などは、実質的にやる内容は同じです。
このように、試験科目の被りも多いので、3つのうち1つでも取っておくと、他の2つの勉強時間の短縮できます。
ですから、先の数字はあくまで目安、と相なります。
わたしの場合、管業の受験の際は、宅建を持っていたので、1.5ヶ月で合格できました。
資格の価値
宅建と管理業務主任者は、設置が義務付けられている必置資格であり、法的需要があります。
まず、筆頭の宅建ですが、宅建の取得者がいないと、不動産業を営業できないし、契約も締結できません。
町の不動産屋には、例外なく、宅建の有資格者がいます。
業者にとって死活に関わるので、有資格者はそれなりに評価されます。
次に、管業ですが、一定規模のマンション管理業者は、管理業務主任者の設置と、彼による業務遂行を義務付けられています。
このように、宅建と管業は、不動産業やマンション管理業で一定の法的需要があるので、資格の価値は高くなっています。
対して、マン管は、名乗るだけの名称独占資格でしかないので、これといった法的な需要もありません。
求人数
当該3つの不動産資格の求人数ですが、如実に資格の価値を反映しています。
求人がダントツに多いのは宅建で、「平均で1,200件前後」前後の求人が常にあります。
ちなみに、ハロワの登録資格のうち、2015年度7月期のTOP100中、54位に入っています。
次に求人数が多いのは管業で、「平均100件」という数字ながらも、資格の中では求人のある方です。
マン管の求人は、ハロワには「実質ない」と考えていいです。「平均15件」前後しかありません。
まとめ的なもの
宅建、管業、マン管という不動産3資格は、資格の価値や難易度、勉強時間からして、「宅建→管業→(マン管)」という順番で取ればいいです。
ですが、法律的素養の全くない人は、手始めに、基本的な問題が多い管業から、手を付けるのも『1手』です。
というのも、宅建は難化傾向にあるので、ややもすると挫折しかねないためです。
比較的易しく、捻った問題の少ない管業で不動産関係の法知識を蓄え、その後で、つまり、来年に宅建に挑戦する、というのも、初心者向けの学習計画に挙げられるかと思います。
まあ、受からない試験じゃないので、やる気と時間のある人は、10月の宅建、12月の管業と受けるとよいでしょう。十分、合格できます。
マン管は、“お好きに”です。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: マンション管理士, 宅建, 管理業務主任者 | 2015年10月6日 10:23 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
ネットスクール新教材メモ-日商簿記2級に合格するための学校レビュー
一口で言うと、新しいとおる簿記シリーズの「日商簿記2級に合格するための学校」は、保留で、様子見です。
わたしが「とおる簿記シリーズ」に求めているのは、“そういうものではない”という塩梅です。
端的に言うと、新シリーズは、“良質な”簡易版です。
新・とおる簿記シリーズ
簿記2級の独学の定番教材だった「とおる簿記シリーズ」は、出題区分の大改定もあったことから、すべて刷新され、装い新たに「日商簿記2級に合格するための学校」となりました。
それぞれに、テキスト(TEXT)と問題集(EXERCISE)とがあります。
当該「日商簿記2級に合格するための学校」は、他の粗製乱造された教材と比べたら、“悪くはない”テキストと問題集です。
新・とおる簿記シリーズは、旧シリーズの長所は踏襲されており…、
①文章には、会計用語を多用せず、会計チックなものに極力しない努力。
②読み易さに徹したレイアウト、文字数を抑える工夫。
③イラストやコラムによる学校的演出。
…といったよい点はたくさんあります。
加えて、新シリーズからは、過去問の解き方が追加されており、過去問との橋渡し的な役割も担っていて、“悪くはない”テキストと問題集に仕上がっています。
しかし、“悪くはない”だけで、決して手放しで推薦できるものではないのです。
ダメ教材ではない。
ダメ教材によくあるケースは、表紙で「わかりやすさ」を全面的に打ち出しているのに、内容は大学の教科書や会計規則集から文章をコピペしただけで、一切まったく噛み砕いておらず、一言で言えば、読み手を舐めている教材です。
かわいらしいイラストと歯切れのいいだけの短文を多用すれば、手にとってくれるし買ってもくれる、そして、大半の買い手は最後までやらないし受験もしないから、“この程度でいい”という出版社のマーケティングが透かし彫りのダメ教材は、本屋の簿記コーナーの棚を結構占めています。
対して、新・とおる簿記シリーズは、こうしたダメ教材とは、一線を画した“作り手の見える教材”であることは間違いありません。
どうすれば「わかる」か、「理解できるか」をシッカリ考えた上で、文字を起こし、編集し、製品化しています。
新しい工夫を、随所に施しています。長文でウンザリしないよう、改行を多用してセンテンスを短く・読みやすくする独特のレイアウト、などです。
よくある、有象無象のダメ教材では決してありません。
しかし、わたしは、先述したように「保留・様子見」です。
「とおる簿記シリーズ」に求めていたもの
端的に言うと、新シリーズは、“良質な”簡易版です。
しかし、簡易になった分、文章は短めで、図(勘定連絡図的なもの)やイラストも少なくなっています。
キッチリ・徹底して・最後まで述べて説明すると長くなるし、冗長になるしで、ライト層からそっぽを向かれるのでしょう。
だから、簡易・簡潔にしたのでしょうが、やはり、新シリーズは、舌足らずなところが目に付きます。
Webや電話相談で補うことができるとはいえ、当該教材だけ完結していないというのは、いただけない、というのが感想です。
わたしが「とおる簿記シリーズ」に求めていることは、『冗長』でもいいし、『文章量が多く』てもいいし、『ブ厚くても』、『値段が高く』てもいいのです。
きっちり理解させてほしいのです。当該教材だけで試験勉強を完結させてほしいのです。
簡潔・簡明なだけの廉価な教材は、他にいくらでもあります。
しかし、そういう教示は、当然の如く説明が端折られていますから、後々、自分で調べたりしないといけないし、メールやら何やらで質問したりする羽目に陥ります。
わたくし事ですが、メールで相談してくる人の大半の教材は、だいたい簡易廉価版を使っています。
そういう手間が苦にならない人は別段構わないのですが、わたしは、そういうメンドクサイ作業を極力省きたいし、時間を割きたくないのです。そのため、教材にはお金をかけます。
もっと言うと、わたしが簿記2級の受験当時、簡易廉価版の教材を使ってドツボに嵌ったからこそ、同じ轍を踏まないよう、“本格派”を推薦している次第です。
ぶっちゃけ言うと…
本屋で当該新シリーズを目にはしていたのです。その時は、(ああ、ネットスクールも簡易廉価版出すんだ)という感想しかありませんでした。
しかし、とおるシリーズを、全面的に当該新シリーズ「合格するための学校」に切り替えるとは、思いもしませんでした!大丈夫か?
個人的な憶測ですが、マーケティング上、いちばんボリュームのあるライト層を狙った教材、と感じています。
本格版は、何かと簡易廉価版に押され気味なので、挽回の意図もあるのかなとも考えました。
悪くはない、新シリーズです。
が、“これだけで済ませたい・終わらせたい・他に余計なものを買ったりしたくない”という本格志向の人のニーズは、満たしません。
参考:日商簿記2級に合格するための学校【テキスト】商業簿記」
参考:日商簿記2級に合格するための学校【テキスト】工業簿記」
過去問は最良質
新しい教材は、“良質な”簡易廉価版となっていますが、一方の、過去問は大変優れています。
簿記2級の過去問は、常に最新の傾向が反映されたものを使ってください。
傾向を掴み損ねると致命的です。
「○月試験対応」といった文言を、購入の際はチェックしてください。
参考:日商簿記2級過去問題集(日商簿記に合格するための学校-とおる簿記シリーズ)
ま、簿記2級の教材は「教材レビュー」を参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記2級 | 2015年9月28日 12:04 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
宅建業者が受け取ることのできる報酬額の上限の憶え方-「3、4、5、6、2」
「宅建業者が受け取ることのできる報酬額の上限」は、宅建試験のみならず、FP試験でもよく問われるところです。
一般生活でも、憶えておくと何気に便利なことが多いので、この際、お勉強をしておきましょう。
(どうして不動産屋が丁寧な言葉遣いをするのか、積極的にセールス攻勢をかけるのか、当該報酬額を知ればわかるってもんです。2000万の中古マンションを決めたら、66万×2の132万の手数料収入ですよ。)
以下のように考えるとすぐ憶えられるので、ご利用ください。
なお、以下の述べるのは、消費税は除いていますし、復興系の所得税も無視しています。
これら消費税や所得税の額分を含めるか否かは、試験によって違いますので、問題の指示を丁寧に読んで、解答してください。
ひねくれた出題や選択肢だと、税抜きの金額だけが表記されていて、解答では「消費税が含まれていないので誤り」とかになりかねません。
3、4、5、6、2
結論から言いますと、宅建業者の数字の憶え方は、「3、4、5、6、2」と、“数字の並べ方”で憶えてしまいます。
もう、ピンと来た方もおられるかと思います。
上記の報奨額の上限表を、じっと見てください。
左の上から順に、3%→4%→5%、
次いで…、
右の上から順に、6万→2万、
…となっていますので、まずは、「3、4、5、6、2」と数字の順番で、主要な数字を憶えてしまいます。
ポイントは、最初を「3」から始めるところと…、
終わりがなぜか、「2」で終わるところです。
ずっと昇順なのに、なぜか最後は、唐突な「2」という数字で終わります。何気にクセがあって、ブツブツ唱えていたら憶えられるかと思います。
最後に2かよっ!的な、三村風の突込みを入れたら更に頭に残ります。
で、残る作業は、取引額区分をキッチリ憶え込みます。
でないと、正確な計算ができません。
取引額の区分は、カンタンです。
「400万」と「200万」の2つの数字しかないので、意識して何回も見ておけば、憶えられるはずです。
400万と200万・・・、結婚できる年収とできない年収なんて考えると、スッと頭に残るように思います。
まとめ的なもの
主要な数字は、「3、4、5、6、2」と数字の並べ方で頭に入れ…、
…で、取引区分の2つの数字を正確に憶えます。
こうすると、そう暗記暗記しなくても憶えられるように思われます。
なお、当該報酬額の上限は、知識問題のみならず、取引額から実際の報酬額を計算させる問題も出るので、落ち着いて計算できるようになっておきましょう。
なお、賃貸の場合は、「1ヶ月」だけなので、そう工夫を凝らさなくても憶えられるかと思います。
カンタンなので、試験で問われることはないでしょう
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: FP技能士, 宅建 | 2015年9月25日 3:24 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |