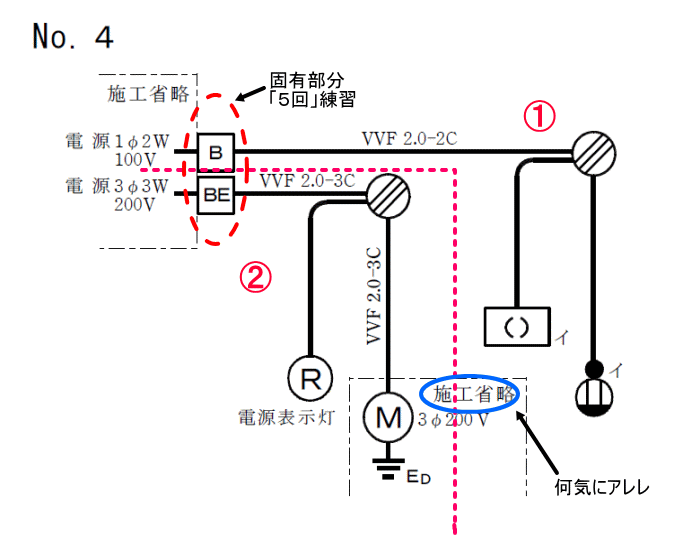2016年度・2電工技能試験・候補問題‐No.4の攻略ポイント(文系ド素人向け)-2つに分けて作業・端子台練習
2016年度・2電工技能試験・候補問題‐No.4のポイントは「2つにわける」と「端子台の練習」です。
一見すると、図記号がたくさんあるので、難しく感じるかもしれません。
が、候補問題4は、固有部分をきちんと練習しておけば、まず受かる問題で、この問題に当たれば、合格はスグそこです。
まず、文系ド素人の方は、上の画像のように、①と②と、ふたつに分けて考えるようアドバイスします。
①と②は、作業的に別個にできるので、「2つに分けて」考えると、余計なことに気を使わずに済み、精神的に楽になります。
①の右側のスイッチ等作業は、“普通”です。他の候補問題の練習を通じて何度もやる作業なので、問題ではないです。
ここでとちるようなら、もっと練習をする必要があります。正直、やばいです。朝から晩まで練習してください。
②の作業は、最初は、モーターやアースの表記があるので怖気立ちますが、作業自体は全然問題ではなく、見掛け倒しです。
というのも、当該部分(三相3線式200V配線)には、問題文に『色指定』があるので、混乱度がものすごく低いからです。
問題分の指示通りに、結線すればいいだけであり、ド素人文系の最強のテクニック『指差し確認』をしながら組んでいけば、まず、間違うことはありません。
1本1本組む度に、「○○と○○、赤色、ヨシッ!」ってな感じです。
指差し確認をしながらだと、他の問題のように、配線が“コチャコチャ”しないので、誤結線のリスクも格段に低くできるでしょう。
さて、本問の最大の山場は、「端子台」の接続です。
本問では、おそらく、「配線用遮断機」と「漏電遮断機」が1つの端子台で代用されるはずです。
問題で指示される端子台上の数字(記号・文言)と、ケーブルとを、取り違えないよう、慎重に接続します。
ド素人文系の最強のテクニック『指差し確認』を、2回した後で、結線することを推奨します。
なぜなら、間違えると、倍の時間をかけて直さないといけないからです。
端子台には、それ独自の注意事項があります。たとえば、皮膜を噛んではいけないとか、電線が5ミリ以上はみださないとかです。
このため、端子台には、“独自の練習”が必要となります。
晩酌をしながらでもいいので、使用済みケーブルで、正確かつ確実に、端子台への結線を練習しておきましょう。酔ってできるくらいでちょうど良いです。
画像にあるように、5回は、使用済みケーブルで練習しておきましょう。
さて、おそらく、最後の段階で、①の回路と②の回路とを合体することになりますが、1つ、深呼吸をして、落ち着いてやりましょう、
慌てていると、接続部分がずれてイライラしたり、果てには電線が抜けたりと、精神的に“ムカッ”とします。
イライラっとすると、ケアレスミスの温床となるので、深呼吸を1つ入れることを、勧めます。
最後に、本試験で本問に当たったら、試験の最後の最後で、必ず端子台のねじをもう一度締めてください。
くっと、ドライバーを挿して回すだけでいいです。
というのも、見直しのときに、ケーブルの皮膜が食い込んでいたり、または、露出が長すぎたりで、『微調整』をする可能性が大だからです。
この際、ねじを緩めて微調整するのですが、その際、100%ねじを締め忘れる!と思っていてください。
ねじの締め忘れは、重大欠陥で即落ちです。
最後に必ず、ぎゅっぎゅと、念のため、ねじを締め直しましょう。
蛇足ですが、施工省略の部分(青丸のところ)も、要注意です。
技能試験では、「施工省略」の処置の際に、時折、「アレ?何するんだっけ?どうやってケーブル切ったっけ?皮膜は取るんだっけ?」などと、パニックに陥る可能性があります。
個人的には、練習中にこれでパニックになったことがあります。
カンタンなところほど、意識的に「手順化」=何をしておくか明白に意識しておきましょう。
本試験のときに「アレレ」となると、結構やばいです。元に戻るのに、確実に時間を失います。
最後に、技能試験の教材については「第2種電気工事士・技能試験のテキスト・教材・工具」に述べているのですが、文系ド素人にとって、あると便利なものを紹介しています。
たとえば…、
「ホーザン 合格クリップ」や、
「ホーザン 合格ゲージ P-925」や、
「ホーザン 合格配線チェッカー Z-22」です。
絶対に必要かというとそうではありませんが、「手助け」にはなるので、万全を尽くしたい方は参考にしてみてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 2016技能 | 2016年1月14日 12:43 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
年末年始の生ゴミに重曹を+臭い一工夫
年末と年始で困るのが、「生ゴミ」です。
言うまでもなく、ゴミの収集がストップするからで、台所やベランダに置いた生ゴミがだんだん臭ってくる方が居られるかと存じます。
しかも、年末年始では、カニやら牡蠣やら海老やらの「ごちそう」を食べるので、殊更に生ゴミが臭う次第です。
また、作るのがめんどくさいので、豪勢な弁当で済ませる方も多いでしょうが、これら弁当ガラも、臭いの原因となります。
で、当該悪臭対策にはどうしたらいいかといいますと、タイトルにあるように、重曹を使うという次第です。
重曹の使い方は、仔犬ができるほどに、簡単です。ですから、配偶者でも可能です。
生ゴミを捨てたゴミ箱に、直に重曹をぶっ掛けるだけです。
生ゴミを入れたゴミ袋の中に、重曹を振り掛けるだけです。
臭いそうな生ゴミには、重曹を溶かした水を霧吹きで吹き付けるだけです。
神経質になる必要は全くなく、臭いがしそうなものに、適当に重曹を振り掛ければいいだけです。
配偶者に間違って振り掛けそうになりますが、そこは我慢です。
てきとーに重曹を振りかけておくだけで、1週間くらいは、生ゴミ臭がしなくなります。
ゴミが出せない年末年始で困っている方は、ぜひとも、重曹の消臭効果を試してみてください。
ところで、生ゴミ臭対策に、あと一工夫付け加えるなら、「小まめな水洗い」と「小まめにビニール袋で包む」と「小まめに紙で包む」です。
弁当ガラや空き缶、ペットボトル、インスタントラーメンの容器などは、水道水で食べかすや調味料、残液をざっと洗い流しておくと、臭いが激減します。
魚介類の食べかすや鳥肉の骨といった、ことさらに臭いそうなものは、それだけを新聞紙やチラシ、フリーペーパーなどで包んだり、ビニール袋に入れたりして隔離したうえで、重曹を振りかけておくと、まず臭いません。
このような工夫をしておくと、臭いがないためか、ゴキブリやらの害もかなり減ります。
「ゴミの日まで、あと1週間もある」ってな方は、先の一工夫と重曹で乗り切ってください。
重曹は掃除用でも構いませんが、これを機に、食用グレードの重曹を買っておくことを勧めます。
キロ単位で買うと、小ぶりの掃除用を買うより単価が安いし、持って帰る手間もありません。
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: 消臭, 重曹 | 2015年12月29日 4:56 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
大掃除のひどい油汚れは、重曹をクレンザー風に使う
「換気扇の油汚れに重曹を」の続編です。
大掃除の最大の敵が、台所の油汚れで、とりわけ、換気扇のそれは、配偶者並に手強い汚れです。
基本的に相手にしたくありませんが、年に1度くらいは、立ち向かわねばなりません。
先の記事では、重曹を水に溶かしてスプレーすると、油汚れは簡単に落ちることを紹介していますが、重曹をクレンザー風に振りかけて擦ると、ド級の油汚れもさっくり落とすことができる、というのが本雑分の内容です。
掃除のやり方は簡単です。
ひどい油汚れには、粉末のクレンザーをシンクに振りかけるかのように、重曹を、たっぷりと大量にドサッと振り掛けるのです。
そして、湿らせたボロ布でゴシゴシ擦れば、べとべとした油汚れが難なく取れてしまいます。(末尾に注意事項あり。)
換気扇のファン1枚なら、15分もあれば、1年分の油汚れが落ちます。
「うわーうわー落ちる落ちる」と、楽しくなるくらいに、ベタベタ汚れが落ちます。
油は酸性で、重曹はアルカリ性なので、重曹が油汚れと相性がいいのは知っていましたが、ここまでよいとは、重曹を使い続けているわたしですが、新たな発見でありました。
重曹は粒子が小さいので、「磨き粉」としても利用されるのですが、今回、この磨き粉用途で、油汚れを「こそげる」のを知ったという塩梅です。
換気扇の羽のみならず、換気扇の外枠も油でべとべとでしたが、重曹のクレンザー風利用で、これまでにない短い時間で、大掃除の難所の換気扇が終了したという次第です。
油が固形化しているなどのひどい油汚れの場合は、重曹をざくっと振りかけて、しばらく放置すれば、油全体が中和されて、ぬるっと取れます。
また、お湯と組み合わせてゴシゴシすると、油汚れの落ち方はさらに加速し、普通のホコリや泥汚れのように、油が落ちます。
以上、換気扇などのひどい油汚れには、重曹をドサドサと、遠慮仮借なく、惜しむことなく振りかける、クレンザー風の利用がよい、という雑文でした。
なお、素手で直に、大量の重曹と接触すると、後々、かなり手がぱさぱさするので、敏感肌の方はご注意ください。
掃除の際は、できるだけゴム手袋をして、作業をしてください。(まあ、油まみれの換気扇を素手で掃除をする人はあまりいないでしょうが。)
まあ、直に触れたその日だけ、ぱさぱさするだけなので、気にならない人は別段、素手で扱っても大丈夫です。
なお、わたしの利用したのは、掃除用重曹ではなくて、食用グレードの重曹です。
食用グレードだったから、肌トラブルが少なかったのかもしれないので、気になる方は、念のため、食用グレードの重曹を利用ください。
価格参考:食用グレードの重曹
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: 重曹 | 2015年12月28日 12:18 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |