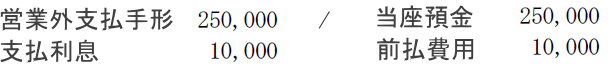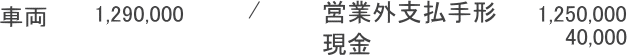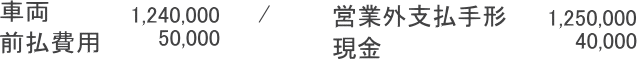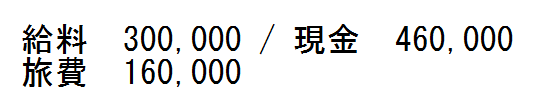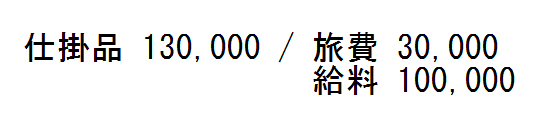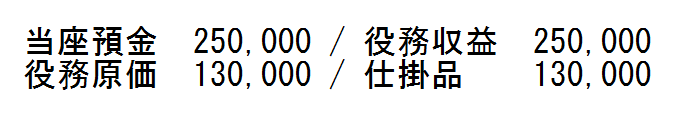有価証券の表示科目は、“超”後回し‐簿記2級ノート
有価証券は、簿記2級の屈指の論点です。
一口で言えば、『出題者が出しやすい』からで、資料上の有価証券の数と種類を、ちょっと増やすだけで、たちまち落伍者続出という、出題者歓喜・ハハハハハハ(受験生泣かせ・ヒイイイイイ)な論点のためです。
で、有価証券の攻略ですが、まず、「表示科目」については、後回しにします。
有価証券が受験生泣かせなのは、「勘定科目」と「表示科目」の2系統の論点があり、それぞれが絶妙に違っているためです。
有価証券の勘定科目
頭が痛くなりますが、有価証券の勘定科目は保有目的ごとに分けられており…、
売買目的有価証券
満期保有目的債券
子会社株式・関“連”会社株式
その他有価証券
…の4つに分類されます。
有価証券の表示科目
で、有価証券の表示科目は…、
有価証券
関“係”会社株式
投資有価証券
…の3つです。
5つ以上はたくさん‐表示は後回し
…読んでいて、わからなくなってきているでしょ?
実はわたしも、テキストで確認しながらの記述となっています。
先述した「表示科目」の後回しとは、「勘定科目」の使い分けがしっくり頭に入っていないのに、「表示科目」までを無理に押えようとすると、必ず、両者の混同が生じてしまうからです。
その他有価証券で仕訳を切らないといけないのに、投資有価証券で切っていたりします。
表示科目で仕訳を切っていたり、その逆もあったりで、物凄くわからなくなってきます。
でも、それは、ごく普通の反応で、時間を追うごとに、わからなくなってくるんです。
「5つ以上はたくさん」です。
勘定科目の4つに、表示科目の3つで、計7つのものを、一時に習得しようとするのは、無理です。
人は、5つ以上のものは、すぐに把握できません。だから、手足の指は5つなのです。
んなもんで、まずは、おおもとの「勘定科目」の4つの使い分けが頭に入るまでは、「表示科目」のほうは、『おまけ』程度に押えて、後回しにするといった次第です。
問題演習の際、有価証券の処理のみならず、表示まで問われていたら、無理をせず、テキストを見ながら解答しましょう。
無理は、誤答の元です。
「有価証券の表示」は、第3問での超頻出論点なので、押えておきたい気持ちは良くわかります。
しかし、なぜ、有価証券の処理と表示が、頻出なのか考えてみてください。
受験生の多くが、有価証券の論点を、しっかりと整理ができておらず、ぽろぽろ失点するから、出題者は微笑しながら出題を続けている、といった次第です。
ホント、無理に憶えようとすると、ごちゃごちゃになってきて、後々、面倒なだけです。
まず、有価証券の4つの分類(勘定科目)を、完全に頭に入れること、です。
なお、4つの勘定科目が頭に根付いていたら、「表示」はすごくカンタンになります。
勘定科目あっての表示科目なので、まず、前者の完全制覇からです。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記2級, 簿記2級‐勉強, 簿記2級‐有価証券 | 2016年9月14日 11:35 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
固定資産の割賦購入で、薄っぺらい受験生が落ちる‐簿記2級新論点ノート
新論点の仕訳のうち、やや注意なのが「固定資産の割賦購入」です。
新旧の論点が入り組んで出題されるので、何気にウザイ論点です。
特にウザイのが「支払利息‐前払費用」を計上しなくてはいけない点で、問題文中には「利息」云々の文字がないので、殊更に厄介な論点です。
個々の論点を、きちんと理解しておく必要があります。
主要論点は、「3つ」
「固定資産の割賦購入」には、主要な論点が「3つ」あります。
その3つとは、「割賦購入時の仕訳」と「固定資産の取得原価」と「手形振出」です。
これら3論点が入り組んでいるので、それぞれをきっちりおさえてないと、まず、ポカをするという塩梅です。
「固定資産の割賦購入」の問題を見たら、まず、「注意点が3つあったな」と思い出して、慎重に解答しましょう。敵は、どこぞに、罠をしけてくるはずです。
割賦がらみの処理
「固定資産の割賦購入」で厄介なところは、「前払利息‐支払利息」が絡んでくるところです。
固定資産を割賦で(分割払い)で購入すると、支払いが長引くので、その分だけの「利息」が発生するという塩梅で、当該利息を、仕訳に落とし込まねばならない、といった手合いです。
公式のサンプル問題は以下。
『(1)静岡商店は、X1 年 11 月 1日に営業用軽トラック(現金販売価額 ¥1,200,000)を割賦契約で購入した。代金は毎月末に支払期限の到来する額面¥250,000の約束手形 5枚を振り出して交付した。』
『(2)X1 年 11 月 30 日 静岡商店は上記約束手形のうち、期日到来したものが当座預金口より引き落とされた』
解答の仕訳は以下。
まず上の(1)の仕訳は…、
…となっており、下の(2)の仕訳は…、
…となっています。
このように、割賦で買うと、「支払利息」を計上するよう指示されており、加えて、購入時には、返済期限が到来していないので、「前払費用」で処理するよう、指示されている塩梅です。
で、支払期限が来たなら、前払利息を、該当する支払利息に振り返るといった次第です。
利息分の把握は、問題文に明記がない場合は、貸借差額で求めるようです。(手形支払額と現金販売価額との差)
「固定資産の割賦購入」の論点で第1は、このように割賦に絡んだ「前払利息‐支払利息」の仕訳が切れるかどうか、です。
先に述べたように、問題文のなかには、「利息」云々の表記がないので、“知っていないとまず仕訳が切れない”という、殊更にイヤらしい論点といえましょう。
「固定資産の割賦購入」を目にした場合は、割賦分の「利息」処理に意を払ってください。
なお、公式では、購入時に支払利息を全額を計上し、決算時に未到来分を前払費用で処理してもよい、とも指摘しており、「決算整理」の問題としても、出題可能性が“大”です。
付随費用の存在‐取得原価に入れる・入れない
「固定資産の割賦購入」が、上記のように「支払利息」がらみだけなら、「ふーん」で終わりなのですが、そうは問屋がおろさないのです。
思い出してください。
固定資産を購入する際、当該購入に費やした諸費用は、「取得原価に含めて」処理したはずです。
先の割賦購入に、当該付随費用の論点が加わると、途端に頭が混乱してきます。
先のサンプルの問題文に、たとえば、「購入にかかる運送料と整備料の計40,000円は現金で支払った」などとあれば、当該費用を「車両」に含めて仕訳を切らなくてはいけません。
このとき、先の「支払利息‐前払利息」の計上を忘れてしまって、当該利息分までも、固定資産の取得原価に入れかねない、という塩梅です。
こんな感じです。
正しくは…、
こんな次第で、「固定資産の割賦購入」は、固定資産の取得原価の論点まで含めて出題されかねないので、それぞれの理解が殊更に必要となっています。
当該取得原価云々は、簿記3級の論点であり、だからこそ、簿記2級では手薄になって、ついウッカリ間違えやすくなっています。
出題者は、大いに突いてくると思われます。
営業外支払手形にも注意
最後に、「固定資産の割賦購入」では、「営業外支払手形」が絡んでくるはずです。
これが、「支払は翌月末である」ならば、「未払金」だけで済むのですが、出題者はそう甘くありません。
営業外目的で手形を振り出した場合の処理も、突っ込んでくるはず、という塩梅です。
ウッカリした受験生だと、サンプル問題文の…、
『額面¥250,000の約束手形 5枚を振り出して交付した。』
…のところで脳髄反射して、「支払手形」の仕訳を切りかねません。
おそらく、5%くらいの受験生は、当該「支払手形」勘定で仕訳を切って、貴重な1点を落とすはずです。
固定資産の購入は「営業外」ですので、「営業外支払手形」で仕訳を切ることを、頭の片隅に置いておきましょう。
まとめ
こんな次第で、「固定資産の割賦購入」には、論点がてんこ盛りであり、新論点の中ではかなり要注意なものとなっています。
新論点の「割賦購入」時の処理のみならず、旧論点の「取得原価の算定」と「営業外支払手形」まで、きちんと把握しておく、といった手合いです。
まず、新論点の「割賦購入」の際は、「利息計上」しなくてはいけません。勉強不足の薄っぺらい受験生はここでまず失点します。
付随費用発生時の「取得原価」の計算が加われば、薄っぺらい受験生は即死でしょう。
そして、「営業外支払手形」で、おっちょこちょいな受験生をふるい分けします。
こんな次第で、「3つ」も受験生を陥れる罠ポイントがあるといった塩梅で、慎重に、丁寧に理解しておく必要があります。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記2級, 簿記2級‐勉強, 簿記2級‐新論点 | 2016年9月13日 11:18 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
役務原価は前中後の処理と仕掛品‐簿記2級新論点ノート
「役務原価」ですが、まず、勘定科目の名前に、少しだけ注意します。
役務原価は、役務“収益”と相対する勘定ですが、役務“収益”の収益という文字に引きずられて、役務原価を、「役務“費用”」と、間違えて憶えている可能性があります。
営業収益-営業費用とか、収益費用対応の原則とか、収益という用語は費用とセットのため、役務原価においても、役務費用と憶えかねないのです。
役務“原価”です。ちゃんと正しい漢字で憶えているかどうかを確認です。
役務原価は前中後
大上段から言うと、役務原価はてんこもりの論点です。
役務原価をめぐる一連の取引では、前中後の3つに注意しなければならず、また、それぞれが独特なので、要領をきちんと押えておかないと問題が解けないです。
以下、役務原価の“やばさ”を見ていきましょう。
役務原価の前‐当期の費用
公式のサンプル問題は、以下の通りです。
「建築物の設計・監理を請け負っている株式会社 中央設計事務所は、給料¥300,000および出張旅費 ¥160,000を現金にて支払った。」
で、解答の仕訳は以下の通りです。
…いたってシンプルな仕訳に見えますが、素で出ると困惑してしまいます。
問題文の“請け負っている”に引っかかって、「請負→役務原価!」と脳髄反射しかねないからです。
当該仕訳のポイントは、役務収益と対応できない役務原価は、いったん「通常の費用」として計上する、という次第です。
役務原価の中‐仕掛品
役務原価の最大の山場は、「仕掛品」で処理するところです。
当該「仕掛品」を使う仕訳は、商業簿記ではそうないはずなので、役務原価では仕掛品勘定を使うことを知っていないと、“絶対に解けない”です。
要領としては以下の通りです。公式のサンプル問題文は…、
「顧客から依頼のあった案件について建物設計を行なったが、先の計上したもののうち給料¥ 100,000および出張旅費¥30,000が当該案件のために直接費やされたことが明らかになったのでこれを仕掛品勘定に振り替えた」
で、仕訳は以下の通りです。
問題文はサンプルですから、「仕掛品」勘定を用いるように指示がありますが、もしこれが、「…明らかになったので、該当する勘定に振り替えた…」であれば、難易度は格段に上がるはずです。
また、当該役務原価と仕掛品は、決算整理でも狙われそうです。
いったん計上された費用、先のサンプルで言えば、旅費や給料について、「旅費のうち○○円は、請負作業に費やされたが当該作業はまだ完成していない」などと指示され、旅費を仕掛品に振り返る作業の当否を問う、ってな塩梅です。
このように、役務原価には、仕掛品を用いた処理があるので、注意が必要です。知らないとまず解けないはずです。
なお、公式のコメントでは、当該仕掛品について、「役務収益と役務原価の認識にタイムラグがある場合には、仕掛品を使うのが望ましい」とのことです。
ですから、「お金を渡してすぐサービス享受」なら、仕掛品に振り返る必要はない、ってな次第です。
役務原価の後‐収益・費用の認識
役務原価は、役務収益が認識されるまでは、仕掛品として計上します。
で、役務収益が認識されたら、それに対応した役務原価の仕訳を切る、ってな次第です。
公式の問題文は以下。
「上記の案件について、 設計図が完成したので、これを顧客に提出し、対価として¥250,000が当座預金口 が当座預金口座に振り込まれた。役務収益の発生伴い、対応する原価を計上する」
で、公式の仕訳は以下。
…ってな感じで、役務収益を計上し、先に計上した仕掛品を役務原価に振り返る、ってな塩梅です。
当該仕訳を切るには、当該取引の前に、費やされた費用が仕掛品に計上されていることを“知っておかねば”、できないので、要注意論点です。
役務原価まとめ
このように役務原価は…、
費用の詳細が判明する前は、いったん期間損益に計上する。
判明したら「仕掛品」。
収益認識の指示があれば、役務収益の計上と、仕掛品を役務原価に振り替え。
…と、3つも処理があるという塩梅で、結構てんこもりの論点となっています。
第1問の仕訳問題でも、第2問の個別論点でも、第3問の総合問題でも、非常に出しやすい(使いやすい)論点なので、一度時間を取って、キッチリ見ておくほうがいいでしょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記2級, 簿記2級‐勉強, 簿記2級‐新論点 | 2016年9月8日 1:16 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |