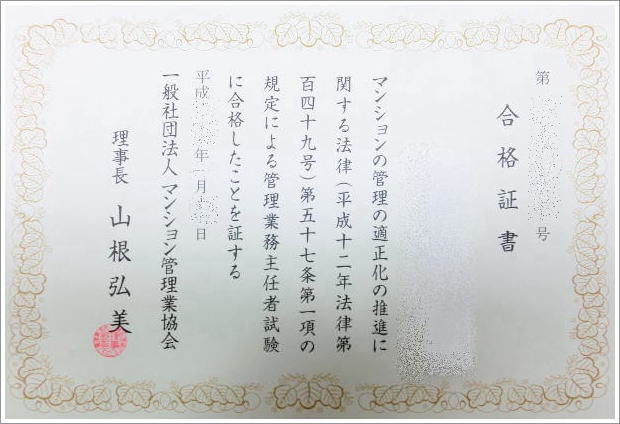令和5年度(2023年度)管理業務主任者の独学
まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。
令和5年度(2023年度)対応済み。試験の傾向や科目別の勉強方法など。最新の令和4年度(2022年度)の本試験の解説も。試験勉強は「順番」が重要。民法は後回し。適正化法からはじめて、区分所有法・標準管理規約・マンション標準管理委託契約書と駒を進め、残りは適当に。団地は飛ばす。テキスト3回、過去問3回、予想問題集等も3回繰り返せば、合格ライン。あと、マンション管理士との併願や過去問リンクも。
【重要】公式をチェックする
R5年度の管理業務主任者試験ですが、現在のところ、「実施予定」となっています。
コロナインフルエンザの動向によっては、試験の中止・延期、および、試験会場の変更などがあるとのことです。
変更等があった場合、「個別連絡はしない」とのことなので、試験1ケ月前からは、「公式」を、まめにチェックするようにしてください。
「公式」で何か発表があった際は、告知しますので、当方の「twitter」をフォローしておいてください。
んでは、本編に入りますが、少々長いので、「お気に入り」にでも入れて、ぼちぼちと目を通してください。
ブログ更新
データ遊びです。「いくつあるか?」問題対策です。
暇な時間があれば、「いくつあるか?は、「2」を選ぶ」を、一読をば。
インデックス
- ひとくち管理業務主任者
- 独学合格のオキテ
- 公式過去問+解説‐再受験生向け
- 【重要】直近試験の傾向について
- 試験科目の特徴‐敵を知る
- 勉強の順番‐民法からやってはいけません。
- 最初は適正化法‐独学の定番
- 次は、区分所有法・標準管理規約とか
- 管業の独特1‐「規約でホニャララ」
- 管業の独特2‐「規約の定め」と「集会の決議」
- 「団地」はメンドクサイので後回し
- その他の法律‐凶悪的に「難化」
- 会計と仕訳問題
- 建物・維持設備‐最難関
- 民法‐合格の保険
- 民法が超イヤな人
- 独学向け教材
- 法改正や改定について
- 「難化」について
- 【他資格】宅建・簿記でかなり有利
- 【他資格】マンション管理士との併願について
- 【リンク集】科目別過去問
- 【リンク集】管理業務主任者のこまごましたもの
ひとくち管理業務主任者
結論から言うと、管理業務主任者試験は、例年、「20%」という合格率が続いており、独学でも“まだまだ”取れる国家資格となっています。
なお、直近の令和4年度(2022年度)試験は、合格率は「18.9%」と、相なっています。
合格基準点は、例年「34~36点」。「50問」出題なので、「7割正解」で合格です。
勉強期間は、法律の素養がない人は「6ヶ月」を、対して、宅建合格者や法学部卒の人等は、「2~4ヶ月」くらいを見ておく、といった塩梅です。
独学向け教材は、「教材レビュー」にまとめていますが、読むのがメンドウなら、必要かつ十分な「 管理業務主任者 基本テキスト 2023年度 」と「 2023年度版 管理業務主任者 項目別過去8年問題集 」で揃えればいいでしょう。
近年は、明白な「難化」傾向にあるので、8~9月以降に、「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を参考に、問題集を追加してください。
ところで、後述していますが、管理業務主任者は、「宅建」や「簿記」があると、もの凄く有利です。
先にこれらの資格の取得を考えても、まったく損はありません。
なお、マンション管理士と併願予定の方は、本ページ末尾の「マンション管理士との併願について」を一読をば。個人的には、『非推奨』です。
公式過去問+解説‐再受験生向け
惜しくも前年・前々年で受からなかった場合、テキストは、法改正等があるので、買い替え推奨です。
しかし、過去問は、単に前年分を追加すればいいだけなので、1冊丸ごと買い換えるのは、お金がもったいないです。
そこで、直近の過去問に、解説を付与したものを…、
…アップしています。
法改正には対応してませんが、傾向をつかむくらいは、利用できるかと思います。
問題と解答は、公式のPDFをダウンロードしてください。
公式:http://www.kanrikyo.or.jp/index.html
なお、PDFでの過去問演習は、PCよりタブレットが使い勝手いいです。受験以外にも役立つので、これを機に買うのもいいです。推薦するのは、最優秀コスパのアマゾン「Fire HD」です。
独学合格のオキテ
結論から言うと、「テキスト精読を「3回」、過去問演習を「3回」、そして、予想問題集・模試問題集を「3回」解けば、穏当に独学合格する」ってな塩梅です。
ぶっちゃけて言うと、本試験問題の6~7割は、過去に問われた問題・選択肢や、テキストの頻出論点・定番論点で構成されているのです。
よって、先に述べたように、テキスト・過去問を「3回」繰り返しておけば、本試験でも6割くらいは、点数できるってな塩梅です。
んで、近年の本試験は、「難化」傾向にあり、これまでにない新傾向の出題もあるので、予想問題集等で「問題慣れ」しておく、ってな次第です。
管理業務主任者試験は、端的に言えば、「暗記と記憶の試験」です。合否は、「数」で決まります。
難しく考えたり、無限にある試験情報を追ったりする前に、目の前の教材を「繰り返す」ことに尽力してください。
【重要】直近試験の傾向について
直近の「令和4年度(2022年度)試験」ですが、教訓を一口で言うなら、「先入観を持たない」です。
当該本試験ですが、傾向にそこそこの変化がありました。挙げていくと…、
・「民法」が先祖返りして、「やさしく」なった。
・今年も、「会計・税務」の問題が3問も出題された。
・「建築・維持管理」は、やはり、ぶっ飛んだ問題が出る。
・今年も、「統計」の問題が出題された。
・今年も、「その他の法」が手ごわい。
・暗記だけでは解けない、「考えさせる問題」の出題が増えた。
…といった塩梅です。
以下に、詳しく見ていきます。
傾向詳細
直近の令和4年度(2022年度)試験ですが、試験問題の難易及び出題数が「流動化」しています。
これまで難しかった科目がやさしくなったり、これまで何ともなかった科目が難しくなったりで、前もって“こう!”と、決めつけておくのは、推奨できません。
これはこう解くといった「先入観」を持たないで本試験に臨んでください。
さて、個別的な傾向ですが、前年に急に難化した「民法」が、「ふつうの問題」になって、点が取れる問題になっています。
しかし、再び難化する可能性が「大」です。シッカリ勉強しておきましょう。
次に、「会計・税務」の仕訳問題ですが、今年も「3問」も出題されました。
簿記の知識がないと、本当に厳しい問題です。
難・やや難の出題が増えている昨今、「簿記3級」の勉強をしておくことを勧めます。
簿記の知識さえあれば、3問フルに取れるので、とても大きいです。
参考:独学の簿記3級:商業簿記
次に、「建築・維持管理」ですが、急激に難しくなっています。
「19問‐コンクリートの中性化深さ」のような、こんなんできるわけないやん、という問題が多かったです。
ただ、過去問・選択肢の「使い回し」がそこそこあるので、お手上げの問題を落としても、何点かは拾えたはずです。
「建築・維持管理」は、過去問演習を徹底して、すべての問題の問いと答えを押さえておきましょう。
「その他の法」ですが、今年も、受験生泣かせの科目と化しています。今後も、「難化」が継続しそうです。
よって、定番の宅建業法など、テキスト・過去問レベルのことに尽力して、1~3点取れたらいいくらいになっておきましょう。
そして、「統計」は、今後の定番問題と化しそうです。予想問題集で出た数字を憶えましょう。プロの技を頼るべきです。
上記科目以外は、穏当に例年通りでした。テキスト精読と過去問演習で、何とかなったかと思います。
「考えさせる問題」について
先に、「暗記だけでは解けない、「考えさせる問題」の出題が顕著。」と述べました。
当該「考えさせる問題」ですが、テキストや過去問に全くない事柄が出題されるも、問題文・資料をよく読んで考えて、勘や推測を働かせれば、何とか解答にこぎつけられる問題です。
「26問‐長期修繕計画作成ガイドライン2」や「28問‐修繕積立金ガイドライン」、「37問‐充当順序」といった問題です。
初見時には、(なんじゃこりゃ?!)としか思えない問題ですが、何とか正解し得る問題となっています。
即、「捨て問」にはせず、何かしらの解答の糸口を得るべく、粘り強く問題に当たってください。
今後も、こういう、暗記の効かない「考えさせる問題」が出題されるように思います。傾向把握だけでも、やっておきましょう。
以上が、直近試験の傾向でした。
次は、個々の試験科目の特徴を見ていきます。
試験科目の特徴‐敵を知る
結論から言うと、手間のかかる難科目は、「民法」「区分所有法」「建築・維持管理」「会計・税務」です。
これらの科目は、まず、分量が多いです。特に、「民法」と「区分所有法」は、試験のメイン科目であるため、憶える量が実に多くなっています。
しかも内容が「法律」であるため、素養のない人は、大変苦労します。
次に、「建築・維持管理」ですが、分量が“これまた”膨大です。
暗記内容も、たとえば、コンクリートのかぶりの厚さ」などの微々たる数字を憶えるのに一苦労します。。
それに、「建築・維持管理」は、難問出現エリアで、ほぼ毎年、解きようのない問題が出題されており、点数の確保に実に苦労します。
最後の「会計・税務」ですが、まだ、税務は対処可能なのですが、会計は「純然たる簿記」の問題ため、仕訳の理屈を知らないと、お手上げとなっています。
先の試験科目の出題数をみていくと、おおむね…、
民法・・・5~6問
区分所有法(標準管理規約との併用問題を含む)・・・11問
建築・維持管理・・・12問
会計・税務・・・3問(会計2問‐税務1問)
…となっていて、合計「32問」も、手間を食う問題となっています。
「会計・税務」は出題数が少ないので捨てても大丈夫ですが、「民法」や「区分所有法」ができないと、合格は、まったく覚束ないものとなります。
こんな次第で、「民法」、「区分所有法」、「建築・維持管理」の3つで、どれだけ点数を確保できるかが、管業試験のキーとなっています。
試験勉強においては、上記3科目を中心に、学習計画を練ってください。
補足‐長期修繕計画作成ガイドライン
「建築・維持管理」で出題される「長期修繕計画作成ガイドライン」ですが、完全に「定番問題化」しています。
「3~4問」が出題されるので、これを「捨て問」にすることはできません。
当該「長期修繕計画作成ガイドライン」は、ボリュームが多いため、ガチ暗記が厳しいです。
よって、取るべき対策は、「テキスト精読」です。
暇があれば、ガイドラインの記述に、目を通しておきましょう。
「10回読め」とは言いませんが、読めば読むほど、選択肢の正誤が付くようになります。
他は、やさしいしラク
残る「マンション管理適正化法」や「標準管理委託契約書」、「標準管理規約」、「管理費等」などは、大半が基礎・基本ばかりの出題で、極めてオーソドックスであり、テキストと過去問を消化していれば、穏当に点が取れます。
しかも、分量・ページ数も少ないため、あまり負担になりません。まあ、大丈夫でしょう。
ただ、最近の試験では、急に「難化」する傾向にあるので、先入観を持たずに臨んでください。
最後に「その他の法」は、先述したように、近年かなり難しくなり、点が取り難くなっています。
深追いはせず、テキストレベル・過去問レベルのことに尽力しましょう。
本ページ後半で述べている、「その他の法律‐凶悪的に「難化」している」や「難化について」も、一読ください。
勉強の順番‐民法からやってはいけません。
「ゼロ」から始める人は、絶対に「民法」からやってはいけません。
管理業務主任者の試験科目は、それぞれが別個のものです。
つまり、「民法」を知らなくても、区分所有者法等は、勉強できます。
民法を知らないと解けない論点もありますが(先取特権など)、極めて少数です。
「民法」から“やらない”のは、挫折するからです。
試験科目のうち、最も手ごわいのは「民法」で、質・量ともに、配偶者なみに面倒くさいです。
民法学習済みのわたしですら、民法はイヤでイヤでたまらず、“メンドクサイ”の一言で一番最後に手を付けました。
民法が重要科目なのは重々承知の助でしょうが、最難関でもあるので、最初は遠巻きにするだけしておきましょう。
不安のある人は、「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」や、「民法はおもしろい
」といった、民法副読本で、頭の地ならしをしておくとよいでしょう。
最初は適正化法‐独学の定番
管理業務主任者の試験勉強で最初に手を付けるのは、最も簡単で、「5点」も配点のある「マンション管理適正化法」です。
適正化法は、細々した条文知識を記憶する科目です。「管理業務主任者証には住所表記がある?ない?」とか、「禁錮2年でダメ」や「帳簿は5年保存」といった規定や数字を、そのまま憶えるだけです。
つまり、適正化法は、『憶えたらそれで1点』といった次第です。
単に憶えるだけなので、適正化法は、前提知識がゼロでも、即、着手できて、即、点の取れるようになるところです。
「民法」や「区分所有法」と比べたら、圧倒的に短期で、実力を養成できます。
こうした次第で、「適正化法」から着手するのが独学の定石です。。
次は、区分所有法・標準管理規約・マンション標準管理委託契約書
順番からすると、「区分所有法」から始めて、次に「標準管理規約」をやり、最後に「マンション標準管理委託契約書」に駒を進めます。
先の順番で進めると、法の理論と実践の“違い”が見えてきて、理解と記憶のノリがよくなります。お勧めの勉強順です。
区分所有法
区分所有法は、マンションや貸しビルの法律です。
「区分所有」は、「民法」等で言う「所有」の概念と、大きく異なるところに特徴があります。(使用に制限がかかっているとか、共用と所有のバランスどころとか。)
本法は、基本は暗記科目なのですが、個々の規定の意義を考えだすと、「よく考えられてるなあ」と中々に興味深く、知的な満足が得られます。
なお、区分所有法は、かなり『法律・法律』しているので、法律的な文章に慣れていないと、骨が折れます。
一時には進めず、少しずつ消化していきましょう。
なお、法律に慣れていない人で、区分所有法が「???」になってしまう人は、次に述べる「標準管理規約」と「マンション標準管理委託契約書」からやるとよいでしょう。
標準管理規約・マンション標準管理委託契約書
ぶっちゃけ言うと、「標準管理規約」と「マンション標準管理委託契約書」は、「暗記科目」です。
規約や管理の知識を憶えるだけなので、「知識ゼロ」からでも、実のある勉強が可能です。
先述したように、『区分所有法が何だかダメ』といった人は、当該2科目から、手を付けるとよいでしょう。
また、当該2科目は、非常に具体的なことが多く、マンションにお住まいの方には、なじみがあるというか、イメージを持ちやすいというか、理解や把握をしやすいです。
自分や家族・知人の住んでいるマンションを頭に浮かべて勉強していけば、(あーあの管理人のおっさんは、こういう契約書の下にやってんだなー)とか、(エントランスの張り紙にはこういう背景があったんだなー)的な理解ができるでしょう。
最後に注意事項があります。
中盤以降は、区分所有法・標準管理規約・マンション標準管理委託契約書の個々を、「比較」する勉強が必要となります。
本試験では、個々の取扱いの「違い」が頻出です。
「区分所有法ではこうなっている」が、「標準管理規約ではこうなっている」「標準管理委託契約書ではこうなっている」といった感じに、それぞれの「違い」を意識して勉強してください。
比較問題にも強くなるし、個々の論点の復習にもなるしで、効率よく勉強できるはずです。
補足‐標準管理規約
最後に、「標準管理規約」の傾向変化について一言。
これまで、「標準管理規約」は、主として「単棟型」が問われていました。
しかし、近年の試験では、「団地型」が問われ始め、んで、R1以降からは、ついに「複合用途型」の規約が問われる始末です。
参考:R3 29問:標準管理規約(団地型)‐団地の雑排水管等の管理及び更新工事
わたしは、これまでは、費用対効果の薄さから、「団地型」などは「捨て問」一択としていましたが、こうした傾向変化を見るにつけて、多少の「対応」が必要と思いました。
不要対効果が実に悪いので、深追いは厳禁ですが、「団地型」と「複合用途型」については、テキストに載っていること・過去問に問われたことは、押えておくべきです。
おそらく、今後の試験でも、「団地型」と「複合用途型」の標準管理規約が、出題されるはずです。
テキスト・過去問レベルの選択肢は、絶対に落とさないようにしましょう。
管業の独特1‐「規約でホニャララ」
管理業務主任者には、「規約でホニャララ」という、独特の出題があります。
たとえば、「届出は○日以内にする」といった規定は、よくあります。
普通の試験なら、「○日以内」の「○日」のところを憶えたらおしまいです。しかし、これが、管理業務主任者となると、大きく異なってくるのです。
たとえば、「集会開催の届出」です。
集会の召集通知は、原則として「1週間前」と法律では定められています。ふつうなら、「1週間前」を憶えるだけです。
しかし、当該規定は、「規約で伸縮できる」となっています。
もう一度言います。「伸・縮」です。
つまり、1週間を伸ばして20日に、縮めて3日に、規約で変更できるってな塩梅です。
次の例を言えば、「立替決議」です。当該決議を行う集会の通知は「2ヶ月前」と法で定められています。
しかし、「規約で伸ばす」ことはできるのです。つまり、期間を延長して3ヶ月にはできるが、短くして1ヶ月にはできないという塩梅です。
大概の試験では、届出等の日数規定は「○日」と固定されており、変化はないのですが、管理業務主任者では、規約で変更が認められるケースが多々あります。
混同しやすいため、出題率が高めです。テキストの「規約でホニャララ」という文言には、3倍は注意してください。
管業の独特2‐「規約の定め」と「集会の決議」
先の3科目(区分所有法・標準管理・契約書)の勉強で、「規約の定め」と「集会の決議」との文言を目にしたら、慎重に、注意深く条文を読んでいってください。
「規約の定め」と「集会の決議」が絡む規定は、非常に複雑で、試験でも頻出です。
「規約で定める」とは、「集会の決議では決められない」という次第です。
たとえば、区分所有法の20条の管理所有者です。
規約で定めないと管理所有者を決めることができません。つまり、集会の決議では管理所有者を決めれません。つまり、規約を変更する「4分の3」が必要になってくるわけです。(集会決議は過半数。要件がきつくなるわけです。)
たとえば、訴訟の提起です。
訴えは、「集会の決議で定める」ので、「規約だけでは決めれない」のです。
「ゴミを捨てたら、即、訴える」と規約で定めていても、「集会の決議」を経ていないので、訴えられないわけです。
これだけでも、結構ややこしいのに、条文や規定によっては、「規約の定め」か「集会の決議」の、どっちかだけでいいのもあり、頭が混沌としてきます。
ここいらの独特な箇所が、区分所有法で一番難しいところで、ここさえ突破できれば、本試験では十分な得点を稼ぎ出せます。
1つ1つを軽く扱わず、それぞれの違いを明白に意識して、憶えていってください。
「団地」はメンドクサイので後回し
区分所有法等で、「団地」規定を目にするでしょうが、「後回し」です。
「団地」は、「1棟のマンション」の法律関係・位置づけが終わってから本腰を入れます。
「団地」は、「1棟のマンション」の法規定・管理規定を、複合的に・応用的に当て嵌めるものなので、全体が済んでからやった方が早いです。
しかも、「団地」はややこしいくせに、出題頻度はそれほどでもありません。「後回し」の一手です。過去問に出たことだけやるか、それか、「捨て問」でもいいでしょう。
その他の法律‐凶悪的に「難化」している
「その他の法律」とは、「不動産登記法」や「宅地建物取引業法」、「品質確保法」、「消費者契約法」、「個人情報保護法」といった法律科目が該当します。
当該「その他の法律」ですが、近年は、本当に難しくなっています。
テキスト・過去問では、見たことのない法律が真正面から問われており、受験生を唖然とさせたはずです。
また、各種法令の総合問題も、実に難しくなっており、確答できた受験生は、ほとんどいなかったように思います。
参考:R2 44問:各種法令
参考:R3 第42問:各種法令
それに、です。
令和3年度(2022年度)以降、「統計」の問題が出題されるようになり、受験生をほとほと困らせたはずです。
参考:R3 第43問:統計
参考:R4 第43問:統計
このように、「その他の法」は、全くを以って、点が取り難い科目へ変貌しています。
まずもって、ほぼ毎回出題されている「宅建業法」は、ガチでやっておきましょう。
んで、残りは、テキスト精読と過去問演習とで凌ぎましょう。。
「その他の法」では、2~3問を正解できたら、最近の傾向からすれば、健闘したといえましょう。
会計と仕訳問題
ぶっちゃけ言うと、テキストの数ページの解説では、仕訳問題が解けるようにはなりません。
わたしは簿記2級を持っていたので会計科目は、まったく問題がありませんでしたが、簿記の素養が「ゼロ」だと、実に苦戦するはずです。
時間がない人は、仕訳問題は捨てましょう。で、その分を、「民法」や「建築・維持管理」に投入しましょう。
対して、時間のある人は、テキストでは勉強せず、簿記3級のテキストで勉強しましょう。
「簿記3級のテキスト・問題集・過去問レビュー」で紹介していますが、簿記3級には、簡易廉価版の教材が売られています。
テキストと問題集が一緒になった「スッキリわかる 日商簿記3級」で2週間くらい勉強すれば、まず間違いなく「1点」取れるようになります。
本式の簿記教材の方が、絶対的にわかりやすいです。餅は餅屋。専用の簿記教材で勉強するのが、遠回りに見えて一番近いです。
管理業務主任者は、書類を多数扱う事務職でもあり、かつ、出納にも関わってくるので、『事務能力』の証でもある簿記3級を取っておいて、絶対に損はないです。
参考:簿記3級の独学
当該会計で点数を取りたいのなら、果敢に簿記3級に挑戦です。
「1ヶ月」もあれば、そこそこできるようになります。簿記試験は「2月」「6月」「11月」にあるので、「2月」と「6月」に受験するのがベターです。
「難化」している管業で、最も有効な難化対策が、「簿記を勉強して、仕訳問題の2点を確実に確保する」です。
建物・維持設備‐難関
管理業務主任者試験の『難関』の1つです。
勉強の対象が、建築基準法から消防法といった法律から、設備の諸規定、たとえば、配管の角度から自転車置き場の明るさ(ルクス数)まで及ぶため、対策がとりずらいこと、この上ありません。
一口で言えば、「数点取れたら上々」で、全問不正解という、致命的な失点を防げるようになってればいいです。
無理して追求はしないが、そこそこは解けるようになっておきます。
建物・維持設備の勉強
要は、テキストを読み込み、過去問演習を何回も繰り返し、過去問に問われたことを、取れるようになっていればいいです。
正直、これ以外にやりようがなく、わたしもテキストと過去問だけで、数点をもぎ取りました。
「建物・維持設備」のお勧め勉強方法は、『1日3問~5問を必ず消化する』です。
一気にやると超メンドクサイし、絶対に長続きしません。ブランクが空くと余計に頭に入っていかないので、毎日少しずつ、慣れて行くのがコツです。
ぶっちゃけ、クイズみたいなものなので、問題演習で凌いでみてください。
ところで、万人に推薦できませんが、設備関係の知識がゼロで、当該「建物・維持設備」を苦手にしている人には、「絵で学ぶビルメンテナンス入門」という本を勧めます。
ビルとマンションでは、直接関係ありませんが、水道電気下水等、設備で被るものは多々あるので、“感じ”はつかめるかと思います。
別段、読まなくとも合格はできます。が、ビルメンテナンスの会社が、マンション管理をしているケースも多く、就・転職用の参考書として、よいかと思います。
なお、ほとんどが「マンガ絵」です。昔の4コママンガ風の絵柄です。
民法‐合格の保険
管理業務主任者の『最難関』です。
「民法」は条文数も多く、面白くともなんともなく、厄介で、ただただ長くてメンドクサイだけですが、耐えに耐えてください。これが『勉強』です。
一口で言うと、全問不正解の「0点」には、ならないようになっておく、です。
「民法」は、おおむね5~6問が出題されますが、3~4点は、最低でも取れるようになっておきます。過去問演習を徹底していれば、なんとか確保できます。
最近の試験傾向からすると、「民法の出来不出来」が直に合格に響くことはありません。
つまり、区分所有法や適正化法が仕上がっていれば、民法が3~4割のひどい出来でも、合格はできるという塩梅です。
しかし、試験は水物。
優秀な受験生が大挙して受験すると、合格点が上がるため、民法でどれだけ点が取れたかで、合否が分かれかねません。
合格の保険が「民法」です。
「民法」ができればできるほど、合格は確実になっていくので、時間があればあるだけ、取り組んでください。
民法が超イヤな人
民法には、本当にジュウジュウと手を焼きます。
テキストが視界に入るのすらイヤになってきたら、挫折の一歩手前。
いったん民法の試験勉強は止めて、別方向から反撃を開始しましょう。
別方向からの刺客、それは『読書』です。
お勧めの入門本は、「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」と「民法はおもしろい
」です。
本書は、まず、ぶ厚くありません!
カチコチの条文解釈は少なく、具体的事例を中心に民法の“ありよう”を説明するので、初心者でも挫折しないで読み通せるのが特徴です。
『読書』というワンクッションを置くと、民法に親しみが湧くし、多少の条文知識・判例知識も身に付くしで、かなり勉強しやすくなります。
宅建の民法にも使えるので、損はありません。
また、基本的な法律用語の意味がシックリ来ていないので、民法が苦手な人も多いかと思います。
「法律用語のコツ」を一読して、用語の使い方の違いをしっかり認識してください。
なお、適正化法では「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」が、区分所有法では「適用」と「準用」多用されています。参考までに。
独学向け教材
独学向け教材ですが、詳しくは、「管理業務主任者 教材レビュー」にまとめています。
まあ、「 管理業務主任者 基本テキスト 2023年度 」と「 2023年度版 管理業務主任者 項目別過去8年問題集 」なら、問題ありません。
上記テキストなら、次に述べる「法改正」等にも対応できるので、お勧めです。
また、予想問題集・模試問題集も、近年では、必須です。
「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」で、8~9月以降に、問題集を追加してください。
法改正・改定について
管業試験ですが、近年は、とりわけ「法改正・改定」の問題が出題されるようになっています。
民法や建築基準法等の法改正はもとより、標準管理規約の改定についても、絶対的にチェックしなければなりません。
例年、最低でも「1問」が、んで、大きな改正・改定があったときは、「3~5問」が出題されています。
改正・改定問題は、結構、突っ込んだ出題のため、“やってない”と、致命的な失点となります。
「改正・改定」の情報については、お使いのテキスト・過去問の出版社が、PDF等で配布しています。
ある程度、試験勉強が進んだ中盤以降は、改正・改定のファイル・小冊子を、“必ず”、熟読精読してください。
先に述べた「管理業務主任者 教材レビュー」で紹介するテキストなら、この点は、安心できます。
「難化」について
本試験は、近年、際立って「難化」しています。
そのため、受験生は、神経質にならざるを得ません。
しかし、なのです。
「難化」を、そう気に病む必要はないです。
というのも、管理業務主任者試験は、合格基準点が前もって決まってないからです。
合格基準点は、受験生の得点動向を踏まえて、試験ごとに定まります。
合格基準点は、「35点」前後ですが、「32~37点」と幅があります。
つまり、「難問」が出題されても、解けないのは他の受験生も同様なので、「難問」の数だけ合格基準点が下がるだけで、最終的な合否には大きな影響はない、ってな次第です。
「難問」が解けなくて、やべーってな感じで、焦ったり動揺したりすると、ケアレスミスを犯しやすくなるので、そっちの方が危険です。
本試験にて、「難問」に遭遇しても、(あーこれは、誰も解けんな。実質的に影響なし。他の問題で点を取る!)ってな感じに、いい意味で、無視してください。
【他資格】宅建・簿記でかなり有利
管理業務主任者試験ですが、他に資格を持っていると、絶大に有利に働きます。
宅地建物取引士(宅建)をお持ちなら、「民法」は、大丈夫です。そして、「その他の法」に出題される、おなじみの「宅建業法」や「借地借家法」も、終わっているも同然です。
んなもんで、宅建を持っているなら、民法の5~6問と宅建業法等の2問強の、計「8問」は済んでいる、といった次第です。
わたしのように、かなり前に宅建を取った人でも、『昔取った杵柄』で、テキストをざっと読んでばっと過去問を解けば、合格レベルにすぐ到達します。
次に、簿記があるなら、「会計・税務」の仕訳問題は、まったく問題ありません。よって、「2問」は、終わっているも同然です。
管理会計の独特のアレがありますが、過去問を解けば、即、対応できるはずです。
こんな次第で、「簿記+宅建」で、「10問」は負担が減る、ってな次第です。
こうした次第で、宅建や簿記を持っている人は、果敢に管理業務主任者試験に挑戦してください。
【他資格】マンション管理士との併願について
基本的に、わたしは、管理業務主任者とマンション管理士との併願に反対します。「マン管は、管業が受かってから」です。
「マンション管理士と管理業務主任者のダブル受験はすべきでない」や「資格ガイド‐マンション管理士」でも述べていますが、試験の肉体的・精神的負担や、資格の価値からして、「併願」は好ましくありません。
市販されている教材には、管理業務主任者とマンション管理士が一緒になったものが多いです。
しかし、こういう編集は、「受験生の数(市場)」が背景にあると思います。
管理業務主任者とマンション管理士は、受験生の数は、それぞれ「1.5万~2万人」です。
たとえば、テキストを作るとします。管業なら管業、マン管ならマン管と、個々に独立したテキストなら、その1冊には、「1.5万~2万人」しか需要がありません。しかし、両者を合体して、「管業・マン管」のテキストとすれば、1冊で「3.5~4万人」と、倍の市場となるってな塩梅です。加えて、製造コストも下がります。
そら、作る方からすれば、パイが大きくてコストの低いものを作るのが「商売」でしょう。しかし、受験生からすれば、管業とマン管の教材が一緒になったからといって、「もの凄く有利になるわけではない」のが実情です。
ぶっちゃけ、「目標」が2つになるため、力や時間を集中できない弊害の方が大きいです。
タニシでも、「戦力は集中せよ」くらいは知っています。んなもんで、わたしは、管業の教材は、専用のものを推奨します。
こうした次第で、併願はアレ、といった寸法です。とはいえ、マンション管理士の受験そのものは、否定しません。
ただ、「併願」はやめるべきで、1年目に管理業務主任者を、2年目にマンション管理士を受ける方が賢明です。それに、管業合格後なら、マン管で、5問の試験免除も受けられます。
ぶっちゃけ言えば、「まずは、価値に勝る管理業務主任者に集中して確実に合格」して、マンション管理士は、管業合格後に考える、といった次第です。
ちなみに、わたしは、宅建と管業はありますが、マンション管理士は持ってません。管業に合格してから月日が流れていますが、マン管を取ろう!と思う必要性や機会に、これまで1度も遭遇していません。このことも、無理して併願する必要はない、と思う理由です。
科目別過去問‐細切れ時間の有効活用に
管業は、過去問演習が物を言います。そこで、出先でも、ざっくり目が通せるよう、科目別に過去問題の一覧リンクを作りました。
試験科目のうち、基礎的な出題が多い「マンション管理適正化法」や「標準管理委託契約書」、「管理費・少額訴訟関係」、「標準管理規約」、「その他の法律(宅建業法・借地借家法など)」は、出先の細切れ時間で、十分に、演習可能かと思います。基礎・基本の確認やおさらいに、ご利用ください。
また、「建築・維持管理」は、「選択肢の使いまわし」対策で、何度も目を通しておきたいので、通勤・通学時間で、消化してみてください。
なお、「民法」や「区分所有法」は、長文も多く、何気に考える問題が多いので、机の前で、腰を落ち着けて解きましょう。また、「会計・税務」は、仕訳を切らないといけないので、出先でスラスラとは行かないです。
管理業務主任者のこまごましたもの
本試験のその他の情報については…、
「管業の合格率と挫折率」や、
「管業の難易度」、
「管業の勉強時間」、
…を、参考ください。
また、管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
★みんなとシェアする