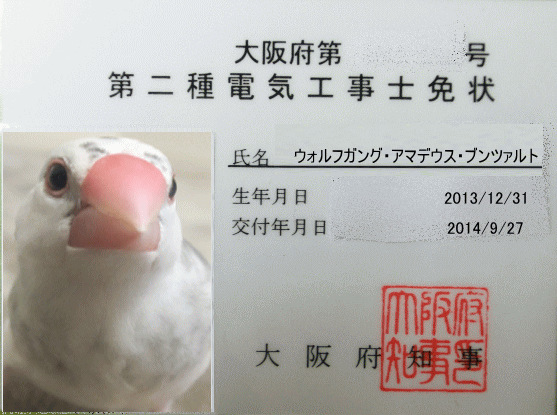郵便局の配達を騙る添付ファイル付き詐欺メールの文面は、こりゃ、だまされるなという件
郵便配達を騙った電子メールが届き、添付ファイルを開けると、ウイルス感染でID・パスワードが抜き取られるという案件です。
正直、ここまで装われると、疲れているときとか、ボンヤリしているときとか、酔ってるときに、被害に遭う強い予感があります。
拡散のため、明記しておきます。
以下、当方に届いた、とあるネット銀行からの注意喚起メールです。
——————————————-
郵便配達を装った以下のような不審なメールに添付されているファイルを
開封したことが原因で、パソコンがウイルス感染したとの事例が
発生しておりますので、あわせて十分ご注意ください。
【郵便配達を装った不審なメール(イメージ)】
件 名:番号XXXXXXXXXXの下で小包の配達
内 容:
拝啓
配達員が注文番号XXXXXXXXXXの商品を配達するため電話で連絡を差し上げたのですが、つながりませんでした。
従ってご注文の品はターミナルに返送されました。
ご注文登録時に入力していただいた電話番号に
誤りがあったことが分かりました。
このメールに添付されている委託運送状を印刷して、
最寄りのJAPAN POST取り扱い郵便局までお問い合わせください。 敬具
JAPAN POSTジャパンの宛先:
〒781-#RANDONMUM(4)#
東京都港区芝浦4-13-23
MS芝浦ビル13F
Post Japan Co., Ltd.
——————————————-
…引用終わり。
ってな感じで、引っかかり率は、かなり高いと思います。
わたしも、こういったタイプの詐欺メールを知らなかったら、添付ファイルを開けそうです。
だって、「怪しさ」がないんですもの。
配偶者やお子さんには、再度、「添付ファイル」は、「絶対に開かない」ことを徹底させるのみならず…、
新たに、「どのような文言があろうと、添付ファイルを開けない」と、「開けるときは、誰かと同伴で」を、ルールに追加しておきましょう。
「少しでも怪しいなら、添付ファイルはクリックしない」
添付ファイルを開ける際は、まず、当該電子メールの差出人のアドレスを検索することは、最低限やっておきます。
おそらく、フリーメールのドメインか、わけのわからないドメインの公算が高いです。
ちなみに、信用度の高いドメインは、「.co.jp」や「.jp」です。
これらのドメインは、正式な担当者を登録しないと使えないので、詐欺に使われ難い傾向があります。
反対に言うと、「.com」や「.net」などは、虚偽の情報でも使えるので、信用度は落ちます。
で、調べられるところは、数分で終わるのですから、検索します。
怪しいところに気付くはずです。
先の詐欺メールでは、「注文番号XXXXXXXXXX」とありますが、これは普通、配送業者なら、送り状番号とか伝票番号を、知らせてくるはずなのです。
それが、「注文番号」となっているので、こら、怪しいなと気付きます。
追加ルールです。
『少しでも怪しいと感じたなら、添付ファイルはクリックしない』です。
詐欺かどうか、だましかどうかは、論理的な、頭を使ってわかる作業というよりかは、皮膚感覚の「感じ」で判断するのが賢明です。
詐欺かどうかは、ん?とか、むむ?で判断していいと、教えておきましょう。
隣で寝ている人の顔を思い浮かべれば、感覚の大事さが、お分かりいただけるかと存じます。
ウイルス感染で金銭被害が出ることを踏まえれば、少々、荷物がアレしようと、困ることはほとんどないです。
昨今のウイルス感染と詐欺の被害の大半は、『添付ファイル』がらみであることを、再度、改めておくべきかと存じます。
なお、郵便局を騙るのなら、ヤマトや佐川、その他の宅配業者を偽装してもおかしくないので、再度、怪しい宅配メールには、注意しましょう。
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: 失敗, 詐欺 | 2016年3月4日 12:44 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
電気工事士法の免状の交付・書き換えの憶え方:第2種電気工事士の筆記・法令-電気工事士法
電気工事士法の頻出論点が、「免状交付の申請先」と、「書き換え」です。
以下、ポイントだけ述べておきますが、これだけで、1点取れるはずです。
免状交付の申請先
「免状交付の申請先」ですが、検索1つで解決です。
まず、『電気工事士 免状』で画像検索をしてみてください。
それか、『電気工事士 免状 ○○県(お住まいの都道府県)』で、画像検索します。
そうすっと、都道府県ごとに、体裁が異なる免状の画像が出てくると思います。
グーグル画像検索:電気工事士 免状
免状は、同じじゃない
上記画像は、大阪府の免状です。
手帳風のかっこいいものもあれば、大阪府のように、レンタルビデオの会員証より安っぽい免状もあります。
そう、電気工事士の免状の仕様は、都道府県によって絶妙に異なっているのです。
つまり、1都1道2府43県の都道府県(知事)が発行するから、“都道府県ごとにいろいろある”という次第です。
反対に言えば、もし、「国」が発行するなら、免状の仕様は「1つ」だったはずです。
いろいろ免状があるのは、「都道府県知事」が発行するから、と憶えましょう。
ひっかけ注意
先に見たように、2電工の免状を発行するのは、「知事」でした。
逆に言うと、経済産業大臣や産業保安監督部長ではありません。
「ひっかけ」問題として、たとえば…、
「2以上の県で電気工事をする場合、経済産業大臣に、免状を申請しなくてはいけない」
…といった出題が考えられます。
「×」です。
言うまでもなく、第2種電気工事士の免状は、知事に申請します。
経済産業大臣は、2つ以上の県にまたがって営業する“電気事業者”が登録する際の申請先です。
産業保安監督部長は、電気事故があった際の、事故報告書の提出先です。
最近は2電工も難化しているので、ひっかけ問題に注意してください。
書き換えについて
免状の書き換えで憶えておくべきは、「住所変更・・・書換え無用」のみです。
免状には、住所表記がなされていません。つまり、住所は、免状の記載事項ではないのです。
元から「ない」ものを、書換えるわけにはいかないので、よって、「住所変更・・・書換え無用」となる、ってな寸法です。
これが一番よく出るので、ピンポイントで押えてしまってください。
なお、結婚や養子縁組などで「氏名」が変ったなら、「氏名」は免状の記載事項ですから、書き換えが必要です。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記・法令 | 2016年3月4日 9:52 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
2016年度・2電工技能試験・候補問題‐No.3の攻略ポイント(文系ド素人向け)‐TS(タイムスイッチ)は端子台代用でカンタン。ラッキー問題。
候補問題の3番は、タイトルでも述べているように「ラッキー問題」です。
本問の固有部分は、「TS(タイムスイッチ)」です。
一見すると難しそうですが、実際の作業は、端子台で代用されるので、全くカンタンです。
テキストのお手本を見て、タイムスイッチの回路の要領を理解したら、後は、組み方を丸暗記するだけです。
ひとつのねじ(端子)に、2本繋げるという、あまりない作業ですが、2~3回練習すれば、絶対にできるようになります。
注意すべきは、「問題文で指示される接地極」だけです。
ここを間違えると、重大欠陥で即不合格なので、慎重に作業します。
わかってはいても、指差し確認をするくらいの慎重さで臨みましょう。
また、端子台の結線方法は何気に注意点が多いので、端子台への結線だけを3回は繰り返して、ミスゼロ状態になっておきましょう。
なお、端子台のねじの閉め忘れで重大欠陥、皮膜を噛んでいると重大欠陥、心線が5mm以上はみ出ていると重大欠陥で、『即不合格』です。
ところで、本試験の問題が、テキストのお手本通りになるとは限りません。
先述したように、何も考えず丸暗記するのではなくて、タイムスイッチ回路の要領を理解して、暗記に入るほうが、安全です。丸暗記だけだと、ちょっと問題の設定を変えられただけで、落ちてしまいます。
さて、他の部分は、全く“普通”で、そう支障はないでしょう。
他の候補問題を解いていれば、絶対にできるようになる、基本的なものばかりです。
タイトルでも言いましたが、本問は「ラッキー問題」です。
作業自体は、今年の候補問題の中で、かなりカンタンな方です。
幸運にも、慎重に、きちんと作業すれば受かる問題に遭遇したのですから、キッチリ、合格してしまいましょう。
最後に、技能試験の教材については「第2種電気工事士・技能試験のテキスト・教材・工具」に述べているのですが、文系ド素人にとって、あると便利なものを紹介しています。
たとえば…、
「ホーザン 合格クリップ」や、
「ホーザン 合格ゲージ P-925」や、
「ホーザン 合格配線チェッカー Z-22」です。
絶対に必要かというとそうではありませんが、「手助け」にはなるので、万全を尽くしたい方は参考にしてみてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 2016技能 | 2016年3月2日 12:51 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |