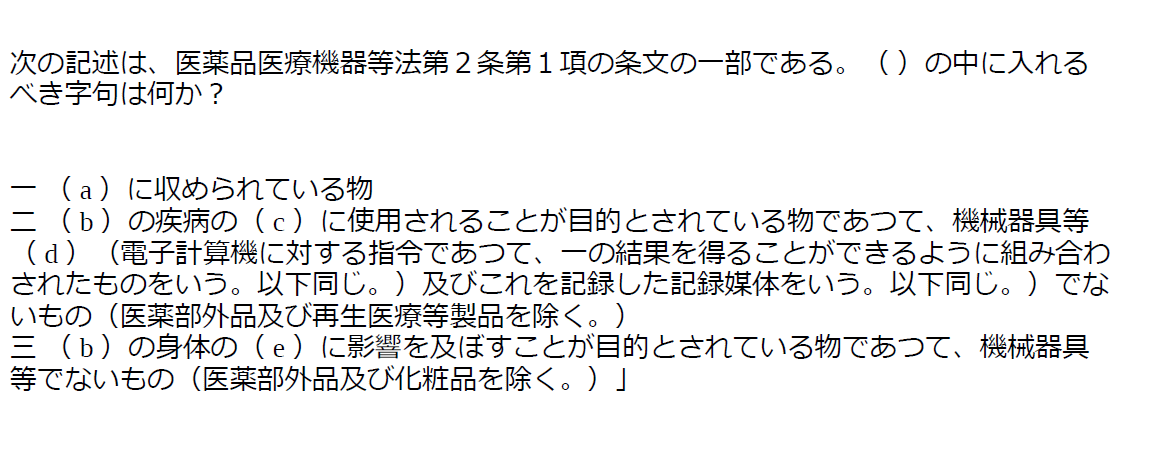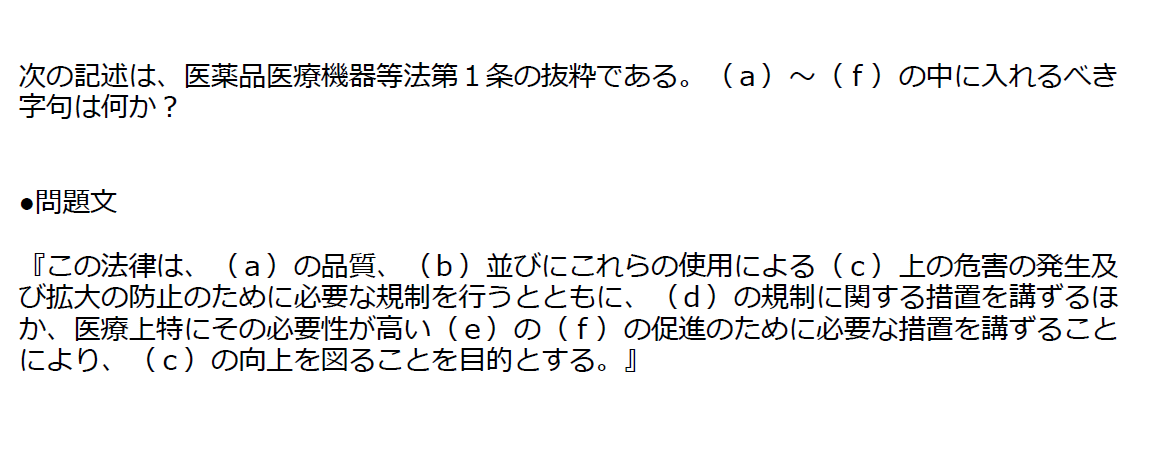工夫して憶える乙種の「○○性」‐危険物取扱者 乙種4類(乙4)の法令
本試験では、それぞれの類の「○○性」がよく問われます。
たとえば、「第1類危険物は、引火性固体である」などと出るわけです。もちろん、「×」で、第1類は「酸化性」です。
本ページでは、当該ド頻出論点の憶え方を、以下に述べていきます。
なお、おさらいですが、それぞれの類の「○○性」は…、
第1類危険物は、「酸化性」。
第2類危険物は、「可燃性」。
第3類危険物は、「自然発火性・禁水性」。
第4類危険物は、おなじみ「引火性」。
第5類危険物は、「自己反応性」。
第6類危険物は、「酸化性」。
…となっています。
最初と最後は、酸化性
一番憶えやすいのは、第1類と第6類の「酸化性」です。
これはカンタンで、「最初と最後は、酸化性」で憶えます。
ご存じのように、危険物は、1類から6類に分類されていますが、最初の第1類と、最後の第6類は、同じ「酸化性」となっています。
んなもんで、「最初と最後は、酸化性」で憶える、ってな寸法です。
「最初と最後くらい、参加(酸化)せい!」と、怒られたような体で憶えるのも一手です。
2と4は、燃える
次に憶えやすいのは、第2類と「可燃性」と、第4類の「引火性」です。
第2類と第4類ですが、これは、「燃える」という共通の性質があります。
んなもんで、ざっくり、「偶数は燃える、可燃と引火」くらいに憶えるといいでしょう。
乙4は、ガソリンや灯油・軽油を扱うので、すぐに「引火性」と憶えられるはずです。
なお、乙2には、「引火性固体」というものもあります。
3と5は語呂
残る3類と5類の憶え方ですが、これは、こじつけに近い「語呂」で憶えます。
語呂は、『35歳で失禁事故(しっきんじこ)』です。
「35歳」のところは、「3類」と「5類」を示します。
「失禁事故=しっきんじこ」の「し」は、「自然発火性」に該当します。
「失禁事故=しっきんじこ」の「きん」は、「禁水性」に当たります。
「失禁事故=しっきんじこ」の「じこ」は、「自己反応性」です。
こんな次第で、「35歳で失禁事故」が意外に頭に残るので、すぐ憶えられるかと思います。
まとめ
1類と6類は、「最初と最後は酸化性」で、それぞれ、「酸化性」です。
2類と4類は、「偶数は燃える、可燃と引火」と、憶えます。
3類と5類は、語呂の「35歳で失禁事故」で、3類は「自然発火性・禁水性」と、5類は「自己反応性」と憶えます。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令 | 2018年7月16日 9:55 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
登録販売者 薬機法第2条「医薬品の定義」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題2
「法規」の穴埋めで、当該「医薬品」の定義は、そこそこ目にするところです。
出題実績も相応にあります。
難易度は、「難」です。いやらしい問題にしています。
本試験では、ここまでは問われないので、安心してください。
解説
念のため、“お気に入り”にでも入れておいて、最低3回は、チェックしてください。
カッコa
(a)には、「日本薬局方」が入ります。
当該規定は、択一式で頻繁に問われるので、しっかり憶えておきます。
なお、配偶者の歯ブラシのように禍々しい出題者は、「ひっかけ」問題で、「日本“医”局方」とか「日本“医療”方」といった、とても紛らわしい語句を、出してくる可能性があります。
「日・本・薬・局・方」と、正確に憶えましょう。
なお、当該日本薬局方ですが、「日本薬局方に収められるものは、すべて、医薬品」となります。
「すべて」という極端な語句が使用されていますが、ここでは、「正しい」です。
よく出るようになっているので、「日本薬局方・・・すべて医薬品」と、ピンポイントで憶えておきましょう。
カッコb
(b)には、「人又は動物」が入ります。
穴埋めでは、あまり出ないところですが、択一式では、よく出ます。
たとえば、「医薬品は、人を対象とするが、動物を対象とするものはない。」などと出題されています。言うまでもなく、「人または動物」が対象なので、誤りです。
保険の意味で、押さえておきます。
カッコc
(c)には、「診断、治療又は予防」が入ります。
これら3つの語句は、医薬品の副作用の定義にて、よく問われるためか、ここでも問われる傾向があります。
なお、医薬品の副作用の定義(世界保健機関:WHO)ですが…、
『疾病の予防、診断、治療のため、または、身体の機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない作用』
…となっています。
医薬品の定義と、副作用の定義では、「予防、診断、治療」が共通しているので、併せて、憶えてしまいましょう。一石二鳥です。
なお、憶え方としては、「ちょーし、こいてんじゃねえ」くらいの語呂で憶えるとよいでしょう。
語呂の詳細は…、
ち・・・治療の「ち」
ょ・・・予防の「よ」
し・・・診断の「し」
…です。
カッコd
「機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム」が入ります。
5つも語句がありますが、“このあたりの1つ”が、かなりの頻度で問われているので、まとめて覚えておきます。
くだらない語呂ですが、「きしょいエプロン」くらいで、憶えてみてください。
配偶者のエプロン姿を思い浮かべれば、即、頭に残る語呂です。
語呂は各語句の頭文字で…、
き・・・機械器具・・・“き”かいきぐ
し・・・歯科材料・・・“し”かざいりょう
い・・・医療用品・・・“い”りょうようひん
エ・・・衛生用品・・・“え”いせいようひん
プ・・・プログラム・・・“ぷ”ろぐらむ
…ってな寸法です。
このうちのどれが問われるので、押さえておきます。
なお、頭が“うに”になるかもしれませんが、先の5つは、「機械器具等」に該当します。
よって、医薬品ではありません。医薬品とは、「機械器具等ではないもの」だからです。
たとえば、「マスクやガーゼ、包帯や脱脂綿といった、医療用品・衛生用品は、医薬品として取り扱われる」とあれば、「×」となります。
これらは、「機械器具等」なので、従って、「医薬品」ではありません。
カッコe
(e)は、「構造又は機能」です。
ふつうに、よく出るところです。憶えておきます。
条文補足‐「二」の読み方について
当該条文の「二」は、括弧がたくさんあるので、読みにくいです。以下のように整理して読むと、文意が通じます。
要は、本体部分は、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)」です。
ほいで、「機械器具等」の説明が、上記本体部分に追加されています。
そう、「機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム及びこれを記録した記録媒体」がそうです。
んで、先の「プログラム」の説明が、先の記述に追加されています。
それが「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」です。
暴言ですが、先の「機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム及びこれを記録した記録媒体」と「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」は、単なる補足説明で、「従」の記述です。
「主」の記述は、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)」です。
まず、「主」の意味を明確にして、んで、「従」を付け足していってください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者 法規, 登録販売者 法規 オリジナル問題, 登録販売者 語呂合わせ | 2018年7月10日 10:29 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
登録販売者 薬機法第1条「目的」の穴埋め問題‐法規 オリジナル練習問題1
当該第1条の「定義問題」は、穴埋め型や択一式で、ほぼ毎年、どの都道府県でも出題されるところです。
難易度は、「難」です。かなりいやらしい問題にしています。
本試験では、ここまで問われないので、安心してください。
解説
近年では、難化傾向を受けて、細かいところまで問われています。んなもんで、“ここまで”やっておきたいです。
念のため、“お気に入り”にでも入れておいて、最低5回は、チェックしてください。
カッコa
(a)には、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品」が入ります。
標準的な問題なら、当該5つの語句のうち、1つが問われます。
しかし、難問となると、選択肢に、たとえば…、
「医薬品、医薬部外品、化粧品」とか…、
「医薬品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品」とか…、
「医薬品、医薬部外品、化粧品」といった風に、“省略バージョン”で、出される可能性があります。
このところは、「5つの語句」が入るので、「い・い・け・い・さん=いい計算」くらいの語呂で、頭に入れてしまいましょう。
各語呂は、それぞれの…、
い・・・医薬品・・・“い”りょうひん
い・・・医薬部外品・・・“い”やくぶがいひん
け・・・化粧品・・・“け”しょうひん
い・・・医療機器・・・“い”りょうきき
さん・・・再生医療等製品・・・“さ”いせいいりょうとうせいひ“ん”
・・・頭文字です。
なお、後述する(e)とよく似ているので、必ず、対比して覚えてください。(a)は5つで、(e)は3つです。
カッコb
(b)には、「有効性及び安全性」が入ります。
あまり出ないところなのですが、「○○性」という文言は、問われやすいところです。
保険の意味で、押えておきましょう。
カッコc
(c)には、「保健衛生」が入ります。
「保健衛生」は、かなりよく出ます。ガチ注意です。
当該保健衛生は、前後関係から類推できません。よって、丸暗記するしかありません。
過去問では、「国民生活」が問われたことがあり、判断に迷った受験生も多かったはずです。「国民生活」でも、文意は通じるからです。
先の「国民生活」以外にも、たとえば、「集団衛生」とか「公衆衛生」とか「国民経済」とか「社会福祉」とかが出て来ても解答できるよう、正確に「保・健・衛・生」と、頭に入れておきます。
カッコd
「指定薬物」が入ります。ここもよく問われます。
本試験では、「抗精神薬」「違法薬物」「違法ドラッグ」「危険物」「毒物・劇物」と、変えられて問われることがあります。
「指・定・薬・物」と、意識して、憶えましょう。
「ひっかけ」で、「指定毒物」とか「指定劇物」、「指定医薬品」で問われても、答えられるようになっておきましょう。
カッコe
(e)は、「医薬品、医療機器及び再生医療等製品」です。
先述したように、(a)は語句が5つですが、ここは、3つとなっており、医薬部外品と化粧品が「ない」です。
ここも問われるところなので、(a)と対比して、憶えましょう。
カッコf
最後の(f)は、「研究開発」で、当該条文の頻出キーワードです。
薬機法の目的の1つに、「研究開発の促進」があるので、きっちり覚えておきます。
本当によく出るところです。
過去問の出題例・・・「規制」も
補足ですが、H29の福岡県試験にて、「規制」が問われました。
該当場所は…、
『この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。』
…の下線部分となっています。
これは、さすがに、わたしも、「???」でした。
こんな次第で、当該定義は、手を変え品を変えて問われているので、当該第1条だけは、念入りに目を通しておきましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者 法規, 登録販売者 法規 オリジナル問題, 登録販売者 語呂合わせ | 2018年7月2日 10:30 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |