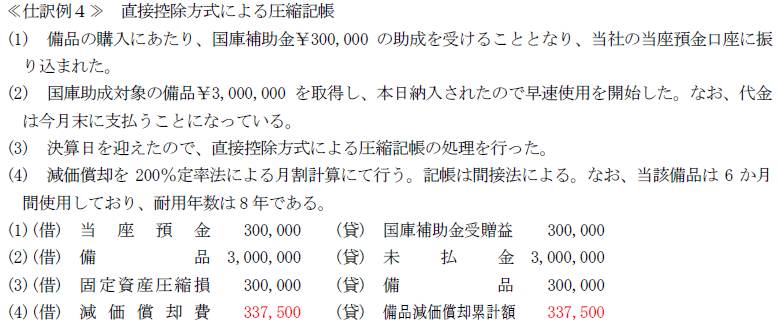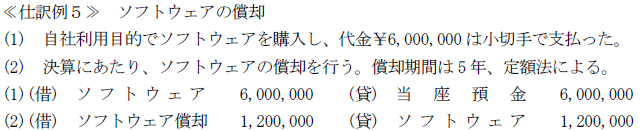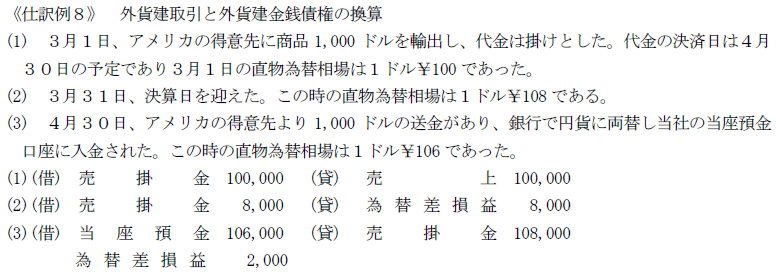簿記2級の出題区分改定スケジュール
H28年度(平成28年6月試験・11月試験、翌平成29年2月試験)より、追加される新論点は、以下の通りです。
記帳内容の集計・把握(※特殊仕訳帳がなくなる)
売買目的有価証券の時価法
債券の端数利息の処理
クレジット売掛金(※勘定科目の言い換え)
電子記録債券・電子記録債務(※勘定科目の言い換え)
引当金の個別評価と一括評価
営業債権及び営業外債権に対する貸倒引当金繰入額の損益計算書における区分
賞与引当金・返品調整引当金
月次処理(売上のつど売上原価勘定に振り替え)
有形固定資産の割賦購入
ソフトフェア
子会社株式、関連会社株式
その他有価証券
収益・費用の認識基準
役務収益・役務費用
創立費・開業費
その他有価証券評価差額金(全部資産直入法)
株主資本等変動計算書の一部
株主資本の係数の変動(積立金や準備金の取り崩しなど)
本支店会計における決算手続き(※ 基本足し算。)
以上が、平成28年度試験より追加される論点です。
数こそ多いのですが、それほど難しい論点はありません。
どう転ぶかわからないのが「月次処理(売上のつど売上原価勘定に振り替え)」で、一番の要注意論点かと思います。
H29年度に追加される論点
H29年度、要は、平成29年の6月試験・11月試験、翌平成30年2月の試験に追加される新論点は、以下の通りです。
圧縮記帳
リース取引
外貨建取引
課税所得の算定
外貨建売上債権・仕入債務の換算
連結会計(アップストリームを除く)
目玉は、連結会計です。
計算がメンドクサイ外貨建取引も追加され、難易度はかなり上がります。
H30年度に追加される論点
H30年度、要は、平成30年の6月試験・11月試験、翌平成31年の2月試験に追加される新論点は、以下の通りです。
税効果会計
製造業を営む会社の決算処理
連結会計(アップストリームを含む)
税効果会計が追加されますが、処理自体はあまり難しくありません。
連結会計(アップストリームを含む)も、大きなところは前年度に追加されているので、そう負担は増えないでしょう。
問題は、「製造業を営む会社の決算処理」です。
当該論点がどう転ぶかわからないので、要注意かと思います。
なお、削除される論点は「簿記2級出題区分の改定ポイント2-なくなる論点(特殊商品売買・社債・繰延資産・本支店会計) 」を参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記2級, 簿記2級出題区分改定 | 2015年8月3日 10:10 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
簿記2級出題区分の改定ポイント4-微妙な論点・要注意論点
多くの論点は、勘定科目の言い換えだったり、簿記1級のダウングレードだったりで、そう不安はないのです。
しかし、怖がらせる意図はないのですが、新しく簿記2級に追加される論点のうち、どうなるのかわからないのが、「製造業を営む会社の決算整理」と「月次決算」と「課税所得の算定方法」の3論点です。
これまでの出題実績がないので、トンテモナイ出題があるなどの、混乱が生じる恐れがあります。
結論から言うと、良質なテキストと問題集を使って、受験のプロのエッセンスを頂くのが一番かと思います。
製造業を営む会社の決算整理
簿記2級には、工業簿記・原価計算が出題されていますが、それらが、商業簿記とうまくリンクできていないのがこれまでの簿記試験でした。
商業簿記の問題は、主に決算の期末処理なのに対して、工業簿記・原価計算のそれは期中処理が多く、問題自体がうまく関わってこなかったという次第です。
これを受けて、「製造業を営む会社の決算整理」という独自の論点が、簿記2級の商業簿記に新たに設置されるのですが、正直、どういう問題になるのかわかりません。
「仕掛品」の決算処理と計上に絡んだ問題なのでしょうが、当該論点は簿記2級の固有論点として採用されるので、これまでに出題実績がなく、どんな問題になるかも不明です。
注意すべき論点かと思います。
当該論点は、平成30年度から、つまり、平成30年(2018年)6月の試験から導入されます。
月次処理
従来の試験では、年に一回、決算日に売上原価を計上していましたが、実務では、売上のつど売上原価を計上して、逐一すばやく、経営状態を把握できるようになっています。
こうした実務事情を受けて、「月次処理」も、出題の可能性があることが明文化されました。
資料によると、「月次処理」だからといって、新たな勘定科目が増えたり処理が異なったりするわけではないと、述べられています。
以下は、資料に掲載されていた仕訳例です。
「販売のつど売上原価勘定に振り替える方法による売買取引の処理」
【例】@800円のものを100個仕入れて、60個を@1,200円で売った。販売のつど、売上原価勘定に振り替えている。
商品 80,000/買掛金 80,000
売掛金 72,000/売上 72,000
売上原価 48,000/商品 48,000
…ってな仕訳となっています。
当該論点は、「決算」がテーマの総合問題にはそぐわないので、出題されるとしたら、「仕訳問題」として出題されそうです。
また、当該月次処理に絡んで、「月次決算の場合による処理」という新論点が追加されています。
資料によると、「従来の年次決算で行われていた、収益・費用の見越し計上や、見越しの再振替仕訳が行われない場合もある」とのことです。
当該論点も、どう「問題化」されるのか明らかでないので、要注意論点です。単純な仕訳問題ならいいのですが…。
当該論点は、平成28年度から、つまり、平成28年(2016年)6月の試験から導入されます。
課税所得の算定方法
「課税所得の算定方法」は、税効果会計との整合を計るために、2級の出題範囲に含まれることになりました。
一般的に、税引き前純利益と課税所得が異なるので、このあたりの実務事情の理解を促すための、導入と相なっています。
簿記の試験ですから、絶対に、難しいものは出題されないと思います。
資料では、貸倒引当金の損金不算入が例として挙げられています。
まあ、出るにしても、FP技能士1級~2級程度の、役員報酬等の損金計上できるもの・できないものの区別や、それらに絡んだ処理が「山」だと思います。
そもそも、当該「課税所得の算定方法」の導入の背景となった、税効果会計ですら、実質は実効税率を掛けるだけの“掛け算”ですから、そこから、とんでもなくレベルの高い内容は出ないと思われます。
当該論点は、平成29年度より、つまり、平成29年(2017年)6月の本試験より導入されます。
微妙なのですが、そう難しい内容は出せないので、基本的な仕組みだけは理解しておきましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記2級, 簿記2級出題区分改定 | 2015年7月31日 8:33 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
簿記2級出題区分の改定ポイント3-簿記1級からのダウングレード系統
ご存知のように、平成28年度から30年度にかけて、簿記2級の出題区分が改定されます。
そのうち、「簿記1級のダウングレード論点」は、以下の通りです。
何が言いたいのかというと、「これらの論点では、大きな混乱は少ない」という次第です。
というのも、以下の論点は既に簿記1級で出題されていて、それらを言うなれば、“簿記2級用に焼き直す”だけなので、試験指導や教材に大きな混乱はあまり生じない、という塩梅です。
言ってしまえば、簿記1級のテキストや問題集の内容を、ちょっといじって簿記2級のそれらに移植するだけであり、「ゼロから作ると言うわけではない」ので、混乱はそう起きないだろうという次第です。
もっと言うと、簿記2級の問題が、簿記1級より難しくはならないだろうし、簿記2級の出題が、簿記1級とまったく異なる異色の傾向になるとは考えられない、といった次第です。
定評のある教材を使えば、そこそこの点数は確保できると思われます。
圧縮記帳
2級でも圧縮記帳が登場します。が、当該圧縮記帳は、1級ではポピュラーな論点で、何度も出題されたことがあります。
商工会議所の配布資料の仕訳例は、以下の画像です。
最初はとっつき難いのですが、処理そのものは難しくないので、それほど心配することはありません。
ソフトウェア
簿記2級では、自社利用のみの処理です。
ぶっちゃけ、簡単です。有形固定資産と同じように償却するだけです。
配布資料の仕訳例は、以下の画像です。
当該論点も心配には及びません。
子会社株式・投資有価証券
売買目的とか満期保有といった、有価証券の「分け方」の問題なので、難しくはありませんし、そう難しい問題も出せないでしょう。
当該論点も心配には及びません。連結会計と関わる子会社株式だけは、よく読んでおきましょう。
リース取引
出題は、ファイナンスリース取引の「借り手」に限定されているので、そう難しくはないと思います。
仕訳例は、以下の画像です。
横文字が多いので、難しいのは、最初だけです。
外貨建取引
従来、外貨建取引は主に大企業に限られていましたが、昨今では中小企業でもバンバン取引を行っている現状を受けて、簿記2級に登場と相なった次第です。
ややこしいというよりも、煩雑です。
どういう処理方法を採っているかを正確に読み込んだ上で、正確に対応する為替レートで計算をしなくてはならず、計算ミスの続出します。
逆に言うと、当該外貨建取引に、配点が来ることが多いので、しっかり計算できるようにしておきましょう。
良質な問題を何度も解いて、確実に“計算機”を叩けるようになっておくことを勧めます。
仕訳例は、以下の画像です。
連結会計
今回の出題範囲の変更の目玉です。
実務動行を鑑みても、「連結会計」が一番大事なところだと思います。正直、今となっては常識レベルですので、試験勉強という意識を薄めて、教養や実務能力の補填の意図をこめて、シッカリ勉強しましょう。
逆を言うと、知らないと恥をかきます。勉強しておいて絶対に損はありません。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 簿記2級, 簿記2級出題区分改定 | 2015年7月30日 11:16 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |