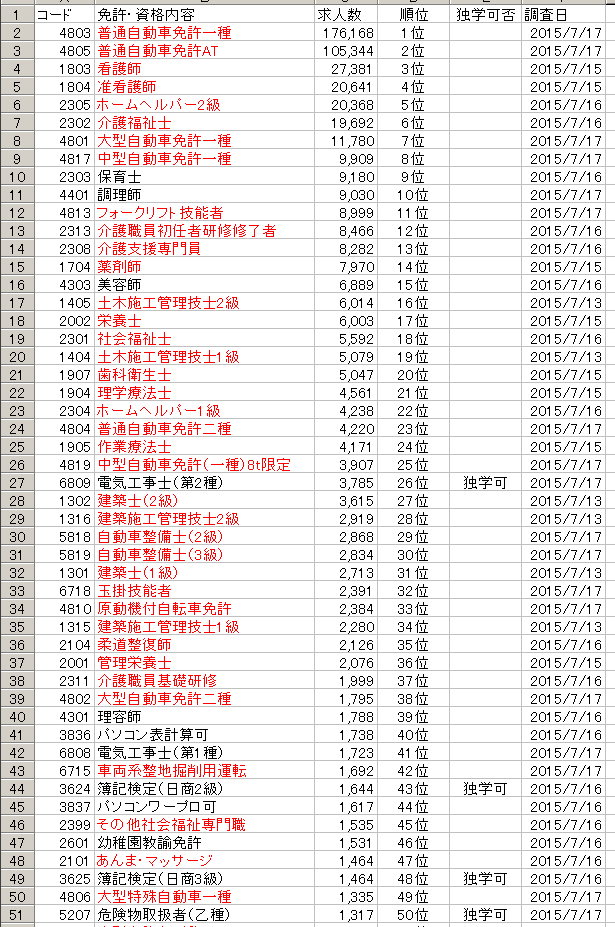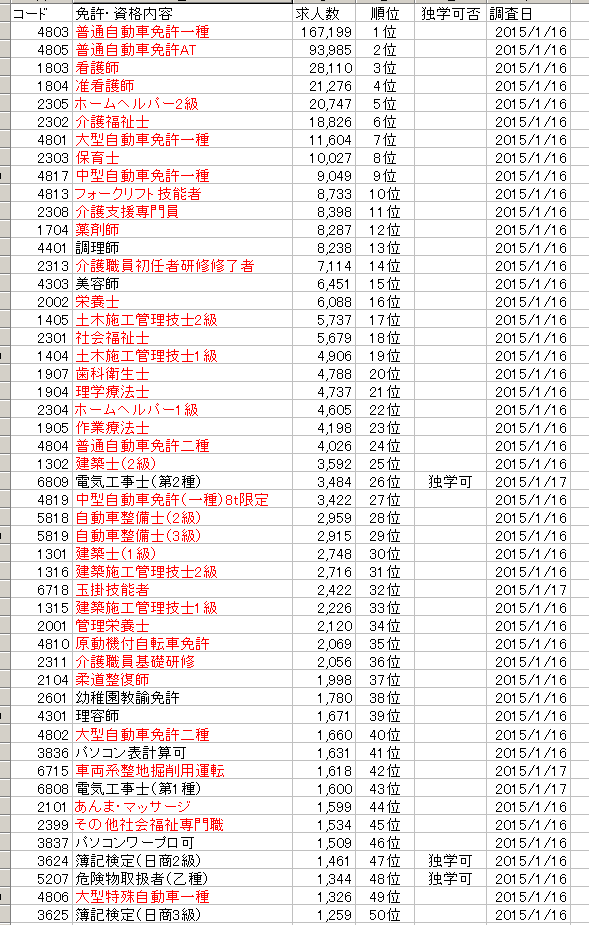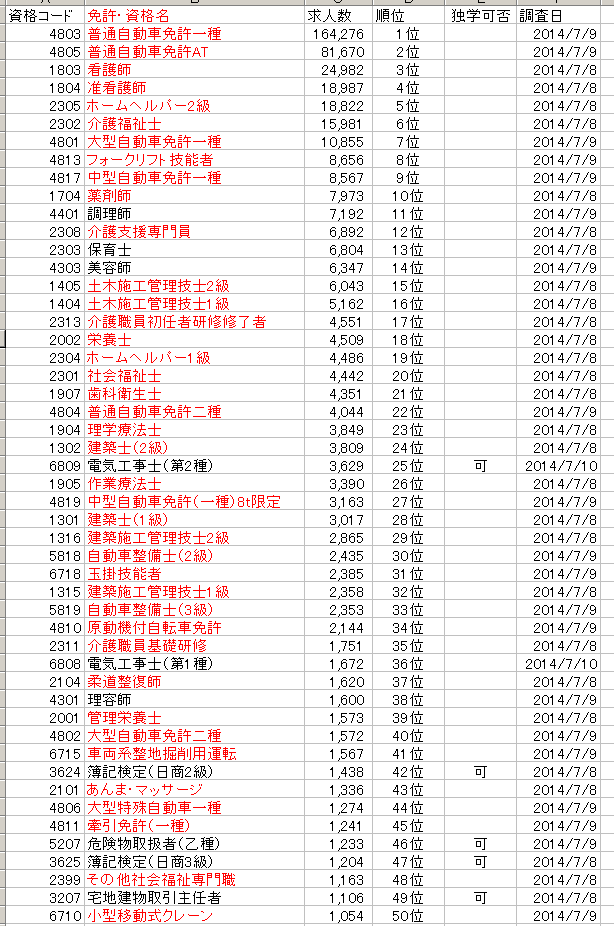資格とは「車・医・建」‐求人数から見る資格
結論から言うと、資格とは、「車・医・建」に尽きる、といった次第です。
現在、資格は国家資格から民間資格まで、数千あると言われています。
勉強目的や自己啓発なら「お好きに」ですが、就職や転職を有利にするとか、人生の保証や保険を得るといった点から、資格の取得を考えているなら、意図・目的と『ズレてない資格』を選ばないといけません。
選択の上で欠かせない指標が、「求人数」なのですが、ハロワの求人数データからすると、求人は「車・医・建」系統の資格に集中しているのが事実です。
つまり、自動車の免許と、医療・福祉・介護の資格と、建設・建築の資格・免許の求人は、『ケタ違いに多い』という次第です。
反対に言うと、「車・医・建」系統以外の資格は、数えられるほどしか求人がないという塩梅です。
2015年度7月の、求人数TOP50のデータです。
赤字の資格が、「車・医・建」系統の資格です。
ぱっと見で十分わかるかと思いますが、セルのほとんどは赤字で占められており、求人の大半が「車・医・建」の資格であることがわかります。
細かくいうと…、
「車・医・建」の資格は、TOP10位中8つあり、「80%」を占めています。
TOP30で区切ると、「車・医・建」以外の資格は4つしかなく、残る26資格が「車・医・建」で「86%」を占めます。
TOP50で区切ると、「車・医・建」以外の資格は12個しかなく、残る38資格が「車・医・建」で「76%」を占めます。
何度も同じことを述べて恐縮ですが、自動車の免許と、医療・福祉・介護の資格と、建設・建築の資格・免許の求人がケタ違いに多いのがわかります。
TOP100でも、実情はあまり変わりありません。
2015年1月のTOP50
時期を変えてみます。
「2015年1月」の求人数TOP50だと、「車・医・建」の資格は40個で、求人数上位の「80%」を占めています。
赤で染まっているのは、変わりありません。
2014年7月のTOP50
「2014年7月」のTOP50でも、「車・医・建」の資格は40個あり、求人数上位の「80%」を占めます。
相変わらず、赤で染まっていますし、上位に挙がる資格も変わり映えありません。
まとめ的なもの
資格・免許の求人事情は、だいたい上記のような次第で、今後も同じように推移していくように思われます。
つまり、自動車の免許と、医療・福祉・介護の資格と、建設・建築の資格・免許に、求人が集中するといった塩梅です。
ざっくり言うと、これらTOP50の資格を取れば、就職や転職という点で、ハズレはないという塩梅です。
そう、有象無象の資格をいくつも取るより、大型免許+危険物取扱者やフォークリフトとか、一念発揮して通学して医療・福祉の資格を取る方が、就職や転職は無難という次第です。
なお、注意点があります。
求人数だけが、資格の価値のすべてではありません。
特殊・特別な資格は、たとえば、高圧ガスを運ぶ際に必要な「高圧ガス移動監視者」などは、やはり相対的に求人数は少なくなってしまいます。が、求人数は少なくても、社会に必要な資格です。
また、上記のデータは、ハローワークに登録されている資格・免許の求人数で、言うなれば「一般的な求人状況」を現わしています。専門的な資格・職業の求人動行を見るにはそぐいません。
当該データは、資格というものを実態を、もう一歩踏まえるために、役立たせてほしく思います。
「○○という資格を取ったら何とかなりそう」と思っていたら、当該資格○○には、求人はなかったなんてことのないように、ご利用いただけたらと存じます。
有名なだけの資格、知名度だけの資格、掛け声だけの資格は、腐るほどあります。
| カテゴリー: 資格の就職・転職事情 | Tags: 資格 | 2015年8月13日 1:57 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
ぬいぐるみ・クッション・座布団の臭いに重曹を-ビニール+霧吹き
ぬいぐるみ・クッション・座布団は、人体との接触が多い割りに、なかなか洗えない物です。
そのためか、そこそこ臭ってきます。
こうした、洗いにくい物の臭いに重曹を使う、という次第です。
ビニール袋で重曹
大き目のビニール袋かゴミ袋に、ぬいぐるみなりクッションなり座布団なり配偶者なり、洗いにくいものを入れます。
重曹を適当にざぱざぱと振り掛けます。
量は適当でいいです。多少掛けすぎても、支障はありません。
ふくろの口を閉じるなり縛るなりして、満遍なく重曹が行き渡るように、2~3回ふくろを振ります。
で、適当なところに放置します。日当たりのいいベランダが最高のロケーションです。
しばらく放置して、付着した重曹をはたいて取り除けば終了です。
これで大体の臭いは取れます。
霧吹きで重曹
大概の臭いは、先のビニール袋+重曹で取れます。
しかし、ときには、配偶者のようなたちの悪い臭いもあります。
この場合、重曹を霧吹きに入れて水で溶かし、当該重曹水をぬいぐるみ等に散布しつつ、日干しして紫外線消毒を行います。
キツイ臭いだと、1回では取れないはずです。
クンクンしても臭いが残っているときは、上記作業を2~3回繰り返します。
重曹水は、結構多めに吹き付けても、天気のいい日ならすぐに乾くので、大丈夫です。
臭いのきついところには、びしょびしょになるくらい、吹き付けてください。
わたしの場合、ついウッカリして、1年くらい干してなかった座布団があって、頑固に臭っておりました。
都合5日間ほど、霧吹き+日干しして、ようやく臭いが和らいだってな寸法です。
ビニールふくろ方式と比べると、多少手間がかかりますが、強力に臭いが取れるのでお試しください。
白っぽいものが滲み出た
重曹を使って臭い消しをしてしばらく経つと、白っぽいものが滲み出るときがあります。
重曹を大目に使った場合や、重曹の除去が不十分なときに、白染みがでます。
当該白っぽいものは、残っていた重曹が湿気(水分)と反応したもので、まあ、一種の塩です。
人体に影響はありませんが、あたかも“汗じみ”のように見えるので、不恰好です。
この場合、クエン酸を水に溶かして、霧吹きで吹き付けてみてください。
薄いものなら1回で、濃度の高いものでも2~3回、吹き付ければ当該白っぽいものは、クエン酸の酸と反応して、なくなります。
なお、重曹は、人体と接触のあるものなので、食用グレードのものを使うのを推薦します。
クエン酸も、掃除用ではなく、食用グレードの方が無難かと思います。
参考:重曹(食用グレード)
参考:クエン酸(食用グレード)
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: クエン酸, 重曹 | 2015年8月10日 12:09 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
洗面台や風呂の排水の悪さに重曹・クエン酸を
結論から言うと、洗面台や風呂の排水が悪くなったら、重曹とクエン酸を試してみる、という次第です。
大概の詰まりは、重曹とクエン酸で直ります。
水の流れが悪くなってきたら、まずは、『重曹をぶち込む』です。
量は適当でいいです。分量等を気にする必要は皆無です。
ざくざくざくざくと排水口に重曹を注いで、コップ一杯の水を流して、10~20分ほど放置します。
重曹は弱アルカリ性なので、酸性の皮脂汚れや石鹸カスと反応して、配管にこびり付いた汚れを中和して取り除きます。
また、重曹は磨き粉に使われるほど微小な粒子なので、髪の毛等の大きなゴミをこそげ取って、流れやすくします。
こんな次第で、多少の排水の悪さなら、重曹を入れるだけで直ってしまうのです。
重曹を投入してしばらく経ったら、流れが元通りかを調べてみます。
元に戻っていたら大成功ですが、まだまだ悪いときもあります。
この場合は、重曹にクエン酸をプラスします。
重曹は弱アルカリ性で、クエン酸はその名の通り酸性です。
両者を混ぜると発泡するのですが、当該発泡で、排水管の頑固な汚れを取り除く、という次第です。
大目の重曹を排水口に注ぎ入れ、クエン酸を適当にぶち込み、で、コップ2~3杯の水を注ぎます。
配偶者もついでに投げ入れたいところですが我慢します。
すると、重曹とクエン酸が反応して、プチプチプチシュワシュワシュワという発泡音がするはずです。
で、10~20分ほど放置してから、流れを確かめます。
大概の詰まりであれば、重曹とクエン酸のタッグで直ります。2~3回繰り返せば、鉄壁でしょう。
だめだったら、市販のパイプクリーナーを使い、それでもダメだったら、汚れによる詰まりではなく、固形物による詰まりか、配管の奥の方の詰まりが予想されるので、業者と相なります。
普通の生活汚れ由来の詰まりなら、重曹とクエン酸で、直るのでお試しください。
市販のパイプクリーナーを買うなんていう、余計な支出をしないで済みます。
なお、重曹は排水口の臭いにも効くので、定期的に重曹を投入すれば、異臭対策+詰まり対策にもなるので、合理的です。
重曹やクエン酸はドラッグストアでも売っています。
が、コストパフォーマンスは断然通販です。
また、手荒れ等が気になる方は、念のため、掃除用は使わず、「食用グレード」にするのを推奨します。
わたしは食用グレードオンリーで、肌荒れ等のトラブルはゼロです。
参考:クエン酸1キロ
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: クエン酸, 重曹 | 2015年8月7日 11:53 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |