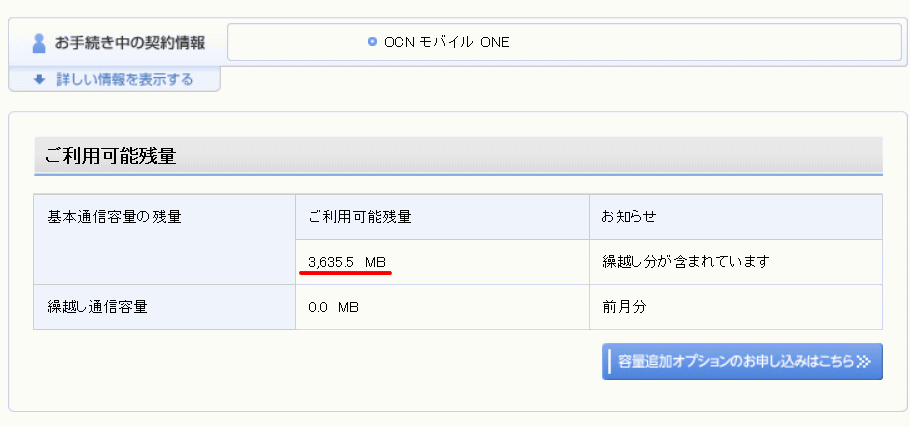ハッカ油でゴキブリ(以下、G)+小虫・羽虫予防-窓を開ける際にハッカ油スプレー
「ゴキブリ対策をしっかりしているのに、ゴキブリ(以下、G)を見る」というのは、夏の風物詩であります。
こういう「対策しているのになぜかいるG」とは、ドアや窓といった開口部からの侵入が考えられます。
そう、窓を開けた時に、こそっと入って来ている、という塩梅です。
当方、洗濯物を干す際に、どうしても窓を開けなくてはならず、例年、Gに悩まされていました。
Gが台所にいるのは、仕方がありません。Gにとっては宝物庫のようなものだからです。
しかし、以前は、水気や生ごみ気、食べ物気が“まったくない部屋”、たとえば、寝室や私室にも、Gの姿を確認していたのです。
ですが、「ハッカ油スプレー」を使うようになって、Gの出現率が、かなり減ったのであります。
小虫・羽虫対策が、ゴキブリにも
当方、窓を開ける際は、ハッカ油スプレーで小虫の類の侵入を防いでいました。
虫は、ハッカ油のメンソール臭をかなり嫌うので、入ってくる虫の数がかなり減るのです。
以前は、部屋のあちこちに、息絶えた小さな虫を見つけて、心を痛めていました。
そこで、窓を開けるときは、ハッカ油を霧吹きに2~3滴を注いで水で溶いたハッカ油スプレーを噴射して、小虫等の侵入を防いでいた、という寸法です。
特に不都合もないので(アブくらい)、当該ハッカ油スプレーを使い続けていると、Gを、あまり見ていないことに気づいたのです。
有体に言えば、ハッカ油のメンソール臭は、Gにも効いて、窓からのGの侵入を防げる、という塩梅です。
2段階窓開け
当方、窓を開ける際は、最初少しだけ、1~2センチ程度、開けます。
で、当該隙間に霧吹きの先っぽを突っ込め、シュシュとしてから、ガラッと大きく開ける、という『2段階』で窓を開けています。
どかっと窓を開けると、その空けた瞬間に入ってくるために、このような「2段階窓開け」が有効です。
あんまり面倒ではない
窓を開けるたびに、霧吹きでハッカ油を噴射なんて、文字だけで見ると、手間と思うことでしょう。
しかし、意外や意外、ハッカ油は芳香剤でもあるので、しゅしゅっと吹き付けると、その香りがなかなかに快適で、あまり「苦」にならないというのが、わたしの実感です。
いまでは、窓を開けるときは、必ずハッカ油スプレーをしています。
コツは数個-100円ショップの霧吹きでOK
当該ハッカ油スプレーは、数個を、「よく開け閉めする窓の数」だけ、用意するのがコツです。
というのも、1個だけだと、持って移動するのが面倒だからです。
また、1個しかないと、最後に使った場所を忘れてしまい、探すという手間が生じます。
ですから、よく開ける窓のところに、霧吹きを常備する、ってな塩梅です。
霧吹きは100円ショップで売っているもので十分。園芸用の丈夫なものはいりません。というのも、Gの活動期は夏なので、夏以外はそう使わないからです。
こんな次第で、ハッカ油スプレーで、Gの侵入率を下げられるといった次第です。
Gの完全予防には到りませんが、予防の一定効果は見込まれる、というのが当方の「強い」実感です。
配偶者に直接吹き付けないでください。
ハッカ油は、ドラッグストアで売っています。
価格参考:アマゾン:ハッカ油
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: ハッカ油 | 2016年8月5日 11:28 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
勉強しない「めやす」の室温30度
夏の暑いとき、とりわけ、日中の時間帯は、勉強をやめます。
われわれは、戦車兵でも潜水艦乗りでもありません。暑いさなかに頑張っても、意味はないです。
スマホなりPCでも、熱を持ち出すと、動きが悪くなります。
「頭」だって同じで、暑くなればなるほど、動かなくなります。
目安は、「室温30度」です。30度以上の室温になったら、勉強は中断です。
室温が30度を超えると、とたんに「頭が動かなくなって」、能率が落ちます。
頭が動かない
「頭が動かない」とは、以下のような状態です。
・テキストの文言が、少しも頭に入っていかない。
・文字を“追う”気がわかない。
・数式や公式が少しも憶えられない。
・読み違いが頻発。
・問題が解けない。
・ケアレスミスが増える。
・書く文字がすごく汚い。常より倍は、汚い・くちゃくちゃ。
・集中できない。すぐ気が散る。ぼんやりする。
・10分前にやったことが思い出せない。
・配偶者がきれいに見える。
…ってな塩梅です。
繰り返しますが、頭脳労働に、暑さと熱は、天敵です。
上記の「頭が動かない」状態になっているなら、勉強の一時中断こそ、頭のよい行為です。
暑い最中、汗をかきながら、テキストと問題集に向かうのは、頭の悪い行為です。
避暑
今では、空調が普及したので、あまり使われなくなりましたが、「避暑」という言葉があります。
その通り、都心部の暑さを避けて、涼しいところに行く・過ごす、といった意味です。
昔の作家が、よくよく軽井沢の別荘を持っていたのも、都会では、暑い夏の間は脳が動かず、仕事にならなかったからです。
彼らにとっては、「涼しいところで頭を使う」のが、仕事の一環だったという寸法です。
我々も、彼らに倣うべきでしょう。
昔から、頭脳労働に、「熱」なり「暑さ」は大敵だったのです。頭をフルに動かすには、涼しくないとダメなんです。
室温が30度以上になったら空調
お昼の時間帯しか、勉強の時間が取れないのなら、「空調」の2文字に尽きます。
繰り返すように、「30度」を越えると、脳の動きは途端に鈍くなります。
ドライでもクーラーでもかまいませんが、室温を落として、勉強に臨んでください。
夏のお勉強は朝か夜
クーラーをかけると体調が悪くなる、または、家に・部屋にクーラーがないといった方は、お勉強の時間帯を変えます。
涼しい朝か、涼しくなる夜に、お勉強の時間を設けます。
昼の勉強に比べると、格段に集中力が増していることに気づくはずです。
先ほど、「暑い最中、汗をかきながら、テキストと問題集に向かうのは、頭の悪い行為」と申しましたが、「暑さ」と「涼しさ」で、どれだけ能率が違うか、体験してみてください。
人は本来、馬鹿ではありません。
意味の薄い行為を続けるから、「馬鹿になる」のです。
温度(室温)と能率とは、強い因果で結ばれています。
暑くて調子が出ないなら、さっさと止めて、涼しい時間に頑張りましょう。
以上、お勉強をサボる口実でした。
| カテゴリー: 勉強ワンポイントアドバイス | Tags: 勉強, 頭 | 2016年8月1日 9:51 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
OCN モバイル ONEの10GB/月コースのレビュ~差額1,300円の価値はあるか?
OCN モバイル ONEに新しく登場した「10GB/月コース」を使ってみました。(当方、音声通話SIMを利用しています。)
ちなみに、以前は「3GB」コースで、容量は「プラス7GB」で、費えは「プラス1,300円」となった塩梅です。
料金の詳細は以下。
音声通話SIMの10GBコースは「税込3,240円」で、3GBコースが「税込1,944円」です。
なお、データ通信の10GBコースは「税込2,484円」で、3GBコースが「税込1,188円」です。
10GBと3GBでは、月額「1,300円」の差がありますが、費用対効果はいかがなものか?ってな次第です。
当たり前だが、とても快適になる
当方、ネットの利用は、ニュースやメールや通販等々で、大量の通信をするわけではありません。
動画はもうほとんど見てませんし、ネトゲーもしていません。
こうした、ネット回線の低需要者からすると、月「10GB」は、余ります。
上記画像は、29日のものですが、3GB近く余っています。
当該利用月の「7月」は、高速モードでネットをビシバシ見まくっていました。
というのも、Windows10のアップデートが月末までなので、新規PCを購入すべく、通販サイトを覗きに覗き、調べに調べていたからです。
でも、この余り方です。
この間、ずっと「高速モード」で、「低速モード」にしたことがありません。
高速モードは、快適で、ほとんどストレスなく、Webページを逍遥できた次第です。
10GBコースは、ふつうにWebサイトを回るのであれば、必要かつ十分な要領です。
調べ物が多い人で、ブラウザのタブを20個も30個も開けているってな人には、適したコースであるかと思います。
また、付け加えるなら、ダウンロードも快適でした。
アップデートに伴うドライバや支援ソフトウェア、アプリ、ロールアップパッケージ等々を落としたのですが、全く支障がありませんでした。
動画を見たらすぐなくなる
基本的に、OCN モバイル ONEのサービスは、「ヘビーユーザー」向けではありません。
つまり、重たいネトゲーや動画をよく見る人には、不適当なサービスです。
ですから、「10GB」という、OCN モバイル ONEの最大容量のコースを選んでも、大量の回線需要は賄えない、といった次第です。
SNSに流れてくる動画を見るなら支障はありませんが、動画配信などを利用すれば、あっという間に10GBなんて消費されてしまいます。
ようつべなどで、猫や小鳥の動画を見まくっていたら、1日もかからず、1GBが吹き飛びました。
10GBプランでも、動画を大々的に楽しむのは無理だった、ってな次第です。
コアタイムは、やっぱり重い
10GBだからといって、通信は早くなりません。
3GBコースと同様に、お昼時や夕方から夜にかけては、格段に重たくなりました。
(せっかく10GBもあるのに)といった、宝の持ち腐れ感はありました。
10GBはやめます。
10GBプランは、わたしには合わなかったです。
非常に快適だったのですが、だからといって、月額「1,300円」を余計に払う価値はあるのか?というと、「否」だった次第です。
音声通話SIMの3GBコースは、先述したように、「税込1,944円」です。対して、10GBコースは「税込3,240円」です。
差額の「1,300円」は、3GBコースの「0.6ヶ月分」にあたります。
10GBコースにして、新たに「1,300円」を費やすよりも、当該金額を3GBコースの支払いに充当したほうがいいじゃん、ってな塩梅です。
バースト転送機能?
また、10GBを止めるのは、「バースト転送機能」という仕様があるためです。
これを書いている時点では、当該仕様は実装されていないようなのですが(延期とアナウンスされており、公式導入の発表なし)、なぜか、当方の環境では、非公式ながら、試験的に実装されているように見受けられ、最初の数秒がすごく早くて、さくさくネットが見れているのです。
このため、低速モードのストレスがかなりなくなっていて、3GBコースの使い勝手がかなり上がっている、という寸法です。
とりわけ、SNSの読み込みが、以前と比べて、格段によくなっています。
「バースト転送機能」が本格的に導入されたら、3GBでも全然いいじゃんという塩梅です。
以上、わたしの10GBコースの使用感でした。
自分にしっくり来るプランは、やはり、「使ってみないとわからない」という感を強くしました。
当方は、「3GB」コースで、必要なときだけ「高速モード」というのが、一番しっくり来ています。
OCN モバイル ONEは、コースの変更に料金はかからないので、試しに10GBコースにしてみるのも、一興かと思います。
参考:OCN モバイル ONE![]()
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: ocnモバイルone | 2016年7月30日 10:20 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |